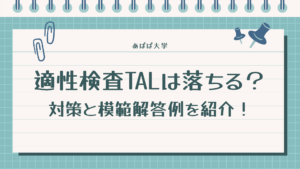最終面接が終わった後に適性検査が求められると「適性検査で落ちるのでは」「自分に不安要素があったのでは」と不安になりますよね。
この記事では、最終面接後に適性検査を求める企業の意図や、最終面接後の適性検査と合否の関係、検査を受ける時に気をつけるポイントについて解説します。
それでも最終面接は面接官との相性も大きく、合格率が低いのも事実(合格率は50%前後と言われています)
最終面接で落ちても最短2週間で内定をもらう裏技として、スカウトサイトABABAがオススメです。
ABABAでは最終面接まで進んだ頑張りが評価されて、優良企業25社からスカウトが届きます。もし選考途中で落ちてもそこまでの頑張りが無駄になりません。
また、ESや一次面接などがカットされているため、内定まで早くたどり着けるのも特徴です。
特に3月から就活後半にかけてはスカウトが増える時期なので、今のうちに登録を進めておくのがオススメです。
最終面接後に適性検査を行う意図とは?

企業が最終面接後に適性検査を行う意図は、足切りというよりは人材の見極めを目的としていることがほとんどです。そのため一次面接前の適性検査よりも、どのような人材なのか細かくチェックされます。
また、”『株式会社アイデム 人と仕事研究所』2018年卒新卒採用に関する企業調査“によると、適性検査の結果を採用で重視している企業は全体の15%弱であり、検査の結果を選考に活用しない企業も多いという結果が出ています。
適性検査の結果だけで合否が決まることはほとんどなく、面接や書類選考などの結果が重視され、検査結果は選考結果を判断するための補助的な材料になることが多いと言えるでしょう。
能力と性格の最終的な見極め

企業によって適性検査の種類は異なりますが、SPI形式を採用しているところが多い傾向です。企業側は就活生の学力や組織との相性のよさを確かめたいので、適性検査の結果をもとに採用するべきか検討します。
足きりとして落とされるケースはあまり多くありません。しかし能力検査の結果が乏しかったり、性格面に問題があったりすると選考で落とされる可能性は十分あります。
内定者の能力把握

最終面接後に適性検査を行う意図として、内定者の能力の把握を目的としている企業は少なくありません。内定者の学力はどれくらいのレベルなのか、どれくらいの平均点が取れているのか分析されます。
このような企業の場合は年度ごとに内定者の記録を取っているので、ある年度だけ記録を取らないということはほとんどないでしょう。
適性検査のコスト削減

適性検査は何かとコストがかかるため、経費削減のために最終面接後に導入する企業もあります。
受験にかかるコストは1人あたり約数百円〜数千円ほど。試験の種類によってはそれ以上の費用がかかるため、受験者の人数が増えれば増えるほどコストが膨大になります。
最終面接後の適性検査は落ちやすい?
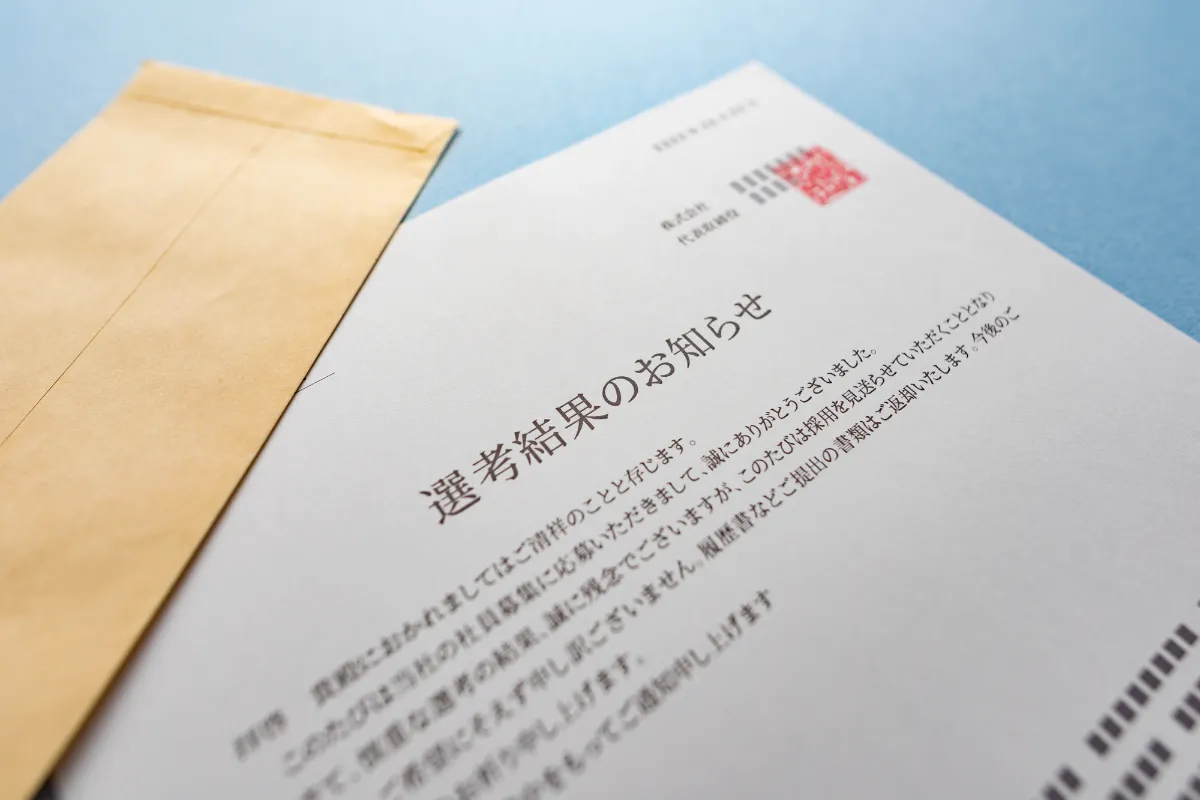
最終面接が終了した後に、適性検査を受ける企業があります。面接はうまく進んだ印象があっても、その後の適性検査で落とされる可能性があるのか、と心配する人も少なくないでしょう。ここでは、最終面接後に受ける適性検査の位置付けについて解説します。
最終面接後の適性検査が特に落ちやすいとは言えない
最終面接後の適性検査の選考通過率について、気になる就活生は多いことでしょう。最終面接後の適性検査は人材の見極めを目的としている企業が多いため、足きりで落とされる可能性は低いです。
ただし無策の状態で挑んでしまうと、適性検査で落とされる可能性は十分あります。そのため日頃から適性検査の対策を行うのが望ましいです。
参考:最終面接の合格率はどのくらい?合否を左右する条件と合格するための対策を解説
適性検査の評価は面接とセットになっていることが多い

最終面接後の適性検査は面接とセットになっているケースが多いです。そのため選考で落とされた場合は適性検査の結果のみならず、面接で落とされている可能性が十分考えられます。
もし選考結果が乏しくなかった場合は、適性検査の結果だけではなく面接での立ち振る舞いに問題がなかったか振り返るようにしましょう。
適性検査の種類
適性検査には、SPIや玉手箱など、数種類ありますが、いずれの検査も大別して2種類の検査で構成されます。ひとつは能力検査、もうひとつは性格検査です。筆記試験形式あるいはWeb形式で実施されます。それぞれの検査内容について、詳しく確認しましょう。
能力検査
能力検査は、採用予定者の基礎学力や論理的思考力を測定するためのテストです。おもに言語分野と非言語分野に分かれ、言語分野では語彙力や読解力、非言語分野では数的推理や論理的思考力が問われます。
企業によっては英語や構造的把握力の問題が出題されます。入社後に英語を使用する機会も想定しているケースでは、英語の読解力や語彙力が試されるでしょう。
構造的把握力は問題解決力や論理的思考の柔軟さを測るもので、ITやコンサルタント業務など、ロジカル思考が重視される職種で導入される傾向にあります。
能力検査について詳しくは、以下の記事を参照してください。
性格検査
性格検査は、応募者の性格特性や行動傾向を把握するためのテストです。質問紙法が一般的で、多くの短い質問に対して「はい」「いいえ」で回答します。これによって、協調性、責任感、ストレス耐性などの特性が評価されます。
受験者は正直に回答すればよく、対策をする必要はないでしょう。企業の目的は、その人のパーソナリティの把握です。採用する学生の価値観や考え方を理解するためで、採用対象者がどのような業務に向いているのかを、判断する材料にします。
性格検査について詳しくは、以下の記事を参照してください。
適性検査の通過率
適性検査の通過率は、応募者からは判断できないでしょう。適性試験は面接や採用試験と組み合わせて実施されることが多く、適性検査で落ちたとしても、応募者はそれが理由で落ちたと聞かされることがないためです。
また、適性検査の重要性は、企業によって異なります。参考にする程度の企業もあれば、面接と同等の選考過程と捉えている企業もあります。大企業を中心に、適性検査で足切りする企業も存在することは、頭の片隅に置いておきましょう。
適性検査に落ちる確率については、以下の記事を参照してください。
最終面接後の適性検査で落ちる原因
ここからは、最終面接後に行う適性検査で落とされる人の共通点について解説します。能力検査・性格検査の2つに分けて特徴を紹介します。
【能力検査で落ちる人の特徴】
【能力検査で落ちる原因】
時間配分ができていない
能力検査の難易度自体は高くないものの、時間配分には注意が必要です。時間配分を適切に行えないと、制限時間内に全ての問題を解けなくなり、落とされる可能性が上がります。
どの能力検査も出題問題数が多いため、短時間で多くの問題を処理しなければいけません。無回答の問題が多い、明らかに適当に選択するなどの事態に陥ると落とされる可能性が上がります。
試験や形式に慣れていない
適性検査に落ちる大きな要因のひとつが、試験形式に対する「慣れ」の不足です。SPIや玉手箱、GABなどはそれぞれ出題傾向や操作方法が異なり、初見では戸惑いやすく、時間内に解き終わらないこともあります。
非言語問題や計算問題では、時間配分の感覚が掴めていないと実力を発揮できない可能性があるでしょう。模試や過去問演習で検査に慣れておくことが、スムーズに問題を解き進めるポイントです。
受験形式についても、事前に把握します。例えばWeb受験の場合、検査は自宅で実施します。自宅のネットワーク環境やPCからのログイン方法を確認しましょう。
スコアが基準を満たしていない
時間内に答えられても、企業側の基準を満たしていないと落ちます。能力検査の出題範囲は幅広く、対策が不十分だと解ききれません。能力検査では全体的な基礎能力を見るため、バランスのよい対策が必要です。
また問題の出題形式を把握できておらず、解答に時間がかかるとスコアのロスが増します。
【性格検査で落ちる原因】
極端な回答が多い
続いて性格検査が原因となる理由をご紹介します。
性格検査は5段階の選択肢で出題されますが、「よく当てはまる」や「全く当てはまらない」などを選びすぎると落とされやすいです。
例えば、「これまで一度も嘘をついたことがない」や「自分の意見は絶対に曲げない」などの少し極端な質問に対して「よく当てはまる」を選んでいないか振り返ってみてください。極端な回答があまりに多いと、嘘をついている可能性があるとみなされる可能性があります。
回答に矛盾が多い
回答に一貫性があることを示すために似たような内容を質問された時には注意が必要です。たとえば、「自分の意見は絶対に曲げない?」という質問の後に「猪突猛進なタイプ?」と別角度で似た質問をされることがあります。
この場合に矛盾した回答をすると、自己分析不足や嘘をついていると判断される可能性があります。
回答にミスがある
性格試験は出題される問題数が多く、200から300問程度出題されることも珍しくありません。性格試験にミスはないと考える傾向にありますが、出題数が膨大だと、思わぬところでミスが発生します。
性格検査で発生しやすいミスは、無回答と回答数です。問題の数が多いため、うっかり回答をスルーする可能性や、複数回答を選ぶ問題でひとつしか回答を選択していないケースもあります。最後まで問題に答えた後、見直しを忘れずに実施しましょう。
最終面接後の適性検査で落ちないためには?【検査別対策】

最終面接後の適性検査に落ちないためには、日頃から対策を行うことが望ましいです。しかし就活生の中には、どのような対策方法がベストなのか迷っている方もいることでしょう。ここからは最終面接後の適性検査で落ちないための対策を能力検査と性格検査別に解説します。
【能力検査】
適性検査の種類や特徴を理解する
適性検査は有名なもので4種類あります。それぞれの特徴を把握して対策しましょう。
| 種類 | 特徴 |
| SPI | 最も多く使われている。前提知識が不要で、短時間で多数の問題に回答する必要がある。 |
| 玉手箱 | 検査にかける時間が他の適性検査より短い。スピーディーな回答が必須。 |
| CAB | IT関連企業で頻出している。論理的思考が問われるので対策必須。 |
| eF-1G | ほかの適性検査より難易度が高いので、対策が必須。 |
問題集を繰り返し解く
企業でどの適性検査が出題されるか分かったら、その適性検査の問題集を買って何度も演習を繰り返しましょう。最初は1回分を制限時間通りに解答して、自分の得意分野と苦手分野を把握すると対策しやすいです。
できるだけ苦手分野を減らし、高スコアを出せるようにしましょう。
対策アプリを利用する
忙しい就職活動の合間でもスマートフォンの対策アプリなら、通学や面接会場へ向かうすき間時間を有効に利用して、適性検査のシミュレーションが可能です。
多くのアプリは、言語・非言語問題を分野別に学習でき、間違えた問題の復習や進捗管理機能も備えています。
アプリは適性検査ごとに用意されています。SPI用の「SPI言語・非言語 一問一答」、玉手箱用の「玉手箱 問題集 解説付き」、クレペリン検査用の「クレペリン トレーニング」などです。エントリーする企業の適性検査ツールを調べて、アプリで事前対策を行いましょう。
時間配分を意識する
能力検査はスピード感が非常に大切です。問題集を解いて苦手分野をつぶした後は、解答スピードを上げる演習をしましょう。1問30秒で解くことを目標にするとよいでしょう。
【性格検査】
自己分析を徹底する
面接では分からない部分を把握するために行われるものが適性検査です。性格検査は企業との相性を見るためのツールという側面もあります。そのため、徹底した自己分析は欠かせません。自己分析を通して自身の価値観や性格を把握して、矛盾した解答が発生しないように対策しましょう。
嘘はつかない
「企業の社風に合うように答えよう」と考えない方がよいです。自分の考えと全く違う回答をすると、どうしても矛盾が生じてしまい嘘がバレてしまいます。そのため、適性検査では決して嘘をつかず、正直に答えましょう。
常識的な回答を心掛ける
性格検査の実施側面として、一般的な常識やマナーを備えているかを測る意味合いがあります。協調性や社会性など、採用後に会社に溶け込めるかを見ています。そのため、一般的な感覚からずれた回答をしないことが大切です。
性格検査の回答の基本は、自分に正直に答えることです。ただし、その答えが社会人としての道徳や倫理観に合致するかを確認しましょう。アプリを使って事前チェックをし、自分の考え方が自己中心的で、社会的な価値観に合っていないと判定が出た場合は、自分自身を見つめ直します。これを機に、社会人としての常識を再確認しましょう。
例題を解いておく
時間がかかりすぎると適性検査を通じて自分を十分に伝えきれません。能力検査と同じく例題を解き、どの程度のスピード感で解答すればよいかを把握しましょう。初見の質問でもすぐに答えられるようになるためには例題を解いておくことをおすすめします。
最終面接に向けての準備
適性検査対策に集中するあまり、最終面接の対策が疎かになっては本末転倒です。重要度でいえば、適性検査より最終面接です。最終面接で自分の存在価値を十分示せるように、しっかりとした面接準備と対策を施しましょう。
これまでの就活を振り返る
最終面接では、エントリーシートやこれまでの面接で伝えた内容との一貫性が重視されます。志望動機や自己PRに矛盾があると、企業側に不信感を与えてしまう可能性があります。
最終面接に臨む前に、自分がこれまでの面接でどのような内容を伝えてきたのかを振り返り、話に矛盾がないように整理が大切です。また、過去の質問やフィードバックからヒントを得て、より深みのある回答につなげることで、成長意欲や企業への理解をアピールできます。
会社と面接官について調べる
最終面接に臨むにあたって、企業研究をより深めることは重要です。事業内容や経営理念、今後のビジョンを改めて調べ直し、自身の志望動機や将来像とどのように結びつくかの整理が大切です。
その上で、最終面接の面接官になる可能性がある社長や役員、部門責任者についても、可能な範囲で調べましょう。名前や経歴、自社サイトやメディアでの発信内容をチェックして、人となりの理解を深めておくことで、より深い議論が可能です。
「REALME」で徹底的な自己分析ができる
能力検査は問題演習を繰り返すことが基本です。一方、性格検査対策で最も効果を期待出来る方法が自己分析です。最終面接後の適性検査が不安な人は、「REALME」をぜひ活用してみましょう。
AI分析で客観的な自己分析ができる
「REALME」はAI面接の結果をもとにあなたの強みや弱みを分析し、14項目の能力を点数化してくれます。自分の能力を数値で把握できるので、自分の長所や短所を客観的な視点で明確化できます。また、企業ごとに求められる強みが可視化されているため、自分にぴったりの業種や企業が分かります。
AI面接で志望企業の内定判定が分かる
「REALME」では、20分のAI面接の内容をもとに志望企業から内定をもらえる可能性を算出してくれます。あなたが志望する企業の最終面接をクリアした学生とあなたのデータを比較し、内定の可能性を割り出すという仕組みです。そのため、現在のあなたの立ち位置を客観的な視点で把握することができます。
また、志望企業の合格ラインをクリアした学生の面接回答例やESなどの閲覧も可能です。面接の回答方法や自己分析に自信がない人は、他の学生の回答例を参考にすることをおすすめします。志望企業の求める人物像を把握した上で自己分析をブラッシュアップできるためおすすめです。
適切なエントリータイミングが分かり内定率が上がる
志望企業の内定判定を確認すれば現在の立ち位置を把握することができるので、最適なエントリータイミングを把握することが可能です。AI面接は何度でも実施可能なため、大学受験の模試のように現在の就活状況に応じてあなたのスキルを確認しましょう
エントリー前に何が自分に足りないかが分かるため、面接対策や適性検査対策におすすめです。
最終面接前のみならず適性検査と面接対策はしっかり行おう

本記事では、最終面接後の適性検査の実態と受かるためのポイントについて解説しました。最終面接後の適性検査は面接の評価とトータルで判断しているケースが多く、落ちた場合には面接での受け答えに問題があると十分に考えられます。そのため少しでも希望の企業に就職するためには、面接対策と適性検査対策の両方に力を入れるのが望ましいです。
志望企業の内定判定率のを飛躍的に向上させ、面接や適性検査などさまざまな所で就活対策が可能な「REALME」をぜひ、活用してみてください。

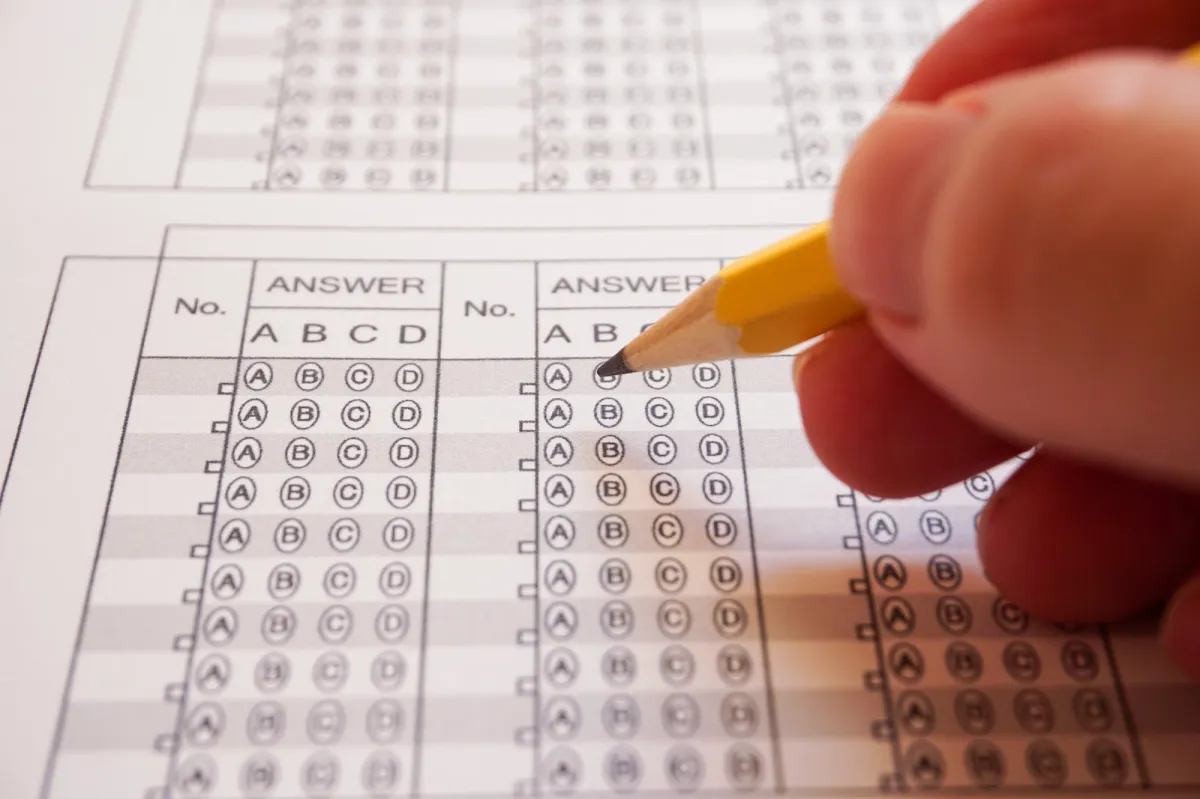
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)