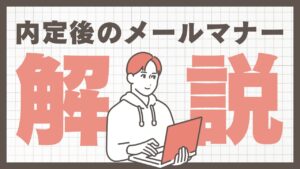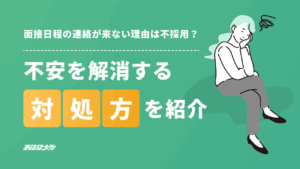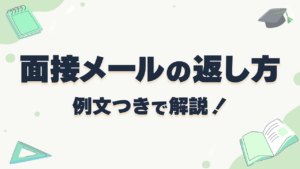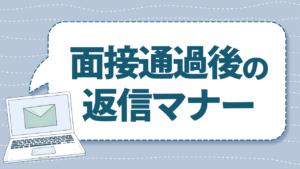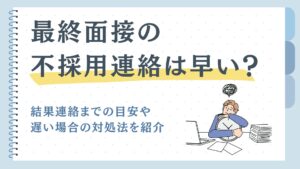新卒就活の面接では、学生時代に力を入れて取り組んだこと(ガクチカ)に関する質問が定番です。企業側は、ガクチカを通じて就活生の人柄や物事に取り組む姿勢を判断します。
ガクチカの内容に自信がなく、話を盛ったり少し嘘を混ぜようと考える人もいるかもしれません。この記事では、ガクチカで嘘をつくと生じるリスクや、嘘が許されないケースについて解説します。
株式会社ABABAの「REALME」は、AIと面接し、客観的な結果を提供してもらえるサービスです。ガクチカの作成にぜひご活用ください。
ガクチカの嘘はバレる?
面接でガクチカに関する質問をされたときに、事実と異なる回答をすると、嘘はどのようにしてバレるのでしょうか。以下で、ガクチカの嘘がバレやすい原因を3つ解説します。
深掘り質問に対応できない
ガクチカで嘘をつくと、深掘りをされたときに対応できないおそれがあります。一般に面接の場では、単発の質問から話を広げて他の質問が繰り返されます。一度嘘をつくと、話を広げて嘘をつき続けることは困難です。
例えば、エントリーシートに嘘のガクチカを記載した際、面接で関連する質問に対応できないケースが考えられます。即答できず考え込む姿勢が見られると、面接官に嘘と見抜かれる可能性があるでしょう。
内容に具体性がない
ガクチカの内容に具体性を持たせられないことも、嘘がバレる原因のひとつです。誰でも語れる表面的な内容のエピソードに終始すると、嘘を疑われます。
ガクチカでよく用いられるエピソードの例は、アルバイトやサークルでの経験です。経験談に嘘が入ると、エピソードの内容が薄くなり、聞き手は内容を想像しにくくなります。成果を示す数字や過程の説明がなければ、面接官に深掘り質問をされる可能性があります。そこで具体的な回答ができなければ、嘘と見抜かれるでしょう。
適性検査の結果と一致しない
新卒就活では、エントリーシートとあわせてWeb適性検査を実施することが主流です。ガクチカとしてアピールした内容が適性検査の結果とズレていると、嘘を疑われるでしょう。
例えば、ガクチカで「サークルのリーダーを務めた」とアピールしたにもかかわらず、適性検査で「リーダーよりもサポート役向け」と示されることがあります。適性検査での回答と、ガクチカで示した行動スタイルに矛盾が見られると、どちらかで嘘をついていると見抜かれます。
ガクチカで嘘をつくリスクは?
ガクチカでの嘘は、その場でバレなかったとしても後々リスクを背負うおそれがあります。ここでは、3つのリスクを紹介します。
嘘がバレると信頼を失う
面接中にガクチカの嘘がバレると信頼を失い、不合格につながるおそれがあります。企業側には多くの面接経験があるため、学生がつく嘘のほとんどは見抜かれるでしょう。ガクチカで語った嘘が一度バレると、そのほかの自己PRや志望動機の内容にも嘘が入っているのではないかと疑われます。
ビジネスの世界ではお互いの信頼関係が重要です。同僚や取引先に対して嘘をつく行為は許されないため、嘘がバレると合格の可能性はゼロに等しいといえます。
内定が取り消しになる可能性がある
面接の際についた嘘の内容によっては、内定を取り消されるリスクがあります。とくに、経歴や資格に関して嘘をつくと内定取り消しのリスクが高まるでしょう。実績に関する情報は、企業が採用の判断基準として利用するためです。
仮に入社まで嘘がバレなかったとしても、入社後に虚偽の事実が発覚するリスクを背負います。企業内での信用を失うだけでなく、懲戒処分や法的措置を取られるおそれもあります。
就職後のミスマッチにつながる
ガクチカで嘘をつくと、採用面接の場を乗り越えて無事入社できたとしても、ミスマッチが起きる可能性がある点がデメリットです。企業は、面接で把握した特徴や長所を踏まえて、新入社員の職種や配属地を決めます。面接で嘘をつくと、求められる役割や社風と、本来の自分にズレが生じます。
勤務先と自分の間に生じる価値観のミスマッチは、若手社員が早期退職する原因のひとつです。面接で本来の自分を表現できれば、自分に適した社風の企業や部署と出会えるでしょう。
ガクチカでついてはいけない嘘
ガクチカで嘘をつくことは、おすすめできない行為です。嘘がバレなければよいわけではなく、内容によっては発覚したとき大きなトラブルにつながるおそれがあります。以下で紹介する3つの事柄は、偽りなく正直に話しましょう。
学歴や職歴
学歴や職歴などのキャリアに関する嘘は経歴詐称にあたります。バレる可能性が高く、法的責任を問われるおそれもあるため虚偽の申告は厳禁です。学歴を詐称し、仮に内定がもらえたとしても、卒業証明書の提出を求められる際に矛盾が生じ、すぐに詐称がバレます。
また、入社後に社会保険の手続きをしたときにも、過去の加入期間に矛盾が生じてバレるケースが多くあります。そのため、アルバイト先に関する嘘は控えましょう。
資格や免許
ガクチカで資格や免許取得を題材とする人は多い一方、資格や免許などの専門性が求められるものに関する嘘はバレやすいため、リスクが高いといえます。
新卒就活では資格がアピール材料として有効です。しかし、未取得の資格や免許を、持っているかのようにアピールしたとしても、合格証や認定証明書の提出を求められると、その時点で嘘がバレます。とくに、業務上で必須であると定められている資格の未取得が発覚すると懲戒処分を受ける可能性が高いでしょう。
成績や出席日数
大学の成績や出席日数に関する嘘は、資料を調べると簡単にバレます。大学での過ごし方を選考で重視する企業が一定数存在します。成績や出席の状況をよく見せるために、ガクチカで水増しして書こうと考える就活生もいるでしょう。
「通算成績で1位だった」「講義や研究に毎回出席した」などの嘘をついたとしても、成績証明書や卒業証明書の提出を求められるとすぐにバレます。大学から公に認定されている事実を偽ることは避けましょう。
ガクチカで許容される嘘
ガクチカでは基本的に嘘はタブーですが、内容によっては多少の脚色であれば容認されるケースも存在しています。ここでは、ガクチカで許容される嘘についてご紹介します。ただし、嘘や脚色自体のリスクは変わらずに存在している点に留意しましょう。
事実を脚色したエピソード
ガクチカでは、事実を脚色したエピソード程度であれば、多少の嘘も許容される場合があります。たとえばアルバイト経験のガクチカで「過半数のお客様が満足した」という表現を使うとします。この表現は、実際に満足したお客様が51%程度の際も使用可能です。なぜなら「過半数」とは、全体の半分を少しでも超えていれば使える言葉だからです。
とはいえ一般的な「過半数」という言葉は、半分を少し超えた程度では不足している印象を受けますよね。そのうえで、「正しい言葉遣いであること」を前提に脚色することは、ガクチカにおいて許容されるケースがあるでしょう。
自分のアピールポイント
自分のアピールポイントに関しても、多少の嘘が許される場合があります。なぜなら自分の性格や強みに関する説明は、自分の主観に基づくからです。たとえば「忍耐力の強さは普通に毛が生えた程度」と認識していても、「私の強みは誰にも負けないほど高い忍耐力です」と言っても構いません。
ただし自分の強みを脚色する際は、説得力を強めるためのエピソードが必要です。エピソードにまで嘘を取り入れると、整合性を取りにくくなってしまいます。事実が根拠として存在しているアピールポイントを、効果的に引き伸ばしましょう。
ガクチカの本筋に影響しない小さな嘘
ガクチカの本筋に影響しない小さな嘘も、許容されやすい傾向にあります。面接では緊張のあまり、咄嗟に小さな嘘をついてしまうことがあります。今までの内容と矛盾する嘘や、最終面接にまで影響を及ぼすような嘘でなければ、大きく気にすることはありません。
ガクチカの例では、ゼミやサークルの人数を多少間違えたところで、本筋には関係ありませんよね。ただし所属するゼミや研究している対象のような、エピソードの本題に関連する嘘をつくのはタブーです。
どうしても嘘をつきたい時の対処法
ここでは、ガクチカでどうしても嘘をつきたいときの対処法をご紹介します。嘘の衝動に駆られてしまうときは、自分の心理状態を分析することが大切。自分の心の強さや弱さを振り返り、必要以上に嘘をつかなくてもアピールできる状態を目指しましょう。
嘘をつきたいのは「自信がないから」
ガクチカで嘘をつきたくなってしまう理由はさまざまです。
- 自分のガクチカに自信がなく、過小評価されるのが怖い
- 周りのガクチカのほうが優れているので、劣等感を抱いてしまう
- 自分を大きく見せることで、優秀な人材であることをアピールしたい など
まずは自分の心理を深掘りし、嘘をつきたい理由を理解することが大切。「ガクチカで大切なのは、インパクトではなく過程や学びである」と認識したうえで、他人と比べる心を手放しましょう。
自己分析してガクチカをブラッシュアップする
ガクチカで嘘をつきたい心理として、自分のガクチカの質が低いことが挙げられます。アピール力に欠けていると自覚しているからこそ、嘘や脚色によってインパクトを与えたいのです。
対処法としては、自己分析してガクチカをブラッシュアップすることが挙げられます。過去の経験を振り返り、感情や着眼点、課題に対する行動などのアプローチを変えていきましょう。一見するとありきたりなガクチカであっても、文章の構成や表現を変えることで、より印象的になるはずです。
企業が知りたいことを理解する
ガクチカで嘘をつきたくなる人のなかには、「自分を優秀な人材に見せたい」という気持ちが空回りしているケースもあります。企業が知りたいことを理解し、ニーズに沿ったガクチカを作成するように努めれば、嘘の必要性も減ってきます。
嘘をつきたくなるほど不安を抱える理由は、企業が「自分の何を審査しているのか」がわからないから。企業がどのような人材を求めているのかや、ガクチカを求める意図を適切に把握できれば、余計な脚色をせずに自分をアピールする方法を探せます。
面接で嘘と思われないためのテクニック
ここでは、ガクチカを含む面接において、面接官に嘘だと思われないためのテクニックをご紹介します。たとえ本当の話をしていても、伝え方によっては嘘っぽく伝わってしまうこともあるでしょう。誠実さをアピールするコツをつかみ、誤解なく内容を届けましょう。
自分だけの経験や学びを盛り込む
面接で嘘だと思われないためには、自分だけの経験や学びを盛り込むことが推奨されます。抽象的なエピソードや詩的な表現は、真偽を疑われてしまいがち。体験談や知識に具体性があるほど、信ぴょう性が高まります。
とくに固有名詞や数字を盛り込んだエピソードは、説得力が上がると同時に論理的な説明にもつながります。自分ならではの性格・感性・知識・着眼・発見をアピールできるエピソードを中心に、オリジナリティの高い文章を作成しましょう。
ESと面接で一貫性を保つ
面接で嘘を疑われないためには、エントリーシートと面接の内容で一貫性を保つことが重要です。たとえばエントリーシートでアルバイト経験についてアピールしていた人が、ガクチカではゼミ活動について語ってしまうと、「結局1番頑張ったことは何?」と疑問を抱かせてしまいます。
全体の一貫性が揺らぐほど、たとえ真実の内容でも嘘っぽい印象に。エントリーシートは提出する前にバックアップを取り、面接で話す予定の内容と整合性が取れているかどうかを確認しましょう。
質問と回答を想定して矛盾を洗い出す
面接における嘘っぽさを解消するためには、繰り返しの練習が効果的です。たとえば面接で想定される質問をリストアップし、回答の回数を重ねていきましょう。質問と回答のやり取りが多いほど、矛盾している内容を洗い出しやすくなります。
AIに質問を何十個か作ってもらい、ある程度回答を送信したうえで「上記の私の回答に矛盾はない?」「回答のすべての一貫性が保たれている?」と質問する方法もおすすめです。面接を練習するほど、本番でうろたえるリスクも減り、咄嗟の嘘もつきにくくなっていきます。
「REALME」を活用して嘘の無い自分の魅力を見つけよう!
「REALME」は、AI面接を行うことによって志望企業の内定判定を算出できるサービスです。ガクチカとして話した内容をAIに分析してもらうことで、自分の強みや特徴を理解できます。嘘のないガクチカを用意し、面接でのアピールにつなげましょう。
自分の強みと弱みを客観的に分析
「REALME」のAI面接で、自分の強みと弱みが把握できればガクチカでアピールする内容を明確にできます。分析できる能力は、「問題解決力」「成長意欲」などの14項目です。
自分の長所をガクチカに落とし込み、説得力のある自己PRをしましょう。自己分析ができていれば、ガクチカで嘘をついて自分を良く見せようとする必要はなくなります。
現時点の志望企業の内定判定を確認
志望企業の内定判定が分かる点は、「REALME」のAI面接が持つ最大の特徴です。合格ラインに達した就活生の平均能力値と比較することで、内定判定を算出する仕組みです。判定は、AランクからEランクをそれぞれ2区分ずつに分けた10段階で評価されます。ガクチカの質を高めて、より高いランクの内定判定を目指しましょう。
合格ラインの学生のガクチカが見られる
「REALME」では、企業の選考通過ラインに達した学生のガクチカや自己PR、価値観などのデータを参照できます。優秀な就活生はどのようにガクチカを組み立てているのかが確認できるため、嘘をつかずガクチカに説得力を持たせる方法が学べます。選考の際に、志望企業がガクチカを評価するポイントも理解できるでしょう。
ガクチカには嘘を書かずに自分をアピールしよう!
今回は、ガクチカで嘘をつくと生じる面接中のデメリットや、入社後に起こりうるリスクを解説しました。安易な嘘がバレると信用を失う結果につながり、責任を問われるおそれもあります。
ガクチカに悩んでいる方は、「REALME」をぜひご活用ください。AI面接による自己分析や、優秀な就活生のガクチカを活用し、嘘のないアピールに取り組みましょう。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)