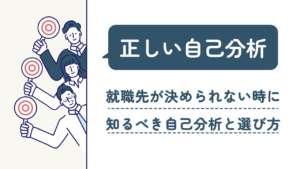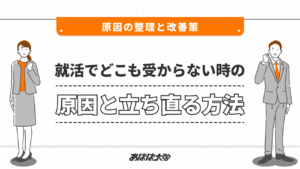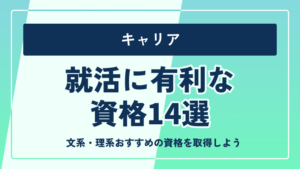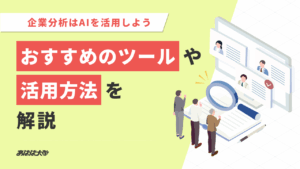面接において、企業が知りたいポイントの一つが「ガクチカ」。 今回は、ガクチカの作り方やアイデア、作成時のポイントなどをご紹介します。テーマ別の例文も解説していきますので、面接でガクチカを活用する予定の人はぜひ参考にしてくださいね。
ガクチカとは何か?定義
ガクチカの意味とは、「学生時代に力を入れたこと」です。就職活動でよく使われる用語であり、エントリーシートへの記載や、面接の定番質問として使われます。企業はガクチカを通じて、応募者の個性や価値観、仕事への取り組み方などを知ろうとします。
ガクチカには「これを書けば絶対に内定を取れる」というものはありません。もちろん特別な経験や実績は注目を集めますが、大切なのは「ガクチカによってどのような経験を得たか」。そして「得た経験がどのように企業に反映されるか」です。
ガクチカの作り方アイデア一覧
ここでは、ガクチカの作り方におけるアイデアをご紹介します。ガクチカのおもな記載内容は、学業・アルバイト・部活など、学生時代の経験全般が対象です。自分の経験をあらためてリストアップしたうえで、企業の印象に残るガクチカを作成していきましょう。
アルバイト、サークル、学業、趣味など幅広く経験を洗い出す
ガクチカの作成では、アルバイト・サークル・学業・趣味など、幅広い経験を洗い出すことが大切です。自分の日常に溶け込んでいた習慣でも、いざ明文化することで大きなアピールポイントになる可能性があります。
多様な経験を棚卸しすることで、自分の強みや成長エピソードを見つけやすくなるでしょう。たとえばアルバイトの接客やリーダー経験、サークル運営、学業における研究、趣味の挑戦なども、立派なガクチカの一つです。
小さな挑戦や日常の努力も立派なガクチカになる
ガクチカは、誰もが羨むようなキラキラした内容である必要はありません。個人レベルの小さな挑戦や日常の努力も、立派なガクチカになります。なぜなら企業は、成果の大きさよりも、継続的な努力や課題への主体的な取り組みを重視しているからです。
たとえば同じ「偏差値65」でも、偏差値60の人が上げるより、偏差値45の人が短期間で上げたほうが、自己PRのインパクトとしては強いですよね。ガクチカの作り方で大切なのは、結果や事象そのものではなく、プロセスでの工夫や身につけた能力・経験なのです。
身近な経験から探す
ガクチカを作成する際は、身近な経験から探すことをおすすめします。「ガクチカには特別な経験が必要」という固定観念を捨て、より日常的な取り組みにピントを合わせてみましょう。企業は大きな成果よりも、日常の課題解決や成長の過程を重視しています。
たとえば自分では「アピールポイントはアルバイトを頑張ったことしかない」と思っていても、視点によっては大きなガクチカに。アルバイトでの接客改善や、チームをまとめるために取り組んだ事柄など、小さなことから実際の体験・工夫をリストアップしてみましょう。
ガクチカ作成時の注意点・ポイント
ここでは、ガクチカを作成する際の注意点やポイントをご紹介します。ガクチカは、内容が美しくまとめられているだけでは意味を為しません。ガクチカによって得られた経験を「企業や働き方にどのように反映させるか」を踏まえたうえで、効果的な内容や方針を作成していきましょう。
企業の事業や価値観と全く関係のない話題は避ける
ガクチカの作成では、企業の事業や価値観とまったく関係のない話題は避けるべきです。なぜなら企業が知りたいのは、応募者との価値観の一致だからです。企業はガクチカから、応募者が企業文化や理念にどれだけフィットできるのかをチェックしています。
またガクチカや企業に関連性があると感じても、宗教・政治・野球などの話題は信頼関係を損ないかねないためタブー。TPOを踏まえたうえで、企業との共通点や関連する話題を選ぶことで、限られた面接時間のなかで適切な信頼関係を築けます。
体験談や具体的なエピソードを盛り込み、オリジナリティと信頼感を出す
ガクチカを作成する際は、体験談や具体的なエピソードを盛り込みましょう。面接官は、今まで何百人ものガクチカを聞いています。定例文を使ったような当たり障りのないガクチカでは、面接官の印象に残りません。場合によっては「コピペのようだ」と悪印象につながるケースもあるでしょう。
ガクチカで好印象を残すためには、オリジナリティと信頼感が重要です。実体験に基づいたストーリーはリアリティや共感を産み、ガクチカに説得力を与えてくれます。結果だけではなく、成長の過程や取り組みの経験などを描写することが大切です。
高評価を得るために必要な要素を抑える
ガクチカで高評価を得るためには、「面接官がガクチカに求める要素」を抑えましょう。取り組みの表面的な事実よりも「どう取り組んだか」、得た能力の説明よりも「入社後に能力をどのように活かせるか」が大切です。
具体的なエピソードや数字を使い、課題解決の過程や学びを論理的に伝えるように心がけましょう。企業が求める視点を理解するためには、企業の価値観やミッションと重なる経験を選んだり、企業の歴史や取り組みを調べたりする過程も求められます。
【テーマ別】ガクチカ例文5選
ここでは、面接に使えるガクチカの例文を5つご紹介します。もちろん、このままコピペで使うのはNG!あくまで参考としつつ、自分ならではの経験を取り入れながら作成してみてくださいね。言葉選びの一つひとつにも、個性や価値観が反映されるのがガクチカなのです。
【例文】アルバイト:飲食店
大学時代に、飲食店のホールでアルバイトを経験しました。「ピーク時の注文遅延・提供ミス」という課題を解決するために問題を分析した結果、スタッフ間の連携不足が原因という仮説を立てました。
解決法として繁忙時にリーダーを設置し、声掛けルールを導入。その結果、提供時間を平均〇%短縮し、クレームも〇%減少しました。この経験で、臨機応変な対応とコミュニケーション能力を身につけ、主体的に課題解決に取り組む姿勢が身につきました。
【例文】部活
大学のバレー部でキャプテンを努めました。当時の課題は、試合での連係ミスや、部員同士のメンタルのバラつきでした。課題解決のためにメンタルケアを兼ねたミーティングや、ロールプレイでの練習を導入し、部員全体の状態を共有するためのシートを作成しました。
その結果、〇カ月後には試合中のミスが〇%減少。地区大会では予選敗退していたのですが、〇位に入賞することもできました。この経験で得たリーダーシップやコミュニケーション能力を、御社での〇〇な働き方のなかで活かしたいと思っています。
【例文】ゼミ
大学ゼミで地域活性化プロジェクトに取り組み、商店街が衰退する原因を分析しました。グループで役割分担をしながら文献調査やヒアリングをおこない、進捗共有や定例会を通して連携を教科しました。
提案内容はゼミ内の発表で高評価を得て、一部のアイデアは実際に自治体に採用され、地域の貢献につながっています。この経験を通じ、課題発見から解決まで論理的に進める力や、協働力・調整力・主体的に行動する姿勢が身につきました。
【例文】サークル
大学の英語ディベートサークルで、部内の議論力格差という課題に直面しました。そこでメンバーをレベル別のグループに分けて、模擬対戦やフィードバックを定期実施。加えて、全体共有会でお互いの課題を発表し合う場を設けました。
その結果、議論力の底上げに成功し、サークル主催大会ではチーム入賞を果たしました。ここで得たのは、主体性を持った課題解決力・チームを巻き込むコミュニケーション力です。
【例文】留学
私は大学2年時、カナダの大学で半年間交換留学を経験しました。授業や日常で言語・文化の壁に直面した際には、現地学生と積極的に交流し、課題設定会や文化体験イベントを企画・参加しました。
結果、語学力が向上し、多様な価値観を理解できるようになりました。この経験を通して、異文化適応力・主体性・課題解決力が身につき、グローバルで活躍する仕事に貢献できる自信を得ました。
REALMEを利用してガクチカをブラッシュアップ
「ガクチカの作り方がわからない」「ガクチカの内容をさらにブラッシュアップしたい」と思っている人におすすめのサービスが、REALMEです。ここでは、REALMEの特徴やガクチカ作成での活かし方などをご紹介します。
強み・弱みを見える化し、ガクチカの説得力アップ
REALMEではAIとの面接を通じて、自分の強みや弱みが可視化されます。
自己分析が進んだ結果、ガクチカ内で描写するエピソードに一貫性が生まれ、説得力を向上できるのが魅力です。自身の非認知能力は14の項目でグラフ化されるため、自分でも気づけなかった強みを把握しやすい仕組みとなっています。
合格者のガクチカ事例を比較・参考
REALME最大の魅力といえるのが、志望企業の「内定判定」をエントリー前に確認できるシステムです。
過去に合格ラインを突破している(=希望の企業の最終選考まで進んだ)就活生の平均能力値を閲覧でき、自身に足りていないポイントを客観的に理解できます。内定判定は企業によって異なるからこそ、ニーズに応じた能力値を事前に把握できるのは大きなメリットといえるでしょう。
志望企業の内定可能性を事前に把握
企業へのエントリーでは「内定の可能性が高い時期を選びたい」と思いますよね。その願いをかなえてくれるのが、REALMEの内定判定機能です。
REALMEでは自社のデータを活用し、「企業が求めている合格ライン」の目安をチェックできます。結果によっては、より内定率が高いタイミングにエントリーをずらすことも可能です。
ガクチカ作成とAI活用で就活を成功に導こう
今回は、ガクチカの意味や作成時のポイントなどをご紹介しました。
ガクチカでは自己PRとは異なり、「強みや能力」だけではなく「経験のプロセス」を重視します。とくに「主体性や行動力」は、例文でも複数挙げたように重要なポイントです。
ガクチカを通して入社後の姿を想像してもらうために、具体的なエピソードを混ぜながら成長過程をアピールしましょう。

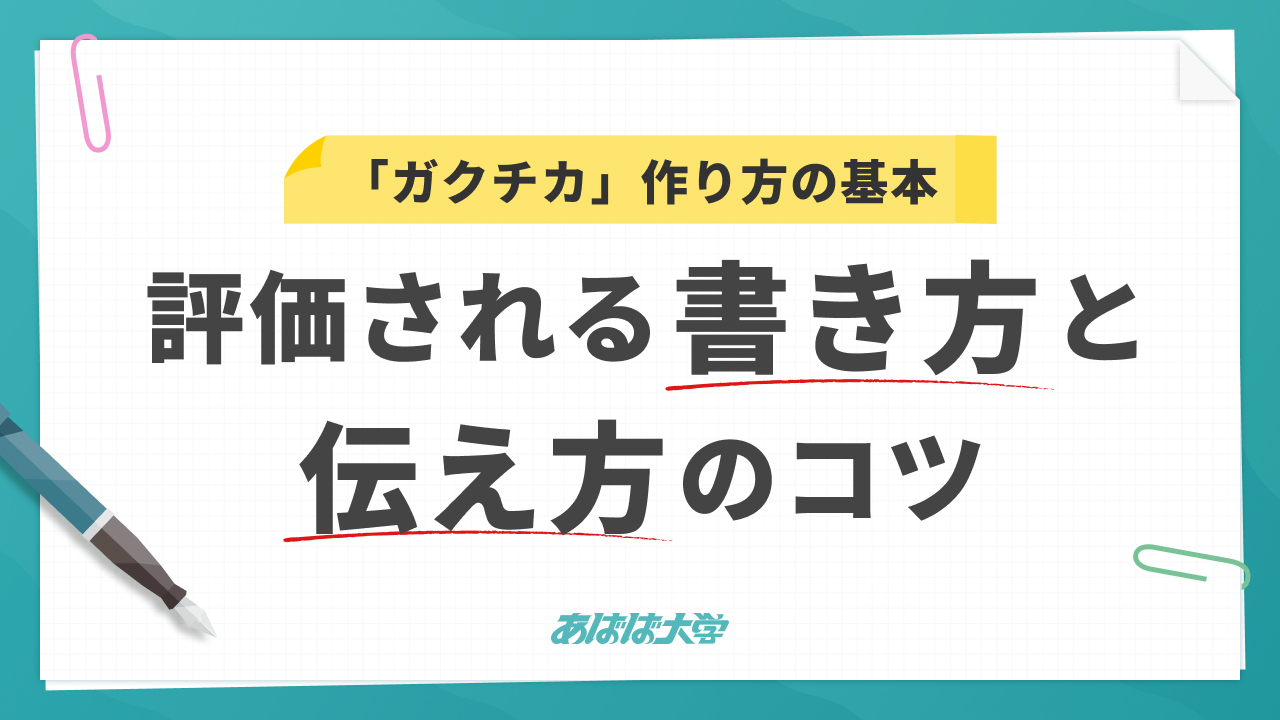
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)