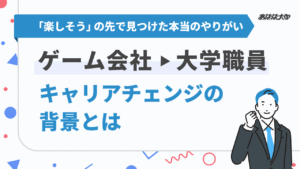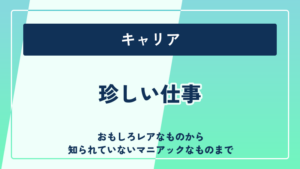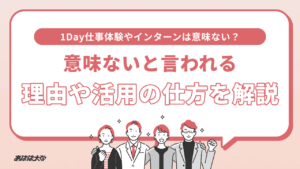進路や生き方について鋭い視点で切り込み、若者から大人まで幅広い支持を集めている岸谷蘭丸さん。この度、YouTube「あばば大学」にもご出演いただいた。
今回のインタビューでは、就活を諦め本名公開の決断に至るまでの心境の変化、自分らしいキャリアを歩むためのヒント、もし自分が就活していたらについて率直に語っていただく。

Youtube「ホンネ会議」での収録を振り返って
──まず、本日の収録はいかがでしたか?
楽しかったです。本当に楽しかった。なんだろう、学生が可愛く見えて、もう自分がおじさんになったのかなって思いました(笑)。年齢的にはそんなに変わらないんですけど、学生同士で話しているのを見ていて、「この後飲みに行くのかな」みたいな雰囲気がすごく分かって。いいなあ、俺も行きたかったなと思って。
女子も可愛いし、美男美女が多くて。
──確かに皆さん若々しくて素敵でしたね。
24歳なので、そんなに変わらないはずなんですけど、若いなって感じました。
就活を検討し始めたきっかけ
──今回の番組に集まっていただいたのが、18歳から25歳くらいまでの直近で就活を終えた、あるいは今就活をしているような方々でした。蘭丸さんご自身も2024年10月頃まで就活を検討されていたということですが、そもそも就活を考え始めたきっかけは何だったのでしょうか?
やっぱり「みんなするから」が大きいですよね。中学に行ったら高校に行くよね、ぐらいの感じで、大学に行ったら就活するよね、ぐらいのものが存在すると思うんです。視野には嫌でも入ってきちゃう。イタリアの大学でも、みんなそうですし。
それと、うちの大学は結構金融とかに行く人が多いんです。「ゴールドマン・サックスに行きます」みたいな人が本当にいるんで。「もったいないな」っていう葛藤がありました。このまま行けば、キラキラキャリアを手に入れられるのに、それを捨てていいのか。それが一番悩みました。
──実際に就活に取り組まれた期間はありますか?
ほぼないですね。ESを書いてみようと思ったりとか、資料をもらったりとか、友達からちょっと話を聞いてみたりもありました。でも、ちょっとやりたくないなっていう…結局、頑張れなかったですね。
働くこと自体はやってみたかったんです。トップファームで働いてみたい気持ちはめちゃくちゃあって。自分が力がなさすぎるっていうのをすごく思ってたんで、ちゃんと労働者として鍛えてもらえるじゃないですか。それが羨ましくて。強度の高い環境でやりたいっていうのが実はあったんで、働くこと自体はやってみたかったんですけど、就職活動っていうのが本当にやりたくなくて。

就職活動への違和感
──就職活動のどういうところが面倒だと感じられたのでしょうか?
同じ髪型して、ダサいリクルートスーツ着て…まあそれは高いやつを買えばいいだけなんですけど。同じところに行って、就職活動に勝つためのレースがあるじゃないですか。そこをゴールとしたときに頑張れなかった。
もっと言うと、お金のために頑張るっていうモチベーションがあんまりなかったっていうのが、でかかったかもしれないです。「なんとしてもお金と地位を得てやる」みたいなのが、あんまりできなくて。
ボストンキャリアフォーラム(グローバル人材獲得のための世界最大級の就活イベント)の特待枠ももらってて、飛行機のチケットまで取ってたんですけど、1週間前にやめました。チケットを破り捨てて、「よし、本名公開しよう」みたいな流れですね。
──1年ぐらい悩まれたということですが…
そうですね。一般的には「もったいないから」って言われるじゃないですか。ここまでキャリアを積んで、やらないって、さすがにじゃん、みたいな。「1年でもいいから働いてみなよ」っていうのは、僕が聞かれたら全く同じことを言うと思うんで。
でも、それはできなかったですね。やっぱり自分の中のいらないプライドもそうだし、謎のプライドと、そこまでお金に困ってなかったみたいな、乾いてなさみたいなこと。乾いてるやつには勝てないんですよね。
本名公開という決断
──就活を辞めて、本名を公開して活動するという決断には、どういう思いがあったのでしょうか?
二択としては、就活を頑張るか、会社を頑張るか。会社にベットできるかどうかっていう、そこだったんです。
創業して1年ぐらいは本当にだらだらしちゃってたんで、何もやってないし、本当にしょうもない学生ベンチャーの失敗例みたいな感じだったんで。就活をするか、会社を頑張るかで、じゃあ会社を頑張ろうって決めたんです。
会社を頑張るってことは、一社会人、一起業家として世の中に出ることだし、それが偽名はおかしいな、と。特に教育だったんで、会社のホームページではもう普通に本名と顔を載せるのは決まってたんで。
また、面白おかしく書かれるのも嫌で。だったら、ちゃんと身一つでというか、批判も受けるだろうけど、ちゃんと言った方が絶対やりやすいよなっていうのもあったし。
本名を公開していないからLinkedInも作れないような状況で、普通に社会人として名刺も配れないような状況だった。もう、そういうところから脱したいな、重しを捨てたいなっていうのもありました。
現代の若者の生きづらさについて
──今回のYoutube撮影では若い世代が生きづらさや同調圧力を感じているというトークテーマがありました。そんな中で、蘭丸さんご自身はどのような価値観や判断軸で進路を選ばれたか教えてください。
はみ出しづらいっていうのはやっぱりあると思います。それは日本はかなりありますね。僕、今日半袖だし、裸足だし(笑)。普通はみんなやらない、しないのかなっていう自覚はあるんですけど。
僕はもう、はみ出しちゃったんで、中学の時点でもレールから逸れて。一回はみ出すと意外と怖くないんです。はみ出すとめちゃくちゃ日本は生きやすいんですけど、はみ出せないと生きづらいだろうと思って。
一回就職するってなって、はみ出したものがまたみんなと同じに戻るのもなんか変だし、どうせはみ出すんだったらもうはみ出し続けていこうかなっていうこともあります。
──自分への理解を深めることが重要だったということですね。
そうです。自分の原体験みたいなものは、振り返ったと思います。なんでこういう価値観になったんだろう、とか、今の自分が捨てられないものって何だろう、なんなら妥協できて、逆になんなら妥協できないかなみたいなのは、すごく考えて。
たぶん自分への理解がすごく深まったと思います。就活を悩むっていうフェーズで結構自分への理解が深まったんで、それはいい意味でも悪い意味でもですね。自分のダメなところはここだから、もうこれは変えられないから、逆算的にそこを強みにしなきゃいけないな、とか。
逆に意外と大人になるとちょっと生きやすくならないですか?学生時代って生きづらくないですか。
やっぱり大人って責任がある代わりに自由を得られますよね。気持ちいいですよね。こんな自由なんだ、20歳でめちゃくちゃ気持ちよかったですもん。

就活生へのアドバイス
──これから就活をしようと考えている学生は、どういった判断軸で進路を選んだ方がいいと思いますか?
どれだけ自分がそこにこだわれるかじゃないですか。やっぱりこだわりって、その人の人間性だし、キャラクターだから。どこまでこだわれるかな気がしてて。
絶対にこうだっていう、負けないものがあるやつがやっぱり勝っていくし、就活は長距離走でもあるし、本当に綺麗にレールの上を走れるかっていう勝負をさせられてるから。結局、コミットメントをどこまで高められるかみたいな勝負なのかなと見ていても思います。
自分が絶対に捨てられないこだわりは何だろうっていう、そこがやっぱりぼやっとしてると、就活軸としてもぼやっとするし。「俺はこういうことがしたいからこの会社に行きたいんです」っていう軸って、やっぱり絶対なきゃいけないと思うんで。
この軸がないやつはバレるし、大人は長く生きてるからバレるじゃないですか。18年生きてきたぐらいの嘘ってすぐバレるので。
──目的を明確にすることが重要ということですね。
そうです。目的がちゃんと明確になってないと、目標も立てられないから、業界も決まらないし、企業のレベル、年収のレンジも決まらないし、働き方も決まらないし。
やっぱり目的の部分がぼやっとしてるっていうのは、目標が決まらないし、目標が決まらなければ手段も決まらないし。みんな手段で悩んでるんですけど、手段じゃなくて、まず目的から考えるべきで。
そういう自己分析、自分の原体験、譲れないものみたいなのって何だろうっていうのは、一番就活軸としてはいいんじゃないかなと思うし、それは年収でも全然いいと思います。
岸谷さん自身の進路選択
──岸谷さんご自身のこだわりについて、もう少し詳しく教えてください。
僕の場合は結構、アメリカに行くか、早稲田に残るかを悩むときにめちゃくちゃそれで悩みました。アメリカに行った方がお金が稼げそうみたいな。早稲田では本当に堕落してたんで、ここから頑張る未来はもう見えなかった。
その時は生活水準を下げられるか否かっていう悩みをめちゃくちゃして、やっぱり下げられない。もうこれ本当にリアルな話、やっぱり下げられんなと思って。じゃあもうそれは軸になるべきだなって。生活水準を下げないためにはどうすればいいんだろう、やっぱり勉強頑張って結果を出さなきゃいけないし、こうこうこうしなきゃいけないしっていうのが、目的の部分がすごくクリアになったんで、目標が出てきて、目標を細分化していって、今年はこれを達成しよう、今月はこう頑張ろう、ここの成績はこうしよう、高校はこの成績だし、大学はこのくらいの成績だし、っていうので。
──理想の自分像についてはどう思いますか。
他にもいろいろありはして、要素としてはぼやっとしてるんですが、自分がどういうキャラクターでいたいかとか、周りにどう思われたいかとか、どういう存在で自分を認識してたいかっていう。自分が理想とする自分と、周りが今評価している自分の評価っていうのが全然違ったんで、本当は俺はもっといけるはずなのに、評価されてねえっていう気持ちだったんで、この自分の、本当はもっといけるはずなのにの自分の理想像を下げるっていうのはできなかったんですよ。
やっぱりなんか、ちやほやされたいし、モテたいし。みたいな、本当に純粋な、こうあるべき、俺はこうあるべきだが、達成されてなかったのが許せなくて、俺はこうあるべきだに、コミットしようって、そこ妥協して俺は適当でいいやと思ったら、そこそこでいいやって思えなかったっていう。突き抜けたいと思ったっていうか。
一定、なんかしらは頑張ったほうがいい。頑張りたくないと思っている学生って言ってもそんなにいない気がしていて、本当は頑張りたいんですけどなんかしらの要因で頑張れていなくて。なんで僕私は頑張れていないんだろう。泣き泣きみたいな。
頑張れていないのは環境のせいだから。環境と目的の設定が甘いから。頑張れないなら環境を変えること、目的をしっかりと設定すること。ただ、大それた目的を立てる必要はないと思っていて、例えば絶対に東京に住みたい。でも八王子でも耐えるか、とか。譲れないラインをしょぼいものでも細分化していくべきだなと。
僕らも海外大学受験のサポートをしているので、絶対に聞くのは、田舎か都会かどっちがいいか、これは最初に聞くようにしてます。
自己分析の重要性と方法
──自分のこだわりを見つけるためには、どう動いたらいいと思いますか?
岸谷:壁打ちですかね。とにかく壁打ち。これはもう、どこに行っても絶対に変わらないと思うんですよ。とにかく人に話すとか、書く、書き出すとか、アウトプットしてみる。
特に現代病ですけど、インプット量があまりにも多すぎて、その情報の整理ができてなくて、頭の中でずっと、ゴミみたいなのがいっぱい溜まって。何も整理できてないような状況がすごくある気がしてて。
やっぱりとにかくアウトプットして壁打ちすること。会話して、人に話して。「この方がいい気がするんだよね」とか、「自分の強みは分からないんだよね」って、めっちゃ聞くべきですね。
就活ガチ勢の子たちはめっちゃやってるし、「強みは俺何だと思う?」っていうのは友達に聞きまくる。意外と友達は見てる。だからやっぱり、人に聞くべきだし、自己開示するべきだし。
自己開示するのが怖いとか、強みがないのが怖いとか、そういう怖さは乗り越えないと、やはり出てこないし。自分の弱さと向き合うことになるのがすごく必要かなと思って。本当に壁打ちしかないと思います。
AIの活用について
──自己分析にAIを活用するのは有効だと思いますか?
岸谷:これは本当に有効だと思う。そういう使い方をするべきだし。本当に単純な壁として使うのは、本当にAIって有能だと思って。真に受けすぎて鵜呑みにしすぎるのは良くないけど、練習相手としては全然いいです。
矛盾点を指摘してくれって言えば、AIの得意なことって一切の矛盾のない文章をはじき出すみたいなのが本当に得意なんで。矛盾点を指摘しろって言ったら、いくらでも矛盾点を指摘してくれるし、おかしいところもいっぱい言ってくれるし。
そうすると、それを考えるっていう作業が生まれるし、考える時に逆に「なんでだろう」って言って聞いてみたらいいと思うし。
それこそ今では面接練習のAIが出てきたってことは、逆に言えば、企業側も面接官としてのAIを絶対に使ってるはずで。AIを倒すために、AIで練習していくっていうのは絶対やるべきなんで。本番で来るAIの面接官を攻略するために、まず練習でAIを使うのは、まじで現代はやって当然。それこそ、人と面接練習をするのと同じなので。そういう意味ではアウトプットの機会が増えてすばらしいと思うし、それ一本じゃなくて色んなものを組み合わせて、っていう上でAIを使うのは最高だと思ってます。
──そうすると仮に蘭丸さんが就活をしていた場合、AIは使っていたと思いますか?
絶対にガンガン使っていたと思いますね。特にもう矛盾点とか、ロジックにムラがあるかどうか指摘してくれるとか、矛盾がある方が、逆になんか、ムラがなくなっちゃうのって落とされると思うんで。
ムラがあると落とされる、やっぱり、エッジが立ってないやつはね、特にトップファームは落とされるから。いかにエッジを立たせるかっていう面白みはあるべきだし、そこをAIが採点してくれるんだったらすごくいいと思うし。
逆になんか、弱い部分をAIで、さらってもらうべきで。自分のロジックが弱い部分とか、ここ聞かれたらしんどいなっていう部分をAIとすごく議論したら、たぶん強い部分っていうのは、どんどんエッジを立たせていくべきだから、それはまた別の使い方で。
AIに使われるんじゃなくて、ちゃんとAIを使うっていうやり方で僕は多分、やってたと思いますね。
どんな機能があるのか分からないですけど、その企業の情報を全部インプットさせて、調べさせて、それを食わせて、「あなたはこの企業の面接官なんです、面接してください」って言えば多分相当リアルな面接をしてくれるはずなんで。
──実はその機能はREALMEに搭載されていて…(笑)。こんなに訴求感あるインタビューにするつもりはなかったんですが(笑)
それやらなかったらアホっすもんね。そのために使えよ(笑)。
蘭丸さんもおすすめするAI面接をするなら「REALME」。企業ごとの面接傾向をAIがインプットしているので、アプリをDLするだけで志望企業のAI模擬面接が可能です。面接データから志望企業の合格に対して不足している部分も分析してくれるので、その後の対策もスムーズにできます。
でもそれこそコネとかがない人は有利になりましたよ、有利っていうか救われるようになりました、今だから。やっぱりだから三田会必要じゃんってなってたけど、確かに、三田会がなくても、AIが勝手に三田会をやってくれるっていう、コネや友達がいない人とか、いい大学に行ってない人とかにもだいぶチャンスが来るようにもなったんじゃないか。

頑張れない人への後押し
──頑張りたいと思ってるけど、行動に移せない人に向けた後押しのメッセージをお願いします。
頑張れないのは環境が悪い。100%環境が悪い。やっぱり、人間は環境によって変わる生き物なんで。
「なんで頑張れないんだろう」って病む時間は、くそ無駄だし。頑張れないのに、「なんで頑張れないんだろう」って考えるのは無駄なので、頑張れない。それはポジティブに捉えるべき。「あっ、これは環境悪いんだ、俺じゃねえわ」っていうポジティブな捉え方をして、頑張るためにどうするかっていう、頑張ることをまず目的にしようっていう気がしてます。
僕はもう環境を変えまくっちゃうタイプなんですけど。本当に同じ場所にいられなくて、それは本当頑張れなくなっちゃうからっていうのが強くて。
頑張りたい気持ちに素直になって、頑張るために環境を変えるっていうのはすごくいいと思います。
世の中やっぱり、コツコツやれる才能があるやつとないやつがいるはずだと考えてる。1年生からやれない奴はやれない。だからもう、やれない側だったやつは、諦めて運命を受け入れて。やれない運命を受け入れて、やるとなった時に、やってきたやつをどう倒すかを考えるべき。
本当に自分の苦手から逃げるっていうことだし、苦手から逃げるっていうのはイコール強みを見つけるっていうことなんですね。何が苦手かなっていうので、自分の強みを見つけるっていうのは苦手を避けることじゃあどうやったら苦手をやらずに効率化できるかな、っていうのが頭の使い方だと思ってて。今はもう、エッジを立てる時代、やっぱり綺麗な五角形はいらない時代なんで。

おわりに
岸谷蘭丸さんのお話からは、現代の学生が直面する選択の複雑さと、自分らしい道を歩むことの重要性が伝わってきた。就職活動という既定のレールに疑問を持ち、自分の価値観と向き合い、最終的に起業家としての道を選んだ彼の決断は、多くの学生にとって参考になるだろう。
重要なのは、他人と同じ道を歩むことではなく、自分自身の「こだわり」を見つけ、それに向かって一歩ずつ進んでいくこと。そのためには自己分析を深め、時には環境を変える勇気も必要だ。AIなどの新しいツールも積極的に活用しながら、自分なりのキャリアを築いていくことが、これからの時代により重要になってくるのかもしれない。
岸谷さんの言葉にあるように、「エッジを立てる時代」において、完璧な五角形ではなく、尖った個性を大切にしていくことが、自分らしい人生を歩む鍵となるのだろう。