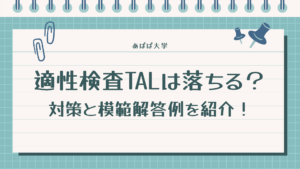性格適性検査は、多くの企業が実施しています。合格基準は企業によって異なり、性格適正検査に落ちる就活生も一定数います。
一方、性格適性検査が志望企業とマッチしていた場合、他の適性検査の結果が思わしくなくても選考を通過できる可能性があるでしょう。
本記事では、性格適性検査で落ちる理由を徹底解説し、その具体的な対策案をご紹介します。
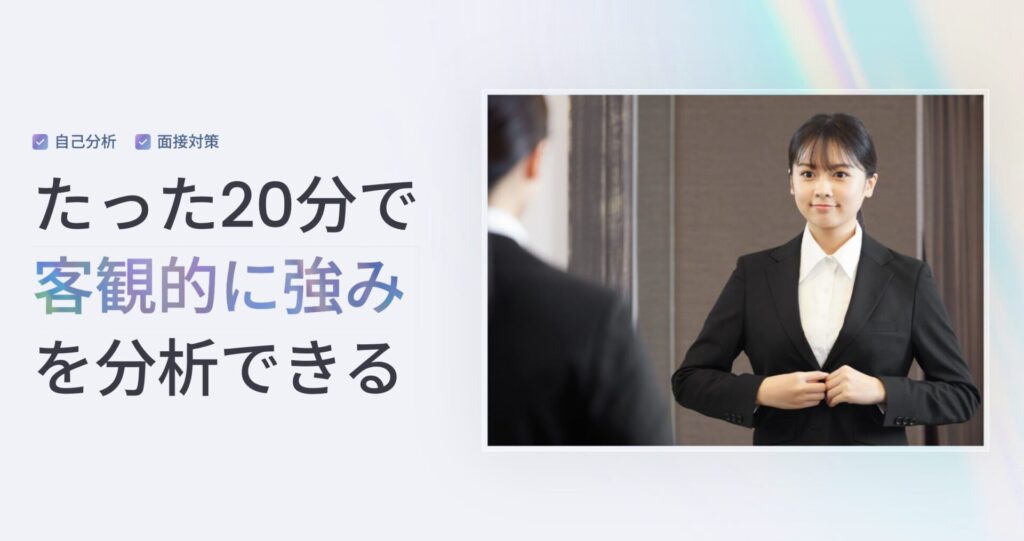
「REALME」では、本番の適性検査前に、志望企業の内定判定を確認できるサービスを提供しています。事前対策の提案やAI診断など、就活生にとって有用なコンテンツを豊富に用意しているため、効率的な内定獲得が期待できるでしょう。
性格の適性検査で落ちる理由
性格適性検査で落ちる人の多くは、求める人物像の相違や回答の矛盾点など、共通した原因があります。以下では、性格適性検査で落ちる人の代表的な原因を詳しく解説します。
企業の求める人物像・社風とマッチしていない
性格適性検査は、企業との相性を見る目的も含まれています。そのため、企業の求める人物像に合わなかったり社風とマッチしていなければ、性格適性検査で落ちる可能性が高くなります。
例えば、求人側が「チームとして働くための協調性がある人材」を求めている場合、応募者が「個人での業務進行を得意とする」とアピールしても、企業側は魅力に感じないでしょう。
ただし、企業が求める人物像に合わせようとしすぎても、嘘や矛盾が発生して印象が悪くなります。
回答に整合性が見られない
答えが極端であったり矛盾していたりするなど一貫性のない回答をすると、嘘をついていると判断されて性格適性検査で落ちる恐れがあります。例えば、「何事にも諦めずに努力する」の質問に「はい」と答えたにもかかわらず、「粘り強い性格である」に対して「いいえ」と回答した場合です。
似ている質問に対して矛盾した回答をすると、信頼性がないと判断され、性格適性検査で落ちやすくなります。
回答に抜けなど不備がある
性格適性検査でひとつの問題に時間をかけすぎた場合、最後まで到達できず未回答の質問が残ります。そのため、本来解けるレベルの問題に回答できず点数が下がり、適性検査に落ちることも考えられます。
適性検査では多くの問題が提示されるため、未回答が多いと、企業側から「この人は時間配分が苦手」と判断されるでしょう。さらに、「自己分析がうまくできていない」「対策ができていない」とみなされるリスクもあります。
企業目線を知っておこう。性格適性検査の導入背景
そもそも性格適正検査は、どのような背景があって導入されたのでしょうか。ここからは、導入された理由や、性格適性検査に期待される効果も紹介します。
初期段階でミスマッチを防ぐため
2021年卒の離職率が16年ぶりの高水準だったことはご存じでしょうか。
その原因のひとつに、入社後のミスマッチが考えられます。「応募者のスキルが不足している」「会社の雰囲気に合わない」などのミスマッチが起こると、離職につながるためです。
性格適性検査は、内定者の特徴を理解するうえで非常に有用な情報です。検査では、応募者の特性や性格を見極め、企業の目指す方向性とマッチするかを判断できます。応募者を客観的に評価するほか、面接では見抜けない素質を把握できるため、初期段階でのミスマッチ防止が期待できるといえます。
また、検査の結果をもとに内定者に適したマネジメントを実施すれば、職場においてスムーズな適応が実現するでしょう。
出典:厚生労働省「01 _241025_新規学卒就職者の離職状況を公表します」
内定後の最適な配属・能力開発で、内定者の生産性を上げるため
一般的に、企業は適性検査結果を資料として利用することが多いといわれています。内定者の能力や分析結果を事前に考慮すると、適切な教育や研修を実施できるためです。
さらに、企業側は性格適性検査の結果をもとに内定者の特性を理解したうえでその人に合った配属先を決定します。内定者の生産性を向上させるためにも、適性検査は大切です。
性格適性検査で落ちないように!受ける姿勢・対策も
性格適性検査は、挑む姿勢が悪かったり対策内容が不十分だったりした場合、落ちる可能性が高くなります。しかし、落ちないためにどのような対策をすればよいか分からないと感じる人も多いでしょう。
ここからは、性格適性検査を受けるにあたって事前に把握したいポイントを解説します。
選考で取り繕わない・着飾らない
選考では、自分を取り繕わず、素直に回答しましょう。過剰に適応したりよく見られたいがために着飾ったりすると、回答に矛盾が生じる恐れがあります。あまり深く考え込まず、直感的に回答することがおすすめです。
選考では紛らわしい表現や問いかけが多い分、素直に答えることで回答に一貫性が生まれます。その結果、企業側から「この人は信頼できる」と判断されることが期待できるでしょう。
万が一答えにくい質問だった場合でも、企業に合わせて自分をよく見せようとはせず、正直に答えてください。
選考全体を通して矛盾がないようにする
適性検査は、質問数を多く出すことで意図的な回答ができないようにしています。もし、自分を偽った回答をした場合、矛盾が生じます。その結果、企業側はその応募者を候補から除外するでしょう。
適性検査は正しい答えを求めていないことがほとんどで、回答者の人物像を捉えることを目的としています。そのため、本来の自分ならどう考えるかを常に念頭に置きながら回答しましょう。
自己分析で事前に質問慣れしておく
自己分析で自分自身への理解を深めることは、就職活動において非常に大切です。問いかけに対して迅速に回答できるよう、質問に慣れておくこともおすすめです。
また、性格適性検査は種類が多く、制限時間が設けられています。時間切れによる未回答を防ぐには、自己分析を行い、迅速に回答できるように練習をすることが効果的です。
そのほか「1問につき回答時間は6秒程度にする」という方法を取り入れると、時間切れを防げるでしょう。
嘘をつかない(ライスケールで発覚する)
選考で嘘の回答をすると、後にライスケールで発覚する恐れがあります。
また、ライスケールはシステムに対して複雑に組み込まれているため、対策しすぎるとかえって引っかかりやすくなります。加えて、不自然な回答になるリスクもあります。
ライスケールで嘘が発覚した場合、仮に性格適性検査に通過しても、企業側が応募者に不信感を抱いている状態で面接に臨まなければなりません。応募者にとって非常に不利な状況であるといえるでしょう。
内定判定・FBがある適性検査「REALME」で選考を先取り

「REALME」のサービスでは、本番の適性検査を受ける前に志望企業の内定判定が確認できます。
REALMEの就職活動支援サービスについて詳しく説明します。
志望企業の内定判定から最適なタイミングで選考を開始できる
就職活動支援サービスを実施する「REALME」では、志望する企業の内定判定を確認できるシステムを提供しています。
AIとの面談を通して新卒採用で重要視される14の能力を点数化し、その結果と合格基準を突破した就活生の平均能力値を比較します。それにより、志望企業の内定判定を事前に把握できる仕組みです。
本番の適性検査の前に、自身の性格やアピールすべきことなどを客観的に確認できるでしょう。
AIによるFBで、自身の対策すべき能力が分かる
「REALME」では、志望する企業の合格ラインに届いていない能力を伸ばすため、AIによるフィードバックや学習コンテンツの提供を実施しています。
現在の自分に足りない能力は何なのかをエントリー前に把握することで、本番の適性検査や選考に対して具体的な対策ができるでしょう。
合格ラインを超える基準のES・自己PRを見れる
「REALME」では、志望企業の合格ラインを越える基準のESデータや自己PRを閲覧できます。
面接の回答例もテキストで確認できるため、適性検査後の面接にそなえてアピール内容をブラッシュアップ可能です。
さらに、自分と同様の経験やアピールポイントを話した就活生のガクチカや価値観などを把握すれば、効果的な対策につながります。
性格適性検査の全体像を理解して就活のプラスにしよう
性格適性検査の全体像を把握することで、不合格を防げます。特に、矛盾や極端な回答、不十分な対策は、性格適性検査で落ちる原因といえます。
性格適性検査を受ける前は、自己分析の徹底や自分の現在地の把握など、事前対策を万全にして臨みましょう。
「REALME」では、適性検査やその後を見据えた対策ができます。内定判定やフィードバックをもとに、戦略的に就職活動を進めましょう。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)