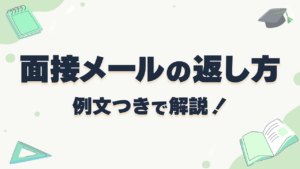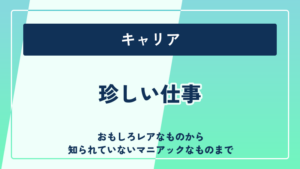AI時代の採用やキャリアの在り方が問われる今、「最強の組織」を築いてきたサイバーエージェントCHO・曽山哲人氏に話を伺った。伊勢丹での販売職からネット業界への転身、20年以上にわたり人事を牽引してきた経験を持つ曽山氏は、8000人規模の組織を支える仕組みをどう生み出してきたのか。そしてAIがもたらす新たな就活・採用の未来をどう見据えているのか。ABABA代表・久保駿貴が、その核心に迫りました。
①キャリアの原点
久保
「本日はサイバーエージェントの曽山さんにAI×就活の未来について、お話をしていただこうかなと思っております。簡単に自己紹介から、宜しくお願いします。」
曽山
「株式会社サイバーエージェント常務執行役員CHO曽山哲人です。そもそも私、最初に大学生で就活をした時は色々受けてたくさん落ちて、内定もいくつかもらったものの結構苦労したんです。1998年に新卒として、百貨店の伊勢丹入社をしているのですが、その前には日本のバブル崩壊が起こったタイミングで、その余波を受け始めた時期でした。
久保
「ありがとうございます。
サイバーエージェントの人事と言えば曽山さん!というイメージですが、曽山さんの伊勢丹時代のキャリアとか、営業時代のキャリアってあまり表に出ていませんよね?僕も初めてお聞きしたので、今回はその辺も伺えればと思います。」
曽山
「そうですね。まず新卒として伊勢丹に入社しまして、紳士服の販売からバイヤーのお手伝いまで、1年目なので何でもやっていました。その後、伊勢丹がeコマースに参入するということになり、自分もそれを手伝ったのですが、これが非常に売れたんです。
『これは面白い!』と、そこからネット業界やテクノロジー業界に行きたいという思いが出てきて、就活をしなおしました。当時はまだ第二新卒のような概念はなかったので、雑誌でたまたま見つけたサイバーエージェントのホームページに自分からエントリーを申し込みましたね。
最初から人事だったわけではなく、広告の営業を6年間やりまして、大体150人くらいの営業部隊のトップを務めた後に、会社の方針で人事部長を任されました。それから20年、2005年から今まで人事をやっています。
自分がサイバーエージェントに入ったときの社員数は20名でした。そこから今はグループ全体で8000名、その変遷をずっと見てきました。しかもその間20年人事をやってきた人間なんて中々いないんじゃないかと思っていますので、いい話が出来るよう頑張ります!(笑)」

曽山
「はい。まずは人事配属になるまでの話からですが、人事を強化しようということで、藤田をはじめとする当時8人の役員による役員合宿で決められたことで、自分の意思ではないんです。
先程20人から8000人を見てきたと言いましたが、すごいスピードで拡大していったんです。20人の1年後には100人、その1年後には300人、毎年のその速度で純増させていく、そういう感じでしたね。」
②新規事業が生まれる仕組み
久保
「そうした中でサイバーエージェントの人事採用をずっと牽引してきたと思うのですが、当時としては珍しい、様々な制度を作ってこられましたよね。」
曽山
「新規事業がたくさん生まれる仕組で言いますと、『あした会議』というものがあります。これは役員たちが年に1回新規事業バトルをするというものなんです。
新規事業のアイデアって社員の皆さんに出してもらうことが多いと思いますし、弊社でも元々はそうでした。ですがある日、社員が藤田に言ったんです。『いつも新規事業コンテストの審査を役員がやってますよね?そして色々なアイデアを落としてますよね?つまり、役員の皆様はよっぽどいいアイデアを持ってるんですよね?』と。」

久保
「そんなこと言っていいんですか?」
曽山
「それを聞いた藤田は『確かにそうだな』と。そして役員たちによる新規事業バトルになったんです。」
久保
「さすがです。」

曽山
「役員は事前に全社員の中から4人だけ、色んな職種の人を横断的に集めてチームを作る。そして、会社の課題を見つけたり新規事業のアイデアを見つけて提案する。これを2006年くらいから毎年開催していて、そこから新会社が30社以上も生まれています。今、サイバーエージェントと言えばスマホゲーム事業が非常に強いのですが、それもこの『あした会議』から生まれた事業なんです。」
久保
「100人くらいの規模の時から新規事業をどんどん興していったという印象なのですが、このコンテスト形式にすることで色々とできるようになったのですか?」
曽山
「そうです。サイバーエージェントは設立直後から新規事業の立ち上げを大量にやってきたんですが、その当時はほぼ全部撤退、参加していた人の多くは離職してしまったんです。藤田自身も言っていることですが、当時は私も含め全員未熟だったので、簡単に言うと新規事業が下手くそだったんです。だから、社員から出てきた色々なアイデアを試してはいましたが、打率が低かった。そこでコンテスト形式を取り入れ、徹底的に深く議論して決めていくようにすることで打率がすごく上がっていきました。」
久保
「どのくらい上がったのですか?」
曽山
「作った新会社の5年後、というのをある年に調べたのですが、ちょうど半分残っていました。昔は1~2割だったことを考えると、5割ってすごい数字だな、と思います。」

③〇〇〇支援で課題が解決
久保
「そんな成長の中で人が一斉に辞めてしまったり、社内での揉め事とかもあったかと思うのですが、人事として、そういった課題の解決に機能したと思うような施策はありましたか?」
曽山
「その意味で言いますと、すごく良かったと思っているのは『懇親会支援制度』というものです。簡単に言うと飲み会の支援です。昔は社員の仲が悪くて、懇親会も食事会もない、互いを称える文化もなかったんです。ところが、業績の伸びていたある部署を見ると、普段からランチも飲みも行っていて、お互いすごく仲良くやっていました。
『こういうのを横展開したほうがいいね』と感じまして、飲み会の支援を決めました。
ルールとしては、必ず上司がいること。同じ世代同士だけにして、変にネガティブな話にならないようにすること。月に1回、1人5000円までです。これを翌月まで持ち越しできないということにしたので、月に1回の表彰式の日、表彰式が終わると皆で飲みに行くという風土ができました。食事を通じると仕事以外の話も出来るようになる。仲良くなる、という効果は業務という面でもすごく良いことなんです。」
④部署間の交流で重要なこと
久保
「今、ABABAも人が増えてきまして、課題が出てきたと思っています。例えば営業とマーケティング、異なる部署間でお互い何をやっているのかが見えなくなったり、交流もなくなってきたりとかがあると思うのですが、こういった部署間での交流はどのようにされていますか?」

曽山
「部署間の交流において重要なことは、上司の仲が良いか、ということなんです。」
久保
「なるほど。」
曽山
「部署の縦割りがある中で、現場の仲が悪い時は大体部長の仲が悪い。これはすごく重要なポイントです。部門ごとに目標があると思いますが、ここに違いがあると部長同士飲みに行っても結構ぶつかってしまうんですね。会社の未来や目標について、部長ごとにちゃんと自分の言葉で現場に伝えられるようになっているか、それが部門の目標になっていないか、ここが重要です。部門の目標が一番になっているようだと、目標が一致しません。『俺は営業だ』『俺はプロダクトだ』これでは仲良くなるわけがない。ですが、例えば『ABABA全体の目標はこれだ』で目標が一致していて、そのためにそれぞれがどういうアクションをするか、という議論なら建設的になるわけです。」

久保
「めちゃくちゃ勉強になります!
未来の目標って抽象的な表現や数字が多いと思うのですが、それを各部長たちが部下に対し、具体で同じ言葉に下ろせるかどうか。こういう理解であっていますか?」
曽山
「そうですね、部長が部下に伝える時の言葉は必ずしも一致しなくて良いと思います。久保さんがそれを聞いたときに『そうだよね』と感じられればOKです。それだけで、それが会社全体の目標なのかどうかがわかりますから。」
久保
「ありがとうございます!」

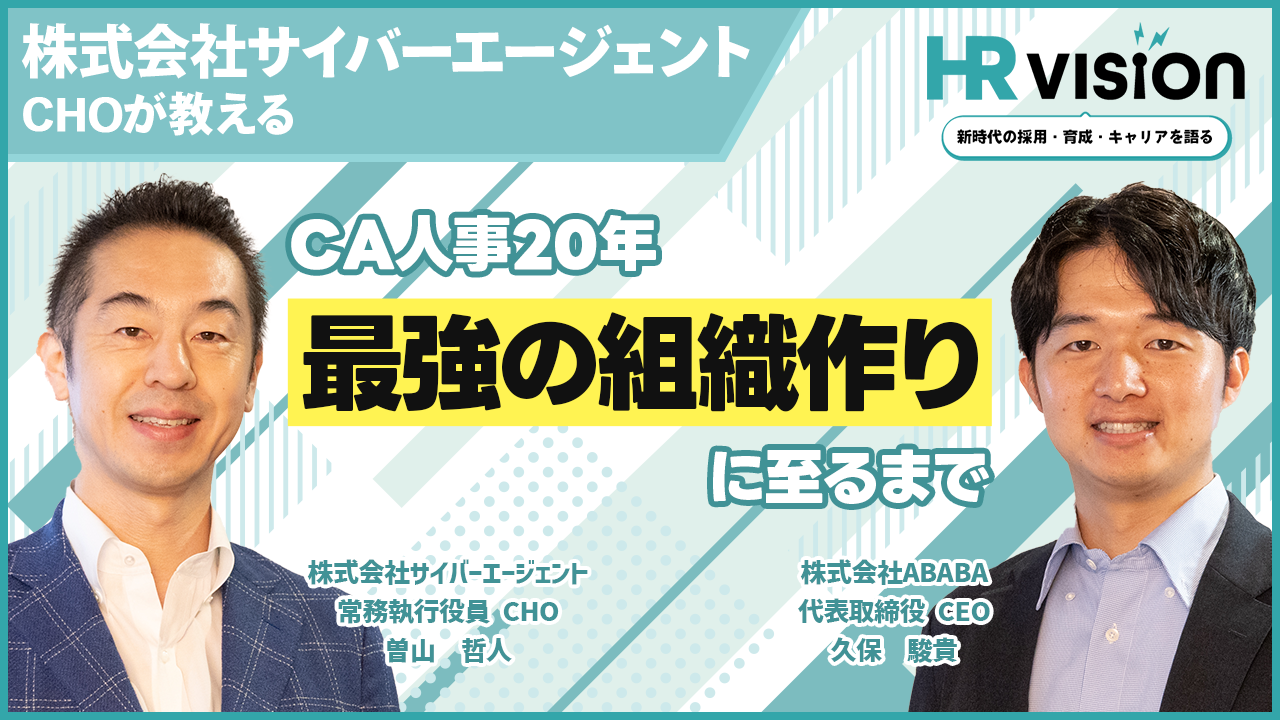
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)