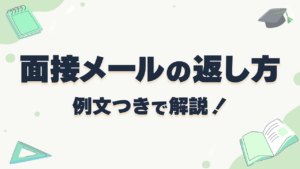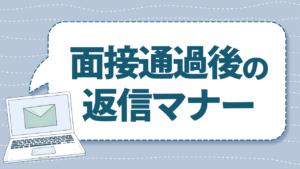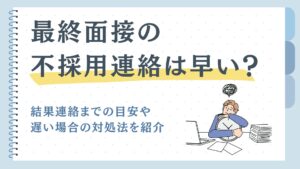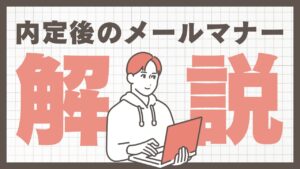就活で落ちたときのメンタルの切り替え方を解説します。就活で不採用になると落ち込むのは当然ですが、メンタルがボロボロになってしまう前に上手く切り替えましょう。落ちるのは当たり前であると考えて、いかに次の選考につなげられるかが重要です。
就活で落ちるのは当たり前!その後の切り替えが大切

就活で落ちてしまうと、まるで自分が否定されたように感じて落ち込んでしまう人もいるでしょう。しかし実際には、単に企業との相性が合わなかったというだけかもしれません。また、複数社を受けているのであれば、そのうちの一社から不採用通知を受けることはごく自然なことです。
実際に、就職未来研究所の「就職白書2024」によれば、1人あたりの就活生のエントリー数の平均は約28.1社、平均内定社数は約2.6社となっています。つまり、25社程度はエントリーしても何らかの理由で不採用となっているのです。
就活生自身としても、最終的に入社するのは一社のみ。また、新卒採用の市場は年々活発化しているといわれています。特に中小企業では新卒採用の求人倍率が増加しており、2024年卒の求人倍率は6.19倍です。
1つの企業に落ちたからといって、他の企業で不採用になるとは限りません。就活で落ちた場合には早めにメンタルを切り替えて、次の選考に意識を向けるようにしてみましょう。
就活で落ちたときのメンタルの切り替え方6選
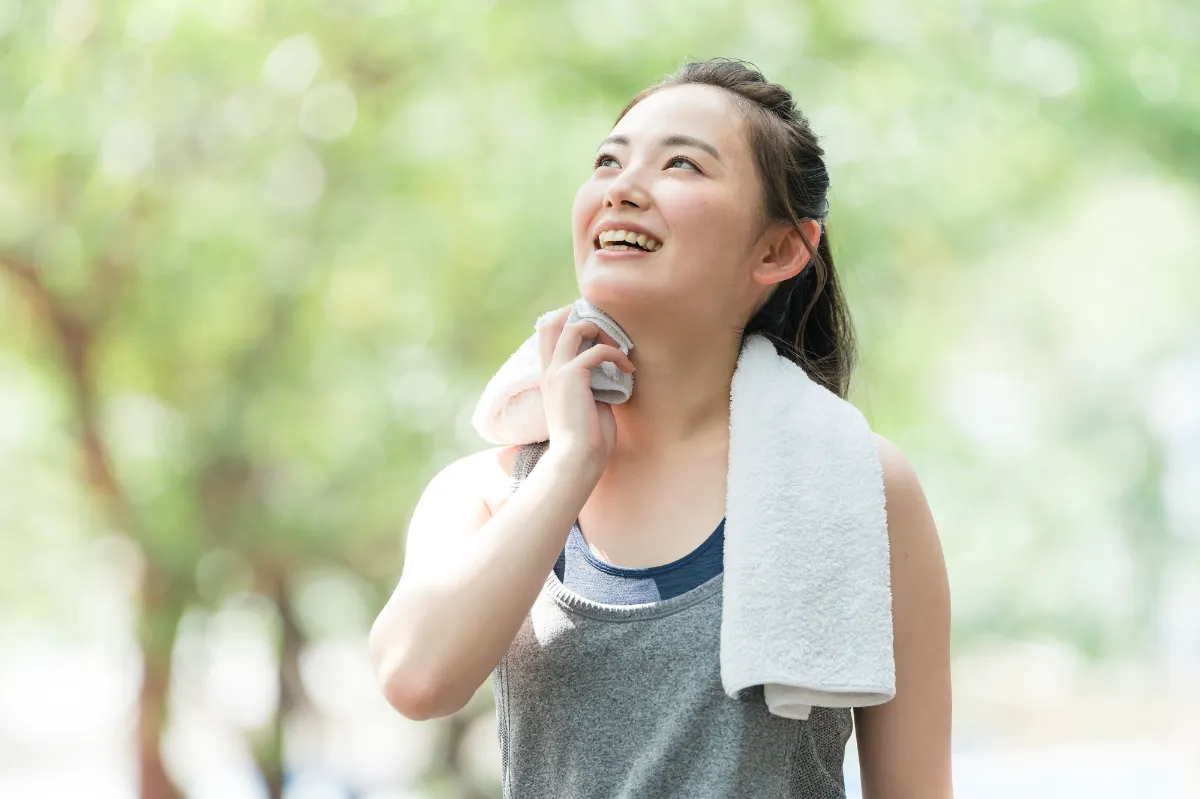
次の選考に向けてメンタルを切り替えるべきであるとわかっていても、実際にどのように切り替えてよいかわからない方もいるかもしれません。ここでは、就活で落ちたときのメンタルの切り替え方を紹介します。
・まずは結果を受け入れる
・自分の気持ちを紙に書き出す
・家族や友人に話す
・ポジティブな思考を心がける
・プロに相談する
・期限を決めてリフレッシュする
・落ちた企業を嫌いになる
それぞれ詳しく解説するので、参考にしてみてください。
まずは結果を受け入れる
就職活動で落ちたときには、まずはその結果を受け入れることが大切です。
不採用自体はほとんどの人が就活の過程で経験する過程であり、特別珍しいことではありません。「あの企業とは合わなかった」「入社後のミスマッチが起こらなくてよかった」というように捉えて、次のステップに進むための一歩を踏み出しましょう。
自分の気持ちを紙に書き出す
自分の今の気持ちを紙に書き出してみることも効果的です。なぜなら、自分の気持ちを紙に書くことで、自分の感情を客観視できるためです。
自分の気持ちを紙に書くことで、気持ちを整理できます。また、客観的に自分を見つめ直すことで、改善点や反省点が見つかるきっかけにつながります。
就活に関する悩みは、話しにくかったり話す相手が限られたりして、誰かに話すことが難しいこともあるでしょう。一方、自分の気持ちを紙に書くことは気軽にできるメンタルの切り替え方です。
家族や友人に話す
信頼できる家族や友人に話すことで、気持ちを切り替えるきっかけとなる場合があります。純粋に話や愚痴を聞いてもらうことはもちろん、具体的なアドバイスが欲しい場合は伝えてみるとよいでしょう。
ポジティブな思考を心がける
就活に落ちてしまうと、どうしても自己肯定感が下がってしまったり、ネガティブな考え方になってしまったりするものです。しかし、気持ちを切り替えられないまま他の企業の選考に進むと、マイナスの影響を与えてしまう可能性があります。
特に第一志望に落ちた場合は立ち直るのに時間がかかるかもしれませんが、意識的にポジティブな思考を心がけることで徐々に気持ちを切り替えましょう。
プロに相談する
「何が悪かったのかわからない」「自分の対策が合っているか不安」といった場合は、就活のプロに相談してみるのも手段の1つです。相談したい内容について事前にまとめておくと、相談の場を有意義にすることができて、具体的なアドバイスをもらえるでしょう。
具体的な相談先は下記の通りです。
・大学のキャリアセンター
・エージェントのキャリアアドバイザー
・就活相談を受け付けているSNSアカウント
期限を決めてリフレッシュする
どうしても気持ちを切り替えられない場合は、思い切ってリフレッシュ期間を設けるのも1つです。「この1日は就活から離れる」といったように、趣味や運動に打ち込むことで気持ちを切り替えやすくなります。
とはいえ、そのまま長期間就活から離れてしまうリスクを避けるために、必ず期限を決めて休息を取りましょう。
落ちた企業を嫌いになる
やや荒療治ですが、自分の気持ちを優先させるために、落ちた企業の悪いところを挙げて、あえて嫌いになる方法もあります。どれだけ魅力的に思える企業でも、1つも欠点がないかといえばそうではないはずです。
ネガティブな感情を持ち続けるとかえって疲れてしまいますが、落ちた直後に「もっといい企業に出会えるかもしれない」といったように、気持ちを切り替える程度であれば構わないでしょう。
就活で落ち込んでもやってはいけないこと
就活がなかなかうまくいかないと落ち込むことが一般的です。しかし、落ち込んでいるからといって以下のことは避けましょう。
・周りの人間と自分を比較する
・第一志望の企業や業界にこだわりすぎる
・大量の会社にエントリーする
・SNSで会社をけなす
それぞれについて、してはいけない理由を解説します。
周りの人間と自分を比較する
周りは就活生ばかりのため、つい自分と周りを比べてしまいます。しかし、「あの人は内定が出ている」「周りは内定が出ているのに自分だけ内定をもらえない」など、周りの人間と自分を比較しても落ち込むだけです。
改善点を見つけるための比較であればよいものの、比較することで自分を否定してはいけません。就活はあくまで自分一人のことであり、進捗を周りと比べる必要はありません。
第一志望の企業や業界にこだわりすぎる
入りたい企業や自分に合うと感じる企業が見つかると、無意識にその企業にこだわる人がいます。しかし、第一志望の企業や業界にこだわりすぎることは禁物です。
第一志望の会社に落ちると、メンタルに大きな影響を及ぼします。また、こだわりすぎて冷静さを失うとその後の選考に悪影響を及ぼしかねません。
たとえ第一志望の企業の選考に落ちても、落ち込みすぎず反省点を確認して次の選考に活かしましょう。
大量の会社にエントリーする
「数を打てば当たる」と、大量の会社にエントリーする行為も避けましょう。なぜなら、エントリーする会社の数を増やしたからといって、内定率は上がらないためです。
内定率を上げるためには、落ちた原因を明確にし、自分に合う企業を見つけることが有効です。過去を振り返らず、とにかく受ける会社を増やしたところで、内定率は上がりません。
エントリーする数を増やすのではなく、自分に合う企業や自分のスキルが活かせる業界を探しましょう。
SNSで会社をけなす
選考に落ちたからといって、SNSで落ちた会社に対する不平不満を書いてはいけません。なぜなら、これから受ける会社の人事部社員が候補者のSNSをチェックする可能性があるためです。
もし、SNSで他社のことをけなすような投稿が見つかると、選考に大きく影響を及ぼします。自社に合う人材と感じていても、人間性に疑問を持たれて採用を見送られる可能性があります。
選考に落ちたことは縁がなかったと捉えて、ネガティブに捉えたり恨みを持ったりして会社をけなす言動は避けましょう。
就活で落ちた時の振り返りポイント
就活で落ちるとネガティブな気持ちになるものの、落ちた経験を振り返って次回に活かすことで、落ちた結果も有意義なものにできます。就活で落ちた際には、以下のポイントを振り返りましょう。
・基本的なマナー
・自己分析
・企業研究
・面接内容
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
基本的なマナー
選考時には、基本的なマナーができていることは大前提です。最低限のマナーもできていない人材を採用すると、企業側はマナーを教えることから始めなければならず、教育にかかる時間と費用などのコストが増えます。
身だしなみは清潔だったか、社会人としてのマナーは適切だったかを振り返ります。
話し方も重要です。正しい敬語が使えているか、聞き取りやすい話し方だったかも併せて振り返りましょう。
自己分析
面接対策として自己分析をしますが、就活で失敗した際には再度自己分析をしましょう。あらためて自己PRの内容を見直すことで、次回の就活ではより自身をアピールできます。エピソードの内容が薄くないか、行動の動機が浅くないかを見直して、面接官がよい印象を持つ自己PRの作成を目指しましょう。
また、将来のビジョンまで話せるかも重要です。「御社に入社したら、将来このようなキャリアコースを考えている」「将来的にこのような仕事に携わりたい」など、将来のビジョンを明確に伝えましょう。
企業研究
企業研究が不足していたことで、就活に落ちた可能性もあります。志望動機が的確に伝えられたか、逆質問ができたかなどを振り返り、企業研究が甘くなかったかを確認しましょう。
企業対して十分に理解できていると判断されると、志望度が高いと判断されます。志望度が低いと判断されると、落ちる可能性が高まります。そのため、第一志望の企業ではないとしても、十分に企業研究をして自分がいかに活躍できるかをアピールしましょう。
面接内容
これまでの面接を振り返って、回答できなかった所はないか、ガクチカや深堀り質問に対応できたかなどを確認しましょう。例えば、質問をさらに深堀されたことで回答できなかったり、予期せぬ質問をされて答えられなかったりしたことがあると、それが落ちた要因の1つと考えられます。
また、ハキハキと聞き取りやすい話し方だったかも振り返りましょう。聞き取りにくい話し方だと、よい回答をしていても悪い印象を持たれます。自信がない場合も、ハキハキと聞き取りやすい話し方を意識しましょう。
面接で落とされるよくある原因
面接で落ちる原因はさまざまなものの、共通する原因はいくつかあります。そこでここからは、面接で落とされるよくある原因をいくつかご紹介します。
面接に落ちた際は、以下の原因に該当していないかを確認して、改善点を見つけましょう。
やる気が伝わっていなかった
自信ややる気が感じられない候補者は避けられます。なぜなら、やる気が伝わらないと内定を出しても辞退されたり、早期離職されたりするリスクが高いと判断されるためです。
面接では、やる気や志望度の高さのアピールが大切です。企業分析をしっかりすることや、なぜその企業に入りたいのかを伝えて、やる気や志望度が高いことをアピールしましょう。
第一印象がよくなかった
第一印象がよくなかったことで、面接に落とされることがあります。これは、面接の内容ではなく第一印象に原因があるため、第一印象の改善が必要です。
例えば、服装が乱れていたり、姿勢がよくなかったり、無意味に笑いすぎていたりすると悪い印象を与えます。服装は清潔で面接に適した服装を着用し、姿勢を常に正し、言葉遣いは問題ないかなどを見直しましょう。
また、笑顔を心がけることは大切です。しかし、笑いすぎているとやる気がない、緊張感がないと逆効果になりかねません。
面接官との相性が悪かった
面接官も人間であり、好き嫌いはあります。そのため、面接官との相性が悪かったことで面接に落ちることがあります。話が合わない、面接の空気が悪いなどを感じたら、面接官との相性が悪いケースです。
面接官との相性の悪さが原因の場合、明確な改善点はありません。そのため、落ち込むのではなく「自分に合う企業ではなかった」「縁がなかった」と捉えて、次の選考に向けて準備を進めましょう。
書類と面接の内容が矛盾していた
書類と話の内容に矛盾があると、面接官は不信感を抱きます。そのため、書類と面接の受け答えは一貫性を持ちましょう。
矛盾が生じると、作り話と思われたり話に芯がない人と思われたりします。その結果、不信感につながって選考に落ちます。
面接対策をする際は、書類に書いた内容を確認しましょう。その上で、質問を想定して矛盾のない回答を意識しましょう。
面接では、書類と同じ内容の質問をされるケースがあります。そのため、自身で提出した資料の内容を把握することは重要です。
質問に対する回答がずれていた
質問に対する回答が、あまりに的外れだと面接に落ちることがあります。これは、質問の意図を察していないまま回答すると、話をきちんと聞いていないと思われるためです。
しっかり話を聞けていないと業務上でトラブルに発展したりミスが増えたりする可能性があります。そのため、質問に対する回答がずれていると、選考に落ちる原因になりやすい傾向です。
面接対策をする際は、よくある質問には回答をあらかじめ用意しましょう。回答を用意することで、まとまりのある回答ができてよい印象を与えられます。
合格・不合格サインには要注意
面接中は、「これがあれば合格」「これがあれば不合格」と判断できるサインがあるといわれています。そこでここからは、合格・不合格サインをご紹介します。
なお、下記のサインが必ずしも合格または不合格につながるわけではないため、参考程度に捉えましょう。
合格サインとして挙げられる行動の例
面接中に以下のような行動があった場合、合格の可能性が高いと判断できます。
・勤務地の希望を聞かれた
・業務に関して詳しく説明された
・面接の時間が予定を大幅に過ぎた
・メモを多く取っている
・次の選考についての説明がある
合格の意思がある場合、次の選考や入社後の話をされる傾向があります。また、興味がある人材の話にはしっかりと耳を傾けて、メモを取る面接官がほとんどです。
不合格サインとして挙げられる行動の例
面接中に以下のような行動があった場合、不合格の可能性が高いと判断できます。
・面接時間が極端に短い
・全くメモを取らない
・面接官の反応が薄い
・逆質問の時間がなかった
・基本的な質問しかされない
・質問を深掘りされない
・入社後や将来のビジョンを聞かれない
不合格の意思が強い場合、質問を深掘りされなかったり面接官の反応が薄かったりします。また、質問が少なく深掘りされないため、面接時間は極端に短めです。
サインに一喜一憂するのはメンタルによくない
前述したサインはあくまで「傾向」であり、必ずしも合格または不合格が決まったわけではありません。そのため、これらのサインに一喜一憂することは避けましょう。
サインに一喜一憂すると、メンタルに悪影響を及ぼしかねません。一喜一憂すると他の選考に悪影響が出るため、何事にも冷静さを保ちましょう。
メンタルを切り替えたあとの対策5選

ここからは、メンタルを切り替えたあとの対策について見てみましょう。
・就活の軸を見直す
・他の企業を探す
・志望業界を変える
・面接練習をする
・スカウトサービスに登録する
それぞれについて解説していきます。
就活の軸を見直す
なかなか選考に通らないという場合、就活の軸を一度見直してみましょう。特に一次選考や二次選考での不採用が続く場合、現在の回答に一貫性がないかもしれません。
就活の軸を見直すことで、面接や書類選考での受け答えに迷いがなくなり、ポジティブな印象を持ってもらいやすくなります。特に、就活初期で設定した軸は後から変わることも珍しくありません。企業研究や業界分析を繰り返す中で就活の軸を見直し、常に就活の軸と志望企業が合致する状態にしておきましょう。
他の企業を探す
志望度の高い企業に落ちてしまうと、その後の持ち駒が少なくなってしまうケースがあります。大手企業や人気企業でなくても、将来性のある優良企業はたくさんあります。少し視野を広げて、これまで知らなかった企業にもぜひ目を向けてみましょう。
例えば、人気企業や知名度の高い企業ばかりにエントリーしているという場合は、BtoBの企業も見てみたり、エージェントにおすすめの企業を紹介してもらったりする方法があります。
志望業界を変える
企業研究や自己分析の結果、志望業界を変えることも1つの手です。企業研究をすると、「この業界は自分に合わない」「思っていた仕事内容と違った」などのケースにつながります。この場合は、より自分に合っていたり、やりたい仕事ができたりする業界への変更を検討しましょう。
ただし、志望業界を変更すると面接回答の練り直しが必要です。再度面接対策をしたり、企業分析をしたりしなければならないことを理解しましょう。
面接練習をする
面接を振り返って、適切に質問に回答できていなかったり、回答できなかったりした際には、これまでの面接で足りなかった部分を練習しましょう。
面接で上手く話せなかったことの要因には、面接対策が不十分であることや、緊張から練習の成果を発揮できなかったことなどが考えられます。特に、本番で緊張しやすい場合は慣れが大切です。何度も練習を行い、周りの人に面接練習を手伝ってもらうことで面接に慣れましょう。
練習時の面接の内容を録音し、聞き直すこともおすすめです。自分がどこで詰まっているのか、話し方は問題ないかなどを振り返り、よりよい回答ができるように工夫しましょう。
スカウトサービスに登録する
最終面接や役員面接で落ちてしまうと、その後別の企業を1から受け直すことがより大変に感じるかもしれません。そういった場合には、スカウトサービスへの登録がおすすめです。スカウトサービスとは、登録することで企業からのオファーを受けられるサービスのこと。
最近では書類選考や一次面接が免除されるものもあるので、効率的に就活を進めたい場合にはぴったりです。
「REALME」で面接対策をしよう
志望企業の内定率を上げるためには、面接対策が必要です。面接対策をする際は、自身で質問を考えたり反復して練習したりするだけではなく、「REALME」の活用もおすすめです。
ここからは、REALMEをおすすめする理由について解説します。
AI面接で志望企業の内定判定が確認できる
REALMEを利用する際は、20〜30分のAI面接を受けます。AI面接の対話内容によって、14の項目がフィードバックされます。フィードバックされた内容と、合格ラインの学生の解答データを比較して、内定判定を確認可能です。内定率が分かれば、「今のタイミングでの応募は辞めよう」「Aの企業の応募は辞めてBの企業に応募しよう」など、効率よく就活が進められます。
また、フィードバックから自身の足りない部分が分かる点もおすすめポイントです。客観的な自己分析から、自分では気づかなかった不足部分が分かります。
AI分析で自身のアピールポイントが分かる
AI面接の結果は、14項目に分けてフィードバックされます。この14項目から自身の強みと弱みが分かる点も、REALMEの特徴です。
面接対策では、自己分析をして自身の強みと弱みの把握が大切です。REALMEを活用すれば、客観的な自己分析の結果が可視化されるため、自分では気づかなかった強みと弱みが分かります。
このように、AIを活用した客観的な自己分析で面接対策ができます。
合格ラインにいる学生の面接回答例が閲覧できる
自身のAI分析の結果を確認できるだけではなく、他の学生の回答例も閲覧できます。合格ラインにいる学生の面接回答例を閲覧すれば、自身の足りない部分やアピールできる強みが分かります。
自分と合格ラインの学生を比較して足りない部分を事前に補えれば、内定率の向上が可能です。
就活で落ちたあとはメンタルを切り替えて対策しよう

就活で落ちたときのメンタルの切り替えについて紹介しました。志望度の高い企業に落ちてしまうと、気持ちが沈んでしまうのも無理はありません。まずは結果を受け入れて、前向きな気持ちになるための第一歩を踏み出しましょう。
その後の対策としては、就活の軸を見直したり、スカウトサービスに登録して他の企業を探したりすることが有効です。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)