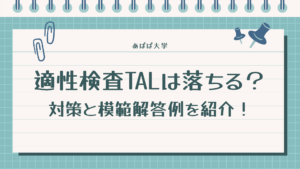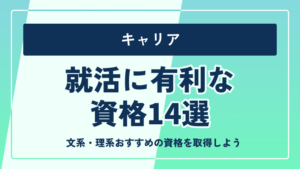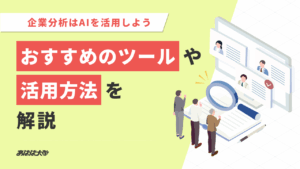就活では自己分析が重要です。自己PRも志望動機もガクチカも、すべての基礎となるのが自己分析。
それはよく分かっていても「やり方が分からない」「自分のことを客観視できない」と悩んでしまいがちですよね。
この記事では、自己分析がうまくできない人のために、簡単に取りかかれる方法を紹介します。
自己分析が苦手な人にオススメの裏技が「REALME」です。AI面接官と面接練習をすることで、自分の強みや向いている業界を客観的に分析してくれますよ。
面接はもちろん無料でできるので、今のうちに自己分析を済ませておきたい人は早めの登録がオススメです。
自己分析ができない人に共通する特徴
はじめに、自己分析ができないという人に共通する特徴を見ていきます。自分に当てはまる特徴を理解して、自己分析を進めるための足がかりにしましょう。
自己分析の目的を理解していない
なぜ自己分析をするのか、その目的を理解していないことも、自己分析ができない原因の1つです。「周りがみんなやっているから」「やるのが普通だと思ったから」というような曖昧な理由でやろうとしても、ゴールが見えなければうまくいきません。また、目的を理解せずに自己分析をしても、正しい結果は得られないでしょう。
自己分析は、志望企業を見つけるため、また志望動機を明確にするために、欠かせない作業です。目的を理解したうえで実施してください。詳しくは後述します。
自己分析のやり方がわからない
やり方が分からないという理由で、自己分析ができない人もいます。また、やり方が分かっているつもりでいても、実は間違っているというケースもあります。
自己分析のやり方にはさまざまな種類があり「これをやればよい」という方法があるわけではありませんが、やり方を誤ると自分の性格や強み・弱み、将来の希望などが把握できません。自分に向いている方法をきちんと学んで実践しましょう。
簡単なやり方については、後ほど詳しく解説します。
深掘りできない
自己分析できないと悩む人には、深掘りできていないケースも多く見られます。
自分のこれまでを振り返って、ただ経験を拾い上げて並べるだけでは、自己分析になりません。自己分析を行うには「なぜ?」という疑問を持つことが不可欠です。
たとえば「学生時代に部活でキャプテンをした」という経験があったとします。それだけを思い出して終わるのではなく「なぜキャプテンになったのか」「キャプテンとしてどのような役割を果たしたか」「その経験をとおして何を感じ、学んだか」と経験を深掘りしてみましょう。「責任感が強い」「コミュニケーションの必要性を学んだ」というような、自分の特徴や学びが見えてくるでしょう。
自己分析により気分が沈んでしまって進まない
自己分析をはじめようとすると、自分の弱みばかりが目について、気分が沈んでしまう人もいます。すぐ自信を失って、深い自己分析ができないというのは、自分に自信がない人や、逆にプライドが高い人に多いパターンです。
しかし、成功体験だけでなく、失敗した体験からも人は学びます。一見するとネガティブなエピソードも、掘り下げていけば強みにつながる要素が見つけられます。
自分を過小評価せず、行動や思考の流れを振り返ってみましょう。

自己分析にかける時間が短い
自己分析にかける時間が短い人も、なかなか深く自分を掘り下げられません。自己分析をするのが面倒だと思っている場合、かたちだけの作業になってしまって、本質的な自己分析につながらなくなります。
自分と向き合うために、十分に時間を取って自己分析を行いましょう。効率よく自己分析ができるツールもあります。自分に合った方法を採り入れましょう。
過去のことを思い出せない
過去のことを思い出すことが苦手で、自己分析が進みにくい人もいます。過去の写真や動画、SNSを見ても当時抱いていた感情まで思い出せないケースです。
自己分析は必ずしも過去の出来事から考える必要はありません。日記や写真、SNSなどを見返したり、家族や知人から話を聞いてもピンと来ない場合は、ここ最近の出来事から自己分析をしても問題ありません。思い出すことが苦手な人は、思いついた過去の出来事をノートにまとめることも効果的です。
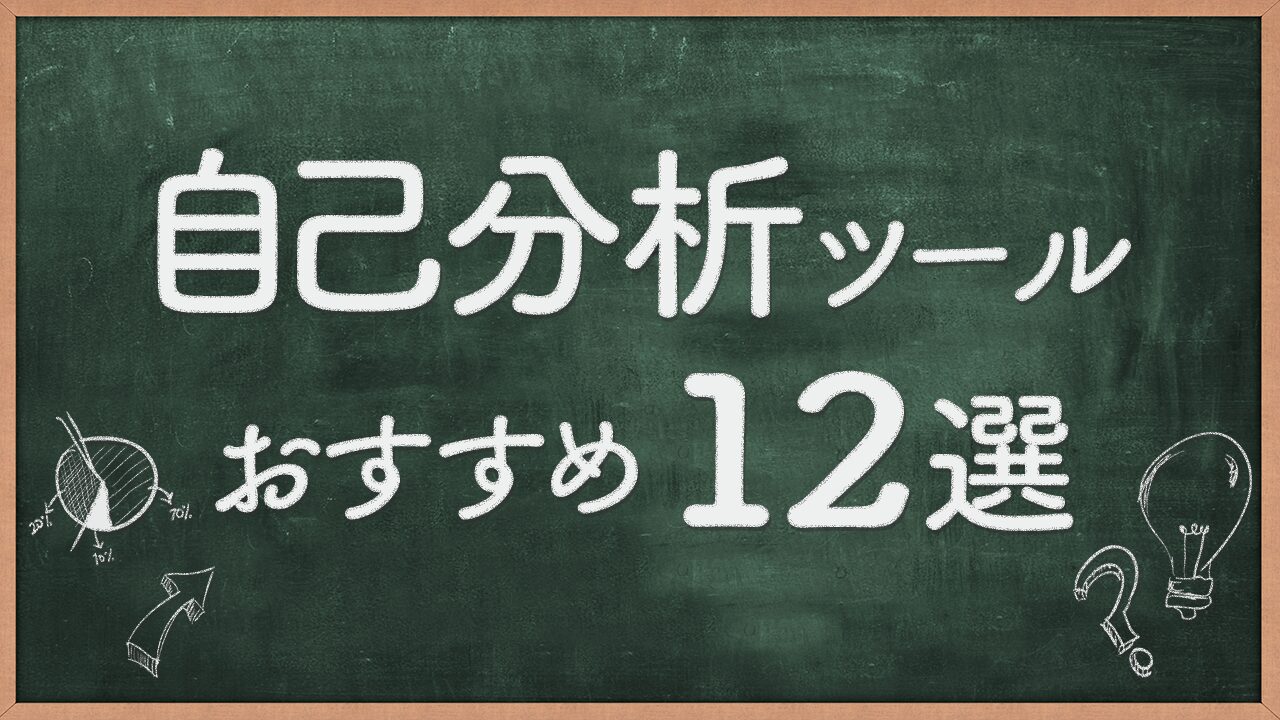
自己分析を行う目的
自己分析は自分の行動や考えを理解する手法です。目的を間違えてしまうと、就活で活かせない自己分析になってしまいます。目的を明確に理解し、これまでの自分を振り返りましょう。就活における自己分析の目的は主に3つあります。
自分の強み・弱みを見つけるため
自分の強みや弱みは、面接でよく聞かれる質問だから把握するだけではなく、自分の強みを理解することで、どのような仕事でその強みを生かせるかが分かるようになります。
自己分析の結果、自分がどのような仕事に向いているか・どのような仕事ならやりがいを感じられるか・どのようなことに興味を持てるか、が分かれば就活の方向性を絞れるでしょう。
面接でのアピールポイントを把握する意味合いもありますが、それ以上に自分に合う仕事を把握することに意味があります。
就活の軸を確認するため
就活の基準となる就活の軸を決める際にも、自己分析は必要です。就活の軸を定めておけば企業選びにブレがなくなり、ミスマッチが減ります。就活の効率も上がり、内定も出やすくなるでしょう。自己分析をする際に、職場環境や業務内容、達成したい目標など働くうえで譲れないものを考えるとスムーズでしょう。また、就活を終えた後もこの時決めた軸に沿ってキャリア形成を考えると、入社後により自分らしいキャリアづくりができます。
自分の適性やビジョンを知るため
就職という人生における大きな選択の前に、自己理解を深めるためにも自己分析は重要な役割を担っています。改めて自分のやりたいことや長所・短所を考えると、自分にどのような仕事が向いているかが分かるようになります。自分自身の適性・ビジョンが明確になると、どのような企業が自分にマッチするかが分かるようになるでしょう。自己分析を通して自分の適性を知ることで、志望業界や職種も絞り込め、抽象的だったやりたいことを具体化する手助けにもなります。
自己分析ができるようになる考え方
「企業が望む人材にならないとダメだから、自己分析をしても意味がないのでは?」「意味があるといわれても、十分な自己分析ができない」と考えている人はいませんか?このような人は自己分析について勘違いしている可能性があります。よくある勘違いについて紹介したうえで、自己分析ができるようになる考え方を紹介します。
他人と比べない
大きな勘違いの1つに、ほかの人より優れた自己分析をしなくてはならないと考えているパターンがあります。しかし、自己分析はあくまで自分と向き合うための時間で、他人と比べる必要はありません。他人と比べて無理に自分を変えてしまっては、本来の自分とかけ離れてストレスに感じる場合もあるでしょう。長所がないからと自分を否定せず、自分を受け入れるための自己分析をしましょう。
自己分析に正解はない
自己分析はテストのように正解があるものではありません。また、一度自己分析をしてしまえば終了、でもありません。自分の価値観や興味関心は時の流れとともに変化します。就活中にも知見が広がることで、自己分析の結果が変わる場合もあるでしょう。自己分析を一度きりと考えると、自己成長の機会を逃す場合もあります。そのため、自己分析は継続してブラッシュアップしましょう。定期的に見直すことで、よりリアルな自分に近い自己分析が完成します。
目標を具体化する手段
自己分析は複雑で面倒だと思っている人もいるでしょう。正しい自己分析は、漠然とした人生の目標を具体化するための機会であり、就活以外にも活用できます。
例えば「お金持ちになりたい」という漠然とした目標をもっているとしましょう。自己分析を通して強みや興味があることなどを把握することで、「お金だけでなく名声を得たいから」「それなら昇進スピードの早い会社なら夢がかなうかもしれない」と具体的な目標にまで落とし込めます。具体的な目標達成のために必要なスキルも分かり、就活の効率化にもつながるでしょう。
自分を好きになる必要はない
自己分析を進めていく際に覚えておきたいのが、「無理に自分を好きになる必要はない」ということ。自己分析は、就活や自己アピールの軸を見つけるための取り組みです。自己分析の過程で自分を嫌いなったとしても、目的達成に支障はありません。
むしろ、自分の短所や嫌いな部分を多く見つけている状態は、自己分析が順調に進んでいる証拠です。自分の短所を無理に好きになるのではなく、短所は短所として受け入れつつ、アピールのニュアンスや方向性を定める際に役立てていきましょう。
記憶力は関係ない
自己分析では、記憶力の強さはほぼ関係ありません。過去の出来事を詳しく覚えていない場合でも、自己分析は十分可能です。
たとえば「自分が何に対して楽しい・悲しいと感じるか」や「興味や関心を惹かれるジャンルは何か」「得意・不得意な作業は何か」などを深掘りするだけでも、自己分析は進んでいきます。
自己分析は、エピソードから導き出せるものとは限りません。過去の出来事の振り返りは、あくまで自己分析の手段の一つであり、すべてではないのです。
企業研究の結果に合わせすぎない
自己分析の際に注意したいポイントとして、企業研究の結果に合わせすぎないことが挙げられます。就活では少しでも企業とのマッチング率を上げるために、企業理念やミッションに合わせ、自分を偽ってしまうケースもあります。
しかし、偽った自分で合格したとしても、最終的に苦しくなるのは自分自身です。自己分析で導き出された結果を尊重しつつ、「企業に合わせる」ではなく「企業との共通点やシナジーを感じられるポイントを探す」ことを心がけていきましょう。
簡単にできる!自己分析のやり方
ここからは、自己分析がうまくできない人のために、試してみて欲しいやり方を紹介します。やりやすそうに思えるものを、ぜひ採り入れてみてください。
自分史を作る
まずおすすめするのは、自分史を作る方法です。世界史の年表のように、これまでの自分の経験や感じたことを時系列に書き出しましょう。
これまでのエピソードを目に見えるかたちでまとめることで、自分の興味・関心や価値観などが見えてきます。
出来事だけを書くのではなく、かかわりを持った周囲の人や、経験から感じたこと・学んだことなども書き込むのがポイントです。いくつもの経験を深掘りすることで、自分が大切にしているものや譲れないものが分かり、就活の方向性が見えてくるでしょう。
モチベーショングラフを作る
過去の出来事に対するモチベーションを表す、モチベーショングラフの作成もおすすめです。モチベーショングラフは、どのような出来事が自分のモチベーションになっていたのかを時系列でまとめたグラフです。縦軸をモチベーション、横軸を時間にして、幼少期から大学生までの出来事を時系列で記載します。「高校受験に成功した時のモチベーションは10段階中10」「恋人に振られた大学2年生の時のモチベーションは10段階中2」など、それぞれのできごとのモチベーションを数値化してまとめましょう。それぞれの点をつないで曲線にすればグラフが出来上がります。自分がどのような時にモチベーションが上がるのか、価値観やこだわりが分かります。
自己分析ツールやシートを活用する
自分だけで自己分析するのは難しいと感じる場合は、自己分析ツールやシートを活用することをおすすめします。用意された質問に答えていくだけで、自分の性格や強みについて診断され、効率よく自己分析が進められるでしょう。
自分では気づかなかった「自分」を知ることができるだけでなく、改善点や自己PRする際のポイントを提供してくれるツールもあります。
自己分析ツールとして、就活支援サービス「REALME」もおすすめです。自己分析がうまくできないと悩んでいる方は、こうしたツールを試してみてはいかがでしょうか。
短所を言い換える
自己分析を進める際は、短所を言い換える取り組みにチャレンジしてみましょう。すべての短所は、長所や個性と表裏一体です。一見するとネガティブな要素でも、多面的に捉えることでアピールポイントとして活用できます。
たとえば臆病な性格は「慎重」、飽きっぽい性質は「好奇心旺盛でフットワークが軽い」などのように、どのような短所も言い方次第で長所に変わります。とくに自分の長所が思い浮かばないときは、短所から逆算するかたちで考えるのがおすすめです。
就活セミナーなどで自己分析の作り方を教わる
自己分析がなかなか進まないときは、就活セミナーで自己分析の作り方を教わるのも良いでしょう。自分自身のことだからこそ、わからない部分も多いものです。第三者のサポートを借りることで、深掘りのきっかけをつかめる場合があります。
セミナー関連のイベントには積極的に参加し、自己分析に関するフレームワークを学んでいきましょう。セミナーの講師は、いわば就活のプロのような存在です。さまざまな自己分析の方法を知っているため、自分に合うやり方も教えてもらえるでしょう。
キャリアアドバイザーに分析してもらう
キャリアアドバイザーに分析してもらうのも、自己分析の方法としておすすめです。キャリアアドバイザーは、日々さまざまな就活生と向き合っています。自己分析の軸の整理や深掘りの方法についても詳しく、良き相談相手になってくれるでしょう。
エージェントの活用はもちろん、大学のキャリアセンターにアドバイザーが在籍していることもあります。相談の際は、今まで試した自己分析方法や、上手く深掘りができない要素などをまとめていくと、より効率的にコツを教えてもらえます。
他己分析をする
他者に自分の性格や強みを尋ねて自分を分析する「他己分析」もおすすめです。外からの視点で自分を把握できるというメリットがあります。やり方は次のとおりです。
①自分についての質問を用意しましょう。
漠然と「私をどのような人間だと思いますか?」と聞くのではなく「私のどんなところが好きですか?」「改善した方がよいのはどのようなところですか?」というような、具体的に答えやすい質問をしてください。
②対面で聞く方法や質問シートに記入してもらう方法など、やり方はさまざまです。
③家族・友人・アルバイトの仲間や先輩など、本音で答えてくれそうな人に依頼しましょう。
このようにして受け取った回答と自己分析の結果を照らし合わせることで、自分のことをより深く知ることができます。
【長所・短所別】自己PR例文集
ここでは、長所・短所ごとの自己PRの例文をご紹介します。記載する文章を基軸にしつつ、自分らしい内容に言い換えながらご活用ください。長所も短所も、自分を構成する要素の一つです。就活というシーンに合ったニュアンスに調整しつつ、効果的なアピールにつなげましょう。
【長所1】コミュニケーション能力に自信がある
コミュニケーション能力を長所として記載する際は、相手の立場になって話を聞ける姿勢を打ち出します。チーム間での信頼関係を築ける能力や、コミュニケーションに応じた課題解決能力をアピールし、企業への貢献のイメージを伝えましょう。
- 相手の意見を引き出す対話力を強みとし、円滑な人間関係を築けます。協働で成果を上げる場面で特に力を発揮します。
- 相手の立場に立って考えることで信頼関係を築く力があります。チーム全体をまとめる役割を担うことが得意です。
【長所2】行動力に優れている
行動力をアピールする際は「計画を立てるだけではなく、すぐに行動に移せる力があること」を強調するのがポイントです。とくに新しい環境に飛び込む勇気や実行力は、あらゆる業種において大きなアピールポイントになるでしょう。
- 計画だけで終わらず即行動する力があります。新しい環境にも臆せず挑戦し、課題解決を積極的に進めます。
- 目的達成のために必要な行動を即実行します。変化に柔軟に対応し、成果につなげる粘り強さがあります。
【短所1】優柔不断である
優柔不断という短所は、慎重さという長所としてアピールできます。また優柔不断になってしまうのは、未来のリスクを想像する力があるからこそ。リスクヘッジや規律を重視する企業での面接では、強いアピールポイントになります。
- 決断に時間を要する面がありますが、慎重に情報を整理し判断するため、結果的にミスが少ないのが強みです。
- 物事を深く考えるため判断が遅れることがありますが、納得感のある選択を重視し結果を確実にします。
【短所2】心配性である
心配性という短所は、慎重さ・計画性・リスク管理能力などの長所に置き換えられます。「万が一に備えられる人」「リスクを周知させる人」の存在は、企業において重宝されるものです。用心深い一面をポジティブにアピールしつつ、業務への正確性や誠実さなどを伝えていきましょう。
- 心配性な面があり、事前準備に時間をかけます。しかしこの特性によりリスク管理や抜け漏れ防止が得意です。
- 不安を感じやすい分、事前調査や確認を徹底します。その結果、トラブル回避や計画精度向上につながります。
自己分析にはAI全国共通模試「REALME」がおすすめ
客観的に深く自己分析がしたい人には、就活支援サービス「REALME」がおすすめです。AI面接を受けることで、精密なフィードバックが受け取れます。
ここからは「REALME」の特徴について解説しましょう。
志望企業の内定判定をチェックできる
「REALME」のAI面接を受けると、客観的な自己分析ができるだけでなく、志望企業の内定判定がもらえます。志望企業の最終面接まで進んだ就活生のデータと比較することで、内定を獲得できる確率がチェックできるため、自分の現在の立ち位置が把握できて、最適なタイミングで志望企業にエントリーすることが可能となります。
第三者からの視点で自己分析ができる
「REALME」のAI面接はフィードバックが充実しており、客観的な視点から自己分析ができます。AIと30分程度の面談を行うことで、就活で重視される14の能力が可視化され、自分の性格や強み・弱みが分かります。「成長意欲」「考え抜く力」「関係構築力」といった能力を点数として把握できるため、自分のアピールポイントを知って、自信を持って就活に臨めるでしょう。
志望企業の合格ラインを超えている就活生のESを閲覧できる
「REALME」には、志望企業の合格基準をクリアした学生の、AI面接やESのデータを閲覧できる機能もあります。これを自分のデータと比較することによって、自分に足りない部分や改善点が把握できます。優秀な学生がどのように自己分析をしているかも、参考にできるでしょう。
自己分析できない原因を理解して最適な対策法を見つけよう
自己分析は、志望企業を選ぶための最初のステップとして重要です。深く自分を知ることによって、効率的に就活を進められます。
自己分析ができない人には「目的を理解していない」「やり方が分からない」「気分が落ち込んでしまう」などの共通した特徴があります。なぜ自分がうまく自己分析できないのか、原因を理解して、最適な対策方法を見つけましょう。
自己分析のために「REALME」を活用したい人は、ぜひAI面接を受けてみてください。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)