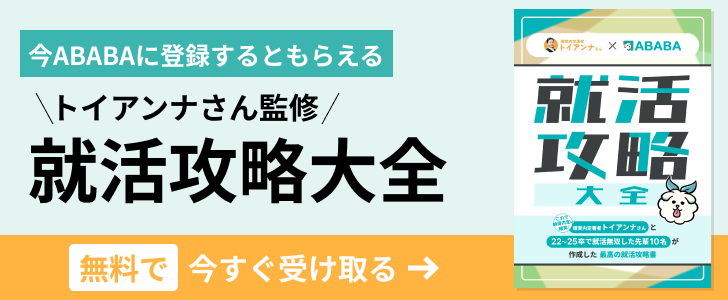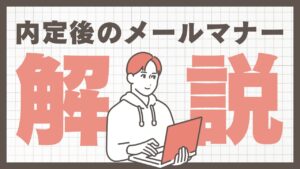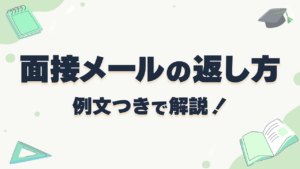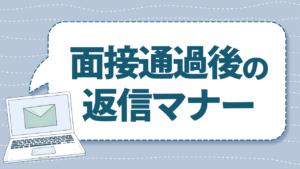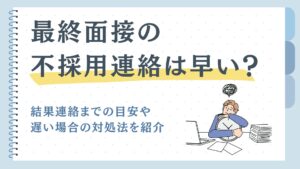就職活動が進む中、内定がなかなか得られず不安を感じていませんか?
本記事では、一般的な就活スケジュールや内定獲得の時期、そして「やばい」と感じたときの具体的な対策方法を詳しく解説します。
合否は運や相性の要素もあるため、まだ選考実施中の企業がある場合、諦めずにエントリーと選考対策を進めましょう。
まだ内定がない人でも、最短2週間で内定が取れる裏技として、スカウトサイトABABAがオススメです。
ABABAでは選考中の頑張りが評価されて、優良企業25社からスカウトが届きます。もし選考途中で落ちてもそこまでの頑張りが無駄になりません。
また、ESや一次面接などがカットされているため、内定まで早くたどり着けるのも特徴です。
就活後半にかけてスカウト数も増えてくるため、今のうちに登録しておきましょう。
就活でいつまでに内定が出ないとやばい?

就活は一斉に始まるため、自分だけ内定が出ないと焦ってしまうことでしょう。
内定を出すタイミングは企業によって異なりますが、一般的な時期の目安を知っておくことで就活を計画的に進められます。
ここでは、内定が出される時期について解説します。
大学4年の5月〜6月が一般的な内定獲得時期
経団連に所属している企業の場合、大学4年の5月〜6月が一般的な内定獲得時期です。就職プロセス調査(2023年卒)によると、初めて内定を獲得した時期は「3月」が最も多く、就職確定先から内定を取得した時期は「5月」「6月」が最も多い回答となっています。
就活が本格的に始まるのは大学3年生の3月頃からで、徐々に会社説明会への参加やエントリーシート(ES)の提出が増えるようになり、4~5月頃になると面接が集中します。その後、徐々に内定が出始めるようになるのです。一方で、通年採用や二時募集などで6月以降に内定を出している企業もあります。
なお、就職活動の終了時期については、「大学4年の10~3月頃」の割合が最も高くなっています(※2)。
※1:“就職みらい研究所 公式HP” 参照
※2: “2023年卒学生の就職活動の実態に関する調査” 参照
大学4年の1月に内定がなければ厳しい
厳密には、「〇月〇日までに内定がなければいけない」といった具体的な期日はありません。
とはいえ、4月入社のための準備期間も踏まえると、大学4年の1月頃までには内定を獲得しておきたいところです。
選考自体は1月以降もおこなわれていますが、すでに採用活動を終えている企業も多く、応募先が限られることは覚悟しましょう。
志望企業や業界ごとにスケジュールは異なる
志望する企業や業界ごとに、選考スケジュールは大きく異なります。業界ごとの具体的な傾向については、以下も参考にしてみてください。
・ベンチャー企業…経団連に参加しておらず、選考が早い傾向にある
・外資系企業…大学3年生の秋頃から選考がはじまる企業もある
・マスコミ業界…夏期インターンシップが選考となる企業が多い
就活の一般的なスケジュール

漠然と「やばい」と感じている方は、一般的な就活の全体スケジュールを把握しておきましょう。業界や企業ごとに詳細なスケジュールは異なりますが、大まかな流れは以下の通りです。
時期ごとのオススメ記事も紹介するので、自信がない人はぜひチェックしてみてくださいね。



就活でいつまでも内定が決まらない人の特徴

就活が長引くと「いつ内定がもらえるのか」と不安を感じる学生も多いのではないでしょうか。内定がなかなか決まらない人には共通する特徴があり、課題や弱点を改善できれば状況が好転するかもしれません。
ここでは、内定が決まらない人にありがちな特徴を紹介します。
就活スケジュールの把握が不足している
就活スケジュールの把握が不足していると、十分に対策できなかったり、応募すべき企業にエントリーできなかったりするリスクが生じます。就活の流れを把握していないせいで、いつのまにか就活後期に突入して「やばい」と感じてしまうケースは多いでしょう。
就活のスケジュールについては、こちらの記事で解説しています。就活スケジュールについて不安がある人はぜひチェックしてみてくださいね。

就活の軸が定まっていない
就活の軸が定まっていない場合も注意が必要です。「ただなんとなく気になる企業を受けている」という状態では、なかなか内定はもらえません。また、明確な軸がないために受け答えの回答がブレてしまい、「入社意欲がなさそう」といったマイナスイメージにつながるおそれもあります。
エントリーが少ない
就活で「やばい」と感じる人の中には、そもそもエントリーが少なくて内定が出ない人もいます。全国求人情報協会の情報によると、就活生のプレエントリー数は平均18.7社、書類選考数は11.4社となっています(※)。応募する企業を絞りすぎたり、大手や人気企業のみを受けたりしていると、内定をもらえる可能性は低くなってしまうのです。
志望動機が薄い
就活が長引く人の特徴の一つに、志望動機の内容が薄いことが挙げられます。
志望動機は面接で必ず聞かれるため、面接官の関心を引く内容でなければ高い評価を得ることは難しくなります。
▼内容が薄いと感じられる志望動機の例
- 企業理念や風土と軸がズレた内容になっている
- 内容の具体性が欠けている
- 競合他社との違い(なぜその企業なのか)が分からない など
志望動機が薄い場合には、自己分析や企業研究が不足していると捉えられる可能性があります。説得力を高めるには、企業が求める人材像や企業理念などを理解したうえで、自分の強みやキャリアビジョンと紐づけてアピールすることが必要です。
回答に一貫性がない
面接での回答に一貫性がない場合には、面接官が応募者の価値観や考え方を理解できず、企業とのマッチング度を測ることができません。また、エントリーシートに記載した内容と面接での発言が異なる場合は、信用を得にくくなります。
▼一貫性がない回答の例
「チームワークを大切にする」とエントリーシートに記載しながら、面接では「個人で成果を出すことに重点を置いてきた」と話す
一貫性のない回答をしてしまう原因には、自己分析の不足が考えられます。自分の軸を明確にして、矛盾のない受け答えができるように準備することが大切です。
面接対策ができていない
面接の対策が不十分な場合は、スムーズな質疑応答や十分な自己アピールができず、選考を通過することが難しくなります。例えば、緊張して声が小さくなったり、定番の質問に即答できなかったりすると、入社意欲が伝わりにくくなるでしょう。
面接でよい評価を目指すには、模擬面接を繰り返し実施することが有効です。
▼模擬面接を実施する方法
- 大学のキャリアサポート担当者に依頼する
- 外部セミナーに参加する
- AIを活用した模擬面接サービスを利用する
模擬面接を重ねて経験を積むことで、本番でも落ち着いて受け答えができるようになります。また、話し方や表情、声の大きさなども意識づけやすくなると考えられます。

就活で「やばい」と感じたときの対策は?

続いて、就活で「やばい」と感じたときの対策を紹介します。
・就活の軸を見直す
・プロのアドバイザーに相談する
・エントリーして持ち駒を増やす
・スカウトサービスを利用する
・志望企業の視野を広げる
・秋採用に企業にエントリーする
それぞれ詳しく見ていきましょう。
就活の軸を見直す
不採用続きで「やばい」と感じる場合、就活の軸を一度見直してみましょう。特に一次選考や二次選考で落ちてしまうケースでは、就活の軸が定まっていないために一貫性のない受け答えをしている可能性があります。
就活の軸を見直すことで、面接や書類選考での受け答えに迷いがなくなることはもちろん、エントリーする企業も適切に選べるようになります。
プロのアドバイザーに相談する
「何から改善すべきかわからない」「就活の方向性が合っているか不安」といった場合は、プロのアドバイザーに相談してみるとよいでしょう。大学のキャリアセンターやエージェントなど、さまざまな相談先があります。
具体的なアドバイスを求める際は、相談したい内容について事前にまとめておくとスムーズです。
エントリーして持ち駒を増やす
さまざまな企業に目を向けて、持ち駒を増やすこともポイントです。就活生の中には、「大手や人気企業以外は受けない」といった考えを持つ人も少なくありません。
しかし、知名度の低い企業の中にも、優良企業はたくさんあります。志望先を絞り過ぎていると感じる場合は、視野を広げてほかの業界や企業にもぜひ目を向けてみてください。
スカウトサービスを利用する
就活で「やばい」と感じている方の中には、何から手をつけてよいかわからない方もいるかもしれません。そういった場合には、スカウトサービスへの登録がおすすめです。スカウトサービスとは、自分の情報を登録するだけで企業からオファーを受けられるサービスのこと。
最近では書類選考や一次面接が免除されるものもあるので、効率的に就活を進めたい場合にはぴったりです。
志望企業の視野を広げる
特定の業種・職種にこだわりすぎると、内定獲得の機会を逃してしまうことがあります。
就活をするうえで、自分が入社したい業種・職種を目指すことは大切です。しかし、志望企業と自分の特性が合っていなかったり、競争率が高く選考に通過するハードルが高かったりする可能性もあります。
志望企業の選択肢を広げれば、新たなチャンスが生まれます。例えば、大手企業ばかりを志望していた学生が中小企業にも目を向けると、就活がスムーズに進むことがあります。広い視野で志望先を検討することで、自分に合った就職先が見つかる可能性が高まるでしょう。
秋採用の企業にエントリーする
就活が長引いている場合は、秋採用を実施している企業に応募する方法があります。
秋採用は、8月下旬ごろからエントリーが始まり、12月初旬までに内定を出す採用活動です。「春採用で予定していた採用人数を確保できなかった」「内定辞退者が現れた」などの企業では、秋採用が行われることがあります。
外資系企業や通年採用を実施する企業では、秋採用を実施しています。就職情報サイトや企業の採用ページをこまめにチェックして、秋採用の情報を見逃さないようにしましょう。
「REALME」で最適なエントリータイミングを知ろう
「いつまでに就活を終えなければならないのか」と焦る人は少なくありません。就活をスムーズに進めるには、エントリーのタイミングを見極めることがポイントです。
就活支援ツール「REALME」を活用すれば、自分にとって最適なエントリー時期を把握して戦略的に就活を進められます。
AI面接で志望企業の内定判定を確認できる
「REALME」では、AI面接を通じて志望企業の内定判定を確認できます。
AIが過去の合格者データと回答内容を比較して分析を行うことで、自分が内定を受けられる可能性が表示されます。
AI面接は約20分で完了するほか、何度でも実施することが可能です。振り返りを行いながら面接での対応力を身に付けられます。
適切なエントリータイミングが分かる
「REALME」を活用すると、自分にとって適切なエントリーのタイミングが分かります。
企業の最終面接まで進んだ就活生の平均能力値を蓄積したビッグデータに基づいて、志望企業のエントリー前に内定判定を確認できるため、内定判定がよいタイミングでエントリーを行うことが可能です。
例えば、応募者数が多い1次募集でエントリーするよりも、2次募集まで待ってエントリーするほうが内定判定の可能性が高くなるケースがあります。
可能性の低い選考プロセスを減らすことにより、効率的に就活を進められるでしょう。
AI分析で客観的な自己分析ができる
「REALME」には、AIによる自己分析機能が備わっています。
自己分析は就活の成功に欠かせませんが、自分だけでは気づけない特性や強み・弱みがあります。AIの分析を参考にすれば、自分の能力や価値観が可視化されるため、ES対策や面接対策に役立てられます。
また、自分とマッチングする可能性が高い業種・職種が提示されるため、エントリーする企業に迷っている人にも有効です。
就活で内定がいつまでも出ない場合によくある質問
Q. 就活はいつまでに終わらせるべき?
就活の進め方は人によって異なるので、明確な期日は特にありません。経団連に加盟している企業であれば、4年生の10月頃に内定式がおこなわれるため、それまでに内定が出ていることが1つの目安にはなるでしょう。
Q. 12月に内定がないとやばい?
12月になると秋採用を終了している企業も多く、「やばい」と感じる人の割合は多いかもしれません。しかし、12月以降に採用をおこなっている企業もあるため、視野を広げることで内定獲得のチャンスはあります。
Q. 平均的な就活終了期間はいつ?
平均的な就活終了期間は約1年〜1年半です。3年生の夏頃からインターンが始まり、4年生の夏頃までに内定を獲得する就活生が多いでしょう。
就活でいつまでも内定が出ないときは「やばい」と感じる前に対策しよう!

就活のスケジュールに明確な期日はありませんが、いつまでも内定が出ないままでは「やばい」と感じてしまうかもしれません。そうならないためにも、就活では早期からの対策が重要です。本記事で紹介したポイントを参考に、「やばい」と感じる前に対策してみてください。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)