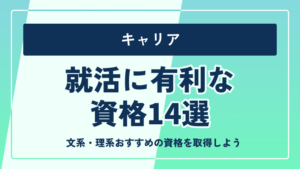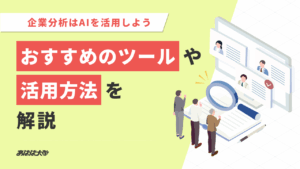「自分の強みが分からない」や「自分にあった企業が分からない」などの悩みを持つ学生は少なくありません。自己分析に対して悩みを抱える学生は多く、自己分析を苦手とする傾向があります。自己分析で自分のアピールポイントが分からないと就活の方向性が定まらず、就職活動を効率よく進めることが難しいでしょう。
本記事では、自己分析が分からない人の特徴や対処法、注意点をご紹介します。記事の最後には、あなたの強みを客観的に分析するAI面接サービス「REALME」についても紹介します。自己分析に苦労する人や就活の目標が決まらない人はぜひ参考にしてください。
自己分析がわからない人の特徴
自己分析を苦手と感じる人には共通点があります。
- 目的を理解せず過去を振り返るだけになっている
- 短所や弱みばかり気にしている
- 自己分析は面倒くさいと思っている
ここからは、自己分析がわからない人の特徴について詳しく解説します。
目的を理解せず過去を振り返るだけになっている
自己分析をする目的が理解できなければ、明確なゴールは見えません。何となく始めるのではなく「自分にあった企業を見つけるため」や「自己PRを考えるため」などの明確な目的を設定しましょう。目的が定まれば、自己分析の始め方や分析すべき項目が分かるでしょう。
一方、これまでの経験や考え方を振り返るだけでは自己分析は完璧とはいえません。今までの経験を整理し、自分の強みや弱み、価値観や興味などを深掘りすることが重要です。
短所や弱みばかり気にしている
自分を過小評価し、短所や弱みばかり気にする人は自己分析が上手くできない可能性が高いです。幼少期から自己PRをする機会がほとんどなかった日本人は、自分のアピールが苦手と言われています。
そのため、今までの経験を客観的に捉えて、自分を評価しましょう。短所しか見つからない場合は、「気が弱い→思いやりがある」など短所を長所に言い換える方法をおすすめします。
自己分析は面倒くさいと思っている
自己分析が分からない人の中には、自己分析がめんどくさいものと勘違いする人もいるでしょう。また、自己分析は長時間机にむかって熟考しなければならないというイメージを持つ人もいるかもしれません。
最近はスマートフォンやパソコンで簡単に自己分析できるツールがあります。自己分析をめんどうに感じる人は、自分に合った分析方法を見つけるとよいでしょう。
自己分析がわからないときの簡単5ステップ
自己分析をどのように進めたらよいかわからないときは、5つのステップに分けて少しずつ進めるとよいでしょう。
- 自己分析の目的を明確にする
- 自分の今の状態を把握する
- 信頼できる周囲の人に自分の印象を聞く
- 過去の経験を振り返る
- 5年後や10年後の理想を洗い出す
それぞれのステップで何をするべきか解説します。
自己分析の目的を明確にする
まずはなぜ自己分析を行うのか、目的を明確に定めましょう。
たとえば、就職活動の軸を固めたい場合や、面接での自分のアピールポイントを準備したい場合、目的によって目標が異なります。自己分析を通して最終的にどのような成果を得たいのかを具体的にイメージすることが、効率的かつ効果的な自己分析の第一歩です。
明確な目的意識があれば、自己理解が深まり、企業選びやキャリア形成にもつながる適切な判断がしやすくなります。さらに、面接の場でも自分の考えを整理して伝えられるようになるため、準備段階で目的を意識しましょう。
自分の今の状態を把握する
自己分析で大切なのは、現在の価値観や強みを正確に把握することです。
自分の現在を把握する自己理解は、なぜその価値観が形成されたのかを過去のエピソードや経験と紐づけて書き出すことで深まります。
自分を知るための質問例としては、以下が挙げられます。
- どんな時にやりがいを感じるか
- 過去に成功した経験は何か
- どんな環境で力を発揮できるか
これらの質問に答える過程で自己理解が進み、就職活動やキャリア形成の基盤が固まるでしょう。
信頼できる周囲の人に自分の印象を聞く
自己分析は自分ひとりで行うよりも、周囲の信頼できる人から自分の印象を聞くと、より深く効率的に進められます。
客観的な視点を取り入れると、自分では気づきにくい強みや特徴が見えてきます。友人や家族、アルバイト先の同僚などに質問し「自分のどんなところが印象に残っているか」「一緒にいてどう感じるか」と具体的に尋ねるとよいでしょう。
率直な意見をもらうために、自己分析の目的を伝え、良い面だけでなく改善点も尋ねるのがおすすめです。多角的なフィードバックをもとに自己理解を深めると、就職活動や将来のキャリア形成に役立ちます。
過去の経験を振り返る
過去の経験を振り返るのは、自己分析において自分の価値観を明確にする大切なステップです。良い経験だけでなく、失敗や困難だったことも書き出すと、より正確な自己理解が深まります。
過去を振り返る際には、以下を自身へ問いかけましょう。
- どんな場面で成長を感じたか
- なぜその経験が印象に残っているのか
- そのとき感じたことや学んだことは何か
自身へ問うと、自分の行動原理や考え方の傾向が見え、就職活動での自己PRや志望動機作成に生かせる具体的な材料を得られます。
5年後や10年後の理想を洗い出す
5年後や10年後の理想の自分を考える際は、現在の価値観をもとに具体的な将来像を描きましょう。理想をはっきりさせると、進むべき道が明確になり、日々の行動や目標設定がしやすくなります。
たとえば、以下の質問で理想を洗い出すとよいでしょう。
- どのような仕事をしていたいか
- どんな生活を送りたいか
- どんなスキルや経験を身につけていたいか
理想と現状のギャップを把握することで必要な努力や準備を逆算できます。そのため、自分の将来像が具体化し、キャリア形成や就職活動でも説得力のあるビジョンを示せるようになります。
自己分析がわからない場合の対処方法
自己分析が苦手な人は分析方法がわからないため、上手に情報収集ができていない可能性が高いです。自己分析の方法はいくつかありますが、簡単ですぐできるおすすめの方法をご紹介します。
モチベーショングラフ
モチベーショングラフとは、人生におけるモチベーションの高さを時系列で表しています。幼少期・小学生時代・中学生時代・高校時代・大学時代にわけて、起こった事柄とそれぞれのモチベーションの高さがどの程度だったかをグラフで表します。
例えば「長年続けていたバスケを辞めなければならなかったため、モチベーションは30%」「大学受験で第一志望の学校に受かったため、モチベーションは90%」など具体的なエピソードと数字を書き込みましょう。
今までの経験とモチベーションを振り返ることで、どのような出来事が自分のモチベーションを左右するかを客観的に分析できます。
自分史
自分史とは自分の歴史を年表のように記すことです。自分の経験を年表に書き出した後、その時どのような感情だったか、どのように行動したかを書き込みましょう。
自分の経験を客観的に理解することで、自分の好きなものや嫌いなもの、得意なことや苦手なことを区別できます。過去の行動や言動を知ることで、自分の強みを知る助けとなるでしょう。
Why?での掘り下げ
自分自身の思考や過去をWhy(なぜ?)と問いかけ掘り下げると、価値観を言語化できます。
例えば、下記のような過去を掘り下げてみましょう。
- なぜ今のゼミを選んだのか
- なんのために留学したのか
- 苦しい場面でなぜ頑張ることができたのか
- なぜアルバイトが楽しかったのか
何度もWhyを繰り返すことで、自分では気づいてなかった強みや価値観を発掘できます。具体的に言語化できるようになると、面接でも根拠を持って発言できるでしょう。
マインドマップ
マインドマップとは、紙の真ん中に自分を置き、自分を中心に趣味や苦手なこと、頑張っていることなどを書き出す方法です。書き出すことで自分の考えを視覚化できるため、頭を整理したい人におすすめです。
マインドマップは以下の手順で行います。
- 中央に自分を置く
- 趣味や苦手なこと、好きなことを書く
- それぞれの連想したことに「なぜ?」と問う
- 「なぜ」と深掘りし価値観をまとめる
見やすさを意識して、短い言葉でまとめたり、視覚的に色分けするなど、工夫しましょう。
ジョハリの窓
ジョハリの窓とは、自分の認識と、他人からの認識とのズレを理解できるフレームワークです。
自分の性質を書き出し、家族や友人に、自分に当てはまっていると感じるものを選んでもらいます。
その性質を下記4つに当てはめることで、自分では思いつかなかった性質や自分の弱みを改善できるヒントを発見できます。
- 自分も他社も理解している性質(開放の窓)
- 自分では理解していないけど、他社に理解されている性質(盲点の窓)
- 自分では理解しているけど、他社に理解されていない性質(隠蔽の窓)
- 自分も他人も理解していない性質(未知の窓)
SWOT分析
SWOT分析とは自分の強みと弱み、そして就活における自分のメリット・デメリットを知るフレームワークです。
- 自分の強み(Strength)
- 自分の弱み(Weakness)
- 自分のメリットになる外部要因(Opportunity)
- 自分のデメリットになる外部要因(Threat)
上記を書き出すことで、就活における自分の立ち位置や課題がよりクリアになります。自分に合った企業や職種の方向性を客観的に判断でき、説得力のある志望動機や自己PRにもつなげやすくなるでしょう。
自分に質問
自分自身に質問をして自分を深掘りする方法です。質問リストを作成し、一問一答することで、自分への理解を深めます。ただ回答するだけではなく「なぜしたのか」「何を得られたのか」といった深掘りを行うことで、より本質的な自己理解につながります。
また自分で質問した内容が、実際の面接で聞かれるものと重なることも多いです。事前に回答を整理することが、自信につながり、面接当日を自信をもって迎えることができるでしょう。
他己分析
他者からの評価を客観的に分析する方法が他己分析です。親友や家族など自分のことをよく知っている人達に自己分析を手伝ってもらうように依頼しましょう。他の人から意見を聞くことで、自身では気づけなかった強みや特徴が見えてきます。
また、自己分析と並行して行うことで、自分と他者との認識のズレまたは一致するところを発見できます。自己分析は1人だけに頼らず、複数の人に頼むことで多角的に自分を知ることができるためおすすめです。
WILL CAN MUST
自分の将来像や理想の働き方を考えるときに役立つのが、WILL CAN MUSTのフレームワークです。
まずは下記3つを書き出してみましょう、
- なりたい姿(WILL)
- 今できること(CAN)
- すべきこと(MUST)
3つの要素の重なる部分から、キャリアや働き方に求めることが見えてきます。
自分自身の求めることを知ることで、就職の軸が定まり、採用のミスマッチを防げますし、理想の職場と感じる企業を選びやすくなるでしょう。
自己分析がわからない人に。自己分析のメリット
自己分析とは、自分の価値観を明確にするために重要です。
就活においても、その先の人生の選択においても、自分を理解していると迷わず方向をえらぶことができるでしょう。自己分析がわからない人向けに、自己分析のメリットを紹介します。
本当にやりたいことがわかる
自分の過去を振り返り、どのようなことに興味を持ち、何にやりがいを感じたかを分析することで「本当に望むこと」が明確になります。
この自己理解が深まると、企業や職種を選ぶ際に「自分の望む働き方」なのか判断できるようになり、入社後の「自分のやりたい仕事ではなかった」という後悔やミスマッチを防ぐことができます。
どの企業を選べば良いかわからない、判断できないという人は自己分析を行うことで選択がスムーズになるでしょう。
自分の強みに自信が持てる
自己分析を行うと、自分の強みや長所を理解できるようになります。もちろん、分析をしなくても、なんとなく自分の強みを理解している人もいるかもしれません。ただ根拠が曖昧だと、面接で深掘りされたときに、うまく答えられず、説得力に欠けることもあるでしょう。
強みや長所の根拠も理解することで、面接でも自信をもって答えられますし、自分に自信がつきます。
また過去を分析することで、新たな強みや長所を見つけられるでしょう。
向き不向きを知ることができる
自分の強みを把握することも重要ですが、弱みも把握することで向いている仕事・向いていない仕事を知ることができます。
やりたいこと=得意なこととは限りません。例えば安定した事務職をやりたいと思っていても、黙々と作業を続けることが苦手な場合、ストレスになり早くに転職を考えるようになるかもしれません。
このようなミスマッチを避けるためには、自分の特性や傾向を客観的に把握しておくことが重要です。
正しい自己分析で「こんなはずではなかった」を防ぎましょう。
面接で堂々と話せるようになる
自分を理解し言語化できるようになると、面接で堂々と話せるようになり、選考通過率がアップします。
面接では、「それはなぜ?」「具体的にはどんな経験?」と1つの回答に対し深掘りされることもあるでしょう。根拠のないままだと、うまく答えられないかもしれません。
ですが、強みやエントリーした理由を、根拠も含め理解していると、練習していなかった質問にもスムーズに答えやすくなるでしょう。またESのPR文作成でも悩むことが少なくなります。
企業に選ばれやすくなる
企業が採用で重視しているのは、単にスキルや学歴が優れている人材だけではありません。実際には、自社と文化や価値観がマッチした人材を求めています。いくら高い能力やスキルがあっても価値観が合致していなければ選考の通過は難しいでしょう。
自己分析で自分の価値観を明確にしておくと、自分にあった企業を選びやすくなります。また、面接でも企業と自身の価値観が近いことを具体的に伝えられると、通過率が向上するでしょう。
自己分析がわからない人が誤解していること
自己理解がわからない人は、いくつか誤解をしている可能性があります。誤解があると、自己理解の本質や進め方などがわからなくなってしまうのかもしれません。
自己理解がわからない人が誤解していることについてご紹介します。
自己分析に完璧はない
自己分析には「ここまでできれば完璧」というゴールは存在しません。
人の価値観や興味は環境や経験によって変化するため、一度まとめた内容も時間がたつと違う視点から捉え直せる場合があります。そのため、最初から完璧さを求めるよりも、現時点での仮の答えを言語化し、選考体験やインターンで得た気づきを加えながら更新していく姿勢が重要です。
就職活動の中で、自己PRが伝わりやすかった場面や逆に違和感を覚えた場面を振り返り、その都度自己分析の内容を見直すと、精度は少しずつ高まります。繰り返しブラッシュアップしていく前提で取り組むと、自己分析へのハードルが下がり、行動にも移しやすくなるでしょう。
自己分析は他人と比べるものではない
自己分析の目的は、自分自身を深く知ることです。他人と比較して優劣をつけるものではありません。
他人より劣っていると感じる思い込みは、自己分析を進める妨げになりがちです。自分には独自の価値観や経験があり、それによって形成された強みや弱みの理解が大切です。
「比較ではなく、自分らしさを引き出していくのが自己分析の本質である」と理解すると、自分自身の成長や進むべき方向性が見えやすくなり、焦りや不安を減らせます。他人と比較せず、自己を見つめ直すと、前向きなキャリア形成に繋がるでしょう。
周りの声も取り入れる
自己分析は自分ひとりで行わなければならないと思われがちですが、自分の視点だけに頼ると、見落としや偏りが生じやすく深い理解につながりません。
そのため、周囲の声や客観的な意見を取り入れた方が、よりスムーズに深く理解しやすくなります。信頼できる友人や家族、先輩などに自分の強みや印象を聞くと、自分では気づかない特徴が浮かび上がってくるので、ぜひ協力してもらいましょう。また、AI面接アプリREALMEを活用すれば、客観的に自分を分析できます。
多角的な視点を得ると、自己理解が深まり、自身の魅力をより正確に把握できるようになるでしょう。
悪いことも振り返る
自己分析は、良い経験や成功だけを振り返るものではありません。挫折や失敗した出来事も含めて過去を見直すと、自分を多角的に理解できます。
悪い経験を乗り越えた過程からも、自分の価値観や特性が浮かび上がるでしょう。失敗の原因やそこから学んだことを整理すると、自己理解が深まり、弱みの克服にもつながります。
成功体験だけでなく、マイナスの経験も自己分析に活かすことが、より実践的で意味のある自己理解を促進します。
自己分析がわからない際の注意点
自己分析がうまくできないと就活が長引いてしまいます。また、自分の特性を活かせる企業に就職できない可能性もあるため注意しましょう。ここからは、自己分析が苦手な人がやってしまいがちな注意点を2点ご紹介します。
思い込みで書かない
自分の思い込みだけで自己分析すると、本来の価値観や強みが見えてこない可能性があります。主観のみで自己分析を行うと本来の自分ではなく、妄想上の自分ができ上がってしまいます。
なりたい自分、こうでありたい自分を考えることも大切です。ただし、今の自分を公正に判断しなければなりません。そのためには、過去の経験や行動から強みを分析する必要があります。
企業の求める人物像に引っ張られない
企業が求める人物像に影響されすぎないように気を付けましょう。志望企業の求める人物像に合わせると好印象を与えられるため、その企業に就職できる可能性が高まります。ただし、本来の自分とズレが大きい場合は、就職後に自分の強みや価値観を活かせない恐れがあります。
自己分析を徹底的に行い、自分の長所・短所を明確にし、自分に合う企業を見つけましょう。
「REALME」を活用して自己分析がわからないを解消!
「自己分析が苦手」「自己PRの方法がわからない」という人にはAI面接サービスの「REALME」がオススメです。AI面接であなたの強みを客観的に分析します。自己分析に不安がある人はぜひ活用しましょう。
合格ラインを突破した学生のESが見られる
「REALME」では志望企業の合格ラインをクリアした学生の自己PRやガクチカ、ESなどが閲覧できます。合格ラインをクリアした学生のESや面接回答例を参考にすることで、自分に最適なアピール方法が見えてきます。自己分析がわからないと悩んでいる人は、同じ経験や同じような強みを持っている人の回答例をもとにブラッシュアップしましょう。
客観的に自分の強みと弱みがわかる
「REALME」を活用すると客観的視点で自分の強み・弱みを把握できます。「REALME」は、面接内容をもとに就職において重要な14の能力を点数化してくれます。今まで自分では気付けなかった強みや弱みを客観的に把握でき、就活に活かせる新たな一面に気づく可能性があります。
自己分析がわからなくて弱みや短所ばかりに目がいってしまった人は、自分では気づけなかった強みを把握するため自信が持てるでしょう。
エントリー前に志望企業の内定判定を知れる
「REALME」のAI面接を行うことで、志望企業の内定判定を算出してもらうことができます。最終面接まで進んだ就活生のデータとあなたのデータを比較した上で内定の可能性を割り出してくれるため、自分の正確な立ち位置を把握できます。
自分の現在地を事前に知れるため、最適なタイミングでエントリーを行うことが可能です。「自己分析に自信がない」「内定に届くか分からない」という人はAI面接を事前にするとよいでしょう。
自己分析がわからないを克服して自分自身を理解しよう!
自己分析がわからないからといって分析を先送りにしていると就活が長引きます。自己分析は就活だけでなく、就職後の働き方を模索したり、将来の人生設計を立てる上でも必要な作業です。就活を始める際は、なるべく早い段階で自己分析を進めましょう。
自己分析は、自分一人で行う以外にサービスやツールを活用することも可能です。苦手意識を持たず、さまざまな方法を活用し、自己分析に対する苦手意識を克服しましょう。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)