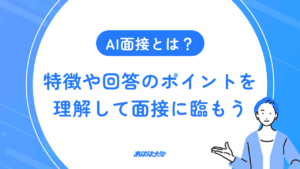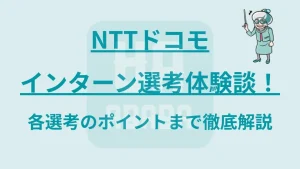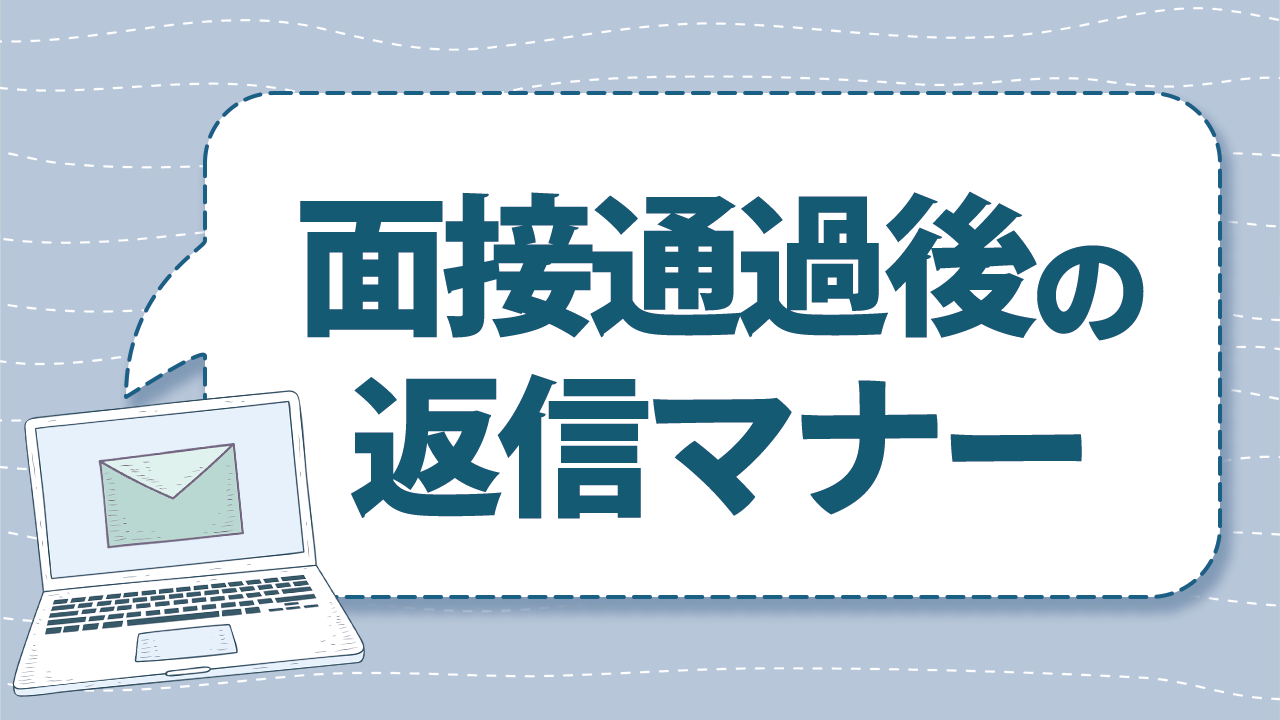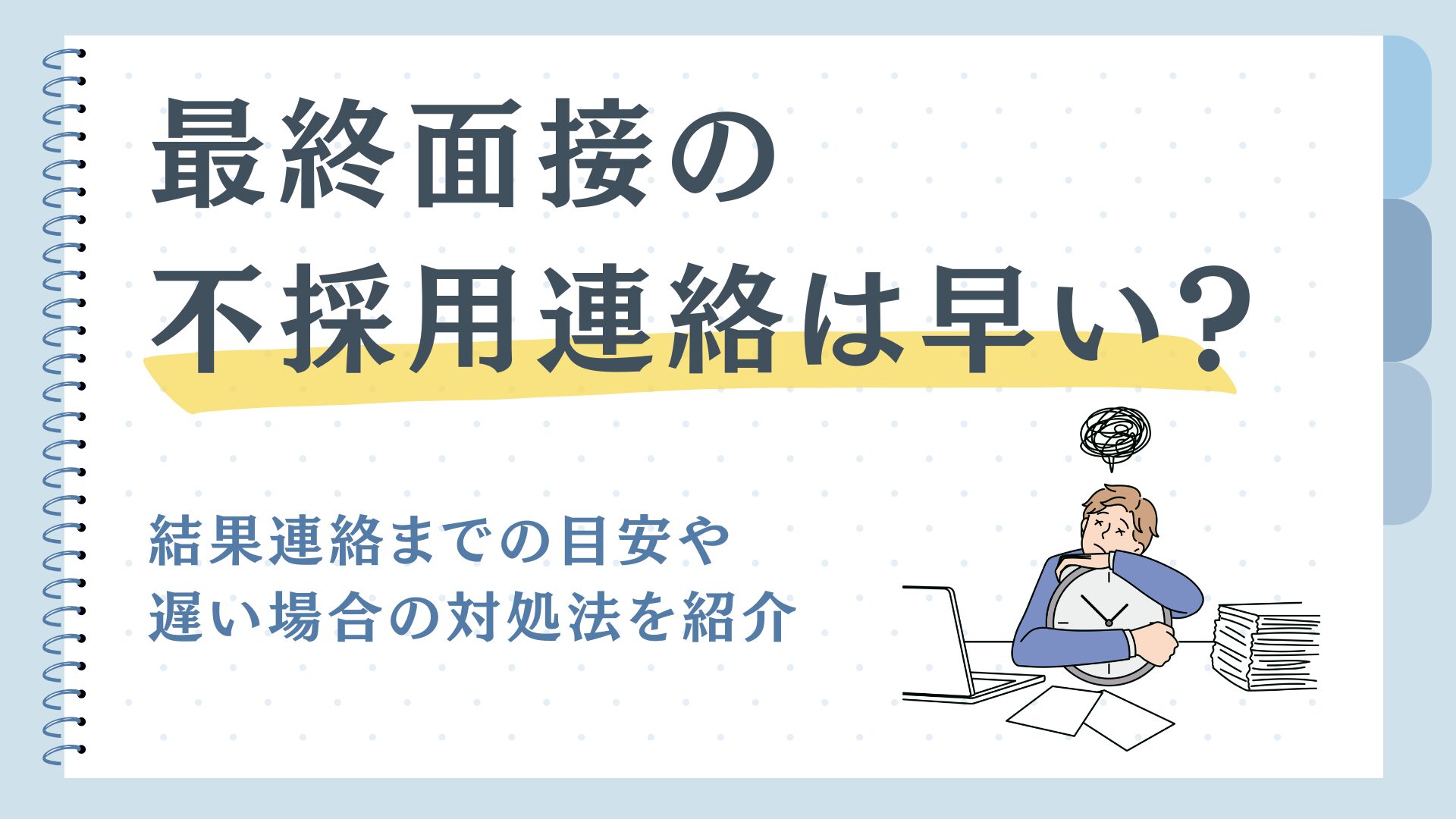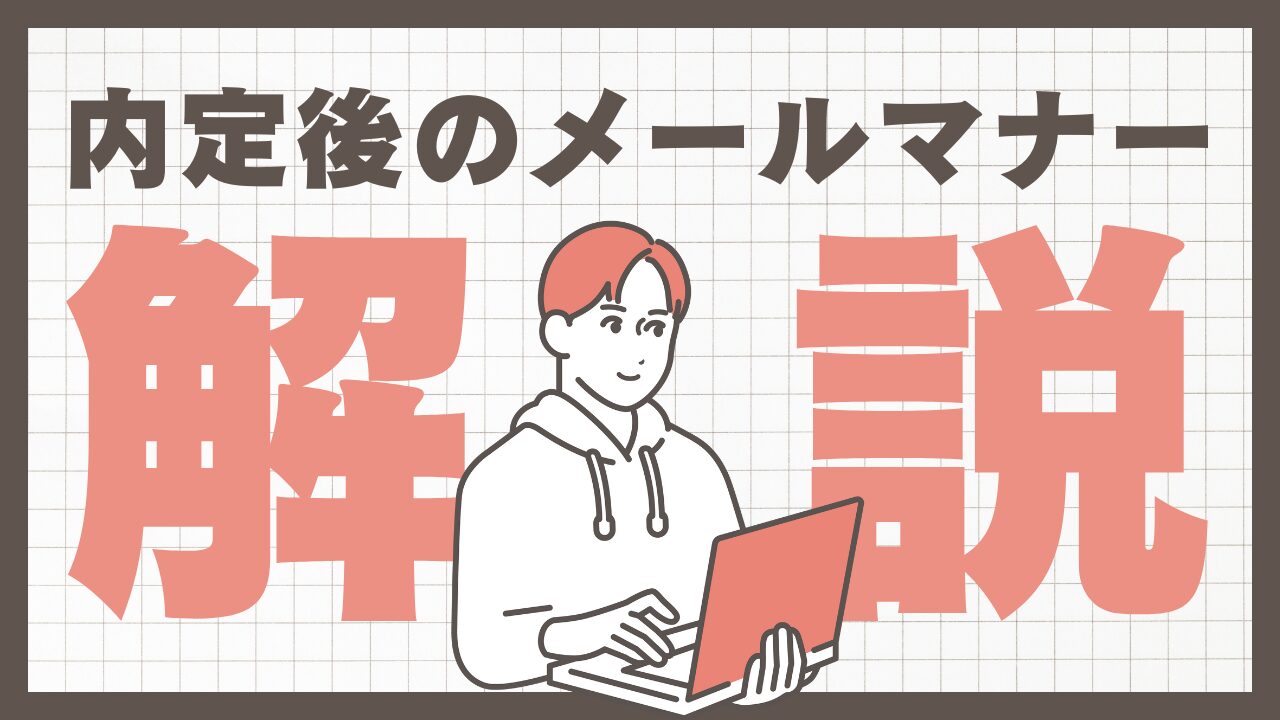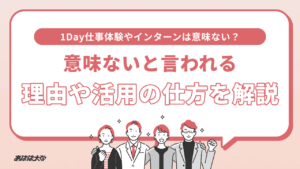採用選考で避けて通れないのが面接です。書類や筆記試験だけでは分からない、学生の人となりや適性を知るために、どの企業も面接を実施します。しかし、なかには「面接がどうしても苦手で就職できない」という人もいるでしょう。
本記事では、面接が苦手な人に実践していただきたい対策や、うまく答えられないときの対処法を解説します。記事の最後には、面接対策をサポートしてくれるツール「REALME」についても紹介します。気になる方は、ぜひ詳細をご覧ください。
面接が苦手で就職できない人の傾向
はじめに、面接が苦手で主食いできない人の傾向について解説しましょう。一言で「苦手」といっても、苦手なポイントは人によって異なります。自分がどの傾向にあてはまるのか考えてみてください。
面接に不安を感じやすい
コミュニケーション自体が不得意であったり、自分に自信が持てなかったりする人は、面接に対する苦手意識を抱えた状態で面接に臨む傾向があります。面接に不安を感じて緊張しやすく、面接官の些細な表情や発言をネガティブに受けとめてしまって、その積み重ねがパフォーマンスの低下を招きます。
このような傾向がある人は、面接に対する考えを変えるよう心がけてください。「面接はテストではなく対話をするところ」「自分が入りたい会社の人に会える」というように前向きな意識で臨めば、不安が軽減できるでしょう。
要点がまとまっていない
要点がまとまっていない状態で質問に答えようとすると、面接官に言いたいことが伝わりにくくなります。その原因としては、緊張して頭の中が真っ白になってしまう、あるいは「完璧に回答しなくては」と意識しすぎている、というケースが考えられます。
この場合は、面接の回答で満点を目指さないことが大切です。60~70点くらい採れればよいという気持ちで力を抜いて臨んでみてください。全力でアピールしようとせずに「面接官との対話を楽しもう」という気持ちになれれば、緊張がほぐれやすくなるでしょう。
逆質問の意図を理解していない
面接の終盤で企業が学生に「何か質問はありませんか」と問いかけるのが逆質問です。企業はこのような逆質問をして、自社に対する学生の熱意や理解度を測ろうとしています。そうした意図を理解していないと、面接で良い結果を残すのが難しくなるでしょう。
逆質問に対して「特にありません」と答えてしまうと「自社に興味がないのでは」と判断されるおそれがあります。どのような場合でも質問なしで終わることのないよう、企業に対する質問を複数用意して面接に臨み、入社の意思をアピールしましょう。
面接がうまくできない人の内定通過に向けた対策
面接が苦手だと感じている人が面接を通過するには、事前に次の5つの対策をすることをおすすめします。
面接の準備を徹底する
準備不足のまま面接に挑むと、スムーズに回答できず、気持ちが焦ってますます答えられないという悪循環に陥りがちです。このような状況を防ぐため、面接準備を徹底しましょう。
面接で質問されることは、自分に対する内容と企業に関する内容に大別できます。自信を持って回答するには、自己分析と企業研究を徹底することが必要です。これによって、志望動機や自分の長所短所などに関して、自分なりの考えが持てるようになり、面接で想定外の質問が出た場合でも慌てることなく回答できるでしょう。
頻出質問に答えられるようにする
どのような質問をされるのか不安な場合は、不安を払拭するために頻出質問を拾い出して予習しましょう。
頻出質問の例は次のとおりです。
- 自己PRをしてください
- 周りからどのような人だと言われますか
- 座右の銘はなんですか
- ガクチカ(学生時代に力をいれたこと)を教えてください
- 学生時代に苦労したことを教えてください
- 大学では何を学んでいますか
- 中学・高校ではどのような部活動をしていましたか
- 志望動機を教えてください
- なぜ他社ではなくこの企業なのですか
- 仕事で壁にぶつかったらどうしますか
- 大学の専攻とは違う業界を志望するのはなぜですか
- この会社の志望度はどのくらいですか
- あなたを採用するとどのようなメリットがありますか
- 当社の商品やサービスについて説明してください
- この業界が抱える課題は何だと思いますか
- 今日は暑いですね
- 緊張していますか
- 5年後のビジョンはありますか
- 仕事以外の夢を教えてください
新卒者に対しては特に、人柄を知るための質問が多い傾向があります。それぞれの質問の意図を考えたうえで、自分なりの回答を準備しましょう。
伝え方を意識する
質問に答える際は、伝え方に関して次のように意識しましょう。
- 結論から話す
- 早口にならないように意識する
- 簡潔に伝える
結論ファーストで話すことで、相手に話が伝わりやすくなります。そのような質問に対しても、結論→理由→具体例→再び結論という構成で回答するよう心がけましょう。
緊張して早口になるのは誰にでもあることですが、せっかくよい回答をしているのに面接官に伝わりにくいのは残念です。普段の8割ほどの速さを心がけて話してください。
簡潔に伝えるよう意識することも重要です。エピソードを盛り込む場合は1つに絞り、回答がトータルで1分以内にまとまるように、日頃から練習しておきましょう。
第三者にチェックしてもらう
実際に声に出して面接の練習をする際は、自己満足に終わらないよう、第三者にチェックしてもらいましょう。家族や友人、キャリアセンターなどに面接官の役をお願いすることで、客観的な意見がもらえます。ときには表情や仕草、多用しがちな言い回しなど、自分では気づきにくい癖を教えてもらえることもあります。
率直な意見を言ってくれる人を選んで、練習相手になってもらいましょう。
模擬面接を繰り返し実施する
模擬面接を繰り返し実施することも必要です。本番を想定したシチュエーションで練習するため「面接の流れに慣れることができる」「面接中の立ち振る舞いやマナーが身につく」「予期せぬ状況にも落ちついて対応できるようになる」といったメリットがあります
人前で話すのが苦手な人や、面接の経験が少ない人におすすめの対策です。
面接でうまく答えられないときの対処法
事前にどれだけ対策をしても、面接でどうしてもうまく答えられないこともあるでしょう。その場合の対処法は次のとおりです。
- 緊張していることを面接の冒頭で面接官に伝える
- 「少し考える時間をください」とお願いする
- 正直に「分かりません」と回答する
面接の1番の目的は学生の人となりを知ることであり、完璧な回答を求めているわけではありません。上記のような答え方を覚えておくことで、回答につまったときでもうまく対処できます。
どのような場合でも黙り込んでしまうことは避け、できるだけ好印象を残せるように努めましょう。
面接が苦手を克服したい方にはAI全国共通模試「REALME」
面接対策を効率的に行いたい方には、就活サポートサービス「REALME」がおすすめです。AI面接を受けることによって面接の内容を改善できます。
ここからは「REALME」の3つのメリットについて紹介しましょう。
合格ラインを突破した就活生のES・面接解答例が見れる
「REALME」を活用すれば、企業の合格ラインを突破した就活生のESや面接解答例を閲覧できます。これを自分のデータと比較することで、改善点が分かります。
優秀な学生が面接でどのように話しているかを知ることは、面接に対する苦手意識を持つ人にとって、大きなメリットとなるでしょう。
AIとの面接で客観的な自己分析ができる
「REALME」で20分程度のAI面接を受けると、精密なフィードバックによって客観的な自己分析ができます。就活で重視される「問題解決力」「伝達力」「柔軟性」といった14の能力が点数化され、自分の強みや弱みが把握できます。これによって、面接でのアピールポイントが明確になり、自信を持って面接に挑めるでしょう。
「内定判定」によりエントリーのタイミングを最適化できる
「REALME」のAI面接を受ければ、企業の最終面接にまで進んだ学生のデータと比較することで、内定を獲得できる可能性が確認できます。この内定判定はA+・A・B+・B……E+・Eの10段階評価で表されるため、大学受験の模擬試験のように自分の現在地が分かります。
内定判定をもとに面接の内容を改善させれば、志望企業へのエントリーするタイミングを最適化できるでしょう。
面接対策を講じて「就職できない」から脱却しよう
本記事では、面接に対する苦手意識を克服するための対策や、うまく話せなくなった場合の対処法をご紹介しました。一つずつ実践して「面接が苦手で就職できない」という状況から脱却し、内定を勝ち取りましょう。
より効率的な就活を行いたい方には、就活サポートサービス「REALME」がおすすめです。ぜひAI面接をお試しください。