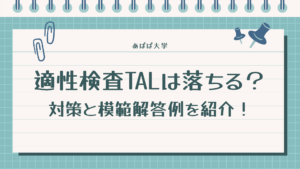ESで何度も書かなければいけない「志望動機」。数十社も受ける多忙な就活生にとっては、AIで作成できないかな、と思ったことも多いのではないでしょうか。しかし、志望動機はAIで作成すると採用担当者にバレてしまうではないかと不安な人も少なくないでしょう。そこで、今回は効率的に志望動機を作成するために、AIを志望動機に活用する具体的な方法を解説します。
AIを活用した就活サービスをお探しの方には「REALME」の活用がおすすめです。
志望動機をAIに丸投げするとバレる可能性が高い
志望動機のAI丸投げは、採用担当者に高確率でバレてしまいます。
企業の人事担当者は年間数百~数千の履歴書を審査しています。なので、もし文章の違和感や不自然な点があった場合、即座に察知することができるのです。
特に面接時に深掘り質問があった場合が危険です。
書面と実際の回答にズレが生じてしまうと、信頼を失う結果になりかねません。
志望動機のAI作成がバレるケース
結論から言うと、AIで作成した志望動機をそのままコピペすると、ほぼ確実にバレます。
採用担当者は膨大な応募書類を見てきた経験から、AI特有のパターンや、不自然さを瞬時に見抜く能力を持っているのです。
ここでは、志望動機のAI生成がバレてしまうケースを具体的に解説します。
言葉や表現に不自然さが残っている
AIで生成された文章には、日本語として微妙な違和感が残ることが多々あります。
例えば「です・ます」調が機械的に連続したり、「貴社における革新的な取り組みに際して」といった過度に堅苦しい表現が並ぶケースです。また、普段の会話では使わないような難解な言葉遣いや、「さらに」「このように」といった接続詞の多用も特徴的です。
一番バレてしまうのは、それらしいことを言っているようで中身が空っぽな文章になってしまっている場合です。「貴社の理念に共感しました」や「自己成長を図りたい」など、どの企業にも使い回せる汎用的な内容は、熱意も個性も感じられません。
自分の言葉や表現に置き換えなければ、採用担当者には「AIを使った」と即座に見破られてしまいます。
正確ではない情報が含まれる
AIが生成する文章に含まれる情報は、100%正確と言えるものではありません。誤った情報を含んでいる場合も多々あります。
これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、AIが学習データから誤った推論をしたり、存在しない情報を正しいかのように出力してしまうのです。
例えば具体的には、企業の事業内容が誤っていたり、すでに終了したプロジェクトに言及したり、競合他社の取り組みと混同してしまうなどがあります。これを防ぐためには、公式サイトやIR情報、最新のプレスリリースなどで必ず事実確認を行う必要があり、これを行わないと、「この応募者は本当に当社を調べたのか?」という疑念を持たれてしまいます。
企業研究が不足していると、志望度が低いと評価されてしまうため、AIが書いている情報を鵜呑みにすることはかなり危険です。
熱意が伝わらない
AIに志望動機を作成させると、良くも悪くもオリジナリティのない、感情の込もっていない文章になってしまいます。
採用担当者は多くの志望動機を見てきているので、その文章に本人の熱意が込められているかどうかを見抜く鋭い観察眼を持っています。
AIが生成する文章は論理的で整っていても、「なぜその企業でなければならないのか」という個人的な思いや体験が欠けています。志望動機で最も重要なのは、自分の経験や価値観と企業の特徴を結びつけて語ることです。「学生時代に○○の経験をしたので、貴社の△△という取り組みに強く惹かれた」などの具体的なエピソードがなければ、採用担当者の心に響きません。
自分の思いの部分は、必ず自分の言葉で表現しましょう。
志望動機はAIでどう作る?具体的な活用方法
さて、ここまでバレてしまうケースを説明してきましたが、志望動機にAIを使うことは決して悪いことではありません。
むしろ、AIは志望動機を効率的にブラッシュアップするためのツールとして活用すべきです。
大切なのは、AIを「代筆ツール」ではなく「思考整理のパートナー」として使うことです。
ここでは、AIの効果的な活用方法を詳しく解説していきます。
AIは壁打ち相手として使う
AIを活用する最も効果的な方法は、壁打ち相手として活用することです。壁打ちとは、自分の考えを相手に話すことで思考を整理する手法を指します。つまり、志望動機を「作ってもらう」のではなく、AIに「質問してもらう」のです。
例えば、「志望動機を考えたいので、私の考えを深掘りする質問を10個してください」というプロンプトを入力します。すると、AIは「なぜその業界に興味を持ったのか」「その企業の何に最も魅力を感じたか」「自分のどんな経験が活かせると思うか」といった志望動機に繋がる質問を投げかけてくれます。
これらの質問に一つずつ答えていくことで、自分でも気づいていなかった志望理由や、企業との接点が明確になっていきます。重要なのは、AIに答えを求めるのではなく、AIを使って自分の中にある答えを引き出すことです。この過程で得られた気づきやエピソードこそが、オリジナリティのある志望動機に繋がります。
プロンプトを詳細に設定する
生成AIの出力品質は、与えるプロンプトの質に大きく依存します。プロンプトとは、AIに与える「指示」のことです。例えば、「志望動機を書いて」という曖昧な指示では、ありきたりな内容しか生成されません。具体的に何をしてほしいのかを、詳細に伝える必要があります。
具体的な手順としては以下の通りです。
①自己分析の結果や自分の今までの経験を具体的に伝える
例)「大学で○○を専攻し、△△のプロジェクトでリーダーを務めた経験がある」「アルバイトで□□の課題を解決し、売上を20%向上させた」
※数字や固有名詞を含めて詳細に記載すること
②希望する職種や業界の特徴、なぜその分野に興味を持ったかの背景を伝える
例)「IT業界の中でも特にフィンテック分野に興味があり、金融のデジタル化に貢献したい」
※具体的な方向性を伝える
③企業研究で得た情報を伝える
例)「○○の事業に興味がある」「インターンで得た△△の体験に感銘を受けた」
※インターンや説明会で得た体験談があると良い
④「①~③を踏まえて(会社名)の志望動機を××字で作成して」と伝える
コツは、自己分析、希望職種や業種、今までの経験、キャリアプランなどのすでに決まっていることや事実を詳細に伝えることです。
自分がどんな人物かをしっかりAIに把握させるプロンプトを設定しましょう。
Webに載ってる企業の情報は事前に読み込ませる
生成AIを効果的に活用するには、事前の準備が必要です。特に志望企業の情報を正確にAIに理解させることで、より精度の高い志望動機を作成できます。
まず、企業の公式サイトに載っている情報をコピーし、AIに読み込ませます。URLを貼るだけではAIが正確に情報を取得できない場合があるので、必要な部分を直接テキストで入力しましょう。
また、最新のプレスリリースや採用ページに記載されている「求める人材像」も忘れずに入力しましょう。これらの情報をAIに学習させることで、その企業特有の用語や価値観を反映した志望動機を生成することができます。
ただし、注意すべきは情報漏洩リスクです。社外秘の情報や、インターンシップで知り得た内部情報は決してAIに読み込ませてはいけません。あくまで公開されている情報のみを使用し、情報セキュリティを徹底するようにしましょう。
志望動機をAIで作る際の注意点
AIで志望動機を作る時に最も重要なのは「AIはあくまで補助ツール」という認識を持つことです。最終的には必ず自分の目で確認し、自分の言葉で仕上げる作業が必要不可欠になってきます。
ここでは、AIで志望動機を作る際に、見落としがちな注意点を具体的に解説します。
自分の表現に書き換える
AIが生成した文章をコピペすることは、絶対に避けましょう。なぜなら、AIがそのまま生成した文章は、採用担当者にすぐにバレてしまうからです。
具体的には、AIで生成した文章の文末や接続詞を書き直したり、個人的なエピソードを入れるなどの方法を使って添削をしてください。
例)AI「貴社の革新的な技術力に魅力を感じ」
→「学生時代に○○を研究する中で、御社の△△技術に出会い、その可能性に心を動かされました」といった具体的なエピソードを交えた表現に変更
この作業を行うことで、文章に自然な温度感が生まれ、バレるリスクを減らすことができます。
また、自分の言葉に直す作業を行うことで、生成された文章の理解も深まり、面接で話す内容との乖離もなくなるのです。
内容に誤りがないかチェックする
AIが生成した内容には、必ず事実確認が必要です。なぜなら、AIで何度も繰り返し生成しているうちに情報が混同したり、変わっていたりすることがあるからです。
特に企業情報については、複数の信頼できる情報源でチェックすることが重要になってきます。
この時確認すべきポイントは、企業の正式名称、事業内容の正確性、最新の取り組みや方針です。例えば、組織再編で部署名が変わっていたり、事業から撤退していたりする可能性があります。
また、自分の実績についても、数値データは正確か、時系列に矛盾はないかを必ず確認しましょう。
最後に、生成された文章を何度も読み返し、論理的な矛盾がないか、前後の文脈が自然につながっているかもチェックしておきましょう。少しでも違和感がある部分は、自分の言葉で書き直すか、その部分を削除することも大切です。正確性を欠いた志望動機は、かえってマイナス評価に繋がってしまいます。
AIは上手に使えば味方|面接対策なら「REALME」
AIは使い方次第で、志望動機の作成も含めた、就活の強力な味方になります。この時重要なのは、AIを「考える代わり」ではなく「考えを深めるため」のツールとして活用することです。
REALMEは、AIを利用して、気軽に模擬面接や自己分析を行うことができるサービスです。たった14の質問に答えるだけで、あなたの強みや価値観を客観的に分析し、就活の軸を言語化してくれます。
また、8000社以上の過去の面接データを基に面接対策が行えます。志望動機について想定される追加質問を事前に把握し、練習できるため、本番の面接で慌てることがありません。
さらに、実際の企業の採用基準と照らし合わせた「内定可能性判定」機能により、志望動機の説得力を客観的に評価できます。AIを味方につけて、他の就活生と差をつけましょう。
AI面接で志望動機の深掘り対策が可能
REALMEのAI面接では、実際に面接で行われた質問を基にして、本番の面接官が行うような深掘り質問を体験できます。会社によっては「最近体験した良いサービスや体験があれば、その理由とともに教えてください」などの独特の質問がされることもあります。このような質問を繰り返し練習しておくと、自然で説得力のある回答ができるようになります。AIだからこそ、何度でも気軽に練習でき、自信を持って本番に臨めるのが大きな強みです。
AI面接の結果から内定判定が出せる
REALMEの最大の特徴は、AI面接の結果を基に、志望企業での内定可能性を判定できることです。過去の内定者データと比較し、あなたの面接結果がどのように評価されるかを客観的に分析します。判定結果には模範解答例も示されるので、回数を重ねるごとに、どんどんブラッシュアップしていくことができます。応募前に面接の完成度を確認でき、内定獲得の可能性を大幅に高めることができるのです。
過去に聞かれた質問をもとに面接練習ができる
REALMEには、実際の企業面接で聞かれた質問のデータベースが蓄積されています。8000社・20万問以上のデータに基づいた質問集を使って、志望動機に関連する想定質問への対策が可能です。会社別に受験することができるので、独特の質問があった場合も安心。実践的な練習を重ねることで、どんな質問にも動じない面接力が身につきます。
志望動機はAIを上手に使えば良いものができる
AIで作成した志望動機は、そのまま使えば不自然が残っていたり、面接との矛盾からバレる可能性が非常に高いです。しかし、AIを「壁打ち相手」として活用し、思考を整理するツールとして使えば、これほど心強い味方はありません。
大切なのは、AIに頼り切るのではなく、自分の経験や価値観を軸に据えることです。詳細なプロンプト設定や企業情報の事前準備により、AIの出力精度を高めつつ、最終的には必ず自分の言葉で仕上げる。この基本を守れば、一人で作るより効率的に、質の高い志望動機を作成できます。
ベースは自分自身で考えることを怠らずに、あくまで補助ツールとして、AIという最新技術を賢く活用していきましょう。

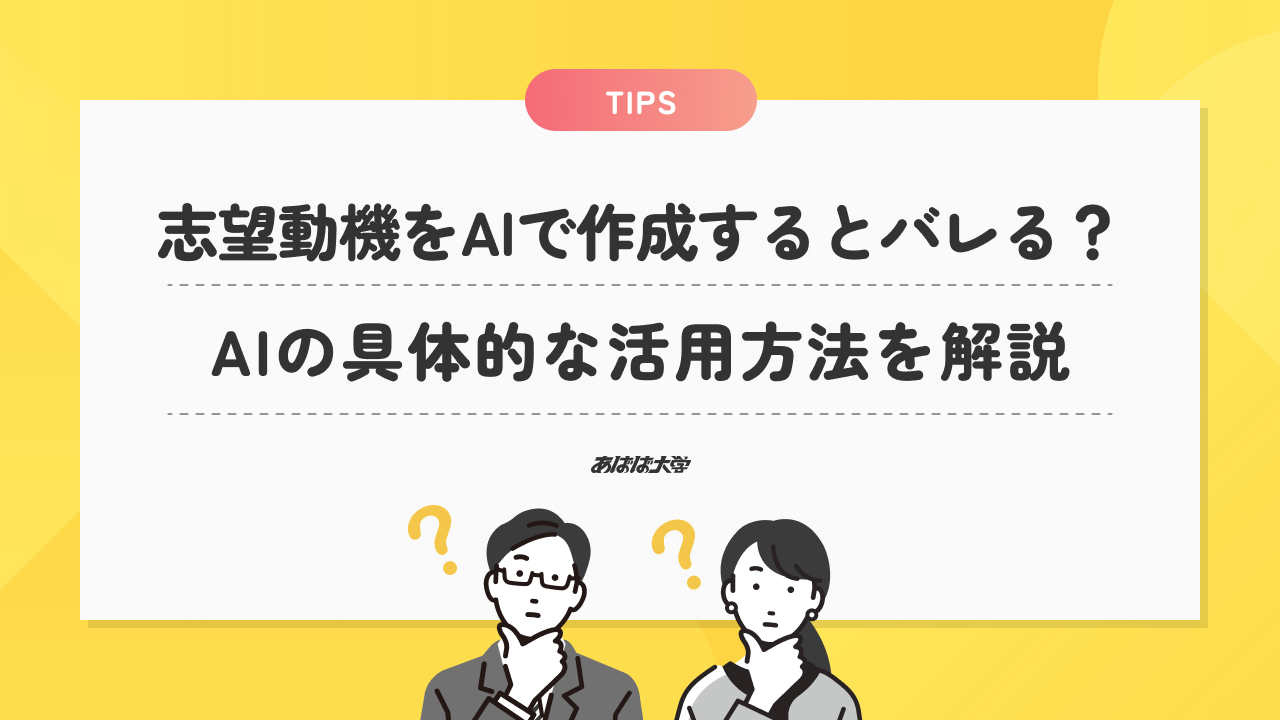
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)