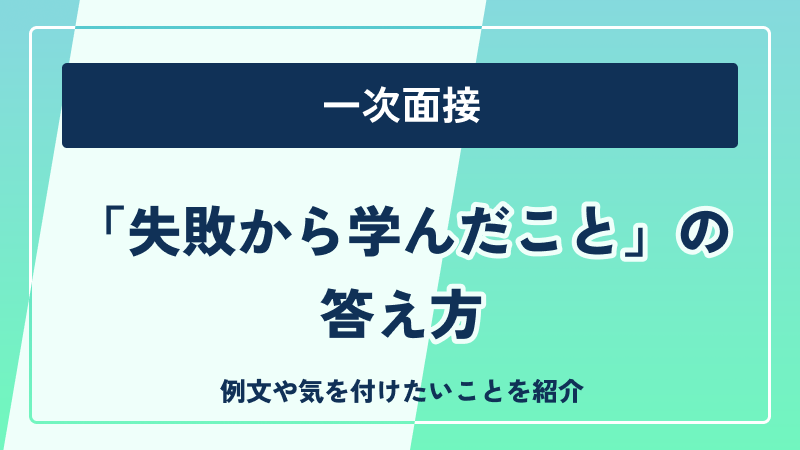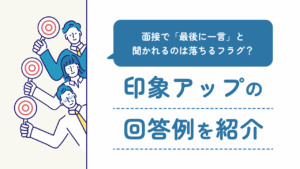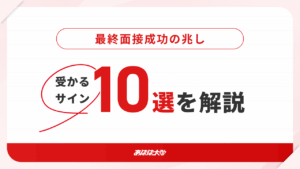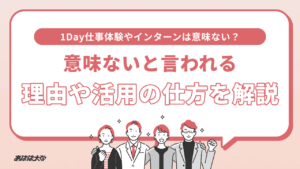この記事のまとめ
- 面接官は失敗から学んだことを通じて適応力や問題解決力を評価している
- 回答の構成は「結論 → 失敗のエピソード → 行動 → 学び」の順が効果的
- 失敗談は仕事に関連する内容を選び、自己理解を示すことが重要
就活を絶対に失敗したくない人向け
- 効率よく就活を進めたい人にオススメ!
- 「面接で落ちてしまうんじゃないか」と不安な人にオススメ!
就活を何から始めていいかわからない人にオススメなのが「REALME」です。REALMEでは就活のビックデータを学習したAIが、模擬面接・自己分析をサポートしてくれます。
面接官が「失敗から学んだこと」を聞く理由
面接官が失敗から学んだことを聞く理由として、以下のことが考えられます。
- 学生の適応力や問題解決力を知りたい
- 失敗への向き合い方を知りたい
面接官の意図を理解して、回答を考えましょう。
学生の問題解決力が知りたい
面接官は失敗をしないことよりも、失敗をした後の適応力や問題解決力があるかを重視します。失敗をしたとき、落ち込んだままで何もできないと、仕事がうまく回らないためです。
仕事上の失敗は誰もが経験することであり、失敗の有無よりもプラスに変える力が重要です。企業は失敗や困難を乗りこえる力をもち、学びに変えられる人物を求めています。
失敗に向き合える学生か知りたい
面接官は失敗談を通して、同じ失敗を繰り返さないように原因追究ができるかどうかを見定めています。
社会人は、仕事上でミスを犯したり、トラブルに巻き込まれたりすることもあるでしょう。失敗に向き合うことで自分の弱みを知り、克服や改善ができます。
面接では、失敗を自分の成長に変えられる人物であることをアピールしましょう。
「失敗から学んだこと」の答え方
失敗から学んだことを聞かれたときは、下記の順番で答えましょう。
1.結論
2.失敗したエピソード
3.失敗に対してどのように行動したか
4.入社後に失敗をどのように活かすか
まずは、どのような失敗をしたかを簡潔に伝えます。つぎに、具体的な状況を説明します。その後、失敗をどのように乗りこえたか、この経験を入社後どのように役立てるかを伝えましょう。
ポイントは失敗のパートはできるだけ短く伝えて、乗りこえたエピソードや学びの比重を大きくすることです。
「失敗から学んだこと」の例文
ここからは、失敗から学んだことに対するエピソードを紹介します。
失敗から学んだことのエピソードが思いつかない人は、ぜひ参考にしてください。
部活動での失敗談
1.結論:私の失敗は、バスケットボール部のキャプテンとしてチームをまとめられなかったことです。
2.内容:試合に勝ちたい想いが先行した結果、ハードな練習を取り入れ、部員に厳しくあたるようになりました。それが原因で、部活をやめたいと申し出る部員が数人出ました。
3.行動:私の反省点は、部員の想いを考えられていなかったことです。それからは、練習メニューや試合の戦術なども部員全員で話し合うようにしました。その結果、部員全員が部活に意欲をもって取り組むようになり、試合で勝つ回数も大幅に増えました。
4.学んだこと:私はこの経験から、キャプテンだからといって一人で抱え込まず、みんなに相談すれば大きな成果につながることを学びました。この経験を役立てて、入社後は団結力の高いチーム作りを目指したいと思います。
アルバイトの失敗談
1.結論:学生時代に飲食店のアルバイトで釣銭を渡し間違えたことが、私の失敗談です。
2.内容:レジ担当をしていたときに、忙しくて慌ててしまい、釣銭を多く渡してしまいました。閉店後、レジのお金が合わず店や従業員に迷惑をかけてしまいました。
3.行動:その後、私は同じミスをしないために、確認を徹底するようになりました。また、忙しいときに失念しないように、レジに「2回確認する」と書いたシールを貼りました。その結果、私だけでなく従業員全員のレジミスが減り、店長からお褒めの言葉をもらっています。
4.学んだこと:なぜミスしたかの原因を追究することで、同じミスは防げると学びました。また、ミスの解決策を共有することで、チーム全体のミスも減らせた点は大きな学びです。入社後はこの経験をもとに、ミスをしたときは原因追及と解決策の共有を徹底したいと思います。
日常での失敗談
1.結論:私の過去の失敗は料理中にやけどをしたことです。
2.内容:家で料理をすることが多く、その日は好物の唐揚げを作っていました。料理に慣れていたこともあり、イヤホンで音楽を聞いていたらいつもより油の温度をあげ過ぎてしまい、油がはねてやけどをしました。
3.行動:慣れているとはいえ、片手間で油を扱うことは危険だったと反省しました。料理中に音楽を聞くことはやめて、集中できる環境を作りました。その結果、唐揚げ作りが上達し、今では音で唐揚げの揚がり具合を判断できるほどです。
4.学んだこと:慣れてきて気が緩むと、ミスが起こりやすいことを学びました。この経験を役立てて、業務に慣れたときこそ慎重に取り組みたいと思います。
「失敗から学んだこと」の回答で気を付けたいこと
失敗から学んだことへの回答次第では、面接官の評価につながらないケースもあります。ここでは回答で気を付けるポイントを紹介します。
「失敗してません」と答えない
「失敗をしてません」「失敗をしたことはありません」と答えることは逆効果です。
そもそも、「失敗から学んだことは?」の質問に対して「失敗してません」は正しい回答ではありません。質問の意図を理解していないとみなされ、評価が下がる恐れがあります。
また、失敗は誰しもが経験するものです。「失敗していない」と答えると、自己理解が足りていないと判断されるでしょう。
仕事に活かせる内容ではない話しは避ける
恋愛や家庭内での失敗など、仕事に活かせない内容のエピソードは避けましょう。面接官は過去の失敗経験から、入社後の業務への取り組みや会社との相性を見定めています。バイトや部活、インターンなど仕事に活かせるようなエピソードを選びましょう。
また、ウケを狙った自虐的な失敗談も控えた方がよいといえます。そもそも面接官を笑わせる必要はなく、むしろ印象を悪くするリスクがあります。
失敗談だけ・挫折経験だけで終わらせない
学生によくあるミスとして「失敗談や挫折経験だけを伝えてしまう」ことがあげられます。
面接官が聞きたいことは失敗ではなく、失敗から学んだことです。
失敗や挫折のエピソードは短くして、その後の行動に重きを置きましょう。失敗経験は失敗から得た学びや対策方法、挫折経験は課題への向き合い方を明確に伝えることが大切です。
AI面接「REALME」で面接対策をしよう

面接は練習や経験を積むほど上達します。失敗から学んだことのようなエピソードトークや面接の受け答えに自信がない人はAI面接「REALME」の利用がおすすめです。ここからは「REALME」の特徴を紹介します。
志望企業の内定判定を確認できる
「REALME」は、AI面接後に内定判定を出してくれます。志望企業の最終面接に進んだ学生のデータと比較した上で内定判定を出しているため、自分の正確な現在地を把握できます。
失敗から学んだことのエピソードが完成したら、内定判定で自分の立ち位置を確認してください。
AIで面接での最適なアピール方法が分かる
自分自身の失敗経験談が作成できても、本当に面接で通用するかどうかは分かりません。
「REALME」では、志望企業の最終面接まで進んだ学生の回答例を確認できます。自分のエピソードと見比べることで、より効果的な伝え方が学べるでしょう。
志望企業に受かるためのFBが確認できる
「REALME」は、面接で重視される14項目の能力を数値化してフィードバックしてくれます。内定をもらうためにどの部分を強化すればよいかが明確になり、対策しやすくなるでしょう。
また、フィードバックをもとに自分の強みと弱みが把握できれば、面接の質疑応答にも役立てられます。
例文を参考に「失敗から学んだこと」で好印象を残そう
面接官は「失敗から学んだこと」の回答を通して、問題解決力や失敗に向き合う姿勢を判断します。面接官の意図を理解し、自分の強みをアピールできるような回答を準備をしましょう。今回紹介した例文を参考にして、面接で好印象を残してください。
また、面接対策や練習には「REALME」の利用がおすすめです。AI面接をはじめとするサービスを活用して、就職活動を有利に進められるでしょう。