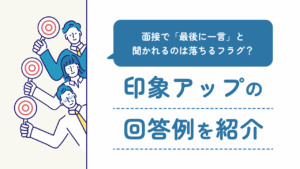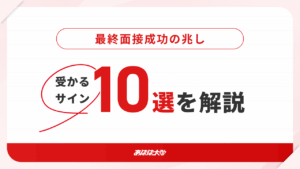新卒採用の面接対策で、具体的にどのようなことをすればよいのかが分からない就活生は少なくありません。「面接でどのようにして熱意を伝えればよいのか」や「逆質問の返し方が分からない」など、不安に思う人もいるでしょう。
本記事では、新卒採用の面接対策について具体的なポイントやよくある質問例など、事前準備に役立つことをご紹介します。
この記事の最後では、AI面接アプリ「REALME」についても紹介します。本番以上に深掘りしてくれるAIとリアルな面接対策が可能のため、面接対策に悩んでいる人は参考にしてください。
知っておきたい面接の基本
就職活動を行うにあたって、面接は避けて通れない通過ポイントです。面接にはどのようなスタイルがあるのか、しっかりと把握しましょう。コロナ禍以降、Web面接やAI面接など、非対面の面接スタイルも増加傾向です。
面接の種類
選考段階に分けて、一次面接や二次面接、最終面接などがあります。最初の面接となる一次面接では基本的な質問が多く、面接官は若手社員や中堅クラスの社員が務めるケースが一般的です。段階が進むほど面接官の役職が上位になる傾向があり、一般的に最終面接は役員や社長が面接官を務めます。
面接手法として、集団面接と個人面接があります。集団面接は複数の応募者を集めて実施され、コミュニケーション能力や協調性が評価されます。個人面接はひとりの応募者に対して、ひとりまたは複数の面接官によって行われ、応募者の個人能力や適性などが評価対象です。
内定獲得まで何回面接があるのかは、企業によって異なります。しかし、面接を実施しない企業は皆無であるため、段階ごとあるいは手法ごとの面接対策が重要です。
面接の形式
面接の形式は、企業によって異なります。最近ではAIをつかった面接も登場しました。
以下ではスタンダードな面接方法をはじめ、代表的な5つの形式とそれぞれの特徴をまとめました。
| 個人面接 | じっくりと質問しやすい点が特徴で、人柄やコミュニケーション能力を深掘りできる |
| 集団面接 | グループワークを行うことで、チームとして仕事ができる人材かを見極めやすい |
| オンライン面接 | エンジニアやIT系では画面を共有することで技術的な能力を確認できるため、パソコンをメインに扱う業種では導入する企業が多い |
| 電話面接 | 会話のみであるため、口調や表現力などを評価しやすい |
| AI面接 | 応募者の回答や表情などを分析し、特性や能力を評価できる |
面接での評価ポイント
面接に際して、企業が応募者のどの部分を評価するのかを確認しましょう。多くの企業が評価するポイントは、人柄と社会人としてのマナー、そして企業との相性です。しっかりと企業側の評価ポイントを理解し、効果的な対策をしましょう。
人柄
採用後、一緒に働くことを考えて、多くの企業が応募者の人柄を重視する傾向です。特に新卒採用の場合、評価する業務実績を持ち合わせていないため、人柄は大きな比重をしめます。
ただし、企業によって求める人物像は異なります。協調性を重視する企業もあれば、主体性やチャレンジ精神を求める企業もあるでしょう。企業の方向性や募集要件などに合わせて、好印象を得られるように自分を表現します。一般的には、新卒採用にあたって、素直さや明るさを求める傾向です。
社会人としてのマナー
人柄と並んで応募者個人を評価する視点として、社会人としてのマナーがあります。例えば、面接時の言葉遣いや身だしなみ、入退室時の立ち居振る舞いなどです。
具体的には、敬語の正しい使い方や丁寧な言葉遣い、清潔感のある服装や髪型などがポイントです。入室時のドアのたたき方や退出時のお礼の述べ方なども評価対象でしょう。
面接時の受付のタイミングも大切です。遅刻しないことはもちろんのこと、適切な時間で受付を済ませましょう。早すぎても企業側へ負荷を与えるため、10分前を目安に面接会場に赴きます。
企業とのマッチ度
企業とのマッチ度は、求める人物像や社風との適合性などで判断されます。企業の理念や文化に対する理解が高く、入社後に活躍できる人材か否かが評価ポイントです。
志望度の高さも評価されます。企業への入社意欲や熱意が強いか、その理由が明確かなどを評価します。企業は長期的な活躍を求めているため、強い成長意欲や明確なキャリアビジョンが大切です。志望度は内定辞退や早期離職を防ぐ判断材料になるため、面接においては重要な評価ポイントです。
効果的な面接対策5選
面接対策として効果の高い5つのポイントを紹介します。具体的には、自己分析、企業研究、質問への対策、模擬面接の実施、面接会場の確認です。いずれもどの企業の面接に対して有効に作用するため、怠らずに準備しましょう。
自己分析をする
自己分析の実施は、就職活動の第一歩です。自己分析をすることで、就活の軸や志望する業界が明確になります。
自己分析を行い、自分の強みや弱み、方向性を把握しましょう。その上で自分の価値観やキャリアプランを明確にすると、どのような仕事が自分に向いているのか、はっきりと見えてきます。
なぜその業界あるいは企業を就職先として選ぶのかが見えてきたら、面接で自分の特徴や強みを裏付ける具体的な経験やエピソードを洗い出します。それらを整理して、自己PRや志望動機として活かしましょう。
企業研究をする
企業研究は、自己分析と同じレベルで重要な面接対策です。しっかりとした企業研究を行うことで、企業の理念や事業内容の理解が進み、面接時に具体的で熱意のある志望動機を伝えられます。面接官からの質問にも的確な回答ができて、自己PRとしても有効でしょう。
応募前に企業とのマッチングを確認する材料としても利用できます。企業研究を通じて、自分が目指す道に合っているのかを判断できるため、入社後のビジョンが明確になるし、ミスマッチを防止できます。
頻出質問や深堀り質問に備える
どの面接においても聞かれる頻出問題や、深掘りされる可能性の高い質問に関しては、しっかりとした準備が必要です。
自己PRや志望動機、ガクチカと表現される学生時代に力を入れたこと、志望動機などは、どの企業面接でも聞かれる質問です。これらの質問に対して的確な回答ができないと、準備不足のまま面接に臨んでいると判断される可能性があります。
深掘りされる可能性の高い質問には、深掘りされた際の回答を用意しましょう。例えばガクチカに対して、なぜ頑張ろうと思ったのか、具体的にはどのような行動をし成果を得たのかなどと深掘り質問がなされます。ケースバイケースで対応できる体勢を整えましょう。
模擬面接をする
本番面接に臨む前に、模擬面接を実施することも有効です。面接に慣れることで緊張を緩和できますし、入退室のマナーを確認できます。
準備として、質問リストを用意し、頻出質問や深掘り質問など、本番を想定した構成にします。面接方法は自分ひとりで行う場合と家族や友人に依頼して、対面で行うケースがあります。Web面接を想定して、ZoomやGoogle Meetなどのシステムを使って、オンラインで実施するのもよいでしょう。
模擬面接の際は、面接の様子を録画します。映像を見直して、改善点をチェックできます。対面で実施した場合は、フィードバックをもらうようにしましょう。録画やフィードバックによって改善点を炙り出し、繰り返し練習することで、自然な受け答えができるようになります。
面接の場所や詳細を確認しておく
本番の面接に向けて、場所や時間など、詳細をあらかじめ確認します。面接練習が完璧にできても、当日のスケジュールを十分に確認していないと、冷静に面接に臨むことが難しくなるでしょう。面接会場までの移動手段を確認し、交通障害や天候など、万が一の際の移動手段を確保します。
面接会場への持ち物もチェックします。提出物が求められている場合は、漏れがないかを確認しましょう。例えばデザイン系の募集の場合、作品の提示を求められるケースがあるため、忘れずに持参します。
【タイプ別】面接でよく聞かれる質問例
面接では、業界や業種に関係なく、ほとんどの企業で聞かれる質問が多くあります。
ここでは、面接の際によく聞かれる代表的な質問例をご紹介します。
自己PRに関する質問
自己PRでは、自分の能力や強みを企業でどのように活かし、貢献できるのかをアピールします。
<自己PRに関する質問例>
- 1分程度で自己PRしてください
- あなたの長所と短所を教えてください
- 自分を一言で表現すると何に例えられますか
- 友達や家族からどのような人物といわれますか
- あなたの強みをどのように活かして仕事がしたいですか など
志望動機
志望動機は、どのような企業においても聞かれる質問のひとつです。回答としては、自分の強みと企業のビジョンや事業内容がリンクする志望動機をつくり、「この企業でしか実現できないこと」を明確に伝えることが大切です。
<志望動機に関する質問例>
- なぜこの業界を選んだのですか
- 弊社は第一希望ですか
- なぜ大手ではなく、中小である企業の弊社を選びましたか
- 弊社に対してどのように思いますか など
学生時代に力を入れたこと
学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」では、経験を通して何を学んだのかを具体的に説明しましょう。ただ単に経験談を話すのではなく、そこから得られたスキルやどのように成長できたのかをアピールします。
<ガクチカに関する質問例>
- 学生時代、何に最も力を入れましたか
- その経験を通して何について学びましたか
- そこで経験したことを仕事でどのように活かしますか
- 経験のなかで課題があった場合、どのように解決しましたか など
自分の強み・弱み
この質問では、自分を誇張したり自慢するのではなく、強みと弱みを正直に伝えることが大切です。
強みをどのように仕事で活かし、弱みをどのように克服するかを説明します。
<強み・弱みに関する質問例>
- 弱みを克服するために努力していることはありますか
- 他人の弱みとあなたの弱みがぶつかった場合、どのように対応しますか
- あなたの強みを仕事でどのように活かしますか など
面接官に好印象を与えるポイント
面接合格を目指すためには、面接官へ好印象を与えられるかが勝負です。ここでは、面接官へ好印象を与えるためにおすすめな方法をご紹介します。
以下のことを面接で積極的に取り入れ、合格を目指しましょう。
熱意を伝える
面接は、経験や能力をアピールするだけでなく、いかにして熱意を明確に伝えられるかが大切です。面接官は、入社意欲を強く感じる応募者に対して好印象を抱き、興味をもつことが多い傾向にあります。
そのため面接では、明るく元気に話し、面接官とアイコンタクトをとりながら自分の意志をアピールすることが大切です。
また、企業への理解を示すことを忘れないよう心がけましょう。企業研究で得た情報を盛り込みながら、なぜ入社したいのかや、企業でどのように活躍したいのかなどを伝えることで、面接官へ好印象を与えられます。
逆質問をする
多くの企業で、面接の終盤に「何か質問はありますか」と聞かれることがあります。これを「逆質問」と呼びます。逆質問は、自分の熱意をアピールできる大きなチャンスです。
企業のことをよく調べて踏み込んだ質問ができれば、「自社へ関心が高い人物」と捉えてもらえるため、より熱意が伝わるでしょう。
以下を参考にして、逆質問に備えることがおすすめです。
- 入社までにどのような準備をすればよいでしょうか
- 研修制度にはどのようなものがありますか
- 貴社ではどのような人材が活躍していますか など
逆質問に対して「特にありません」と答えることは避けましょう。面接官から「自社への関心が薄い人物」と捉えられる可能性があり、悪い印象を与えかねません。
面接のフェーズでアピールする点を変える
すべての面接で同じ回答をするよりも、形式に合わせて答える内容を変えた方が、好印象を与えられるでしょう。
例えば集団面接では、協調性や自己主張へのアピールが大切である一方、個人面接では自己開示が求められます。
また、集団面接では、「他の人の発言に対してどのように思うか」などの質問が出題されるケースがあるため、他者の意見をしっかり聞くことが大切です。
面接の形式に合わせて対策を練ることで他の就活生と差別化を図り、面接官へ好印象を残せるでしょう。
AI全国共通模試「REALME」で事前に内定判定
面接における模範解答を事前に知りたい人は、「REALME」 がおすすめです。「REALME」では、面接対策としてAI面接や自己分析のサポートなど最適なサービスを無料で提供しています。AI面接は本番の面接以上にリアルな面接対策ができるため、ベストな状態で本番の面接へ臨めるでしょう。
過去の合格ラインからAIで抽出した面接の模範回答を確認できる
「REALME」では、志望企業の合格ラインをクリアした学生の面接回答例や、自己PR・ESなどの閲覧が可能です。これらのデータを参考にすれば、志望企業の面接でどのような回答をすればよいのかや、現時点での具体的な改善点が見えてくるでしょう。
面接で自分をどのようにアピールすればよいのかが分からない場合は、 「REALME」を活用しましょう。
志望企業の内定可能性を判定!
「REALME」 は、AI面接を行うことで志望企業から内定をもらえる可能性を算出してくれることが特徴です。志望企業の最終面接まで進んだ学生のデータと自分のデータを比較した上で内定の可能性を割り出してくれるため、現在の自分の立ち位置を客観的に把握できます。
AI面接は何度でも実施可能なため、内定判定が向上したタイミングでエントリーすることが可能です。
「REALME」では内定判定に基づいて志望企業の合格基準に届いていない能力や改善点をフィードバックしてくれるため、新卒の面接対策として高い効果が期待できるでしょう。
AIの客観的な分析で強み弱みが分かる
「REALME」のAI面接なら、あなたの強みや弱みを客観的に分析してくれます。新卒採用で重要視される能力を14の項目で点数化してくれるため、自分では気づけなかった強みや弱みを把握できます。これを参考にすれば、新卒の面接対策を効率よく進めることができるでしょう。
新卒の面接対策は事前準備が肝!徹底的に準備しよう
新卒の面接対策では、自己分析をはじめ、企業研究や面接マナーの理解などの事前準備が大切です。これらの準備を徹底して行うことで、深掘り質問に対して具体的に回答できたり、熱意を伝えることができます。
新卒の面接対策を入念に行うためには、「REALME」のAI面接を活用しましょう。志望企業の合格ラインに至った就活生のデータを参考にすれば、新卒採用の面接で自分をどのようにアピールすればよいのかが見えてきます。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)