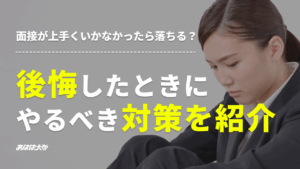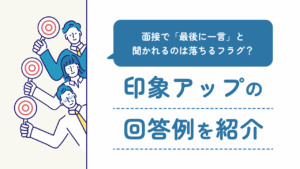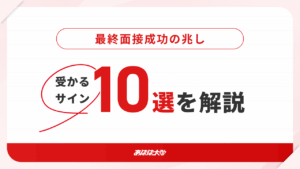就職活動において、集団面接や個人面接など、さまざまな形式の選考が取り入れられています。日常生活で面接を受ける機会があまりないため、本番前に練習したいと考える人も多いでしょう。
本記事は、面接の練習をはじめるタイミングや準備しておくこと、練習方法などを紹介します。また、記事の最後に、志望企業の内定率を飛躍的に向上させる面接練習や自己分析、ESなどすべての就職対策ができる「REALME」のAI面接についても紹介します。
1人で面接を練習することが不安な人は活用しましょう。
面接練習はいつからはじめれば良い?
面接は日常生活で受ける機会が少ないため、どの程度練習をすればよいか判断が難しいです。そのため、本番直前に一度練習をして流れをつかんでおけば大丈夫と、安易に考える人も少なくないでしょう。
企業面接は、本番数日前に一度練習すれば合格できるほど簡単ではありません。
面接練習は複数回することを見越して、早めにはじめる方がよいでしょう。一例として、採用活動の開始が卒業・修了年度の6月以降のため、面接練習は大学3年生の3月頃からはじめるとよいでしょう。
面接練習をする前に準備すること
面接練習の準備が足りないと、どのように話せばよいか、受け答えの何が不十分だったかが分からないことがあります。
ここでは、面接の練習をする前に準備することについて紹介します。
これから面接練習をする人は参考にしましょう。
自己分析をする
面接の受け答えでは、一貫性を持たせて答えることが重要です。
一貫性のない返答をすると、就活の軸が定まっていないと判断されて低評価になる可能性があります。面接の前には、自己分析によって自分の強みや弱み、価値観を明確化する作業が必要です。
自己分析を行うことで、面接でアピールしたい内容を整理でき、質問に対して根拠を持って話しやすくなるため、自己PR・志望動機などの説得力を高めやすくなるでしょう。
面接の流れを把握しておく
面接においてはある程度決まった流れがあり、段階ごとに守るべきルールやマナーがあります。ルールやマナーを守れない応募者については、受け答えが及第点であっても低評価になる可能性があります。
返答と関係ない部分で評価を下げることを防ぐために、面接前にどのような流れで面接が進むかを事前に把握するとよいでしょう。
選考が集団面接か個人面接かによって面接の流れは微妙に異なります。多くの場合は以下の流れです。
- 受付・待機
- 入室
- 面接
- 退室
入室時には、名前を呼ばれてからドアを3回ノックして入ることが一般的なマナーです。
席に座る際は面接官に促されるまで待ち、荷物は足元に置きましょう。
よくある質問内容を想定し返答を考える
面接では、どのような職種・業種であっても聞かれやすい頻出の質問があります。
そういった質問にきちんと答えられないと、面接への準備が不十分だと思われるでしょう。そのため、面接練習を行う前に頻出の質問を調べて、返答を考えることがおすすめです。
頻出の質問には、以下のものがあります。
- 志望動機
- ほかに受けている会社の有無
- 自己紹介
企業がよくある質問をする意図について考えながら返答を用意すると、自身の内面について深く掘り下げた答えができるためおすすめです。
面接でよく聞かれる質問と回答例
ここでは、面接でよく聞かれる質問と回答例を紹介します。
- 自己紹介をしてください
- なぜ当社を志望するのか教えてください
- 学生時代に力を入れたことは何ですか
- 短所と長所を教えてください
- キャリアプランを教えてください
自己紹介をしてください
ほとんどの面接で、自己紹介を始めに聞かれます。なかには内容や時間を指定する企業もあるでしょう。
氏名・大学・学部といった基本情報に、アルバイトやアピールなどを添えた1分程度の回答がおすすめです。
回答例
〇〇大学の(氏名)と申します。教育学部で〇〇について学んでおります。サークルには所属しておりません。アルバイトとして大学一年生の頃から塾講師をしており、小学生の成績向上のため日々試行錯誤しています。本日はよろしくお願いいたします。
なぜ当社を志望するのか教えてください
志望理由もよく聞かれる質問です。他の企業でも通じる内容は、良い評価に繋がりにくい可能性があります。企業研究を徹底し、企業の強みや特徴を踏まえた独自の理由を説明しましょう。
回答例
御社の「安全・確実な物流で社会を支える」という理念と物流の基盤に惹かれ志望しました。私はサークル活動で大規模イベントの物資管理を担当し、計画性と正確性の重要さを実感しました。この経験を活かし、物流の効率化と品質向上に貢献したいと考えています。
学生時代に力を入れたことは何ですか?
面接でのよくある質問として「ガクチカは何ですか」と聞かれるケースもあるでしょう。
嘘を付いて大げさな結果や内容にする必要はありません。具体的な取り組みの内容や学びなどが分かりやすく伝わるようにしましょう。
回答例
ゼミで地域カフェの売上改善に挑戦し、来客データを分析して新メニュー案を提案しました。SNS広告も併用し、1ヶ月で平日来店数を20%向上させる結果につなげました。入社後は御社のサービス価値向上に貢献したいと考えています。
短所と長所を教えてください
強み・弱みといった言葉で聞かれるケースもよくある質問です。エピソードを交えて矛盾が無いように語りましょう。弱みは、プラスの要素に言い換えられるのが望ましいです。
回答例
私の長所は、データを論理的に分析し、改善点を見つけ出す「分析力」です。ゼミでのプロジェクトで、来店データと客層分析から新メニューを提案し、売上を前年比15%伸ばしました。一方で慎重すぎるあまり判断に時間がかかることがあるため、優先順位を大切にするよう心がけています。
キャリアプランを教えてください
キャリアプランで見られるポイントは、具体性や姿勢、企業への理解度です。志望動機や強みとの整合性を意識しつつ、目標に向けて努力できる姿勢をアピールしましょう。
回答例
学生時代にSNS企画の分析と改善に取り組んだ経験から、課題を数値で捉え施策に落とし込む力を磨きました。入社後はユーザー理解とデータ分析の基礎を身につけ、3年目には自ら改善案を提案できる存在を目指します。将来的にマーケティング施策の企画立案を担い、事業成長に貢献したいです。
面接練習方法とコツ6選
本番前に、面接練習で経験を積むことは重要です。
面接練習は、効率的な練習方法を把握して行うと効果を高められます。
ここでは、面接の練習で意識したいコツを6つ紹介します。
- 会話のキャッチボールを心がける
- 言葉遣いに気を付ける
- 結論ファーストで話す
- 質問内容だけでなく立ち振る舞いにも気を配る
- 面接練習用アプリなどを活用する
- 2人以上で模擬面接を行う
これから面接の練習をしたいと考えている人は参考にしましょう。
会話のキャッチボールを心がける
面接で事前に用意した返答通りに答えようとするがあまり、面接官とのコミュニケーションがおざなりになる就活生もいます。
面接では質問の返答内容だけでなく、コミュニケーションスキルもチェックされるため、面接練習で回答を丸暗記しないように注意しましょう。
文章を丸暗記するのではなく、自然なやり取りの中で面接官に自分の意見や長所を伝えることが重要です。状況に応じて臨機応変に対応できるかどうかが求められることもあるため、会話のキャッチボールを心がけましょう。
言葉遣いに気を付ける
面接では、返答の内容以外に伝え方や話し方などにも注意しましょう。
よくある失敗例は、丁寧に話すことを心がけすぎて「二重敬語」のような間違った言葉遣いになることです。
「二重敬語」や「バイト敬語」など、面接に適切でない言葉遣いをしないように、面接練習の段階で意識するとよいでしょう。自分では正しく話せているつもりでも、無意識に間違った言葉遣いになることがあります。
結論ファーストで話す
面接で相手が分かるように話そうと意識するあまり、説明や前置きが長くなってしまう人がいます。面接では限られた時間で情報を伝えなくてはならないため、前置きの長い回答は得策ではありません。
短い返答でも伝わるように構成を意識しましょう。面接での受け答えは、結論から始め、その後に理由や具体例を述べ、最後にもう一度結論を強調する(PREP法)構成がおすすめです。
質問内容だけでなく立ち振る舞いにも気を配る
面接練習をする際は、立ち振る舞いにも気配りが必要です。入室時の振る舞いや姿勢、表情まで面接では評価されます。練習時は自分が話している様子を録画し、以下の内容などをチェックしましょう。
- 背筋を伸ばした正しい姿勢か
- 目線が泳いでないか
- 表情は硬くないか
- 身振り手振りは適切か
立ち振る舞いの印象が悪いと、内容が良くても面接官に話が伝わりにくくなってしまいます。内容が適切に評価されるよう、話し方以外の部分にも気を配りましょう。
面接練習用アプリなどを活用する
面接官役と就活生役が見つからないので模擬面接の練習ができないという人は、面接練習用のアプリやツールの活用を検討してみてはいかがでしょうか。面接アプリを使えば、一人でも模擬面接ができるため、繰り返し練習したいときにおすすめです。
面接アプリにはさまざまなものがあり、それぞれ機能や特徴が違います。1人で何度も練習する場合は、さまざまな質問がランダムに出題されるアプリや、自分の返答を録音できるアプリがおすすめです。また、面接官視点でアドバイスしてくれるアプリもあります。
2人以上で模擬面接を行う
家族や友人を面接官に据えて模擬面接を体験することもおすすめです。
友人・家族・先輩など、身近な人に協力してもらうことで、受け答えや話し方などについて客観的な視点でフィードバックをもらえます。2人以上で行うと本番のような緊張感のある面接が体験できるため、面接の雰囲気を事前に掴めるでしょう。
面接練習時に意識したいポイント3つ
ここからは、面接練習時に意識したい3つのポイントを紹介します。
- 面接官の話を最後まで聞く
- 少し大きめのボリュームで話す
- 本番に近い環境で実施する
話す内容だけではなく非言語の要素も本番を意識することが大切です。
面接官の話を最後まで聞く
面接官の話を遮る行為は失礼にあたります。最後まで話を聞くよう、練習でも注意しましょう。質問内容が分かったとしても、話を遮って回答すると印象は大きく下がってしまいます。
「冷静さに欠ける」「課題を正しく理解しない」など、社会人に求められる点の評価も下がってしまうでしょう。
面接は、企業と就活生の相性をはかる大事なコミュニケーションの場です。矢継ぎ早に話すことは避け、面接官の話を最後まで聞き、成り立つように気を配りましょう。
少し大きめのボリュームで話す
面接本番は、緊張して声が小さくなったり早口になったりする可能性があります。練習段階で少し大きめのボリュームで話しておくと、その声量が定着するでしょう。
大きな声でハキハキと話す様子は「自信を持っている」と良い印象にも繋がります。練習の段階で、大きめの声で話す癖を身に着けておくのがおすすめです。
緊張して少し声が小さくなっても、最適なボリュームに落ち着く可能性があります。面接練習では、あえて少し大きい声量で問題ありません。
本番に近い環境で実施する
本番への意識が足りず練習と考えすぎると、中身の薄い時間になってしまいます。面接特有の緊張感によって話す内容を忘れたり、立ち振る舞いを誤ったりする可能性もあります。
そのため、集団面接や面接官が複数いるパターンなど、さまざまな形式を練習で体験すると良いでしょう。
なるべく本番に近い環境で実施すると、緊張感を味わえます。面接の雰囲気に慣れておけば実力を十分に発揮し、準備を無駄しない納得感のあるやり取りに繋がります。
おすすめの面接練習アプリ
客観的な意見があると、面接スキルは伸びやすいです。ただし1人でしか面接練習を行えない状況もあるでしょう。そんなときは、便利な面接練習アプリを活用するのがおすすめです。面接の練習が効率的にできるアプリをご紹介します。
REALME

REALMEはAIを使って面接練習ができるアプリです。20〜30分の面接練習の後、14項目の能力を点数化してくれます。AI面接では実際の面接よりも深掘りした質問をされるので、回答の掘り下げ練習も可能です。
さらに志望企業の最終選考に進んだ就活生と、面接結果を比較し内定判定をデータ化。客観的に、自分の面接を振り返ることができます。
能力や価値観も可視化されるので、自己分析も同時に行うことが可能。分析結果をもとに、マッチする企業や、業界を確認することができますよ。
SpeakViz
SpeakVizはAIが模擬面接の相手となり、回答内容を分析し、フィードバックをくれる面接対策アプリです。就活だけではなく、受験、英語の面接などにも対応しています。回答によって、深掘り質問を臨機応変にしてくれるため、まるで本番のような面接練習が可能。また話すスキルの向上にも役立ちます。回答から、話す速度や、声の大きさを分析し、改善点を指摘してくれるため、面接だけではなく就活後も役立つスキルが身につきます。
steach
steachはAIが面接練習をもとに、人事目線で良い点と悪い点をフィードバックしてくれるアプリ。「写真のみ」「音声のみ」「動画」の3つのモードで、面接対策を行えるので、話し方だけではなく表情に関してもアドバイスしてくれます。練習した内容を文字起こしすることも可能なので、客観的に回答を確認するために使うのもおすすめです。話し方の癖や、回答構成の見直し用にも活用できます。
面接練習アプリ
面接練習アプリは、模擬面接を体験できるアプリ。希望する業界ごとに面接官のタイプを選べるので、本番と近い状態で面接練習を行うことができます。
質問も自分で好きなものを指定可能。回答用のメモも作成できるので、面接前の振り返りにもおすすめです。
また、面接練習後はAIが5つの項目で面接を評価してくれます。改善のためのアドバイスももらえるので効率的に面接力を高めたい人におすすめです。
ChatGPT
ChatGPTなどの、AIサービスを面接練習に活用するのもおすすめです。AIアプリのメリットは自分用にカスタマイズして使えるところ。例として、面接でうまく答えられなかった内容だけを覚えさせ、何度も練習を繰り返すことも可能です。また、自分の強みや自己分析の結果、志望する企業の求める人材を入力することで、回答例のアドバイスももらえます。就職活動中のパートナーとして、面接練習でも上手に活用するのがおすすめです。
面接練習を行うメリット
面接練習を行うと得られるメリットがあります。面接スキルを向上させることは、今後の人生で必ず役に立つでしょう。就活中の面接はもちろん、入社後のプレゼンテーションや商談でも活かせる面接練習のメリットを紹介します。
伝わる回答ができるようになる
面接練習を繰り返すことで、面接官に伝わりやすい回答ができるようになります。どんなに良い回答でも、伝わりにくい言い回しをしていたら評価につながりません。
アプリなどを使い、客観的に自分の回答を振り返ることで、「正しく伝わるか」判断しやすくなります。
また、2人以上で面接練習を行うときは、意図が伝わるかフィードバックをもらうことも効果的です。
何度も面接練習を行い、伝わりやすい言い回しや構成力を取得しましょう。
自信を持って当日を迎えられる
面接は誰にとっても緊張する場であり、頭が真っ白になったり、うまく言葉が出てこなくなったりすることも珍しくありません。しかし、面接練習を重ねることで自信がつき、本番の緊張を和らげることができます。自信を持つために、本番と似た環境で入室から退出までを模擬練習しておきましょう。
アプリによるAI診断を活用すると、良い箇所や悪い箇所を客観的に確認できるので、改善を繰り返すと、より自信を持って当日を迎えやすくなります。
自信を感じられる人材は面接官の印象にも残りやすいです。
話すスキルが向上する
面接練習を繰り返すことで、自分の話し方を客観的にチェックできるようになります。とくに録音や録画を活用した練習では、口癖や「あのー」「えーと」などの、無意識に出てしまうフィラーも改善が可能です。話すスピードや声のトーンも、録画を確認・改善することで正すことができるでしょう。
これらを繰り返すことで、面接以外でも役立つ話すスキルが向上します。話すスキルは企業からも求められるため、選考通過率も高まる可能性があります。
面接練習やりすぎ?足りない?最適な回数
面接練習の回数について悩むこともあるでしょう。結論から言うと、練習する回数に正解はありません。自分で納得できるまで行うのがベストです。
面接で緊張しやすい人や、話すことが苦手な人は、1人で練習するだけではなく、厳しくチェックしてくれる第三者との練習も複数回取り入れると自信に繋がります。
逆に話すのが得意な人や、PRが得意な人は、面接練習よりも企業分析などに時間を活用した方が良いケースもあります。
なので、自分のスキルに合わせて面接練習の回数を決めましょう。ただし、やりすぎると丸暗記のような不自然さが出てしまうので注意が必要です。
AI全国共通模試「REALME」では今すぐ面接練習が可能
面接前に、自分の強みやアピールポイントなどを正しく把握したい人は、AI面接ツール「REALME」がおすすめです。AI面接による客観的な強み・弱みの分析や、就活対策に役立つデータなどを豊富に提供してもらえます。
AIとの模擬面接で客観的な自己分析ができる
「REALME」は、AI面接後に就活で重視される14項目の能力を点数化してくれます。数値で確認できるため、客観的な視点で自分の強みや弱みを明確に把握することができます。自己分析は履歴書やエントリーシートの作成時にも役立つため、効率よく就活対策を行うことができます。
エントリータイミングを最適化する内定判定が確認できる
「REALME」のAI面接を受けると、志望企業の内定判定を算出してくれます。
志望企業の最終面接に進んだ学生と自分のデータを比較した上で内定の可能性が割り出されるため現状の自分の立ち位置を把握できます。
「REALME」のAI面接は何度でも実施可能なため、分析と改善を繰り返しながら内定判定を向上させましょう。
AIで抽出したES・面接解答例が閲覧できる
「REALME」は、志望企業の合格ラインをクリアした学生の面接回答例や自己PR・ESなどの閲覧が可能です。
過去に好成績を出した学生の面接回答例を参考にすることで、志望企業の求める人物像やアピールポイントなどを把握できます。面接練習で回答の作成に行き詰まったときは、ほかの人の回答を参考にしてください。
「いつから」ではなく「今から」から面接練習をはじめよう
面接練習は、本番直前でなく早めにはじめることがおすすめです。自己分析を行ったり、身近な人に模擬面接を手伝ってもらい、適切な回答を用意できるようにしましょう。面接練習では、「会話のキャッチボール」や「言葉遣い」に気をつけて結論ファーストで話しましょう。
効率的に面接練習をしたい場合は「REALME」のAI面接アプリを活用しましょう。面接アプリを使えば、一人でも模擬面接ができるため、手軽に面接練習を始めることができます。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)