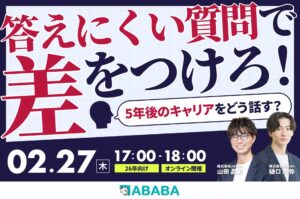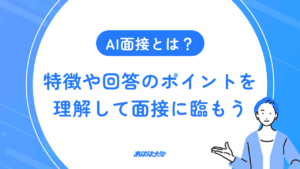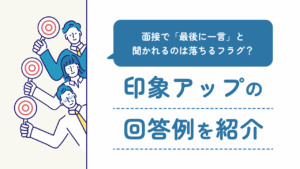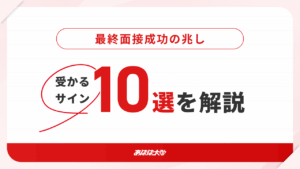就活の面接に臨む人のなかには「面接に受かる自信がない」「面接に受かる方法を知りたい」と考える人も多いでしょう。たとえ面接に受かる万能な方法はなくても、面接のコツをつかむことで選考を通過しやすくなります。
本記事では面接に受かりやすい人の特徴を洗い出し、合格を勝ち取るコツを紹介します。これから面接に臨もうとしている方は、ぜひ参考にしてください。
記事の最後には就活サポートツール「REALME」についても解説します。面接への不安を軽減させたい人や、効率的に面接対策をしたい人は、ぜひ詳細をご覧ください。
面接で受かる人の特徴
企業が採用したい学生とは、どのような人物なのでしょうか。内閣府が行った企業の採用活動に関する実態調査によると「採用したい学生の人物像(最大8つまで回答)」に対する回答は、次のとおりでした。
| コミュニケーション能力が高い(78.6%)協調性がある(72.4%)誠実である(63.4%)チャレンジ精神が高い(49.9%)行動力がある(49.1%)責任感が強い(30.7%)ストレス耐性が高い(30.4%)リーダーシップを発揮できる(24.2%)専門性・能力を伸ばしたいという意識が高い(24.0%)論理的思考力が高い(23.9%) |
調査対象となった企業の8割近くが「コミュニケーション能力が高い」と回答しました。次いで多い回答は「協調性がある」「誠実である」でした。
このような結果から、学生にコミュニケーションスキルや協調性を求める企業が多いことが伺えます。つまり、面接においては「面接官との会話のキャッチボールがスムーズにできること」が重要であると考えられます。
出典:内閣府「企業の採用活動に関する実態調査」令和2年10月
要注意!面接で落ちる人によく見られる特徴
ここでは、面接で落ちる人によく見られる特徴についてご紹介します。「繰り返し練習しているのに落ちてしまう」「一次面接すら通らない……」という人は、自己PRの文章そのものに改善点があるかもしれません。面接に落ちてしまう理由を知り、具体的な改善につなげていきましょう。
面接の振り返りをしていない
面接でよく落ちる人の特徴として、面接の振り返りをしていないことが挙げられます。面接で落ちるのには必ず何かしらの理由があるもの。振り返りをしない限り、その理由に気づくことができません。
たとえば、自己PR文を見直さず、いつも同じ文章で機械的に伝えるだけになっていませんか?自己PRに改善点があるままでは、どれほど面接慣れをしても良い印象を与えられません。録音や録画、第三者の協力などを得ながら、改善点を見つけることから始めましょう。
伝えたいことをうまく言語化できていない
伝えたい内容をうまく言語化できていない場合も、面接で落ちやすくなります。面接でもっとも大切なのは熱意や情熱です。しかし残念ながら、熱意だけでは合格できないのが現実です。相手にとってわかりにくい言葉ばかりを選んでいるままでは、熱意を的確に伝えられません。
面接では、事前に「何をどう話すのか」を明確にすることが大切です。自分が伝えやすい言葉ではなく、相手にとって伝わりやすい言葉を選ぶように心がけましょう。
相手が話してほしいことを話せていない
面接によく落ちる理由としては、相手が話してほしいことを話せていないことも挙げられます。面接はビジネスシーンであるとともに、自分対面接官のコミュニケーションの場でもあります。たとえば面接官が仕事観について聞いているのに、応募者が人生観について語り出したら、「コミュニケーションが取れない人だな」と思われてしまいますよね。
自分が話したいことを話してばかりでは、円滑なコミュニケーションは難しくなります。相手が何を求めているのかを冷静に見極め、思考を整理しつつ会話のニーズに応える姿勢を持ちましょう。
適切な言い換えができていない
面接時に適切な言い換えができていないことも、落ちやすくなる理由の一つです。たとえば面接においては、自分の弱点も言い方次第で強みになるもの。しかし弱みを弱みのまま伝えてしまうと、面接官にとっては「ただの欠点」として伝わってしまいます。
素直さや誠実さは高評価にもなり得ますが、せっかくのアピールポイントを「言い換え不足」で潰してしまっている可能性も。今一度自己PR内容を見直し、短所を長所に変換するための工夫を取り入れてみましょう。
【フェーズ別】一次・二字面接と最終面接のコツとは?
ここでは、一次・二次面接と最終面接のコツを、フェーズ別にご紹介します。面接は段階が進むごとに趣旨が変化するため、応募者側が備えるべき姿勢やPR内容も変わります。フェーズごとのポイントをつかみ、高評価につながるアピールにつなげましょう。
【一次・二次面接】基本の部分をしっかりと押さえる
一次・二次面接では、「企業の概要」や「ビジネスマナー」といった基本の部分をしっかりと押さえることが大切です。一次・二次面接で見られるのは、企業との相性やポテンシャルの高さ。最終面接と比べて深掘りされる質問は少ないからこそ、最低限のマナーやルールが求められます。
たとえば敬語の正しい使い方や、円滑にコミュニケーションが取れる力、相手にとって失礼のない態度、論理的な説明力など、「社会人として必須のスキル」を求められるのが一次・二次面接。反復練習によって解決できる要素も多いため、練習と改善を繰り返していきましょう。
【最終面接】一次・二次とは異なる側面でアピールをする
最終面接では一次・二次面接とは異なり、社長や役員クラスなどの上層部が面接官になります。実務能力の確認だけではなく、入社後のキャリアビジョンや、企業とのマッチングの最終的な確認などがおこなわれます。
とくに仕事観や働き方に関しては深掘りされやすく、企業の文化や価値観と合致してるかどうかが重視される傾向に。自身のキャリアプランを再度確認し、企業に合った内容を伝えつつ、一次・二次面接で答えた内容と整合性を取ることが重要です。
面接に受かる方法6選
企業が学生に求める人物像をふまえ、面接に受かるための対策方法を6つ紹介します。十分に準備をして面接に臨みましょう。
選考別に目的を理解しておく
就活の面接には一次・二次・最終といった段階があり、実施する目的が異なります。面接を通過するには、それぞれの目的を理解し、選考に合った対策をすることが必要です。
- 一次面接
目的は、学生が企業の採用条件を最低限クリアしているかをチェックすることです。身だしなみや言葉遣いなどの「ビジネスマナーが備わった人材」であるかが鍵となります。1人あたりの面接時間が短い傾向があるため、第一印象が重要になるでしょう。
- 二次面接
目的は「入社後に活躍できる人材」を見極めることです。質問内容が深くなり、回答した理由をさらに深掘りして聞かれることも多くなります。事前に業界・企業分析を徹底的に行うことが重要です。
- 最終面接
社長や役員が応募者の採用を判断する目的で行います。「入社意欲の高い人材」であるかがポイントとなるため、業界・企業への熱意をしっかり伝えることが必要です。入社後のビジョンを明確に語れるよう準備しておきましょう。
会話のキャッチボールを意識する
先述したとおり、企業はコミュニケーションスキルの高い学生を求める傾向があります。そのため、面接での会話のキャッチボールは重要です。
完璧な回答をすることは、それほど問題ではありません。意識したいのは、面接官と自然な会話をすることです。想定される質問の回答を細かく書いて丸暗記しても、一方的に話すだけになり自然な会話はできません。言いたいことはメモ書きにする程度にして、普段どおりの対話ができるようにリラックスして臨みましょう。
面接官の話をよく聞き、程よく相槌を打つことも必要です。質問の意味が分からないときは、慌てずに「今の質問は〇〇〇という意味でしょうか」と確認しましょう。分からないことを質問できることも、重要なコミュニケーションスキルです。
人柄がわかるアピールをする
企業は面接をとおして、学生の人柄を知ろうとしています。新卒者は社会人としての経験がなく、これまでの実績で評価することができません。そのため「自社の社風に合っているか」「一緒に働きたいと思えるか」といった人柄が重視される傾向があるのです。
面接では自分の人となりが伝わる内容をアピールしましょう。学業・部活動・アルバイト・留学などのガクチカを話す際には、伝えたいと思う性格に合ったエピソードを用意してください。
入社意欲の高さを伝える
入社意欲の高さを伝えることも重要なポイントです。これは二次面接、最終面接と進むにつれ、より重視される傾向があります。
面接で入社意欲を伝えるためには、志望企業の「経営理念」「事業内容」「中期経営計画」「求める人物像」などを前もってチェックし、まとめておきましょう。企業研究をしっかりと行っている姿勢そのものが、入社意欲の表れとなります。
企業研究の方法としては「企業の公式サイトやパンフレットを読む」「企業のプレスリリースを確認する」「業界に関するニュースをチェックする」といった手段が挙げられます。
OB・OG訪問をするのもおすすめです。実際に働く社員の声は貴重な情報源となり、面接での受け答えに活かせるでしょう。
キャリアビジョンを明確にする
新卒者には、仕事での実績がまだありません。代わりにポテンシャルが重視される傾向にあるため、キャリアビジョンを明確にして面接に臨むことが重要になります。
キャリアビジョンとは「将来こうなりたい」と思い描く、自分の理想像です。終身雇用の崩壊や経済活動の停滞など、社会にさまざまな変化が起きている今、中長期的な将来像を持った人材は企業を活性化させる貴重な存在であると考えられます。面接の前に、はっきりとしたキャリアビジョンを描いておきましょう。そのステップは次のとおりです。
- 過去を振り返って自己分析をする
- 将来やりたいことを書き出して目標を設定する
- 目標達成に向けたスキルや行動を洗い出す
最後のスキルや行動は複数あってよいのですが、多すぎる場合は実行しやすい順に列挙してみてください。こうすることで、高いポテンシャルを保って面接に臨めるでしょう。
社会人として振る舞う
面接では受け答えの内容だけでなく、社会人としてのマナーもチェックされます。基本的な振る舞い方のポイントを、改めて確認しましょう。
- 訪問マナー
集合時間の15分ほど前に到着し、5分前までには受付を済ませましょう。受付の担当者と接するときも、気をゆるめないようにしてください。
- 入室マナー
軽く3回ノックをして「どうぞ」と言われたら「失礼いたします」と答えてドアを開け、入室します。ドアを閉めるときは、後ろ手で閉めないようにしてください。
- 座り方のマナー
ドアを閉めたあと、面接官のほうを向いてお辞儀をします。角度は30度ほどで、このとき「よろしくお願いします」と言ってもよいでしょう。その後、椅子の横まで歩いていって立ちます。「お座りください」とうながされてから、椅子に座りましょう。
- 面接での行動マナー
面接で何か聞かれる前に話し出すのはマナー違反です。面接官からの質問を最後まで聞いてから答えましょう。自信がないと思われないよう、面接官の目を見て話すよう心がけてください。
面接で受かる方法の一つ!よくある質問と回答例文を紹介
ここでは、面接でよくある質問と回答例文をご紹介します。面接では企業独自のオリジナル質問をされるケースもありますが、どの企業でも聞かれるような「定番の質問」も多いものです。面接で聞かれやすい内容にあらかじめ備え、自信を持って本番に臨みましょう。
学生時代に頑張ったこと
いわゆる「ガクチカ」は、面接で聞かれる定番の質問の一つ。ガクチカのアピールでは、出来事自体ではなく「その経験で自分は何を学んだのか」や「その経験で企業にどのよように貢献できるのか」を伝えることが大切です。
【例文】
大学では、ゼミ活動で企業との共同プロジェクトに取り組みました。メンバー間の意見調整や進行管理を担い、計画遅延を解消し納期を守ることに成功しました。この経験から「全体を見渡し、状況に応じて柔軟に対応する力」を身につけました。御社でもチームや部署間の橋渡し役として、円滑な業務推進に貢献できると考えています。
自身の長所・短所
自身の長所や短所も、面接で聞かれる定番の質問。とくに短所を伝える際は、ネガティブイメージを残さないための「言い換えの工夫」が大切です。どのような個性も言い方次第で強みになります。辞書やAIなども活用しつつ、自分を魅力的に伝える言葉を考えましょう。
【例文】
長所は「冷静に物事を分析し、最適な解決策を見つけられる点」です。一方で、慎重に考えるあまり行動が遅れることがありました。現在は、まず行動してから改善する「スモールステップ」の意識を持つことで、スピードと精度を両立しています。これにより、的確かつ迅速な業務対応が可能です。
3年後・5年後の将来像
入社後のキャリアビジョンも、面接で聞かれる定番の質問です。明確な回答であるほど長期的な貢献が期待でき、入社への本気度も伝わります。3年後・5年後を目安に、理想とする将来像について考えてみましょう。
【例文】
3年後には業務の全体像を把握し、一人で案件を完遂できる戦力となることを目指します。5年後には後輩の育成やチームの進行管理を担い、組織全体の成果向上に貢献したいと考えています。そのためにも、日々の業務で知識と経験を積み重ね、改善提案や効率化にも積極的に取り組みます。
面接に受かるための対策にはAI全国共通模試「REALME」
面接の対策をより効率的に行いたい方には、就活サポートサービス「REALME」がおすすめです。AI面接を受け、フィードバックをもらうことで、面接内容を改善できます。
ここからは「REALME」の3つの特徴について解説しましょう。
AIとの面接で客観的に強みや弱みが分析できる
「REALME」では、20~30分程度のAI面接を受けることで、精密なフィードバックが受け取れます。そのなかで、就活で重視される14の能力が点数化され、自分の強みや弱みを客観的に分析できます。「関係構築力」「問題解決力」「ストレス耐性」などの能力が可視化されることで、自分のアピールポイントが分かり、自信を持って面接に挑めるでしょう。
合格圏内のES・面接解答例が閲覧できる
「REALME」を利用すれば、志望企業の合格圏内にいる学生のESや面接解答例が閲覧できます。これらを自分のデータと比較することで、改善点が把握できます。優秀な学生が自身のキャリアビジョンをどのように描いているのかも、参考にできるでしょう。
内定判定でエントリータイミングがわかる
「REALME」のAI面接を受ければ、企業の最終面接に進んだ学生のデータと比較することで、内定獲得の可能性を確認できます。この内定判定は、大学の模擬試験のようにA+・A・B+・B……E+・Eの10段階の評価で表されます。面接前に自分の現在地を知ることによって、最適なタイミングで志望企業にエントリーできるでしょう。
面接で受かる方法を押さえて選考に通過しよう
本記事では、面接に受かる人の特徴を紹介するとともに、面接の対策方法を6つ解説しました。ぜひ一つずつ実践して、面接合格を勝ち取ってください。
面接対策をより効果的に行いたい人には、就活サポートサービス「REALME」がおすすめです。AI面接や内定判定を活用して、就職活動を成功させましょう。