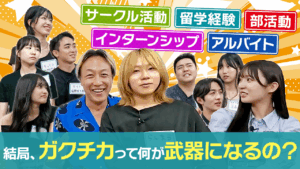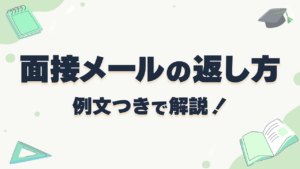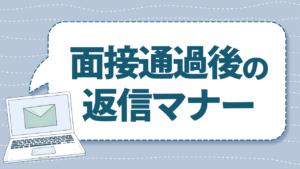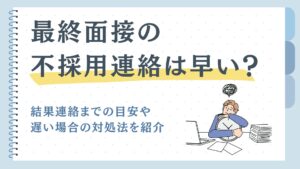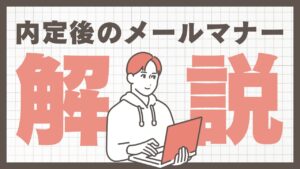AIでESを書くのは当たり前?それともリスク?
「ChatGPTで自己PR書いたら一発で通った!」「AI使ったのバレて落ちた…」
XやInstagramで、こんな投稿を目にしたことはありませんか?
もはや「AIでESを書く」ことは、就活における新しい選択肢の一つとして認識されつつあります。でも、本当にそのAI任せのES、企業の人事にバレていないと思いますか?
実は、数百通のESを読み慣れた人事担当者にとって、AI生成の文章は想像以上に見抜きやすいものなんです。だからといって「AIを使ってはいけない」わけではありません。使い方次第で、AIは就活における強力な味方になってくれます。
この記事では、現役の人事担当者への取材をもとに、AI利用がバレるメカニズムから、バレない活用法まで、就活生なら絶対に知っておくべき情報をお伝えします。
あなたのES、本当に”バレてない”自信ありますか?
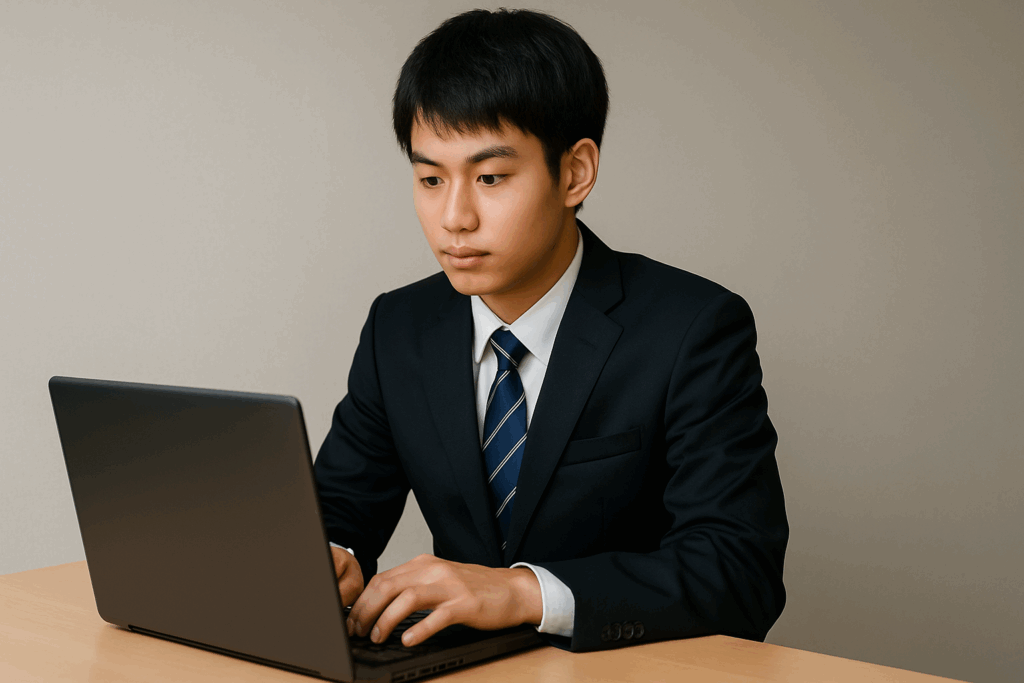
人事の視点から見た「違和感」の正体
AIで書いたESを人事が見抜くポイント
人事担当者が最初に気づくのは、文体や語彙の不自然さです。ChatGPTをはじめとする生成AIには、特徴的な「クセ」があります。
「〜において」「〜に関して」「〜を通じて」といった固い表現の多用。「多角的な視点」「包括的な理解」「シナジー効果」など、普通の学生が使わないようなビジネス用語の羅列。
ある大手メーカーの人事部長は言います。
「読んでいて『うまいけど、なんか違う』と感じるESが増えましたね。文章は完璧なんですが、22歳の学生が書いたとは思えない表現が散りばめられている。特に、具体性に欠ける抽象的な表現ばかりが続くと、すぐにピンときます」
AI生成ESがバレる最大の理由は“志望動機の浅さ”
AI生成ESのもう一つの特徴は、どこの会社にでも使い回せる汎用的な内容です。志望動機で具体的な企業名や事業内容への言及が極端に少なく、「成長できる環境」「挑戦的な文化」など抽象的な表現でお茶を濁している。
「貴社の〇〇事業に興味がありますと書いてあるのに、その事業について一切触れられていないESを見ると、『ああ、これはAIだな』と分かってしまいます」(IT企業人事担当者)
技術的検出ツールの導入が進む企業も
最近では、AI文章検出ツールを導入する企業も現れています。「GPTZero」や「AI Detector」といったツールは、文章の特徴を解析してAI生成度を判定します。100%の精度ではありませんが、明らかにAI生成とわかる文章は高確率で検出されます。
また、過去のES データベースとの類似性チェックも一般的になってきました。同じプロンプトから生成された似たような文章が複数提出されれば、当然人事の目にも止まります。
人事が持つ「違和感センサー」の精度
しかし、最も恐ろしいのは人事担当者の経験に基づく直感です。毎年数百通、多い企業では数千通のESを読んでいる彼らにとって、「自分の言葉で書かれた文章」と「AIが生成した文章」の違いは、驚くほど明確に感じ取れるといいます。
「文章のリズム、語彙選択、そして何より『体温』みたいなものが違うんです。AIの文章は完璧すぎて、逆に人間らしさがない。面接でその人と話してみると、文章との温度差がはっきりわかります」(金融業界人事マネージャー)
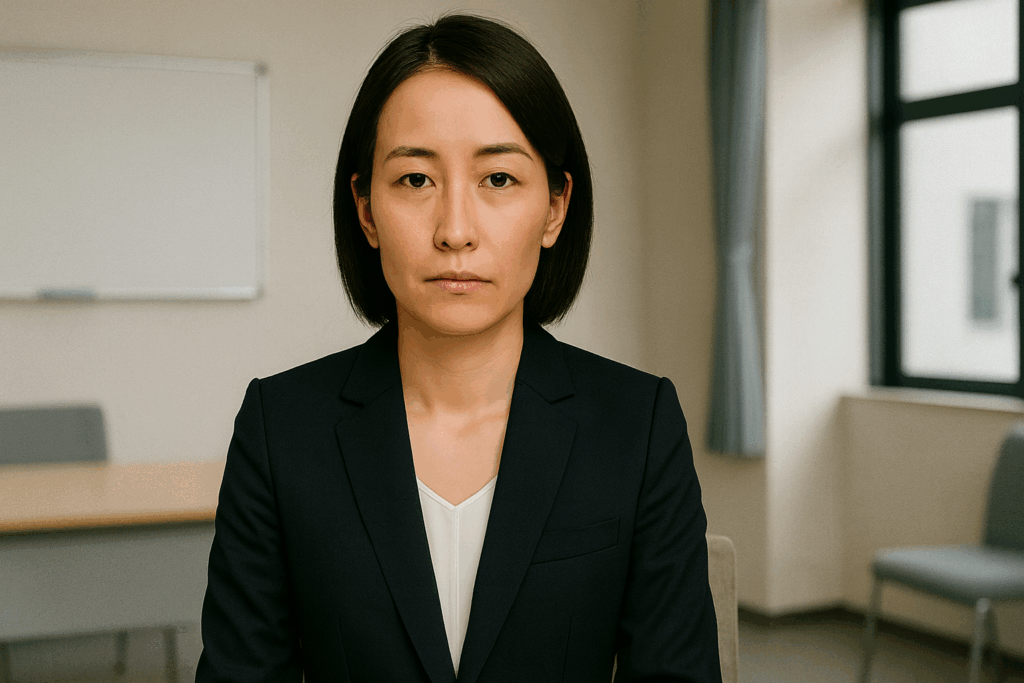
現場の本音を直撃取材
大手企業人事の見解「完全否定はしないが、丸写しは一発アウト」
都内の大手商社で新卒採用を担当するA氏(30代)は、AI利用について意外にも寛容な姿勢を見せます。
「正直、AIを使うこと自体は悪いとは思いません。ただ、丸ごとコピペして提出するのは論外です。私たちが見たいのは、その学生の思考プロセスや価値観。AIが生成した完璧な文章ではなく、その人なりの表現で書かれた『生の声』なんです」
A氏によると、AI利用がバレたからといって即座に不合格にするわけではないといいます。重要なのは面接での整合性。ESの内容を自分の言葉で説明できるかどうかが、最終的な判断基準になるそうです。
ベンチャー企業人事の視点「文のうまさより『自分の言葉』感を重視」
一方、急成長中のSaaS企業で採用責任者を務めるB氏(20代)は、より厳しい見方をしています。
「弊社では『その人らしさ』を最重要視しています。文章がうまくなくても、その人の体験や思いが伝わってくるESの方が、AI生成の完璧な文章より100倍価値があります。面接で『ESのこの部分、詳しく聞かせて』と言ったとき、明らかに内容を理解していない学生がいるんです。それって、結局自分で考えていない証拠ですよね」
人事のリアルな判断基準
複数の人事担当者への取材から見えてきた共通の判断基準は以下の通りです:
許容範囲
- 文章構成や表現のヒントとしてAIを参考にする
- 自分の体験や考えをベースに、AIで文章を整える
- 誤字脱字チェックや文法確認での利用
NGライン
- 丸ごとAI生成をそのまま提出
- 具体的な体験談もAIに作らせる
- 面接で説明できない内容を書く
「結局、ESは面接の材料でしかありません。重要なのは、その内容について面接で深く語れるかどうか。AIに頼りすぎて自分の考えがない学生は、面接で必ずボロが出ます」(メガベンチャー人事部長・C氏)
AI利用によるメリットと落とし穴
効率化と学習効果のメリット
AIを活用することで得られるメリットは確実に存在します。
時短効果
最も大きなメリットは時間の短縮です。通常2-3時間かかるES作成が、AIを使えば30分程度で骨格を作ることができます。複数社への応募を考えると、この時短効果は計り知れません。
文章構成の学習
「起承転結」や「PREP法」など、論理的な文章構成をAIから学ぶことができます。特に文章を書くのが苦手な学生にとって、「型」を覚える教材としては優秀です。
語彙力の拡張
自分では思いつかない表現や言い回しを知ることができます。ただし、これは諸刃の剣でもあります。
オリジナリティの欠如というデメリット
一方で、AI利用には深刻なデメリットも存在します。
没個性化のリスク
AI生成の文章は、どうしても「優等生的」で「無難」な内容になりがちです。人事が求める「その人らしさ」や「個性」が失われてしまう危険性があります。
志望企業特化の薄さ
汎用的なプロンプトで生成した文章は、どの企業にも当てはまる内容になってしまいます。企業研究の深さや志望度の高さが伝わりにくくなります。
面接対策の甘さ
最も危険なのは、AI生成した内容を十分に理解しないまま面接に臨むケースです。
実際の失敗事例:人事担当者が目撃したケース
ケース①:説明できない自己PR
「リーダーシップを発揮してチームをまとめた経験について、AIで立派な自己PRを作成。しかし面接で『具体的にどんな困難があったの?』と聞かれて答えられず。結局、実際の経験は『サークルの飲み会の会場を決めただけ』だったことが判明」(小売業界人事)
ケース②:同じフレーズの大量発生
「『多様性の中で自分の価値を発揮し、組織の成長に貢献したい』という全く同じ表現のESが、同日に10通以上届いた。明らかに同じAIプロンプトを使っている」(製造業人事)
ケース③:企業研究の浅さが露呈
「弊社の『革新的な事業展開』に魅力を感じると書いてあったが、面接で『どの事業のどの部分が革新的だと思ったの?』と聞くと、『えーっと…全体的に』としか答えられなかった」(IT企業人事)

プロが教えるバレないための実践的手法
AIを「素材メーカー」として使う
AI を効果的に活用するための最重要ポイントは、「AIは完成品を作るツールではなく、素材を作るツール」として使うことです。
ステップ①:自分の体験を整理する
AIに頼る前に、まず自分の体験や考えを箇条書きでも良いので整理しましょう。「大学時代に一番頑張ったこと」「なぜその企業に興味を持ったか」「将来どうなりたいか」を、AIなしで考えます。
ステップ②:企業情報を具体的にインプット
単純に「志望動機を書いて」と指示するのではなく、企業の具体的な事業内容、最近のニュース、企業理念などを含めてプロンプトを作成します。
例:以下の情報をもとに志望動機の骨子を作成してください。
・企業名:〇〇株式会社
・志望職種:マーケティング職
・興味を持った事業:△△サービス(具体的な特徴も記載)
・私の経験:大学でマーケティング研究会に所属、××の企画を担当
・将来の目標:デジタルマーケティングの専門家になりたい
ステップ③:出力された内容を50%以上リライト
AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、必ず自分の言葉に置き換えます。特に以下のポイントを重視しましょう。
・自分が普段使わない言葉は削除
・具体的なエピソードを追加
・企業への言及をより詳細に
ESや面接対策で悩んだときは、AI搭載の就活サポートツール「REALME」を活用することをお勧めします。単純な文章生成ではなく、あなたの体験や価値観を深掘りしながら、企業に合わせたオリジナルなESの作成をサポートします。従来のAI文章生成ツールとは異なり、面接での再現性も考慮した実践的なアドバイスが受けられます。
「自分らしさ」を保つ実践テクニック
音読チェック法
完成したESは必ず声に出して読んでください。自分が普段話している言葉と大きく違う表現があれば、それは修正が必要なポイントです。
体験談の深掘り
AIは一般的な体験談は作れますが、あなただけの具体的な詳細は作れません。「そのとき何を感じたか」「どんな失敗をしたか」「そこから何を学んだか」といった感情面や学びの部分は、必ず自分で追加しましょう。
企業カスタマイズの徹底
同じ自己PRでも、志望企業ごとに「なぜその企業でそのスキルを活かしたいのか」を変えることが重要です。AIはその橋渡し部分の生成が苦手なので、ここは人間の仕事です。
面接対策まで含めた総合戦略
ESの内容を3分で説明する練習
ESの各項目について、面接で聞かれたときに3分以内で具体的に説明できるよう準備しましょう。特に以下の質問は確実に来ます
- 「このエピソード、もう少し詳しく聞かせて」
- 「そのとき一番大変だったことは?」
- 「そこから何を学びましたか?」
想定質問の準備
ESに書いた内容から派生する質問を10個程度リストアップし、それぞれに対する回答を用意します。この作業はAIに任せてはいけません。
AIは道具、価値はあなたの中にある
AI技術の発展により、ES作成における選択肢は確実に広がりました。しかし、取材を通じて明らかになったのは、「AI利用の是非」ではなく「AI利用の方法」が合否を分ける重要な要素になっているということです。
人事担当者たちが口を揃えて言うのは、「AIが悪いのではなく、AI任せにしてしまう思考停止が問題」ということ。あなたの体験、価値観、そして志望動機の根幹は、AIには作り出せません。
AIをうまく活用して効率を上げつつ、最終的に自分の言葉で語れる内容に仕上げる。そのバランス感覚こそが、これからの就活生に求められるスキルかもしれません。
最後に、大手人事部長の言葉を紹介します「AIは優秀な道具ですが、道具はあくまで道具。大切なのは、その道具を使ってあなた自身の価値をどう表現するかです。あなたの価値は、あなたの中にしかありません」

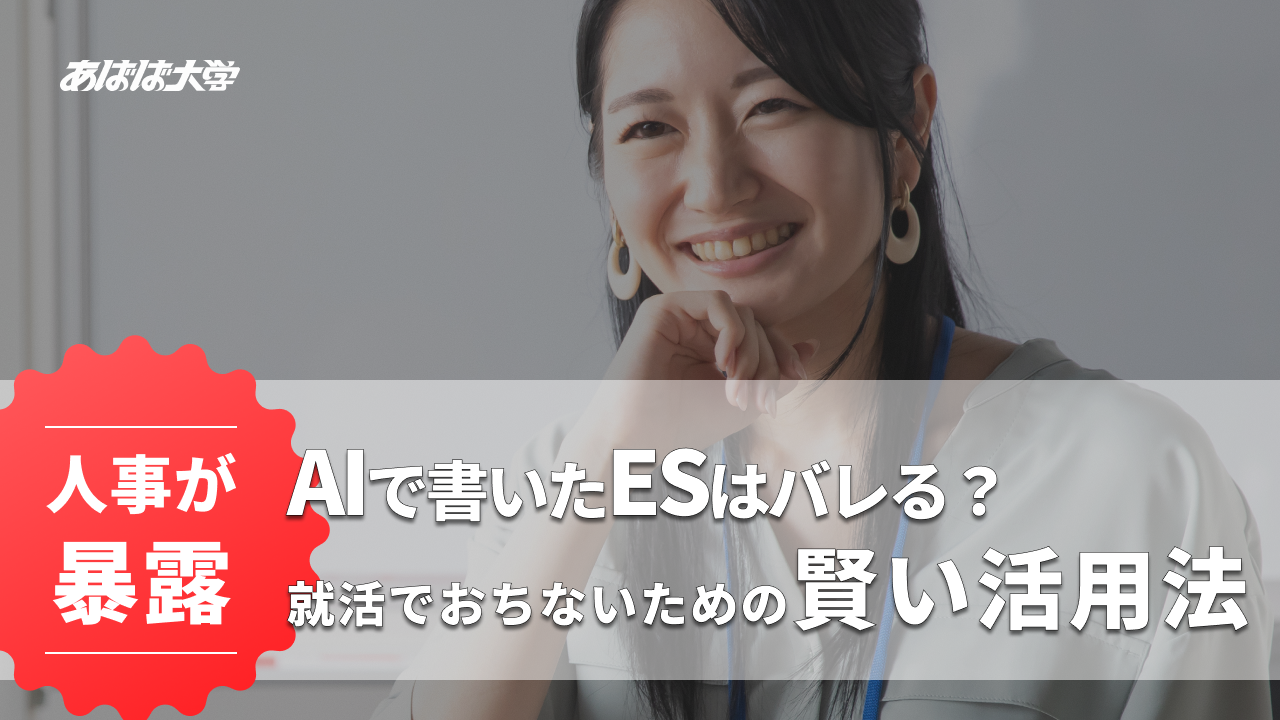
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)