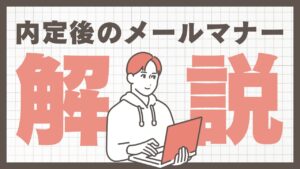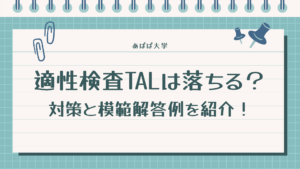就職活動で必ず聞かれることが、「学生時代に力を入れたこと」=ガクチカです。
ガクチカの文字数はエントリーシートを提出する際に企業側から指定され、300字程度の文字数を指定されることが多いです。
本記事では、300字でガクチカを作成する場合の構成や作成のポイントについて紹介します。
全ての就活対策をひとつで完結できる「REALME」では、AI面接をもちいた客観的な自己分析と、志望企業の内定判定の確認が可能です。また、志望企業の合格ラインを超えた学生のES・ガクチカも閲覧できるため、ガクチカの作成が苦手な方は回答例を参考にすることをおすすめします。
「REALME」を活用し300字で魅力的なガクチカを作成しましょう。
300字のガクチカとは?
ガクチカとは、学生時代に頑張ったことや特に力を入れた体験談を指します。就職活動中は、必ずといってよいほど聞かれる質問のため対策は必須です。
300字の文字指定は一般的な基準です。今後、複数の企業で300字のガクチカを作成する機会があるでしょう。指定された文字数で魅力的なガクチカを作成するには、部活やアルバイトなどの活動に取り組んだ過程や、具体的なエピソードを交えつつ作成する必要があります。
企業がガクチカを300字に指定する理由
まずは、企業がガクチカを300字に指定する理由をご紹介します。300字は、レポート用紙でいえば約4分の1程度。実際に字面で起こしてみると、決して長いテキスト量ではないことがわかります。なぜ多くの企業はガクチカで300字にこだわるのでしょうか?
端的にわかりやすく説明する能力をチェックするため
企業がガクチカを300字に指定する理由として、学生が「情報を端的にわかりやすく説明する能力」を見極めることが挙げられます。上記でも触れたように、300字は自己アピールとしては少ない印象を受けます。だからこそ「限られた文字数で情報をまとめる力」が求められるのです。
情報を端的かつ論理的にまとめる力は、社会に出た後にも幅広いシーンで必要になるスキルです。企業はガクチカを通して、情報処理力や想像力、論理的思考力などもチェックしているといえるでしょう。
採用業務の効率化を図るため
採用業務の効率化も、企業がガクチカを300字に指定する理由の一つです。とくに応募者が多い企業では、採用担当者が確認するエントリーシートの枚数も膨大になります。文字数制限を設けない場合、何十行も自己アピールを記載する応募者もいるでしょう。
ガクチカの文字数指定は、採用担当者の負担を下げ、効率的かつ時短で採用業務を遂行するための手段なのです。どの応募者も同じようなテキスト量であれば、読了のスピード感を維持しながら審査できます。
使い回しを防止するため
企業がガクチカの文字数を300字に指定する理由としては、「ガクチカ文のテキストの使い回し」を防止するためも挙げられます。企業のなかには、ガクチカを300字ではなく400字で指定するケースも多いものです。
自社も400字で指定すると、他社のために作成したガクチカを使い回されてしまうリスクがあります。志望する企業ごとに回答を作り直すような、真面目で誠実な学生を採用するために、あえて300字という短い文章量で指定しているのです。
300字のガクチカの構成
300字のガクチカで採用担当者に好印象を持たせるには、どのような構成にすればよいのでしょうか。分かりやすく効果的にアピールする方法として、以下を意識するとよいでしょう。
結論
はじめに明確な結論を言い切ることで、あなたが伝えたいことを相手に理解してもらうことができます。
そのため、全体の内容を簡潔にまとめ、何に取り組んだのかを明確に述べましょう。伝えたいことを明確にし、興味を持ってもらうことで採用担当者の印象に残すことができます。
理由
活動内容を端的に述べた後は、背景となる「ガクチカに取り組んだ理由」について説明しましょう。取り組んだきっかけや、抱えていた課題、目標などを説明することで、その後のエピソードに説得力を持たせられます。
300字の指定がある場合、エピソードの背景を具体的に述べると指定文字数を超える可能性があります。その場合、内容を簡潔する又は文字数を省略するなど工夫しましょう。
行動
取り組んだガクチカの具体的なエピソードを述べましょう。課題解決や目標達成のためにとった行動や、工夫などを詳細に述べることが大切です。部活やアルバイト活動における、具体的なエピソードをまじえて説明すると、相手に分かりやすく伝えられます。
主体性や積極性、コミュニケーション能力など、アピールしたいポイントにつながるエピソードを選ぶとよいでしょう。300字に収まるよう意識しながら、深掘りされても答えられるような回答を用意することがおすすめです。
学び
最後に結論として、ガクチカを通して得られたことや学んだことについて説明します。活動に取り組んだ結果や、経験から得られたこと・学んだことを伝えましょう。
その際は、入社後の意気込みや貢献できることにつなげて伝えられるとより効果的です。
ガクチカで得た経験を活かして、入社後どのように活躍をしたいか、具体的な姿をイメージできるような内容に作成できるとよいでしょう。
矛盾や疑問が生じない一貫性のあるガクチカの作成が大切です。
300字指定のガクチカの例文
ここでは300字以内に指定されている場合のガクチカの例文をご紹介します。ガクチカでは、結論から課題、エピソード、結果、企業への貢献という順番が大切。文字数をオーバーしないように心がけつつ、取り組みをコンパクトにまとめていきましょう。
部活の場合
私がガクチカで取り組んだことは、部活でキャプテンとしてチームの連携を強化したことです。以前は連携不足によるミスが多く、試合に苦戦していました。そこで私は、定期的なミーティングと練習中の積極的な声掛けを提案・導入し、チームの意思疎通を改善しました。その結果、メンバー間のコミュニケーション力が磨かれ、地区大会でベスト4に進出できました。この経験により、リーダーシップと調整力が磨かれました。入社後は経験を活かし、チームの協力体制づくりに役立てたいです。
アルバイトの場合
私がガクチカで取り組んだことは、アルバイト先の飲食店におけるクレーム対応の改善です。忙しい時間帯にクレームが増加しやすく、顧客満足が低下していたことが課題でした。私は対応マニュアルの見直しを提案し、スタッフ間の情報共有を強化しました。さらに丁寧な接客を徹底した結果、クレーム件数が30%減少し、顧客満足度の向上につながりました。この経験を通して身につけた対応力とチームワークの重要性を活かし、入社後も顧客満足向上に努めます。
ゼミの場合
私がガクチカで取り組んだことは、ゼミでの発表資料作成の効率化です。従来の仕組みでは資料作成に時間がかかり、発表に必要な他の準備が遅れるという課題がありました。そこで資料作成のテンプレートを作成してメンバーに共有し、進捗管理も徹底しました。その結果、資料作成時間が20%短縮され、質も向上しました。この経験を通して私が学んだことは、効率的な業務遂行の重要性です。入社後は経験を活かし、業務改善に尽力したいと考えています。
300字でガクチカを書く際のポイント
300字の文字指定をされた際は、ポイントを押さえて書きましょう。採用担当者の印象に残りやすく、魅力的な内容に作成できます。以下で紹介するポイントを意識しましょう。
エピソードは1つにする
ガクチカを書く際は、具体的なエピソードを交えて作成しましょう。その際、エピソードは1つに絞ることをおすすめします。
300字の文字指定がある場合、限られた文字数で伝えたいことを明確にし、相手にアピールする必要があります。なぜならば、複数のエピソードを盛り込むと、本当に伝えたいメッセージがぼやけるからです。もっとも伝えたい内容だけを残すことで、アピールポイントを明確に伝えられます。
数字を使って書く
限られた文字数で分かりやすく相手に伝えるには、定量的な表現を盛り込むことも重要です。数字を使って結果を伝えると、具体性が増し、信ぴょう性が高まります。
結論を伝える際は、具体的に「〇〇%の向上を実現」や「大会で〇位入賞」など数字で実績をアピールするとよいでしょう。
明確な実績がある場合には、「たくさん」や「多くの」などの表現ではなく、数字を使ってアピールができると、採用担当者に分かりやすく伝わり、印象に残りやすいです。
結論でインパクトを与える
ガクチカを作る際は、最初の結論でインパクトを与えましょう。ガクチカには論理的な説明が求められますが、丁寧な起承転結は必要ありません。冒頭で「私が学生中に取り組んだことは〇〇」ですと記載し、どのようなテーマでガクチカを展開するのかをイメージさせましょう。
その後に、最初に提示した結論を補強するようなかたちでエピソードを展開します。「何をしたのか」が定義されているからこそ、締めとなる「何を得たのか」が強く印象付けられます。
簡潔に伝えることを意識する
ガクチカの作成では、内容を簡潔に伝えることを意識してください。300字でガクチカを伝えきるためには、無駄なエピソードや例を省き、要点だけを明確に伝える工夫が必要です。
熟語や慣用句などを多用すると、貴重な文字数が割かれたうえに内容もわかりにくくなってしまいがち。詩的な表現や文学的な表現は控え、シンプルでわかりやすい内容を心がけましょう。まずは情報を一通り書き出したうえで、情報の取捨選択をするとスムーズです。
文字数が過不足な場合の対応策
300字と文字数が指定されていても、内容やエピソードによっては文字数の不足や、指定文字数をオーバーするでしょう。そうした場合の対応策を紹介します。
ガクチカが300字以内にならず困っている人は、ぜひ参考にしましょう。
多いときの対応策
300字をオーバーする場合は、不要な部分を削るところから始めてみましょう。文末の表現を変えたり、なくても意味の通じる部分を省略するなど、もっとも伝えたいところ以外の不要な文章を削ることで、全体の文字数を減らせます。
そのほか、言い換えて短縮できる単語がないか、また不要な接続詞を使用していないかなども確認しましょう。
エピソードを削るのではなく、表現や単語の言い換えで文字数を削る工夫もおすすめです。
少ないときの対応策
反対に300字に満たない場合は、経験やエピソードを深掘りしたり、自分の思いや感情、考えなどを加えるとよいでしょう。ガクチカに取り組んだ理由やきっかけなどの背景について盛り込むこともおすすめです。
また、エピソードに関しては、採用担当者から深掘りして質問される可能性があります。「〇〇の活動をしました」や「〇〇の目標達成のために頑張りました」など、漠然とした内容ではなく、活動の具体的な内容や目標達成のためにした努力、そこから感じたことなどを詳細に述べましょう。文字数も増やせて採用担当者の印象に残りやすいガクチカが作成できるでしょう。
AI面接「REALME」で自分の特性を客観的に知ろう
就活対策におすすめの「REALME」なら、AIとの面接を通じて客観的な自己分析による強み・弱みを把握できます。志望企業に対して効果的なガクチカを作成するためにも、自分を客観視することは大切です。あなたの強み・弱みを明確にし、自分の特性を客観的に正しく理解しましょう。
志望企業の内定可能性が分かる
「REALME」では、AI面接による客観的な自己分析が可能です。志望企業の最終面接まで進んだ学生の面接データと自分の面接データを比較し、志望企業から内定がもらえる可能性を算出してくれます。志望企業の最終面接に進んだ学生のデータを参照した上で内定の可能性を割り出してくれるため、自分の正確な立ち位置の把握が可能です。エントリー前に志望企業の内定判定が分かるため、より効率的な就活対策ができるでしょう。
AIで抽出したES・面接解答例が見られる
「REALME」のAI面接では、最終面接基準をクリアした学生のESや面接回答例、ガクチカなどの閲覧が可能です。回答を参考にし、300字と文字が指定されたガクチカの作成や、面接の回答方法に不安のある方は回答例を参考にすることをおすすめします。
AI分析で自身の強みと弱みを把握できる
「REALME」のAI面接では、あなたの強み・弱みを分析し、14の項目に分けて能力を点数化してもらえます。そのため、強みと弱みを把握でき、自分の長所・短所が明確になります。志望企業に対してあなたの強みをどのようにアピールすればよいか、どのような改善が必要なのかを適確に分析できるため、効率的な選考突破が期待できるでしょう。
14項目の能力ごとにFBも受けられるため、自身のアピールポイントを明確にしてガクチカを作成すれば、より魅力的なアピールが可能でしょう。
300字で面接担当者の印象に残るガクチカを作成しよう
ESでは300字の文字数指定をされることは少なくないでしょう。限られた文字数で面接官の印象に残る魅力的なガクチカを作成することは、ほかの就活生と差を付けるためにも重要なポイントです。今回紹介した構成やポイントを意識してガクチカを作成し、300字で面接官に好印象を持ってもらいましょう。
300字のガクチカに関するよくある質問
ここでは、300字の制限があるガクチカに関するよくある質問をご紹介します。とくに初めてガクチカを作成する人や、400字以上のガクチカしか作成していない人はぜひ参考にしてくださいね。簡潔で効果的なガクチカを作成し、面接官に自分の魅力や強みを印象づけましょう。
300字程度の場合はどのくらい書けばいい?
300字のガクチカを作成する場合は、全体の9割以上を埋めるように心がけてください。つまり270字以上の内容を作成していれば良いということになります。「300字以内」ではなく「300字程度」といわれていれば、310字以内であれば問題ないでしょう。
とはいえ面接官は「簡潔かつわかりやすいガクチカ」を求めているため、やはり270~300字がベスト。反対に、270字に満たないガクチカは「本気度が足りない」と思われてしまう可能性があるため、最低限以上の文字数は担保するべきです。
ガクチカは平均で何文字くらい?
面接で企業が求めるガクチカの文字数は、平均で400字程度が一般的です。もし企業から指定された文字数制限がない場合は、400字前後を目安に記載しましょう。
400字であれば、結論・課題・エピソード・成果・学びの一連の情報を的確に伝えつつ、企業への貢献についても十分な文字数を得やすくなります。400字を多少超える程度であれば問題ありませんが、500字に達すると少々長い印象が強く、採用担当者への負担が大きくなってしまいます。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)