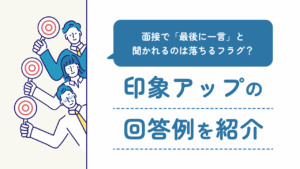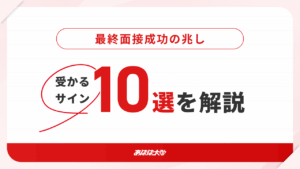この記事のまとめ
- グループディスカッションでは、「答えのない社会問題」や「時事ニュース」など抽象度の高いテーマがよく使われる。
- 企業は、議論を通じて学生の思考力・協調性・積極性を評価するため、発言姿勢や聞く姿勢も重要となる。
- テーマに関する知識の幅を広げ、他者の意見を尊重しつつ議論を前進させることが評価のポイント。
就活を絶対に失敗したくない人向け
- 効率よく就活を進めたい人にオススメ!
- 「面接で落ちてしまうんじゃないか」と不安な人にオススメ!
就活を何から始めていいかわからない人にオススメなのが「REALME」です。REALMEでは就活のビックデータを学習したAIが、模擬面接・自己分析をサポートしてくれます。
グループディスカッションとは
グループディスカッションとは、学生を4人〜8人のグループに分けて、1つのテーマについて議論する形式の選考方法です。身近なテーマからビジネスに関するテーマまで、幅広く出題されます。企業側はグループディスカッションを通して、他の学生との関わり方や協調性、論理的思考の有無などを判断しています。
グループディスカッションの目的
グループディスカッションは普段の生活で行うことが少なく、就職活動で初めて経験する人もいます。ここでは、グループディスカッションの目的について紹介します。
面接では分からない一面を見るため
グループディスカッションは、複数の就活生が集まって意見を出し合いながら進めます。
エントリーシートの記述や面接などでは見いだせない一面を確認できるため、グループディスカッションが採用されていると考えられます。
そのため、グループディスカッションに参加した際は、自分の意見を主張するだけでなく、他者の意見に耳を傾けたり、グループの意見をまとめることを意識する必要があります。
協調性やコミュニケーション能力を見るため
「グループディスカッション」では、ほかの就活生と関わりながら、自分の意見を主張したり、相手の意見を聞く必要があります。選考側はこのプロセスをもとに、応募者がグループでどのような役割を担うことができるのかを判断します。
リーダーとして議論をまとめる、意見をまとめて聞き入れるなど、自分に合った役割を担って議論に参加することが重要です。
種類別!GDのテーマ一覧とコツ
グループディスカッションはいくつか種類があるため、種類を見極めた対策が大切です。ここでは、グループディスカッションにおける種類別のテーマ例と対策のコツやポイントについてご紹介します。
討論・主張型
討論・主張型とは、あるテーマについてグループ内で討論して、結論を導き出す形式です。ディベートのように賛成・反対の立場で分かれる形式や、お互いが自由に意見を出し合う形式が存在します。
答えの存在しないテーマを設定するケースが一般的で、結論よりも討論の進め方や協調性が評価の対象となる傾向があるでしょう。
意見の異なるメンバー同士で結論を導き出すには、物事の判断基準を統一する必要があり、共同作業への適性、協調性が問われる形式といえます。
テーマ例
| ・50年後はどのような社会になっているか ・ものを売るときに必要な力はなにか ・リーダーに必要なものはなにか ・よい社会とは何か ・AIによって生活はどう変わるのか ・よい本とはどのような本か ・仕事で大切なのは効率?質? ・愛とお金のどちらが大切か ・小学生にスマホは持たせるべきか ・テレビCMかYouTube広告どちらが有効? |
コツ・ポイント
| ・グループ全体が納得する答えを出す ・抽象的テーマに対する解決策を導く |
課題解決型
あるテーマに基づいて議論する形式のグループディスカッションとして、課題解決型も定番のひとつです。テーマとして目標を与えられ、それを達成するためのアイデアを導き出す形式です。
多くのテーマは、ビジネスや社会問題の視点で設定されます。たとえば、「売上を○○%向上させる施策」や「少子高齢化の対策」などが想定されるでしょう。
グループ内で問題点を明確に設定したうえで、周囲に納得してもらえるアイデアを伝える意識が大切です。高い論理的思考力が求められる形式といえるでしょう。
テーマ例
| ・首都圏のビジネスホテルの売上を伸ばす施策は? ・外国人観光客の一人当たりの支出額を増加させるためにはどのようにすればよいか ・今後の旅行業界はどのような業界と手を組んでいけばよいか ・日本でキャッシュレス決済を普及させるには ・サラリーマンの英語力を向上させるためにはどのようにすればよいか ・ハンバーガーショップの売上を3年で1.3倍にする施策を考えよ ・百貨店の売上を向上させるには ・今後、旅行業界はどのような業界と手を組んでいけばよいか ・お気に入りの雨傘を使いたくなる施策は?を考える ・日本のレンタカーの売上を推定し、それを1.2倍にせよ |
コツ・ポイント
| ・問題点を明確にし、解決策を出す ・その企業が行っている事業の具体例が出されることも多い |
企画立案型
企画立案型とは、新規事業やビジネスモデルの施策を考える形式のグループディスカッションです。各グループで立案したアイデアを発表する流れで進行します。
企画立案型のテーマには、企業の特徴や業界のトレンドに沿った内容が頻出するため、論理的思考力やプレゼン力に加えて、業界や企業の研究も大切です。
斬新で柔軟な発想力を評価基準とする企業がある一方で、実現可能な範囲で論理性のあるプレゼンを求める企業も存在するでしょう。
テーマ例
| ・新幹線の新しいサービスを考案せよ ・テーマパークで新しく追加するアトラクションを考えてください ・外国人観光客をターゲットとしたベンチャー企業のビジネスモデルを構築せよ ・○○市でできる、新しい町おこしイベントを考えてください ・弊社の既存商品を生かした新しい飲食店のコンセプトを考えてください ・夏場にスキー場を活用できるイベントやビジネスと考案してください ・スポーツビジネスを始める総合商社が最初にとるべき方策とは ・大手コンビニチェーン会社の新規事業を考えてください ・新商品をこの会社で出すならどのような商品を出しますか ・令和の子どもに人気が出る新しい特撮ヒーロー像を考案してください |
コツ・ポイント
| ・論理的思考に基づいたアプローチによる目的を設定する ・業界や企業のビジネスモデルを理解する |
選択型
選択型は、討論・主張型に近い特徴をもつグループディスカッションです。対立する2つの議題に関して、どちらが望ましいかをグループ内で選択し結論づけます。
テーマは、個人の価値観や経験によって意見の分かれやすいものが多く、双方の特徴を把握し比較検討したうえで結論を出す意識が重要です。
他の形式と比べて、選択型はグループ内で意見が割れやすいため、異なる意見をぶつけながら結論を導き出す協調性やリーダーシップが試されます。
テーマ例
| ・うどんとそば、世界に売り出すならどっちか ・日本の首都を移転にするにはどこかよいか ・小学生に今一番学ばせるべき習い事は何か ・家庭にあるものを1つ無人島に持っていけるなら何がよいか ・新店舗出店の場所はどこが最適か ・上司はどのような性格の人物が理想か ・大学の授業はWebか対面のどちらがよいか ・「家族・恋人・親友・お金」に優先順位をつけてください ・企業が一番大切にすべきは利益か社員か社会貢献か、それとも何か別の事柄か |
コツ・ポイント
| ・答えを選んだ理由やプロセスが重要 ・選択肢を比較するために基準の設定を明確にする |
分析型
課題解決型に似た形式として、分析型も存在します。提示された資料やデータをもとに、テーマに基づいた分析を深めてグループ内の結論を導き出す形式です。
経営数値や企業の特徴など、資料に記された情報を正しく解釈して、分析のすり合わせとともに結論を導き出す読解力や思考力が求められるでしょう。
企業側は、用意した資料とテーマについて一定の正答を用意することがあります。ポイントを押さえた結論が出せると、高評価が期待できます。
テーマ例
| ・とあるファミリーレストランがとるべき経営戦略は? ・あるテーマパークの料金を変動にすべきか固定にすべきか ・今年どのような芳香剤を出すべきか ・次の5人のうち2名を採用する場合、誰を採用するべきか ・資料を読んで会社の業績改善方法を考えなさい ・ホームセンターを新規出店するなら、以下4つの候補地のうちどれがよいか ・資料からA大学の入学者の増加対策を考えよ ・資料を読んで経営の立て直し戦略を考えなさい ・インドネシアでの都市開発事業でどのパートナーと組むべきか ・ショッピングセンターのテナントに空きが発生した。次の5店舗のうち、どのお店を開店させるべきか |
コツ・ポイント
| ・他の選考に比べて結論を重要視する傾向がある ・数字ベースで論理的に原因を特定できるかが重要 |
フェルミ推定型
フェルミ推定とは、自分の知識と思考力を活用して、調査や測定が難しい規模の概算を推定で導き出す手法のことで、グループディスカッションでもフェルミ推定型を取り入れる企業があります。
「日本に存在する道路標識の数」のように、通常であれば短時間で計算できない規模のテーマが設定されます。身近な部分から範囲を広げて概算するうえで、大まかな数字感覚と計算能力が問われるでしょう。フェルミ推定の設問が出ても焦らず対応できるように、テーマ例をもとに事前練習をおすすめします。
テーマ例
| ・ラーメン店の1日の売上は? ・日本にあるコンビニの数は? ・日本国内にある電柱の本数は? ・東京にあるカフェ1店舗の売上は? ・日本の缶コーヒーの市場規模は? ・映画館の1日の売上は? ・全国の女性の数は? ・日本で飼われている犬の数は? ・箱根にある温泉旅館の年間売上は? ・東京都内のマンホールの数は? |
コツ・ポイント
| ・導き出した数値の根拠を論理的に説明できるかがカギ ・最低限の基礎知識を身につけておく |
ブレインストーミング型
ブレインストーミングは、新たなアイデアを出したいときに有効な議論の方法です。ルールや形式を定めず、参加者同士で自由に議論を進める点が特徴です。
グループディスカッションにおけるブレインストーミング型は、漠然とした答えのないテーマに対して、さまざまなアイデアを出し合う目的で実施されます。
自由な討論形式では、制限時間内に結論を出せず終わるケースも想定されるため、グループ内でテーマに対する解釈や判断基準を統一することがポイントです。
テーマ例
| ・働くことの意味は?・理想の社会人とは? ・社会人と学生の違いは? ・よい会社の定義とは? ・海外市場の情報収集方法は? ・残業をなくすために必要なことは? ・この業界の10年後を予測してください ・仕事と家庭どちらを優先した方が幸せ? ・顧客を獲得するために必要な営業スキルは? ・日本の投票率をあげるためにどのようにすればよいか |
コツ・ポイント
| ・答えの正確さよりも、答えにたどり着くまでのプロセスが重要 ・テーマの定義を全員で共有してから議論する |
【STEP】グループディスカッションの流れ・手順
グループディスカッションは、大きく分けると3段階の構成から成り立ちます。流れは以下の通りです。
- 準備:役割→時間配分→定義・前提条件のすり合わせ
- 実施:アイデア出し→議論をまとめる
- プレゼン→説明できる形に整える
自己紹介や役割分担は、その後の議論を活発化するために重要です。まずは、コミュニケーションがとりやすい印象を周囲に与えましょう。
次に、テーマをしっかりと定義づけすることで議論のズレを防ぎ、ディスカッションをスムーズに進められます。意見を出し合い、結論にたどり着いたら、端的に説明できるようなプレゼン方法を確認することが重要です。
面接官の評価チェックポイント
グループディスカッションでは、面接官は以下のポイントを評価しています。
- 協調性
- 積極性
- コミュニケーション能力
- 論理的思考力
それぞれについて詳しく解説します。
協調性
周囲とのバランスが取れているか、周囲を配慮する気持ちがあるかなど、採用担当者は協調性について確認します。
グループディスカッションは、とにかく自分が話せばよいわけではありません。自分の意見を伝えつつ、周りの意見にも耳を傾けて、全体の意見をまとめます。なかなか話に入れない人がいたら話を振ったり、話がまとまらなければ話をまとめようとしたりするなど、周囲を見て行動できる人はよい印象を持たれます。
仕事の多くはチームワークが重要であるため、グループディスカッションを通して協調性があるかを採用担当者は見極めています。
積極性
積極性があるかどうかを見ているケースもあります。
話を聞くだけではなく積極的に発言する姿勢を示したり、周りの意見も聞きつつ自分の意見を話すことが積極性をアピールするためには大切です。
なかなか話に入りにくいケースもあります。しかし、一言も発しないまま終わることはことは避け、タイミングを見て自分の意見をしっかりと伝えましょう。
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力も重要です。なぜなら、仕事は複数人でするものであり、どのような職種でもコミュニケーション能力が求められるためです。
自分の意見だけではなく全体をまとめようとする姿勢があるか、課題解決に向けて誘導できているかを見て面接官はコミュニケーション能力の有無を判断します。積極性は重要である一方で、周りの意見を聞かず自分の意見ばかりを通すとマイナス評価に繋がる可能性があります。
自分と周りの意見をまとめて、テーマの答えを導き出しましょう。
論理的思考力
グループディスカッションで高い評価を得るには、論理的思考力も不可欠です。議論では他者の意見を正確に理解する必要があり、異なる複数の意見をまとめて結論に向かううえで、論理的思考力が問われます。
また、自身の意見を周囲の参加者に理解してもらうには、相手を納得させられる論理性が求められるでしょう。質問を受けたときは、根拠を立てて分かりやすく説明することが重要です。
グループディスカッションで高評価を得るポイント
グループディスカッションで高評価を得るためには、以下のポイントの意識が大切です。
- 周囲の意見を聞く
- 自分の役割を見極める
- 積極的に発言する
それぞれについて詳しく解説します。
周囲の意見を聞く
積極性をアピールすることは大切なものの、周りの意見を聞くことも大切です。自分が発言することだけに必死にならないよう注意して、場の雰囲気を読むことも心がけましょう。
ときには、自分と異なる意見が出ることもあります。この際、否定はせず違う意見にも耳を傾けて受け入れることが大事です。
グループディスカッションは相手を論破する場ではありません。自分の意見を伝えつつ、周りの意見に耳を傾ける人の方がよい印象を持たれます。
自分の役割を見極める
自分の役割を見極めて行動すると、好印象を与えられます。
司会やタイムキーパーなどの役割が決まっている場合はその役割に従いましょう。役割を決めていない場合は、場の雰囲気で自分の役割を見極めて行動します。自分の役割を見極めて、自分で考えて行動するスキルは、社会人として大きな武器になります。
また、役割のある人をフォローする配慮があると、よりよい印象を与えることが可能です。自分の役割を全うするばかりではなく、周りを見て必要に応じてサポートしましょう。
積極的に発言する
前述の通り、面接官は積極性を見ます。そのため、自分の意見があれば積極的に発言しましょう。
周りに合わせることも大切ですが、周りばかり気にして自分の意見を出さないことはNGです。自分の意見もしっかりと伝えつつ、周りの意見にも耳を傾けることが重要です。
また、意見だけではなく、全体の意見をまとめる動きができると好印象を与えられます。メンバーそれぞれの意見を聞いて、結論を導き出しましょう。
グループディスカッションの対策方法
「グループディスカッション」は就職活動以外で行うことが少ないため、どのように対策すればよいのかが分からないという人も多いでしょう。
ここでは、「グループディスカッション」の対策方法として有効なものを2つ紹介します。
普段から自分の意見を持つ
「グループディスカッション」では、社会で起こった事柄やニュースが議論のテーマになる場合があります。このとき、全く知らないことや意識していないことが議論のテーマで出てくると、うまく対応できず消極的な姿勢になるでしょう。
対策として、世間のニュースに対して自分の意見を持つ習慣をつけることが重要です。新聞を読み、出来事を要約したり、考えを文章化するなどの対策が有効です。
ただし、テレビや新聞で取り上げられた意見の丸写しではなく、自分なりの意見を考えましょう。
動画を見てイメージする
「グループディスカッション」の空気感や進行の流れを掴むには、「グループディスカッション」を行っている様子を見ることが有効です。
YouTubeをはじめ、動画サイトでは模範例がアップされてます。動画で一通りの流れを把握するとイメージを掴めるため、就職活動対策として一度チェックすることをおすすめします。
グループディスカッションでのNG行動
グループディスカッションにおいて、以下のような行動はマイナス評価につながります。
- 発言が少ない、または無言
- 人の意見を否定する
- 与えられた役割を果たさない
- 場の雰囲気を乱す
それぞれについて詳しく解説します。
発言が少ない・無言
発言が少なかったり、無言だったりすると「やる気がない」「志望度が低い」と思われるためNGです。周りを見ながら、適度に自分の意見を伝えるようにしましょう。
また、意見を発しても声が小さかったり、聞こえにくかったりすると、マイナス評価につながります。意見を伝える際は、全員に伝わる声の大きさや速度を心がけましょう。
緊張すると早口になりやすいため、ゆっくりと話すことを意識すると聞き取りやすくなります。
人の意見を否定する
自分と意見が違っても、人の意見をただ否定するような発言は厳禁です。なぜなら、グループディスカッションは他の人の意見を論破したり、否定したりする場ではないためです。
ディスカッションを行うと、自分の意見を否定されたり異なる意見を述べられたりすることもあります。この際、強い言葉で反論したり議論を止めたりしてはいけません。
グループディスカッションでよい印象を与えるためには、相手の意見も尊重して自分の意見を伝えることが大切です。
与えられた役割を果たさない
決めた役割を果たせなかったり、違う役割を勝手に担ったりする行動もNGです。なぜなら、これらの行動は他の人が混乱して議論が進まなくなるためです。議論が円滑に進むように、決められた役割を全うしましょう。
また、与えられた役割を放棄することは、責任感がないと捉えられます。責任感の有無は合否に大きく影響するため、それが原因で選考に落ちる恐れがあります。
場の雰囲気を乱す
場の雰囲気を乱さないように注意しましょう。
場の雰囲気を乱す言動とは、以下のような言動です。
- 議論と関係のない話をする
- 一人だけ熱くなる
- まとまりかけていた意見を否定する
- 他の人が理解できない用語を多用する
場の雰囲気を見ながら、その場に合わせた言動を心がけましょう。
全国共通模試「REALME」で内定確率をチェック
グループディスカッションのテーマ対策が完璧でも、後にある個別面接がうまくいかないこともあります。今の自分が内定をもらえるレベルであるかを知りたい人には、「REALME」での内定確率チェックがおすすめです。
内定判定で現在の自分と志望企業の距離を確認できる
グループディスカッションに受かると、いよいよ個人面談です。自分のレベルが他の就活生と比べてどの程度か、不安に思う人もいるでしょう。
新卒就活版の全国共通模試「REALME」は、AIとの面談を通して、志望企業の最終面接まで進んだ就活生と自分の実力を比較できます。自分の現在地を把握することで、面接への正確な対策が可能です。
合格ラインを突破した学生のESや面接回答を閲覧できる
グループディスカッションはテーマに沿って議論するため、複数の就活生と関わります。一方で、個人面接に進むと、他の就活生がどのような回答をしているのかを知ることは困難です。
「REALME」では、志望企業における過去内定者の面接やエントリーシートからAIで作成した模範回答を閲覧できます。合格基準に達した就活生のデータを閲覧することで、必要なスキルや知識の確認に役立ちます。
自分が秀でている・足りないスキルや特性をAIで客観的にわかる
「REALME」でAI面接を受けると、内定判定だけでなく、内定をとるためのフィードバックも確認できます。今の自分が秀でている点や足りないスキルを客観的に判断できるため、面接対策をしやすいことが特徴です。
グループディスカッションの前にREALMEを活用し、自分の実力をチェックすることで、ディスカッションに対して自分が補うべきスキルや知識が明確になるでしょう。
グループディスカッションのテーマを先取りして選考を有利に進めよう
グループディスカッションは、種類やテーマに沿った対策をすることで、慌てることなく取り組めます。苦手意識がある人は、前述の例題を利用して何度も練習し、経験を積むことが重要です。
グループディスカッションのテーマを先取りし、選考を有利に進められたら、個人面接の対策も考えましょう。自分の実力や内定判定を知りたい方は、「REALME」によるAI面接にチャレンジしてみてください。

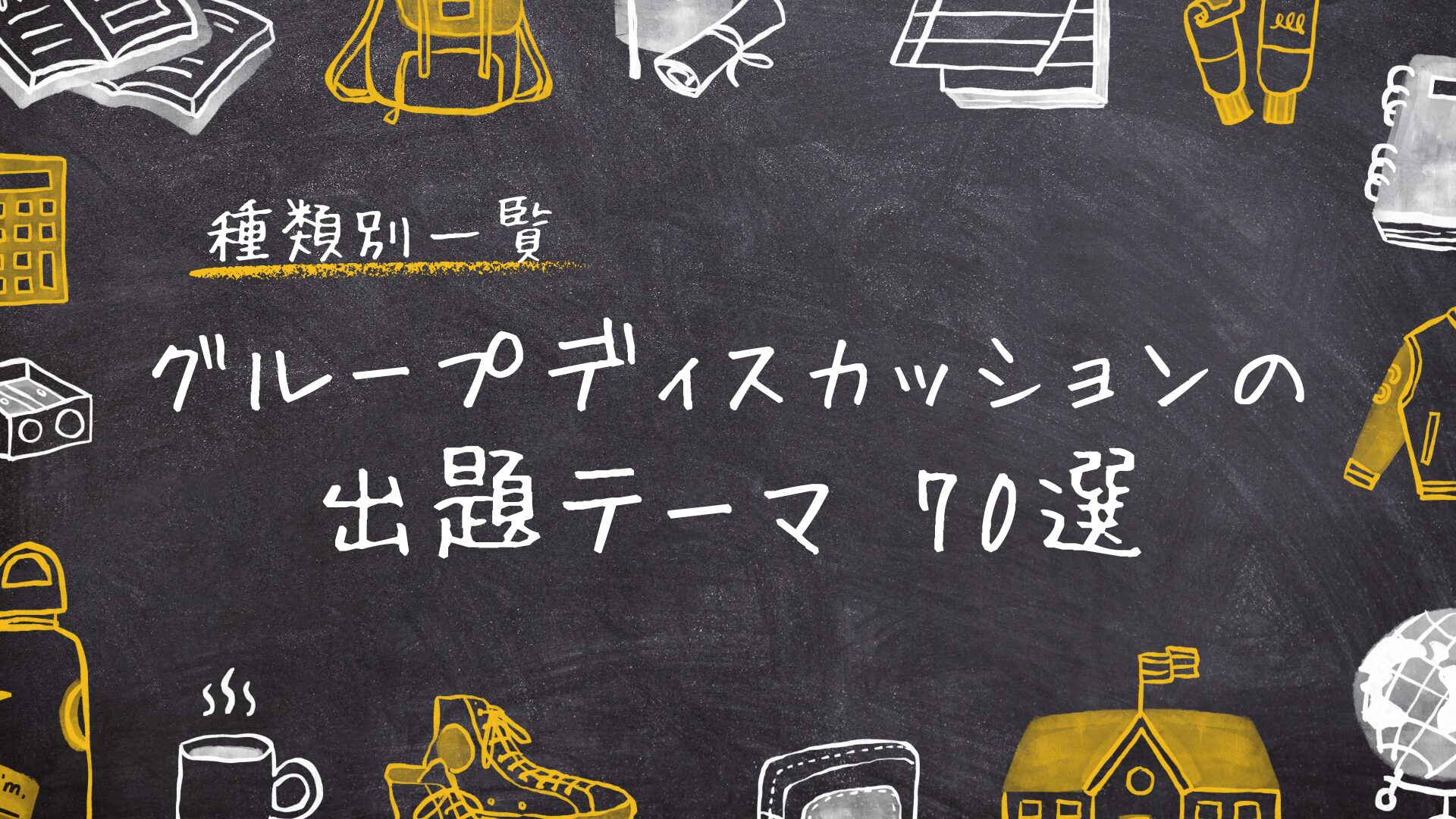
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)