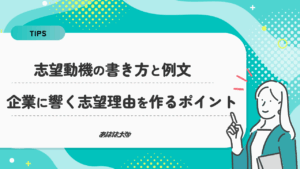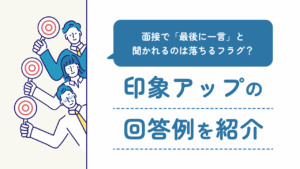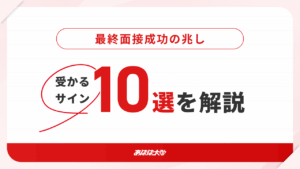就職活動の面接で、「自分を色に例えると、何色だと思いますか」と質問された経験はありませんか。面接で聞かれることは、自己紹介や志望動機、ガクチカについて質問されることが多いとされています。
一方で、突拍子もないことを聞かれる場合があります。突拍子のないことのひとつが「自分を色に例えると」という質問です。
本記事では、「自分を色に例えると」を面接で質問する意図を詳しく解説するほか、色別の回答例もご紹介します。ぜひ、参考にしてください。
「REALME」では、AI面接を通して自分の能力を点数化するサービスです。面接を通じて自分の特性を客観視し、自分を象徴する色が何色なのかを分析できます。ぜひ、活用してください。
「自分を色に例えると」の質問意図は?
「自分を色に例える」と質問する意図は、就活生の特性を把握するためだと考えられます。
以下では、色に例えることで、どのようなことが分かるかを詳しく解説します。
人柄を知るため
色を確認する意図には、その人の人柄を知りたいということが挙げられます。また、自分自身をどの程度知り、自己分析ができているのかを確認する目的もあります。
例えば、温厚で優しい性格が魅力である場合は、暖色を選ぶ傾向が高いでしょう。一方で、誠実で冷静な人は寒色を選ぶことが多いと考えられます。
このように、自分を色に例えることで、採用担当者は自社にふさわしい人材かを確認し、入社後のミスマッチを防ぐ目的があるといえるでしょう。
そのため、無理に企業の色に合わせるのではなく、自分を表現できる色の選択が大切です。
素顔を知るため
素顔を知りたいという思いから質問することもあります。これは、不意に出る少し変わった質問によって本来の姿が見えやすいためです。
定番の質問は、多くの学生が回答を準備しています。また、面接会場では緊張していてなかなか素を出せません。
そこで、あえてなかなかない質問をして、その人の素顔を知ろうとします。素顔を知ることで、本当に自社に合う人材かを確認したいという意図があります。
柔軟性を知るため
採用担当者は、「自分を色に例える」などの突拍子もない質問に対して、就活生がすぐ回答できるかどうかを見ることで柔軟性を確認しています。日頃から自己分析をしている人は、唐突な質問に対しても柔軟に答えられる傾向にあります。
唐突な質問に落ち着いて対応できる人は、仕事に置き換えた場合も同様な対応ができるでしょう。例えば、同じ業務内容でも質問の仕方は人によって異なるため、相手の意図を汲み取り、適切に対応できる柔軟性が求められます。
そのため「自分を色に例えると」の質問は、柔軟な回答力や、緊張感のある場所での対応力がどの程度あるかを把握するためだといえます。
論理的に話せるかを知るため
「自分を色に例えると」という唐突な質問には、就活生が論理的に回答できるかを把握する目的があります。答えのないことに対して自身の考えをまとめ、ベストな答えが回答できるかを見極めるためと考えられるでしょう。
この能力はビジネスの場で非常に大切な思考で、重要視する企業も多いといわれています。
自分を色に例える時のポイント
自分を色に例える際、よい印象を与えるためには以下のポイントの実践が大切です。
・長所と結びつける
・具体的なエピソードを入れる
・PREP法で話す
・入社後の活かし方を話す
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
長所と結びつける
例える色を考える際は、印象としての色ではなく自分の長所や強みから考えましょう。色から理由を考えるのではなく性格から色を考えることで、理由を考えやすくなるだけではなく、質問に回答しながら自分をアピールできます。
先に色を考えると、その色に対する理由を考えます。すると、色を答えることが目的となり、自分をアピールできません。
自分の長所をもとに、合う色を見つけましょう。
具体的なエピソードを入れる
例える色と理由が決まったら、次になぜその色なのかの具体的なエピソードを話します。具体的なエピソードを入れることで、話に説得力が出たり印象に残りやすくなったりするためです。
具体的なエピソードを入れる際は、色とエピソードが一致するかを確認します。色と全く関係のないエピソードを話すと内容にまとまりが出ず、話したい内容が伝わりません。
PREP法で話す
「自分を色に例えると」の質問だけではなく、質問に回答する際はPREP法を意識しましょう。PREP法とは、結論・理由・具体例・結論の順で話す話し方のことであり、これを意識することで伝えたい内容が伝わりやすくできます。
また、PREP法で話すと論理的な話し方ができると好印象を与えられます。論理的な話し方は、仕事をする上でも重要なスキルです。
自分の長所をアピールしつつ、話し方のスキルもアピールしましょう。
入社後の活かし方を話す
最後に、具体的にその企業でどのような貢献ができるかを伝えます。企業研究をして、その企業に合う活かし方を話しましょう。
「自分を色に例えると」を質問された際、色を伝えるだけで終わらせることはNGです。色のみを伝えるのではなく、自身の強みや貢献できることをアピールして、よい印象を与えましょう。
自分を例える色の選び方
面接でよく聞かれる「あなたを色で例えると?」という質問は、第一印象だけでなく自己理解の深さも試されています。感覚で選ぶのではなく、色のイメージや自分の強みとしっかり結びつけて答えることで、納得感のある自己PRにつながります。ここでは、自分に合った色を選ぶための考え方をわかりやすくまとめます。
主要な色のイメージを知る
自分を例える色を選ぶときは、まず主要な色がどんな印象を持たれているのかを把握することが大切です。例えば、赤は情熱や行動力、青は誠実さや冷静さ、黄色は明るさや柔軟性など、同じ色でも複数の意味を持つため、面接での回答も幅を持たせやすくなります。色のイメージを知っておくと、自分の性格や強みをどの色と結びつければ最も伝わるのか判断しやすく、説得力のある回答につながります。
では、色が与える印象はどういうものなのでしょうか?
| 赤 | 情熱、行動力 |
|---|---|
| オレンジ | 活発 |
| 黄色 | 柔軟性、明るさ |
| 青 | 誠実さ、冷静さ |
| 緑 | 謙虚さ、穏やかさ |
| 白 | 素直さ、清潔さ |
自己分析からPRポイントを書き出す
色を決める前に、まずは自己分析を通して自分の強みや性格をしっかり整理することが欠かせません。最初に色を選んで当てはめるのではなく、「自分は何を大切に行動してきたか」「どんな場面で力を発揮してきたか」を洗い出し、PRの軸を明確にします。そのうえで、強みと結びつく色を選ぶと回答に一貫性が生まれ、説得力がぐっと高まるでしょう。長所を書き出してから、それに最もフィットする色を当てはめる流れにすると、“意味のある色選び”ができ、面接官の印象にも残りやすくなります。
思い浮かばないときは周りの声を聞く
自分にしっくりくる色がどうしても思い浮かばないときは、家族や友人など身近な人に意見を聞いてみるのが意外と効果的です。普段のあなたをよく知る人だからこそ、「○○っぽい雰囲気」「こういうところが強みだよ」と客観的な視点で特徴を捉えてくれます。第三者からの言葉は、自分では気づけなかった魅力や傾向を知るヒントにもなり、回答の精度を高める材料になります。周りからの声を組み込むと、面接官にも説得力が伝わりやすく、“その色を選んだ理由”がより深みのあるものになります。
「自分を色に例えると」の回答で知っておきたいこと
面接でよく聞かれる「自分を色に例えると?」という質問は、正解を探すものではなく、あなたの個性や価値観、自己理解の深さを見極めるためのものです。どんな色を選ぶかよりも、“なぜその色なのか”を筋の通った言葉で伝えられるかがポイントになります。ここでは、回答するときに知っておきたい考え方や押さえておくべきポイントをまとめて紹介します。
他の学生と回答する色が同じでもOK
グループ面接や集団面接で、他の学生と同じ色を答えてしまっても心配する必要はありません。色そのものに優劣があるわけではないため、「被った=減点」にはなりません。面接官が知りたいのは“その色を選んだ理由”や“自分のどんな特徴を反映しているのか”という背景部分です。同じ色でも、エピソードや価値観が違えば印象はまったく変わります。むしろ、似た回答の中で「どう差別化するか」を見せるチャンスにもなるので、色より“語る理由”を丁寧にまとめることが大切です。
強みやPRとかぶっても良い
「自分を色に例えると?」では、自己PRや長所で話した内容と重なってしまっても全く問題ありません。むしろ、テーマが変わっても同じ強みが一貫して表れていることは、面接官にとって“軸がある学生”という好印象につながります。無理に新しいエピソードをひねり出すより、すでに話した内容を“色”という切り口で再構成した方が説得力も安定します。同じエピソードでも視点を少し変えるだけで伝わり方は大きく変わるため、強みを裏付ける話と色を自然に結びつけて回答すると、より納得感のある自己表現ができます。
選ぶ色に正解はない
自分を例える色に“正解”は存在しません。面接官が評価するのは色そのものではなく、「なぜその色を選んだのか」「どんな性質や強みを表しているのか」という理由の部分です。同じ色でも人によって背景や価値観は違うため、選択肢が被っても問題ありません。むしろ、色を通して自分の性格・行動特性・柔軟性をどう表現するかがポイントになります。色に悩むより、あなたの強みやエピソードと結びついた“選んだ理由”を丁寧に語ることが、説得力のある回答につながります。
「自分を色に例えると」の回答例文
自分を色に例えた回答では、自分の性格や特性、得意なことを盛り込み、選んだ理由を具体的なエピソードで明確にしましょう。これらのポイントを踏まえ、各色の例文をご紹介します。
赤
私を色に例えると、赤色です。学生時代は、部活動や学校行事で中心的な役割を担い、自ら声をかけ率先して行動する積極性があったため、赤色を選びました。
所属するバレーボール部では、向上心を活かし練習に打ち込むだけでなく、チーム全体の団結力をたかめるため、積極的にコミュニケーションを取り合いました。
また、互いの練習内容を確認、フィードバックする方法を考案し、その結果チームを勝利へ導いた経験があります。
御社のチームプロジェクトでも同様に、持ち前の向上心を発揮し、チーム内で積極的なコミュニケーションを取りながら、新たなことにチャレンジしたいと考えています。
青
私を色に例えると、青色です。学生時代は、学校行事やアルバイトでリーダーを努め、冷静な判断力と安定感のある洞察力でチームをまとめてきました。
リーダーシップを発揮するだけではなく、客観的な視点でチーム全体を見渡し、より広い視野を持って様々なことに取り組んできました。
部活動ではサッカーに打ち込み、焦らず一歩ずつ、日々の練習を着実に励んできました。試合で劣勢に立たされた場面でも、相手の隙を的確に捉え、チームを勝利に導いた経験が多くあります。
冷静な判断力と客観的な視点を武器に、御社でも広い視点をもち、業務に貢献したいと考えます。
紫
私を色で例えると紫です。紫は「青の冷静さ」と「赤の情熱」を併せ持つ色として扱われ、バランス感覚のある人柄を表すときに便利です。状況に応じて落ち着いて判断しつつ、必要な場面ではしっかり行動に移せることができます。そんな“二つの面”を自然にアピールできます。論理性と感情のどちらも大切にしている人、チームの中で調整役にも挑戦する人などに特に向いている色です。
冷静に状況を整理する一方で、目標達成に向けて行動力も発揮できるバランスの良さが強みだからです。大学のプロジェクトでも、全体を見て課題を整理しつつ、自ら率先して改善案を提案し、チームを前に進める役割を担いました。
黄
私を色に例えると、黄色です。黄色は協調性を象徴する色だと考えています。大学での教育工学研究活動を通して、その協調性を活かし活動をしてきた経験があります。
周りの学生とコミュニケーションを取りながら、協力して研究を進め、皆のモチベーション向上のために、明るくチームを盛り上げました。
大学1年生で参加したボランティア活動では、地域清掃を通して多くの住民から感謝の言葉をいただきました。このときに、人のために何かをすることへの喜びを感じたほか、感謝の言葉が原動力になり、物事を成し遂げられるのだと気付かされました。
これらの経験から、協調性があり、感謝の気持ちを大切にすることから黄色に例えられると考えます。
緑
私を色に例えると、緑色です。私はゆっくりと着実に成長するタイプで、日々積み重ね努力することが得意です。
大学3年生の頃、特に苦手だった英語の学習を毎日決まった時間に行い、半年後には200点以上という点数向上を実現しました。
高校時代は、バレーボール部のスパイク練習で、毎日50本を目標に打ち込みました。その結果10ヶ月後、試合で5本連続の得点を決め、チームを勝利へ導いた経験があります。
私はゆっくりと着実に成長できる性格であるため、この能力を活かし御社へ貢献します。
オレンジ
私を色に例えると、オレンジ色です。私は幼い頃から、周囲を明るくし、元気づけることが得意です。高校時代のテニス部では、積極的にチームを盛り上げてきました。厳しい練習期間を部員全員で乗り越えた結果、引退試合で見事優勝しました。
私は周囲を明るくする陽気な性格が自分の強みだと考えています。
そのため、御社でも持ち前の明るさを発揮し、困難な状況を乗り越え、会社の成長に貢献したいと考えています。
白
私を色に例えると、白色です。白には「何色にも染まらない公平な色」というイメージがあります。私は、この白のように素直な心を大切にしたいと考えています。そのため、この色を自分を表す象徴として選びました。
大学時代、私は2つのサークルに参加し、それぞれ異なる役割を担当しました。臨機応変な対応が得意なため、どのような状況にも柔軟に対応し、どちらのサークルでも「最優秀」と評価されました。
御社でも、偏見なく素直に物事を受け入れ、相手の話に耳を傾け、一人ひとりの意見を尊重しながら、円滑なコミュニケーションを図りたいと考えています。
黒
私を色に例えると、黒色です。黒色は芯の強さや個性を象徴する色のためです。私は、どのような状況でも、自分の軸をしっかりと持ち、芯がブレず、バランス感覚にすぐれているため、周囲からは「芯が強い人」とイメージされます。
学園祭やサークルイベントでは、他のメンバーとの連携を密に行いながら積極的に参加し、チームの一員として貢献しました。また、高校時代のバスケットボール部では、目標達成に向けて、チームの核として常に前向きな姿勢で取り組み、自己記録更新に挑み続けました。
これらの経験から、周囲と協力しながら自らの役割を明確にし、持ち前の芯の強さを活かして、御社に貢献したいと考えます。
「自分を色に例えると」と聞かれた際の注意点
「自分を色に例えると」と聞かれた際、以下の点に注意しないと逆効果です。
- 前置きや説明が長過ぎる
- 短所を答えない
- 類似質問にも答えられるようにしておく
- 好きな色を答えるだけにならない
- 長所と色のイメージが一致しないのはNG
それぞれについて詳しく解説します。
前置きや説明が長過ぎる
回答は、端的にまとめることが大切です。なぜなら、色についての説明や前置きが長過ぎると、内容が曖昧で何を伝えたいのかが分からなくなるためです。
前置きや説明が長くなる場合は、短くても伝わりやすい内容になるようにPREP法を見直しましょう。PREP法を意識することで、相手に伝えたい内容、つまり自分の強みを伝えられます。
短所を答えない
回答に正解はないため、どの色を答えても問題ありません。しかし、短所から色を答えることはNGです。なぜなら、短所から色を例えるとアピールができず逆効果になるためです。色を探す際は、短所ではなく長所や自分の強みから探すようにしましょう。
面接での質問に対する回答は、自分をアピールする場です。長所を色に例えて、自分を採用するメリットについて伝えましょう。
好きな色を答えるだけにならない
「自分を色に例えると?」という質問に、単に“好きな色”を答えてしまうのは避けたいポイントです。面接官が知りたいのは嗜好ではなく、色を通してあなたの性格や強み、価値観をどのように説明できるかという部分です。好きな色を挙げるだけでは、自己理解や言語化力を示せず、アピールにつながりません。「なぜその色なのか」「どんな行動・経験と結びつくのか」を具体的に語ることが大切で、そこにあなたらしさを表すことができるでしょう。
長所と色のイメージが一致しないのはNG
色に“絶対の正解”はないものの、自分の長所と色のイメージがかけ離れすぎている回答は説得力を失ってしまいます。たとえば「情熱があり行動力もあります。だから青です」と伝えてしまうと、一般的に青が持つ“冷静・誠実・落ち着き”といった印象と噛み合わず、面接官は「なぜ青?」と疑問を抱いてしまいます。色を選ぶ際は、まず自分の強みを整理し、その強みと色が自然に結びつくかどうかをチェックすることが大切です。イメージが一致していれば回答に一貫性が生まれ、説得力もぐっと高まります。
類似質問にも答えられるようにしておく
似たような質問が来る場合に備えておくことも大切です。
「自分を何かに例えると」という質問は意外とあります。今回は色をご紹介しましたが、動物や物などに例える質問をされることもあります。この際、回答が変わるだけで理由には一貫性を持たせるようにしましょう。
一貫性がないと、「自分の軸がない」とマイナスな印象を与える可能性があります。
「REALME」で自分の特性を知ろう!
「REALME」は、AI面接で自分の能力を定量化し、志望企業の内定判定が分かるサービスです。AI面接を通して、自分の能力を点数化しフィードバックしてくれるほか、志望企業の合格基準を超える就活生のデータや、AI面接での対話内容を閲覧できることが特徴です。
このほかにも、就職活動を効率的に行うためのサービスを豊富に用意しています。
詳しくは以下をご覧ください。
AI面接で強みと弱みを可視化
「REALME」では、AI面接を通して自分の能力を可視化し、模擬面接の的確なフィードバックを提供しています。自分の特性を客観的に把握でき、自分の強みや弱みを可視化することで、自分を何色に例えればよいのかが明確に分かるでしょう。
志望企業への内定判定を確認
「REALME」は、点数化した自分の能力を、志望企業の最終面接まで進んだ就活生のデータと比較し、その結果に基づいた内定判定結果を出してくれることが特徴です。結果から、合格基準と比較した自己分析の方法が可能です。現段階の自分に何が足りないのか、効果的なアピール方法を確認できます。
合格ラインのES・面接データの確認が可能
「REALME」では、志望企業の合格基準を超える就活生のAI面接データを、テキストで分かりやすく確認できます。また、自分と同じアピールポイントを話す就活生の自己PRや価値観も閲覧できるため、効率的な自己分析が可能です。
他の就活生が、自分をどのような色に例えているのか、特性をどのようにアピールするのかを客観的に確認できます。
自分と向き合って自分のカラーを見つけよう!
「自分を色に例えると」の質問は、就活生の人柄や特性を把握するためであることが分かりました。この質問では、「選んだ色」を重視するのではなく、「選んだ色の理由」を明確に伝えることが求められます。
「REALME」は、自分の強みや弱み、特性をテキストで分かりやすく確認できるため、自分が何色になるのかを倫理的に分析できるでしょう。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)