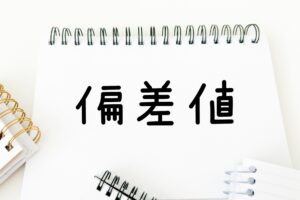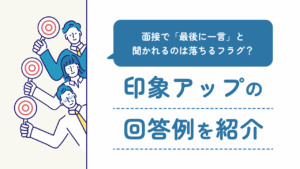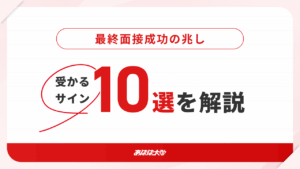就活においてアピールできる能力の1つが、適応能力です。
適応能力が高ければ、新しい職場や仕事内容に対してスムーズに馴染み、効率よく仕事ができます。
一方で、適応能力は数値や資格などの明確な基準が少なく、就活の際、どのように伝えればよいのかが分からないという人も多いでしょう。
今回の記事では、企業から適応能力を求められる背景や、適応能力の高め方、アピール方法などについて紹介します。
就活を控えている方はぜひ参考にして、相手に伝わる自己アピールを考えましょう。
適応能力とは?
適応能力とは、環境や状況に合わせて立ち位置や考え方、行動などを柔軟に変えられる能力です。
ただ立ち位置を変えるだけではなく、どのような行動をすればよいのか、自分の立ち位置が変わることによって周囲にどのような影響があるのかを適切に思考する能力も含まれます。
企業への入社時はもちろん、新しい技術の導入や部署移動などの、働くうえで避けられないさまざまな変化に対して柔軟に対応できることから、就活時には高く評価されます。
企画職やクリエイティブ職などの環境が変わりやすい職種を目指す人にとっては、特に評価されやすいアピールポイントです。
適応力が求められる背景
就活時に適応力が求められる理由は、以下の背景があるためです。
- VUCAの時代であるため
- 人材の流動性が高いため
- テクノロジーの進化が早いため
それぞれの背景について詳しく解説します。
VUCAの時代であるため
VUCAとは、「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の4つの頭文字を取った言葉です。これは環境が目まぐるしく変化していて、将来の予想が難しい状況のことです。
VUCAの時代になりつつある理由として、新型コロナウイルスの世界的な蔓延が挙げられます。新型コロナウイルスの感染拡大によって、これまでの常識が通用しなくなったり、将来が不透明になったりしました。
変化の激しい時代であるため、適応能力が求められます。
人材の流動性が高いため
人材の流動性が高いことも、適応力が求められる理由の一つです。
これまでの日本は、同じ会社に定年まで勤める人が多い傾向にありました。しかし最近では働き方が多様化しており、人材の流動性が高まっています。例えば、企業で経験を積んでからフリーランスに転身するケースが増加しています。
仕事上で短期間にさまざまな人と関わる機会が増えていることは、適応能力の高さが重視されている理由です。
テクノロジーの進化が速いため
テクノロジーの進化も、適応力が求められる背景に含まれます。
近年、AIやIT技術は日々目まぐるしく発達しています。テクノロジーの進化が速く、新しい技術やシステムに素早く慣れる能力が求められる社会になりました。
特に最近では、DXを進める企業が増えています。DX化が進めば、スムーズに仕事に慣れるための適応力が求められます。
「適応力」が特に好アピールになりやすい職種3選
適応力は多くの職種で好アピールになる強みです。中でも、とくに適応力が重視されやすい宿主を3つご紹介します。
営業職
営業職で成果を上げるためには、常に変化する顧客ニーズを的確に把握し、柔軟に対応する適応力が欠かせません。
たとえば、同じ商品を扱っていても、顧客ごとに求めるポイントや重視する価値観は異なります。そのため、相手の性格や状況に応じてアプローチ方法を変えられる人ほど、信頼を得やすくなります。
適応力が不足していると、顧客の変化に気づくのが遅れ、商談のチャンスを逃してしまうことも珍しくありません。営業現場では、目まぐるしく移り変わる市場や顧客の要望に素早く対応できる力が、結果に直結する重要な要素です。
クリエイティブ職
クリエイティブ職では、常に新しい技術やトレンドが登場し、柔軟な発想とともに高い適応能力が求められます。
たとえば、デザインや映像制作の現場では、クライアントの要望や市場の変化に迅速に対応しなければなりません。困難な課題や予期しないトラブルが発生した際も、適応力があれば状況を前向きに捉え、最適な解決策を見つけて乗り越えることができます。
適応能力の高い人は、変化を恐れず新しいスキルを積極的に習得し、常に最新のクリエイティブ表現を追求できるため、業界で長く活躍しやすいのが特徴です。
企画職
企画職では世の中のトレンドを素早くキャッチし、新しい企画を提案する力が求められます。適応力が高い人は、変化する市場や顧客のニーズに敏感に反応できるため、時代に合ったアイデアを生み出しやすいのが特徴です。
また、企画の現場では予期せぬトラブルが発生することも珍しくありませんが、適応力があれば冷静に状況を判断し、柔軟な発想で解決策を導き出せます。
そのため適応力は、企画を成功に導くために欠かせない要素と言えるでしょう。
適応能力が高い人の特徴
適応能力が高い人には、共通して以下の特徴があります。
- 好奇心が旺盛である
- どんな人にもコミュニケーションが取れる
- 楽観的で前向きである
- 全体を俯瞰で捉えられる
それぞれについて詳しく解説します。
特徴を把握して、適応能力が高い人材を見極めましょう。
好奇心が旺盛である
好奇心が旺盛な人は、適応能力が高い傾向にあります。なぜなら、好奇心が旺盛だと新しい価値観や知識を取り入れることに前向きなためです。
新しいことに前向きに取り組める人は、変化に対して抵抗がなく自然と高い適応能力を身につけています。加えて、自分と異なる考えや価値観を持つ人に対してもスムーズに受け入れられるため、さまざまな意見や価値観を吸収できるスキルがあります。
このように、好奇心が旺盛な人は変化や異なる価値観に抵抗がなく、前向きに捉えられるため適応能力が高いといえるでしょう。
どんな人ともコミュニケーションが取れる
コミュニケーション能力が高く、どのような人とでもスムーズにコミュニケーションが取れるという特徴もあります。
会社にはさまざまな性格や立場の人がいて、共に働く人との交流は欠かせません。しかし、なかにはコミュニケーションが苦手でなかなか職場に馴染めなかったり、苦手な人とはスムーズにコミュニケーションが取れなかったりする人もいます。
しかし、適応能力が高い人は性格に合わない面がある人、上司や先輩・後輩を問わず、スムーズにコミュニケーションが取れます。
楽観的で前向きである
楽観的で前向きな性格の人は、適応能力が高い傾向にあります。これは、楽観的で前向きな人はトラブルに慌てることなく対応できるためです。
仕事は必ずしも予定通りに進められるとは限らず、ときに思わぬトラブルに直面することや失敗することもあります。この際、適応能力が高い人は自分で判断してトラブル解決のためすぐ行動に移せます。
逆に、ネガティブで適応能力が低い人は、トラブルや失敗に悩むことやひどく落ち込む人がほとんどです。
全体を俯瞰で捉えられる
物事を俯瞰的に捉えられる人も適応能力が高いといえます。なぜなら、全体を俯瞰的に見られる人は今いる環境の変化や新しいことを把握でき、スムーズに取り組めるためです。
全体を俯瞰で捉えられる人は、目の前のことに一喜一憂しません。目的をぶれずに遂行できるため、新しいことや変化があってもスムーズに受け入れて、適応しようと努力します。
適応能力の高め方
性格や周りの環境で自然と適応能力が高い人はいます。しかし、以下の方法を実践すれば、適応能力が身についていない人でも高められます。
- 固定観念や先入観を持たないようにする
- 変化と多様性を受け入れる
- 失敗や新しい体験を恐れない
- 他者からの評価に耳を傾ける
それぞれについて詳しく解説します。
固定観念や先入観を持たないようにする
固定観念や先入観を持たないように意識しましょう。なぜなら、固定観念や先入観があると変化や新しいことを受け入れにくくなるためです。目の前で起こっていることのみで判断せず、裏側にある理由や経緯を知るようにすることで、適応能力が自然と向上します。
変化が生じたり新しいことが増えたりすると、「従来のやり方を変えたくない」と思うこともあるでしょう。しかし、変化に対応するためには固定観念や先入観を捨てることが大切です。
変化と多様性を受け入れる
環境や人間関係の変化は、時にストレスにつながります。しかし、それを受け入れる努力が大切です。
仕事は必ずしもずっと同じ環境や人間関係でいられるとは限りません。上司が変わって体制が変化したり、辞める人や新たに入社する人がいたりと、環境や人間関係の変化が起こることはあります。この際、変化をネガティブに捉えるのではなく、ポジティブに捉える努力をすることで、適応能力を高められます。
失敗や新しい体験を恐れない
失敗を恐れていると、新しいことにチャレンジできません。適応能力が低い人は、新しいことへの挑戦に対して「うまくできるか不安」「失敗したらどうしよう」と、マイナスに考える傾向にあります。しかし、意識的に「やったことがないなら、やってみよう」の精神を持つことで、適応能力を高められます。
挑戦に不安を感じても、積極的に新しいことにチャレンジしましょう。
他者からの評価に耳を傾ける
家族や友人からの評価に耳を傾けることも、適応能力を高める方法の一つです。なぜなら、他者からの評価に耳を傾けることで、周りの意見を柔軟に受け入れるスキルを身につけられるためです。
適応能力を高めるためには、自分の考えばかりに固執してはいけません。他の人からの意見に耳を傾けて、さまざまな角度からの考えを受け入れましょう。
場合によっては、「それは違う」と反論したくなることもあります。しかし、その場で反論すると今後意見をもらえなくなることもあるため、反論や言い訳をしたくても意見を受け入れる意識が大切です。
自己PRで「適応力」をアピールする時の基本構成
自己PRで「適応力」を明確に伝えるには、結論→理由・具体例→結論の流れを意識するとよいでしょう。
自己PRで「適応力」をアピールする際の基本的な構成について解説します。
【結論】適応力があると言い切る
まずは最初に「私には適応力があります」と結論から明確に伝えましょう。
冒頭で自信を持って言い切ることで、採用担当者に強みが何かを瞬時に理解してもらえます。逆に結論を後回しにしてしまうと、話に集中してもらいにくくなり、伝えたい部分がぼやけた印象になってしまうため注意が必要です。
まずは「適応力がある」と断言し、次の段階で理由や活かし方を展開していきましょう。
【理由と具体例】適応力がある理由を具体例で補足する
最初に適応力があることを断言してから、具体例を交えて理由を話します。たとえば、新しい環境で素早く成果を出した経験や、チームでの協力によって結果を出したエピソードなど、具体的な事例を交えて説明すると説得力が増します。
家族や先輩など第三者から評価された経験や、主体的に行動した実績があれば、客観的な裏付けとして加えるとより効果的です。
【再度の結論】適応力があることを再び伝える
自己PRの締めくくりでは、改めて「私は適応力に自信があります」と明確に伝えましょう。再び結論を伝えることで、強みが印象付けられ、面接官にも記憶に残りやすくなります。
さらに、入社後にどのように適応力を活かして企業に貢献できるかを伝えることで、採用担当者に実際の活躍イメージを想像してもらいやすくなります。たとえば、「変化の多い職場環境でも柔軟に対応し、状況に応じて最適な行動を選択することで、チームや組織の成果に貢献できます」と具体的な活かし方を述べるのも効果的です。
最後にもう一度、適応力があることを強調し、企業が求める人物像と自分の強みが合致していることを伝えることで、説得力のある自己PRとなります。
適応能力のアピール方法
就職活動では、筆記や口頭で自分の長所を伝える場面があります。
その際に、適応能力があることを伝えられると、職種によっては大きなアピールになるでしょう。
ここからは、適応能力のアピール方法を紹介します。
「グループにすぐ溶け込めた」というように具体例を交える
自己アピールのときは、単に「適応能力が高い」と告げるだけでは、どの程度高いかを伝えることが困難です。
適応能力をはじめとした自分の長所を伝えるときは、具体的な話を用いて伝えることが大切です。
具体的なエピソードを添えると、聞き手や読み手が能力について把握しやすくなります。
エピソード例
- 2年生から入ったサークルに素早く順応し、入って1か月で2年生のリーダーを任されるほどになった
- 小中高と転校が多かったため、どの学校でも早く馴染め、各地で親しい友人を作れた
「柔軟性」「臨機応変な対応」など魅力的に言い換える
状況やエピソードによっては、「適応能力」という言い方では、細かいニュアンスが伝わらないこともあります。
「柔軟性」「臨機応変さ」など、状況に応じて名称を変え、相手に自分の強みが伝わる自己アピールをすることがおすすめです。
能動的に対応する「適応能力」と受動的に対応する「順応力」の差についても理解しておくとよいでしょう。
言い換え例
- 技術やトレンドなどの変化が激しいIT業界でも、常に最新情報を吸収して仕事に活かしていきます
- 与えられた仕事や自分の立ち位置に応じて、臨機応変に対応できるよう努めます
適応能力のよいアピール例
- 過去のエピソードを交えてアピールする
- 企業で適応力をどのように活かしたいのかを伝える
適応能力をアピールするときは、適応能力を身につけたり発揮したりしたエピソードに加えて、将来企業でどのように役立てられるのかを交えて伝えることが有効です。
「部活で身につけたコミュニケーション能力を活かし、上司や同僚と連携を取り合って仕事を進めたい」「留学経験で得た広い視野とチャレンジ精神で、さまざまな仕事に挑戦したい」など、自分の適応能力を活用した会社への貢献方法をアピールするとよいでしょう。
適応能力のもっとよくなるアピール例
- 適応能力を身につけたきっかけのエピソードを伝える
- 自分の意志を持って適応できることを伝える
適応能力を身につけるきっかけになった具体的なエピソードがあるときは、分かりやすく簡潔に伝えることが大切です。
具体的なエピソードがあることで、就活のためのアピールではなく、その人の本来持つ長所であると認知されやすくなります。
「転校が多かったため、すぐに周囲に順応するスキルを体得した」「ゼミの活動で準備していた方法が失敗した際、計画の再調整や方法変更の提案で、柔軟な対応力が得られた」など、適応能力を身につけるきっかけになった出来事を伝えると、採用担当者の印象に残りやすくなります。
自己PRで「適応力」を伝える際の例文
自己PRで「適応力」を伝える際の例文を、3つのパターンにわけてご紹介します。
新しい環境に馴染みやすいことをアピールしたい場合
私の強みは、新しい環境へすぐに馴染める適応力です。
大学時代、交換留学で異なる文化や生活習慣の中に飛び込みましたが、積極的に現地の学生と交流し、短期間で多くの友人を作ることができました。この経験から、初対面の人とも臆せずコミュニケーションを取り、どんな環境でも早く順応できる自信があります。
入社後も、この適応力を活かして新しい職場やチームに素早く溶け込み、周囲と協力しながら成果を上げていきたいと考えています。
例文では、新しい環境でも積極的に行動し、短期間で人間関係を築いた経験を通じて、柔軟な適応力と前向きな姿勢があることを具体的に示しています。入社後も早期に職場へ溶け込める点が強みです。
コミュニケーション能力に自信があることをアピールしたい場合
私の強みは、相手の意見をしっかり受け止めつつ自分の考えも分かりやすく伝えられるコミュニケーション能力です。
大学のゼミ活動ではリーダーとして、意見が対立した際も全員の話を丁寧に聞き、納得できる解決策を提案することで、チーム全体が協力し合い、目標を達成することができました。
入社後も、相手の立場や状況に応じて柔軟にコミュニケーションを図り、職場やチームの円滑な連携や成果向上に貢献したいと考えています。
例文では、単に話す力だけでなく「聞く力」や「調整力」も強調されています。また、入社後の具体的な活かし方に触れることで、企業側に活躍する姿をイメージしてもらいやすくなっています。
状況把握能力をアピールしたい場合
私の強みは、状況把握能力です。
大学時代、サークルでイベント運営を担当した際、参加者の動きや会場の雰囲気を常に観察し、トラブルの兆候を早期に察知しました。スタッフ間で迅速に情報共有し、臨機応変に役割を調整することで、混乱を未然に防ぎ、イベントを円滑に進行できました。
入社後も、現場やチームの状況を的確に把握し、最適な対応策を提案することで、組織の成果に貢献したいと考えています。
例文では、単に状況を把握するだけでなく、観察力や情報共有、臨機応変な行動までを具体的に示しています。イベント運営という多様な人が関わる現場で、予兆を見逃さずにトラブルを未然に防いだ経験は、職場でも同様に冷静な判断力と柔軟な対応力を発揮できる根拠となります。
適応能力のアピールがうまくいかない例
適応能力の高さをアピールする際、うまくアピールできないことがあります。例えば、「自我がない」「流されやすい」と思われたり、一貫性が保てていなかったりすると、適応能力をアピールできません。
ここからは、適応能力のアピールがうまくいかないケースを具体的にご紹介します。
「自我がない」「流されやすい」と思われる
前述の通り、適応能力の高さは社会において必要なスキルの一つです。しかし、場合によっては「適応能力が高い=流されやすい」と捉えられることがあります。
エピソードを伝える際、「主体性がない」と判断される内容のエピソードはマイナスです。自主性を伴っていることが分かるように、エピソードを組み立てて話しましょう。
一貫性が保てていない
一貫性が保てていないと、志望度が低いと判断される可能性があります。特に、面接や書類に書いたエピソードと、「適応能力が高い」アピールが矛盾しないように一貫性を保つことが大切です。
例えば、過去の失敗談を聞かれてコミュニケーション能力が低いエピソードを話したり、環境に馴染めず苦労したことを話したりすると、適応能力が高いことのアピールと矛盾します。この場合は、過去の失敗談を聞かれた際に適応能力が高いこととの矛盾が生じないエピソードや言葉選びが大切です。
適応能力を活かせる職種・業界
- クリエイティブ系
- 営業
- 企画
- IT業界
- コンサルティング
適応能力はどのような職種でも役立ちますが、特に新しい技術に対応しなくてはならないIT業界や、流行に左右されやすいクリエイティブ職や企画職で重視されます。
求められる知識やスキルの移り変わりが速く、常に学ばなければならない職において、適応能力は特に重要です。
AI面接「REALME」で自己PRの型を見つけよう
就職活動においてアピールすべき自分の強みを分析したい方には、 「REALME」の利用がおすすめです。
REALMEなら、AIを用いて自分の能力を分析できます。
「適応能力が他の就活生と比べて高いか低いか」を、グラフや数値を用いて客観的に判別できます。
過去の学生データから「適応能力」を含む自己分析ができる
「適応能力」は、「REALME」の結果として提示される項目としては「柔軟性」「関係構築力」にあたります。
この2つの数値を見れば、自分の適応能力がどの程度であるかを、一目で判断可能です。
また、REALMEでは、これらの数値を、蓄積してきた過去の学生データと比較できるため、他の人と比較して自分がどこを強みとしているかを判断できます。
「柔軟性」「関係構築力」以外にもさまざまな能力を分析できるため、アピールできる自分の強みが明確になります。
AIで志望企業に受かるための最適なアピール方法が分かる
「REALME」では、AIによる模擬面接を受けられます。
AIとの面接内容から、適応能力を含む多様な能力の判定と、企業ごとに定められた採用要件に基づいた内定判定が算出されます。
それらを活用することで、面接での受け答えや自己PRの改善に有効です。
フィードバックを反映して、適応能力を含む自分の強みを具体的に伝えられる練習をしましょう。
行きたい志望企業の内定可能性を事前に判定できる
「REALME」では、人気の企業を中心とした200社前後のデータを活用して、志望企業や近い業界に対して、現時点における内定の可能性を判定できます。
たとえば、自身の適応能力(REALMEでいう「柔軟性」「関係構築力」)が、志望企業の求める水準に位置するかの判別が可能です。
自分のデータを見返すだけではなく、志望企業において最終面接まで進んだ他の学生の面接回答例や自己PRなども閲覧できます。
また、対応する企業は今後も増加する予定です。
適応能力のアピール・向上で就活力もUPさせよう
適応能力は、クリエイティブ職やIT業界などをはじめとする、全業界で重視される能力です。
コミュニケーション能力や行動力に直結し、他の能力と絡めながらアピールしやすい長所といえます。
一方で、伝え方を誤ると「流されやすい」「自分の意見がない」ととられることもあるため、アピール時のエピソードはよく考えて選ぶことが大切です。
自分の適応能力を判定したい人には、「REALME」の利用がおすすめです。
35項目で利用者の能力を判定し、アピールに適したスキルを可視化します。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)