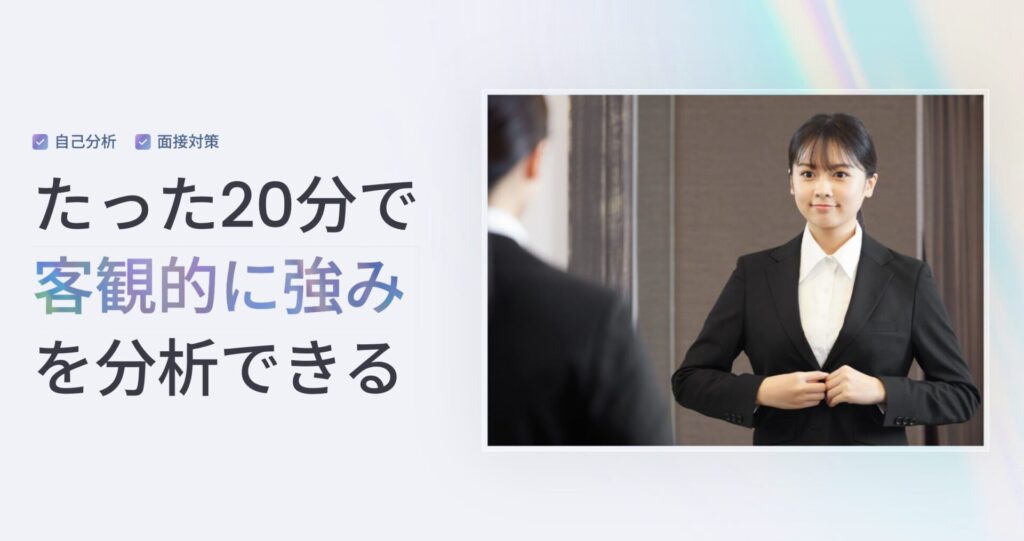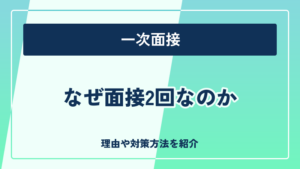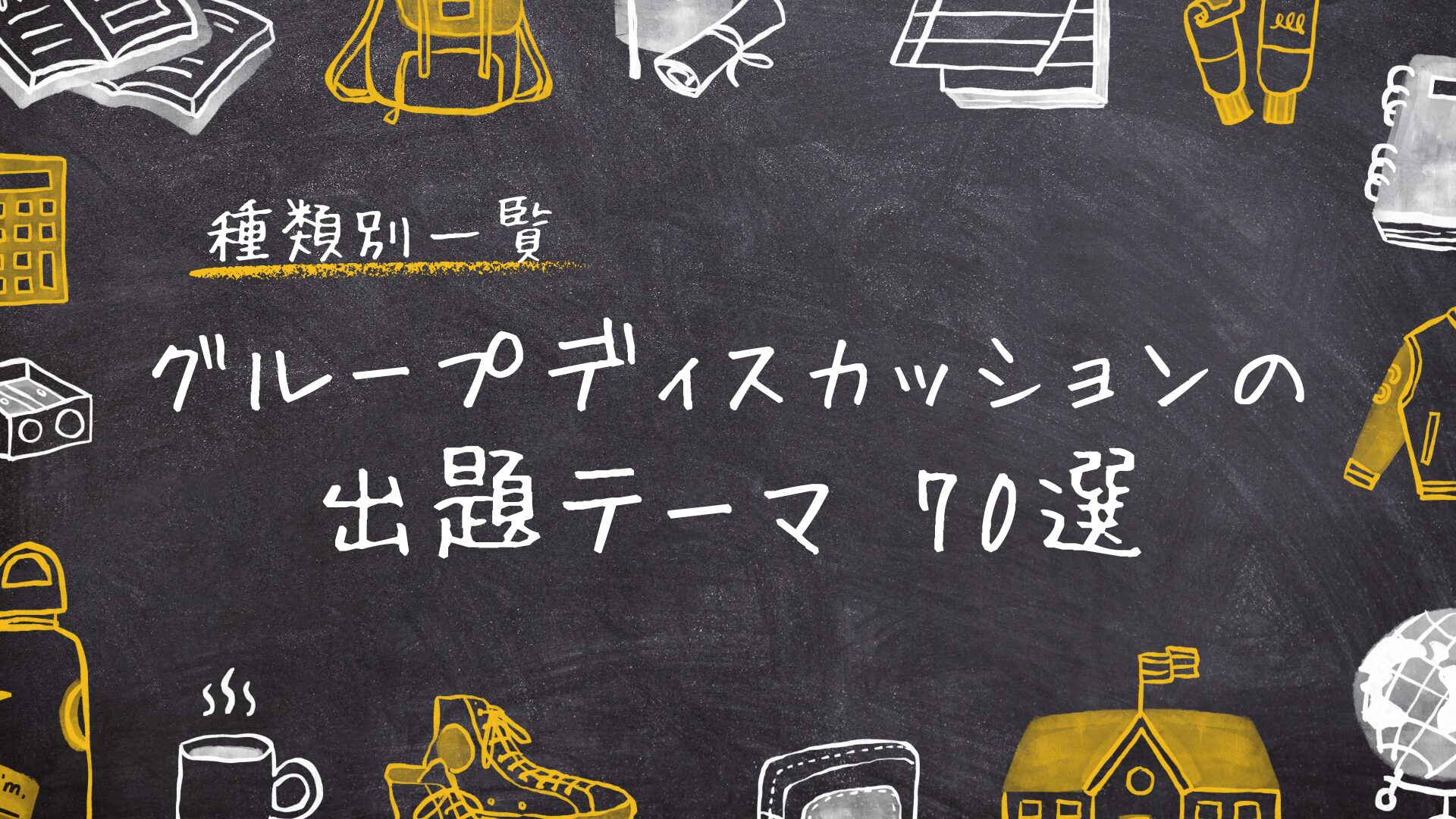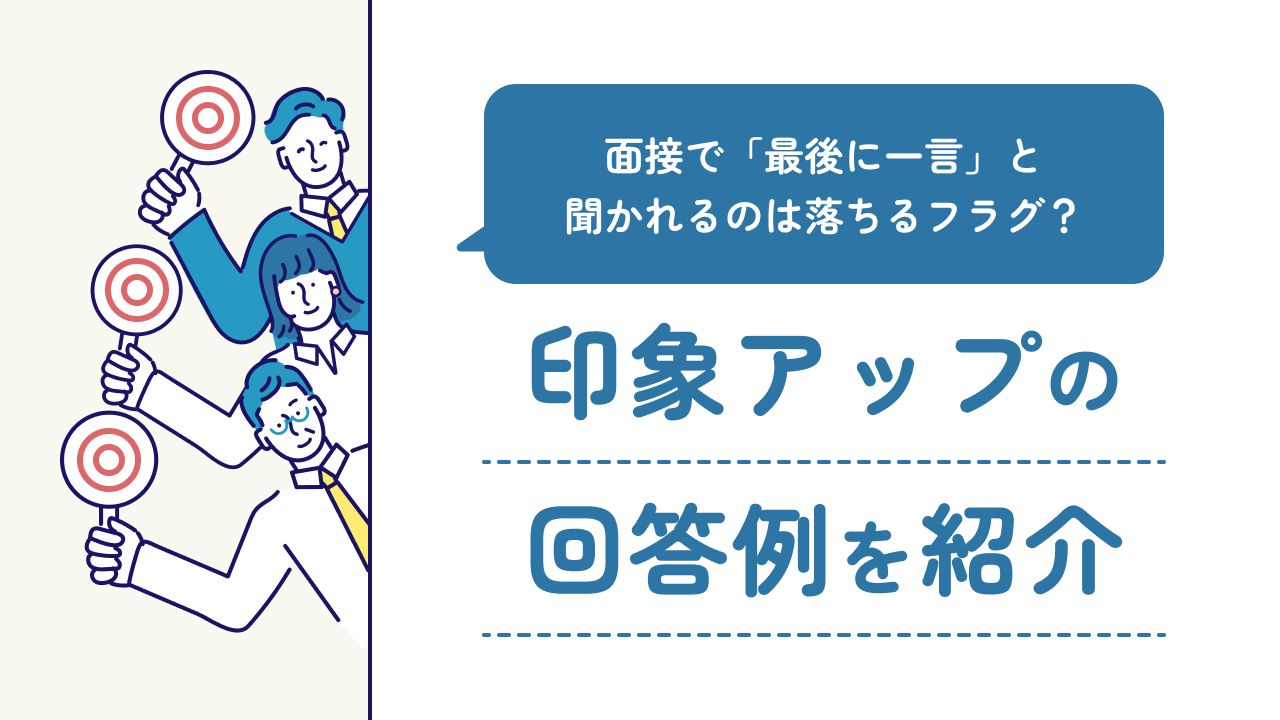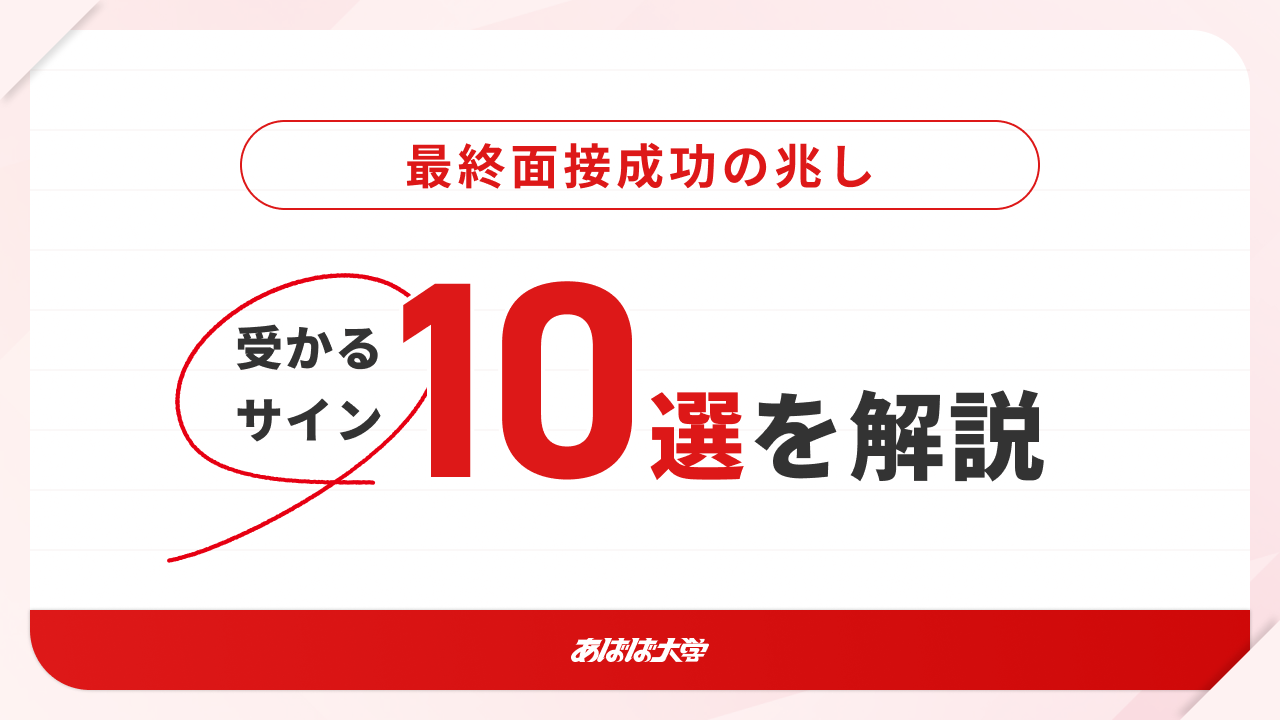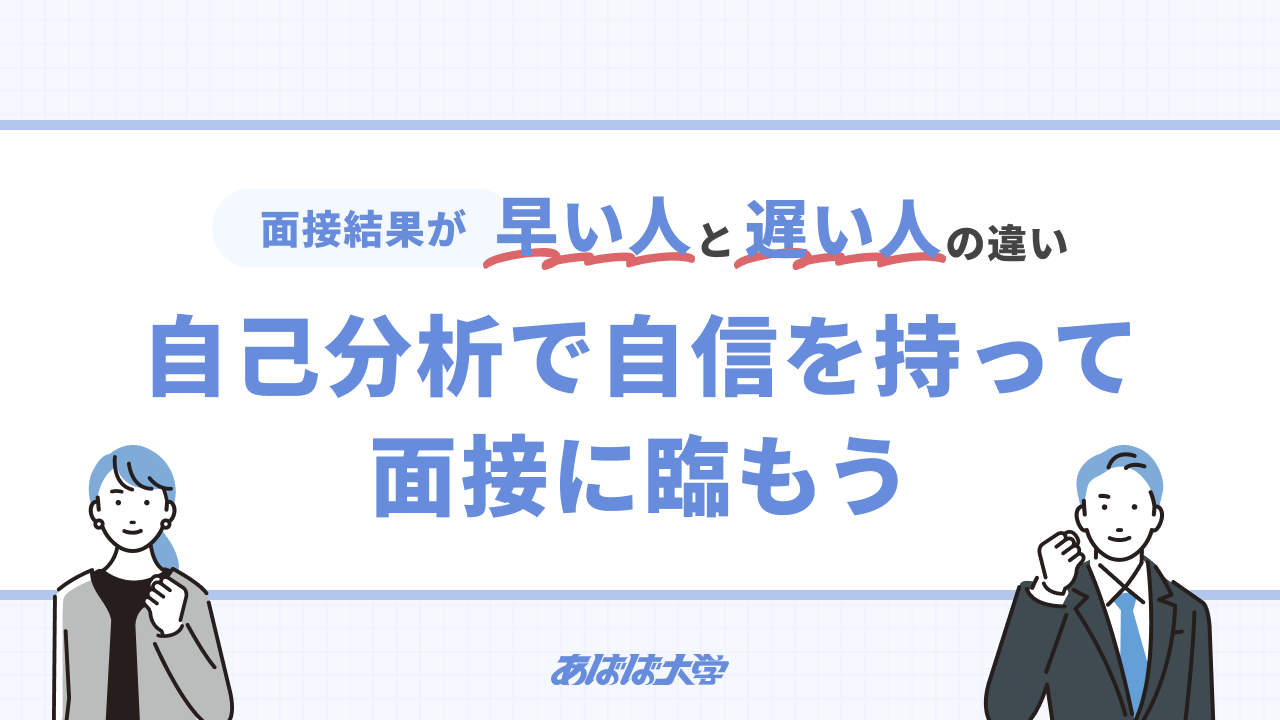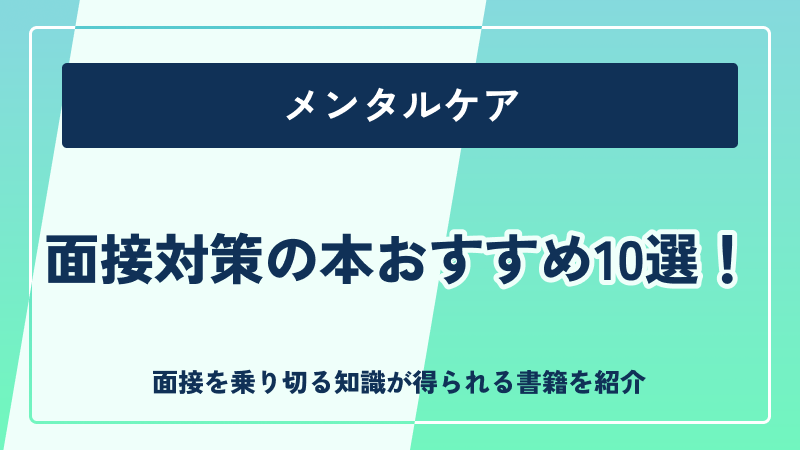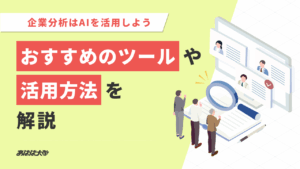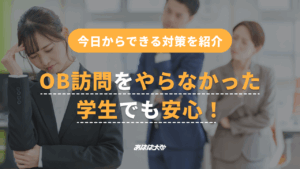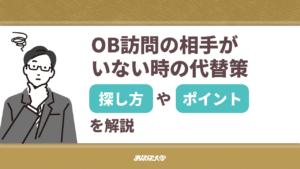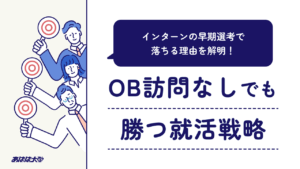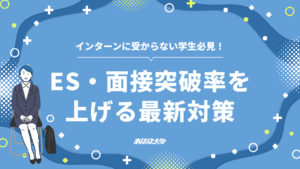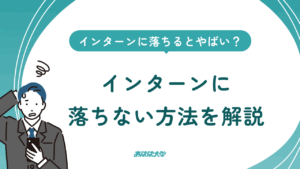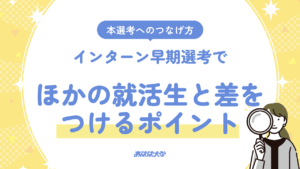一次面接と二次面接の違い
質問される項目

一次面接では、志望動機や自己PRなど基本的な質問が多いです。二次面接になると、エントリーシートや一次面接で答えた発言を、より具体的に深掘りする質問が増えていきます。
「入社後、どのような業務で貢献したいか」など、将来のキャリアプランに関わる質問が増える傾向にあるので、選考の進度に合わせた対策が必要です。
評価基準

一次面接では社会人として必要なマナーの有無、二次面接ではマッチング度や志望度を評価されやすい傾向にあります。
どちらもエントリーシートと異なる回答をしてしまうと、面接官に不信に思われてしまい、ミスマッチだと判断されてしまうかもしれないため注意。
面接官の年次や役職

選考が進むと、面接官の年次や役職も高くなっていくことが多いです。一次面接では若手社員が担当することが多いのに対して、二次面接では人事担当、場合によっては社長が面接官になるケースも想定されます。
一次面接を身につけたばかりの付け焼刃で乗り越えられたとしても、二次面接はそう上手くいきません。緊張に負けて自分の魅力を伝えられない可能性もあるので、落ち着いて対策を練るようにしましょう。
一次面接の特徴
選考人数が多く面接時間も短い

一次面接は、書類選考を通過した応募者一人ひとりと話す機会になります。応募者数が多いと通過する人数も増えるので、1回約15~30分と短い時間制限を設けていることが多いです。
面接通過の基準はそれぞれですが、一次面接で応募者を一気にふるいにかけて落とす会社も少なくありません。応募者の倍率で安易に「一次選考に通過するのは容易」と判断できるわけではないため、十分に対策をしてから臨むようにしましょう。
一次面接では重役社員が面接しないケースが多い

面接では進度に合わせ、高いポジションにいる社員と面接する機会が増えます。
一次面接は最も初めの採用進度のため、重役の方と話す機会は少なく良くも悪くも採用に直結する選考フェーズではありません。
過度な緊張をせず、面接官とコミュニケーションを取りながら自分の魅力や人柄、熱意をアピールしましょう。
エントリーシートに書かれた基本情報を確認する

一次面接では、志望動機や自己PRなど、書類選考で書いたエントリーシートに沿った基本的な質問が多い傾向にあります。矛盾が起きないように自分の魅力をアピールすることが大切です。
「この業界、会社で働きたいと思った具体的な話を聞かせてください」と、エントリーシートの内容を深掘りする質問を受けることもあります。志望度や基礎力を見られるので、一次面接前にはしっかり復習するようにしましょう。
一次面接の対策方法
前述の一次面接の特徴から、以下の対策が有効です。
・社会人としてのマナーを見直す
・ESを振り返る
・定番質問の回答を考える
・面接練習をする
それぞれの対策方法について詳しく解説します。
社会人としてのマナーを見直す
一次面接では、基本的なマナーができているかが選考で見られる要素の1つです。
例えば、髪が長い場合は後ろで1つ結びにしたり、ネクタイの色や締め方に誤りがないかを確認したりしましょう。
また、所作を見られることも多い傾向にあります。お辞儀の角度や入退室の際の挨拶など、基本的なマナーを意識することも大切です。
面接では、緊張して覚えた所作を忘れてしまうこともあります。どのような状況下でも自然とできるように、何度も練習しましょう。
ESを振り返る
自身のESを振り返って、内容を把握することも対策の一つです。なぜなら、一次面接はESの内容を元に質問されることが多いためです。
ESと一次面接の際の回答に矛盾があると、一貫性がないと判断されます。一貫性がないことはマイナスイメージにつながるため、落選の原因になりかねません。
ESの内容は頭に入れて、回答に差異がでないようにしましょう。
定番質問の回答を考える
一次面接は定番質問が基本です。志望理由を聞かれたり自己紹介、自己PRをするよう要求されたりします。最低限、定番の質問に対する回答は準備しましょう。
事前に想定できる質問に答えられないと、「最低限の準備もしていない」と採用担当にマイナスな印象を与えます。思わぬ質問をされた際は仕方がないものの、定番の質問にはスムーズに答えられるように準備しましょう。
回答を決めたら、忘れないように何度も練習をします。口に出して練習をして、緊張しても内容が飛ばないようにしましょう。
面接練習をする
周りの人に協力してもらい、面接練習をしましょう。
どれだけ準備をしても、いきなり面接に臨むと失敗するリスクが高まります。なぜなら、本番の面接には緊張感があるためです。
緊張すると、早口になったり頭に入れた内容を忘れたりします。話し方やスピードなどに注意して、面接練習をしましょう。
また、表情や所作にも気を付けて話します。特に、緊張すると表情が硬くなりやすいため、練習の際に表情を意識することは大切です。
二次面接の特徴
面接担当が年次や役職が高い人になる

一次面接と比べて、二次面接では人事担当などの年次や役職が高い人が面接担当になることが多いです。年次が上がると、即席で身につけた付け焼刃は通用しないので、一次面接よりも高評価を得づらい傾向にあります。
経験豊富な社員を前に緊張してしまい、本来の自分の実力を発揮できずに不合格になる可能性も高いです。一次面接を通過したからと油断せずに、しっかり準備をしてから臨むようにしてください。
踏み込んだ質問が多くなる

「入社後どのように貢献したいか」「10年後のキャリアプランを教えてください」など、二次面接では応募者に対して踏み込んだ質問が増えます。面接前にしっかり準備をしないと答えられない場合も多く、即興の発言では通用しないことがほとんどです。
すぐに答えられず黙ってしまうのはもちろん、発言によってはマイナスに捉えられてしまう可能性もあります。一緒に働く仲間としてふさわしいかを判断するので、相応の準備と心構えが必要です。
選考フローによっては最終面接になる

選考フローや速度感は、企業によって大きく異なります。三次、四次面接など段階が多い場合もあれば、二次面接が最終面接になることも多いです。早い企業では、二次面接で内定が決まることもあるので、十分に対策することが必要になります。
最終面接だと知らずに二次面接に挑んでしまい、準備不足やその場の緊張感、重圧に負けてしまうという方も多いです。自信を持って二次面接に臨むためにも、事前にしっかり対策を練るようにしましょう。
二次面接の対策方法
前述した二次面接の特徴をもとに、二次面接に効果のある対策方法は以下の通りです。
・一次面接を振り返る
・深掘り質問に備える
・自己分析と企業研究をする
・逆質問を考える
それぞれについてくわしく解説します。
一次面接を振り返る
一次面接が終わったら、すぐに一次面接の内容を振り返りましょう。なぜなら、二次面接でも一次面接と同様の質問をされる可能性があるためです。
同様の質問が出た場合、一次面接での回答と一貫性をもたせることが大切です。一貫性のない回答をすると、マイナスイメージにつながります。全体の軸がぶれないように気を付けます。
また、時間が経つと一次面接の内容を忘れてしまうため、一次面接を終えたら合否の結果が出ていなくても振り返りをしましょう。
深堀り質問に備える
深掘り質問に備えることも対策の一つです。なぜなら、二次面接は1つの質問を深掘りされることが多いためです。
二次面接まで進むと、企業は応募者が自社に合う人材かを見極めようとします。より候補者のことを理解するために、より踏み込んだ質問が増える傾向にあります。
志望動機を明確にして、深掘り質問をされた際にスムーズな回答できるように準備しましょう。
自己分析と企業研究をする
深堀り質問に答えるには、自己分析と企業分析が重要です。面接対策やES作成時に自己分析をしますが、二次面接に向けて改めて自己分析をしましょう。改めて自己分析をすることで、志望企業の明確化や深掘りされた際の回答が見つかります。自身のやりたいことやキャリアプランを明確にしましょう。
また、なぜこの企業に入社したいのかをアピールするためにも企業分析は必要です。企業分析が不十分だと、「自社やこの業界に興味がない」「内定を出しても辞退される可能性が高い」など、採用担当ににマイナスのイメージを持たれます。
逆質問を考える
二次面接以降は、逆質問を聞かれることが多い傾向にあります。そのため、逆質問も考えて備えます。逆質問を促された際に「特にありません」と回答することは避けましょう。
逆質問は、入社意欲をアピールするチャンスです。「業務のやりがいは何ですか」「このプロジェクトで特に力を入れている点はどこですか」など、企業分析をして的確な逆質問をします。
注意点として、ホームページや求人に記載されている内容を聞くことは厳禁です。逆質問をしても、企業研究ができていないと判断されたり、自分で調べて解決できるスキルが身についていないと思われたりします。
「REALME」ひとつで全ての面接対策ができる!

面接対策にはREALMEの活用がおすすめです。なぜなら、REALMEには以下の特徴があるためです。
・AI面接で志望企業の内定判定が確認できる
・AI分析で客観的な自己分析やES対策ができる
・合格ラインにいる学生データが閲覧できる
それぞれについてくわしく解説します。
AI面接で志望企業の内定判定が確認できる
REALME利用時には、20分程度のAI面接を受けます。面接結果と過去のデータを比較して、志望企業の内定判定が分かります。
志望企業の内定判定を知ることで、最適なエントリータイミングが分かることや、エントリー先を迷っている際に内定率の高い企業を選択できるなど、就活の効率化が可能です。
また、内定率向上のアドバイスが受けられる点もおすすめする理由です。
AI分析で客観的な自己分析やES対策ができる
面接後は、対話内容から14項目のフィードバックが受けられます。フィードバックされた内容を確認することで、客観的な自己分析が可能です。これによって自身の強みや弱みが分かり、ESや面接対策ができます。
改めて自己分析をして、自身のアピールポイントを明確化しましょう。
合格ラインにいる学生データが閲覧できる
自身のデータだけではなく、合格ラインにいる学生のESや面接回答を閲覧することも可能です。合格ラインの学生データと自身のデータを比較すれば、自分に足りていない点が分かります。
面接前に不足点を把握して補えば、内定率向上が期待できます。
一次面接と二次面接の違いを学んで対策しよう

一次面接と二次面接の違いや特徴、評価ポイントを紹介しました。選考が進むと特徴や評価ポイントも異なるので、本番前にしっかり対策することが大切です。本記事を参考にして、一次面接や二次面接の突破率を高めましょう。面接が終わったら、その日の振り返りも欠かさず行うようにしてください。