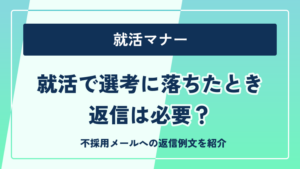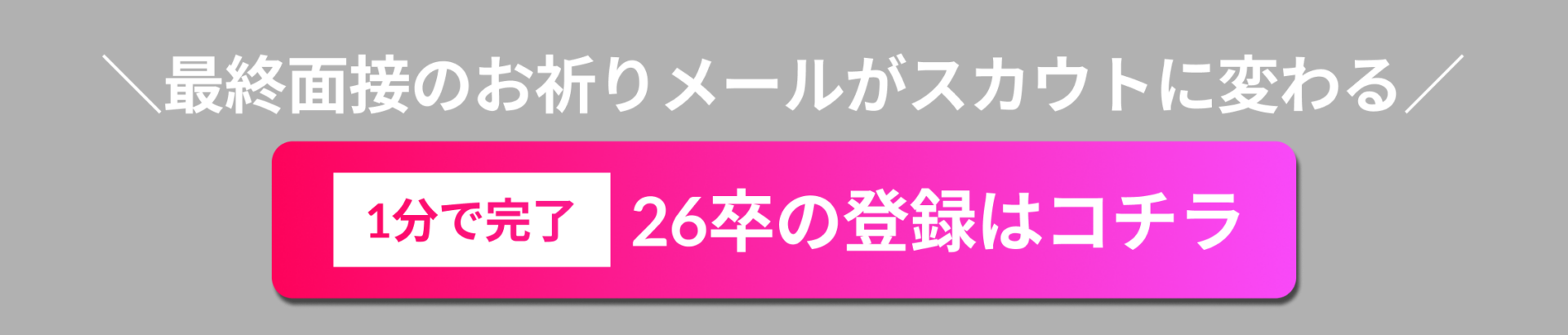高学歴であるほど就活を有利に進められますが、進め方を間違えてしまうと思うように内定がもらえないこともあります。本記事では、高学歴な就活生が押さえるべきポイントや、高学歴なのに就活に失敗してしまう理由を紹介。適切な対策ポイントを押さえて、就活を成功させましょう。
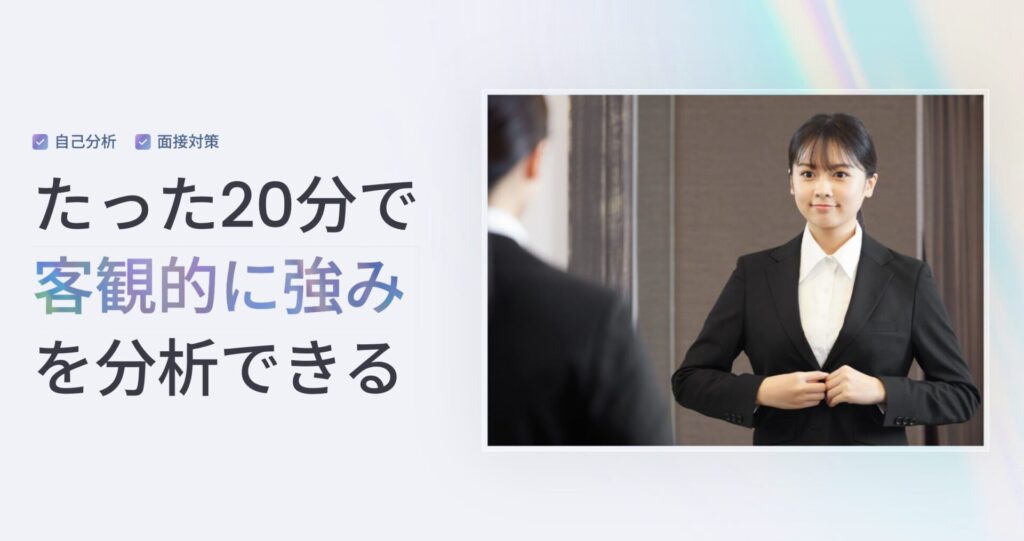
高学歴でも就活に成功するとは限らない?

日本国内で就活する場合、高学歴であることは就活での大きなアドバンテージとなります。しかし、高学歴であること自体が成功を保証してくれるわけではありません。
高学歴はあくまで就活を有利に進められる要素の1つにすぎず、個々人のスキルやコミュニケーション能力、対策状況などによっては苦労するケースもあります。
せっかくの高学歴を存分に活かすためにも、就活対策は早めにスタートしましょう。
高学歴なのに就活に失敗する理由

高学歴なのに就活に失敗する理由にどのようなものがあるか見てみましょう。
・情報収集が遅い
・理想が高い
・人気企業しか受けない
・コミュニケーション能力が足りない
・学歴を過信している
それぞれ解説していきます。
情報収集が遅い
表向きには「学歴不問」としている企業でも、高学歴なほどOBOG訪問をしてもらいやすかったり、選考時にプラスの要素として捉えてもらえたりするメリットがあります。
しかし、情報収集が遅ければ、このようなメリットを活かすのは難しいでしょう。また、情報不足により選考過程で十分な準備ができず、必要以上に自信が失われてしまう可能性もあります。
プライドや理想が高い
高学歴であるがゆえに、自分の学歴に見合った、あるいはそれ以上の条件を就職先に求めてしまうことがあります。プライドや理想が高すぎると、実際に市場が求める条件とのギャップに直面し、「就職活動に失敗した」と感じてしまうかもしれません。
人気企業しか受けない
人気企業や大手企業の場合、倍率が高くなり選考通過の難易度も高まります。応募者数が多くなればなるほど、万全の対策で臨んだ場合でも、内定を勝ち取ることは難しくなるでしょう。
倍率の高い人気企業ばかりにエントリーした結果、「1社からも内定がもらえなかった」という事態も珍しくありません。
コミュニケーション能力が足りない
企業は学歴だけでなく、チームワークやプロジェクト管理スキルなど、実務に必要なソフトスキルも評価します。その中でも基盤となるのがコミュニケーション能力です。
高学歴であってもコミュニケーションスキルが能力が不足していると、就職活動で不利になる可能性があります。
学歴を過信している
学歴の過信が、就活に失敗する原因となることもあります。
高学歴でも簡単に内定が出ることはありません。高学歴な人材も「自社に合わない」「採用してもメリットを感じない」「マナーができていない」などの理由で、選考に落ちる可能性はあります。
高学歴で就活に失敗する人は、「高学歴なら大丈夫」と過信して準備を怠っている傾向にあります。しかし、内定は学歴だけで決まるわけではないため、学歴に依存しすぎないことが大切です。
高学歴な就活生が押さえるべき就活のポイント

ここからは、高学歴な就活生が押さえるべき就活のポイントについて解説します。
・早期選考やインターンに応募する
・中小企業にも応募する
・積極的に情報収集をおこなう
・幅広い業種や企業に応募する
・油断せず選考対策をおこなう
・就活サービスを活用する
それぞれ見ていきましょう。
早期選考やインターンに応募する
早期選考やインターンには積極的に応募しましょう。優秀な就活生を早期採用するために、早期選考やインターンシップを開催している企業はたくさんあります。
高学歴の学生が早期選考の段階で自分の能力やスキルをアピールできれば、競争が激化する本選考に先駆けて内定獲得のチャンスが広がります。
中小企業にも応募する
大手や人気企業だけでなく、中小企業にも目を向けてみるとよいかもしれません。「せっかくいい大学に入れたのだから、有名企業に入社したい」という気持ちもわかりますが、大切なのは自分に合った企業に入社することです。
中小企業では社員1人ひとりの貢献が組織の成果に反映されやすく、若手の頃から責任あるポジションを経験できる可能性があります。また、フレキシブルな働き方に対応している企業も多く、人によっては大手企業よりも自分のスキルを生かせるかもしれません。
積極的に情報収集をおこなう
「就活は情報戦」といわれるほど、就活において情報収集は欠かせません。業界のトレンドや志望先の経営状況、社風、例年の選考過程など、早期段階から積極的に情報収集をおこないましょう。
幅広い業種や企業に応募する
自分の専攻分野に偏らず、さまざまな業種や企業を受けてみましょう。考え方を変えて選択肢を増やすことで、内定率の向上が可能です。
「自分はこの業種が合っている」「この学科を専攻したからこの仕事が向いている」と判断して、一部の業者や企業に偏って応募すると、就活に失敗するリスクがあります。
幅広い業種や企業に応募することで、自分に合う業種や企業が新たに見つかる可能性もあります。
油断せず選考対策をおこなう
企業の選考では学歴が重視されることもあるものの、最も大切なことは人柄です。自己PRを適切にすることで、内定率が上がります。
「高学歴なら大丈夫」と過信せず、面接対策や自己分析、企業研究などの基本的な選考対策を十分にしましょう。また、学歴以外の強みを考えることで、より面接官に自身の魅力や採用するメリットをアピールできます。
就活に油断は禁物です。第一志望の企業でなくても、しっかりと選考対策をしましょう。
就活サービスを活用する
学歴に関係なく、初めての就活に不安や悩みはつきものです。1人で抱え込まずに、就活サービスを活用して効率的に進めましょう。
大学のキャリアセンターだけでなく就職エージェントやスカウトサービスなど、さまざまな相談先があります。就職に関する相談はもちろんのこと、ESの添削や面接対策などもおこなってくれるので、2〜3社程度登録しておくとよいでしょう。
REALMEで自分に合った企業を探そう

高学歴でも就活に失敗しないためには、十分な選考対策が必須です。面接対策の一つとして、REALMEの利用がおすすめです。
ここからは、REALMEをおすすめする理由について解説します。
AI面接で客観的な自己分析ができる
REALMEを利用する際は、20〜30分程度のAI面接を受けます。AI面接の対話内容によって、14の項目がフィードバックされ、客観的な自己分析が可能です。
客観的に自己分析をすることで、自身の強みや弱みが分かります。場合によっては、自分で気づかなかった自身の強みや弱みが分かることもあります。
志望企業の内定判定が分かる
志望企業の内定判定が分かる機能もあります。
これは、AI面接の結果と合格ラインの学生データを比較して、志望企業の内定率を数値化したものです。現在の志望企業の内定判定が分かるため、最適なエントリータイミングを判断できます。
また、複数社の応募で迷っている際、内定率を参考に優先順位を決められて、効率よく就活を進めたい際におすすめの機能です。
内定判定を参考に、効率よく内定を勝ち取りましょう。
合格ラインにいる学生データが閲覧できる
自身のデータだけではなく、合格ラインの学生データや面接回答を閲覧できる機能もあります。合格ラインの学生データと自社のデータを比較することで、自身の足りない部分を補えます。
不足箇所を改めて見直して、内定率の向上を図りましょう。
高学歴の就活でよくある質問
高学歴でも就活に必ず成功するとは限りません。そこで最後に、高学歴の就活でよくある質問に回答します。
疑問や不安を解消して、志望企業の内定を勝ち取りましょう。
高学歴だと就職に有利?
学歴を重視する企業があるため、高学歴が有利に働くこともあります。しかし、高学歴なことだけを判断基準に内定は出ません。なぜなら、学歴が高いことと仕事のできることがイコールとは限らないためです。
大企業や人気企業は高学歴の人材が多く在籍しています。しかし、就活においては多くの就活生のなかで、学歴だけに頼らずどのように自分をアピールするのかが大切です。
高学歴で中小企業に行くとどうなる?
高学歴の人は大手企業に就職しなければならないことはありません。また、高学歴の人が中小企業に行くことは就活に失敗したとはいえません。中小企業に行くことにもメリットがあるためです。
例えば、成長途上の企業で実力を発揮できたり、昇進や昇給のチャンスが大きかったりします。安定した大手企業に比べて、中小企業の方が大きく成長するチャンスがあるともいえます。
高学歴でも就活に失敗する人の特徴は?
高学歴でも就活に失敗する人には、学歴に慢心して準備を怠るという特徴があります。
あくまで学歴は数ある評価基準のひとつです。高学歴であれば無条件に採用されるわけではなく、人柄やその企業に合うかも重要です。
「高学歴なら就活は楽勝」と過信せず、徹底した面接対策やESの作成が求められます。学歴はあくまで一つの武器であり、他にも自分をアピールできる武器を作りましょう。
高学歴を活かして就活を有利に進めよう!

高学歴の就活について解説しました。学歴が採用に直結するわけではないですが、高学歴であることが就活のアドバンテージとなることは間違いありません。ぜひ本記事で紹介したポイントを押さえて、就活を成功させましょう。