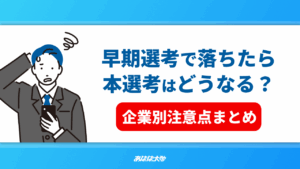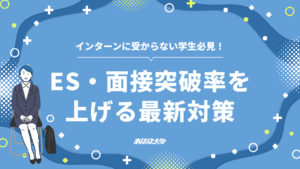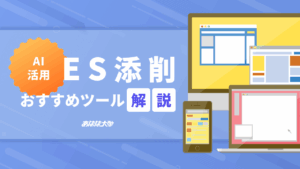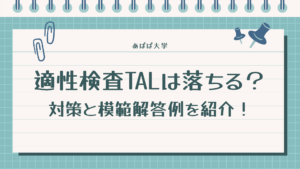就職活動で提出を求められるエントリーシート(ES)は、面接前に自分自身の適性や熱意を伝えるために重要です。
就職活動を始めるまで自分自身の長所や短所などについて深掘りしたことがなく、どのように書けばよいのか分からないと人もいるでしょう。
今回は、ESを書くときに手が止まってしまう要因や、書けないときの対策について紹介します。
記事の後半では、ES作成に役立つ就活支援ツール「REALME」についても紹介します。
ESが書けない理由
ESを書くときに何を書けばよいのかが分からなくなる理由は、いくつかの傾向に分けられます。
ここでは、ESの作成に苦戦する人の多くが抱える課題や問題点について解説します。
自分に当てはまるものがないかを確認しましょう。
志望動機がない
ESでは、志望動機を文章化しなければなりません。
入社意欲が低かったり、希望する業界・職種であればどの企業でもよいという気持ちで就活に臨んでいたりすると、志望動機の作成で手が止まりやすいといえます。
志望動機では、その企業を選んだ経緯や入社後にやりたいことなどが評価点になるため、志望企業について事前に詳しく調べることがおすすめです。
応募先の企業を決めるときは、周りの意見や評価などに流されず、自分に合う企業を探すことが、説得力のある志望動機を書くポイントです。
アピールポイントが分からない
ES作成の準備段階にあたる自己分析では、通常あまり意識しない、自分自身の内面に目を向けなくてはなりません。
一方で、いざ自己分析をしようとしても、自分のアピールポイントが分からず悩む人も多いでしょう。
就職活動におけるアピールポイントは、ほかの応募者と被らないような特別な能力を求められているわけではありません。
自身の過去の経験や人柄を振り返り、深掘りできる長所やスキルを選ぶようにしましょう。
書き方が分からない
自己分析までは問題なくできても文章力に自信がなかったり、正しい書き方が分からないケースもあります。
書いているうちにどのような内容が評価されるのかが分からなくなる場合もあるでしょう。
ESの文章構成で迷ったときは、できる限り論理的で簡潔に書くことがおすすめです。
不要な説明を長々と書くと読みにくくなり、簡潔に結論を述べている人と比べて内容が伝わりにくく低評価をつけられる可能性があります。
書く時間がない
ある程度の長さの文章を書くことに対して心理的なハードルがあったり、他の就活準備に追われ、ES作成に割く時間がないと考える人もいます。
就活の時期は忙しくなるため、まとまった時間が必要なES作成を後回しにする人は多いでしょう。
就活中は時間の管理がとても重要になり、何を優先してやるべきか、スケジュールを逆算して組むことが大切です。自己PRやガクチカなどはある程度内容を決めておき、志望動機は企業別に考えるなどの工夫で、ES作成の時間を作りましょう。
ESが書けないときの対策
ESの作成で行き詰ってしまう場合は、自身のやりたい仕事や業種が定まっていない傾向にあります。
ここでは、ESがうまく書けないときに行うべき対策を2つ紹介します。
ES作成が苦手だと感じる人は参考にしましょう。
自己分析をする
ES作成で手が止まってしまう原因は、自己分析の不十分が挙げられます。
ES作成に乗り出す前に自己分析を徹底し、ESでアピールするべき自身の強みや長所を明確にしましょう。
それらのエピソードを言語化し、文章化することも重要です。
自己分析の方法としては、自分史づくりやモチベーショングラフなど、さまざまなものがあります。
独力での自己分析が難しい場合は、家族や友人に協力を仰ぎ、第三者からの意見を聞くことも効果的です。
企業研究をする
ESでほぼ必ず求められる志望動機については、企業研究が十分かどうかが重要です。
業種や職種だけではなく、企業理念や事業内容、社風などを調べてから志望動機を書くとよいでしょう。
企業研究ができていると、入社意欲をアピールできるほか、自分と企業のマッチ度も高まります。
十分な企業研究は応募先へのアピールのためだけではなく、応募者自身が本当にその企業で働きたいのかを判断する材料にもなるでしょう。
ESが書けないときに意識すること
ESが書けない、書いたものの納得がいかない場合は、採用担当者がESを評価するときにどのような点を見るのかを意識することが重要です。
ここでは、ESをうまく書けないときに意識したい点を3つ紹介します。
空欄を作らない
ESの文章を作成するとき、簡潔に主題を伝えようとするあまり文字数が少なくなることもあるでしょう。
記入欄に対してあまりにも空欄が目立つ場合、志望意欲が低いとみなされる可能性があります。
ESで文章を記入するときは、文字数の指示がない場合でも、記入欄に対して8割以上を埋めることが理想です。
一方で、話題が横にそれたり、不必要な言葉を入れたりするとマイナス評価の対象になります。
だらだらと文字数稼ぎをすることは避け、説得力のある文章を心掛けましょう。
完成した後読み直す
ESが完成したものの納得いかない場合は、書いた文章を自分で読み直したり、家族や友人に読んでもらうとよいでしょう。
完成した文章に一通り目を通すことで、採用担当者が読みやすいように書けているかが客観的に分かります。
また、誤字脱字のチェックや、言葉遣いなどの細かい点についても、書きながら修正するよりも完成してから見直した方が気づきやすくなるでしょう。
目で見て分かりにくいときは、声に出して読むことが効果的です。
PREP法を意識する
ESで必要とされる内容をきちんと書けていても、文章の構成に問題があるとマイナス評価になる可能性があります。
読みやすい文章の構成がよく分からない場合は、PREP法がおすすめです。
PREP法とは、Point(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(まとめの結論)の順に文章を構成する方法で、最初に結論が出てくることで主題が分かりやすくなります。
読み返したときに、何を伝えたいのかが簡潔に分かりやすい文章を意識しましょう。
AI面接「REALME」で面接対策を始めよう
ESの作成や準備段階の自己分析で悩むときは、就職活動に役立つツール「REALME」の活用がおすすめです。
「REALME」ではAIとの模擬面接ができ、面接結果から就職活動に役立つフィードバックを受けられます。
志望企業の内定判定を一覧で確認できる
「REALME」ではAIとの面接結果を過去の合格者データと比較することで、現時点での志望企業の内定判定・合格確率を閲覧できます。
これによって、早めにESを提出するべきなのか、エントリーを遅らせて二次募集まで準備をした方がよいのかを判定できます。
エントリーするかどうかを迷っている企業への判断材料にもなるでしょう。
合格ラインを超えた学生のESが見られる
「REALME」では自分の内定判定のほか、過去に志望企業の合格ラインを超えた学生のESや面接回答を閲覧できます。
ESを作成したものの自信がない、何かが足りないと感じるときは、過去に合格した学生のESを参考にすることで、高評価につながる文章が書けるでしょう。
自分のESと合格者のESを見比べて、何が足りないか、どのような差があるのかを分析しながら書くことがおすすめです。
AI面接後のFBで面接力を強化できる
「REALME」ではAIと面接練習するだけではなく、面接結果をもとに内定につながるフィードバックをもらえます。
AIが分析した項目から、内定に不足している部分が明確に分かり、自分では気づきにくい話し方やマナーも改善できます。
また、自身の強みや弱みも客観的に分かり、ESで書けるアピールポイントが明確になるでしょう。強みに合った企業や業種も確認でき、企業とのミスマッチも防げます。
ESが書けない理由を把握して適切な準備をしよう
ESは、就職活動において企業にアプローチする第一段階だといえます。
ESを作成するときは事前に自己分析や企業研究をし、何をアピールするべきなのか把握してから書きましょう。
文章の構成や誤字脱字のチェックなど、採用担当者が読みやすい文章を心掛けることも重要です。
自己分析には、AI面接で自身のアピールポイントが分かる「REALME」の利用をおすすめします。

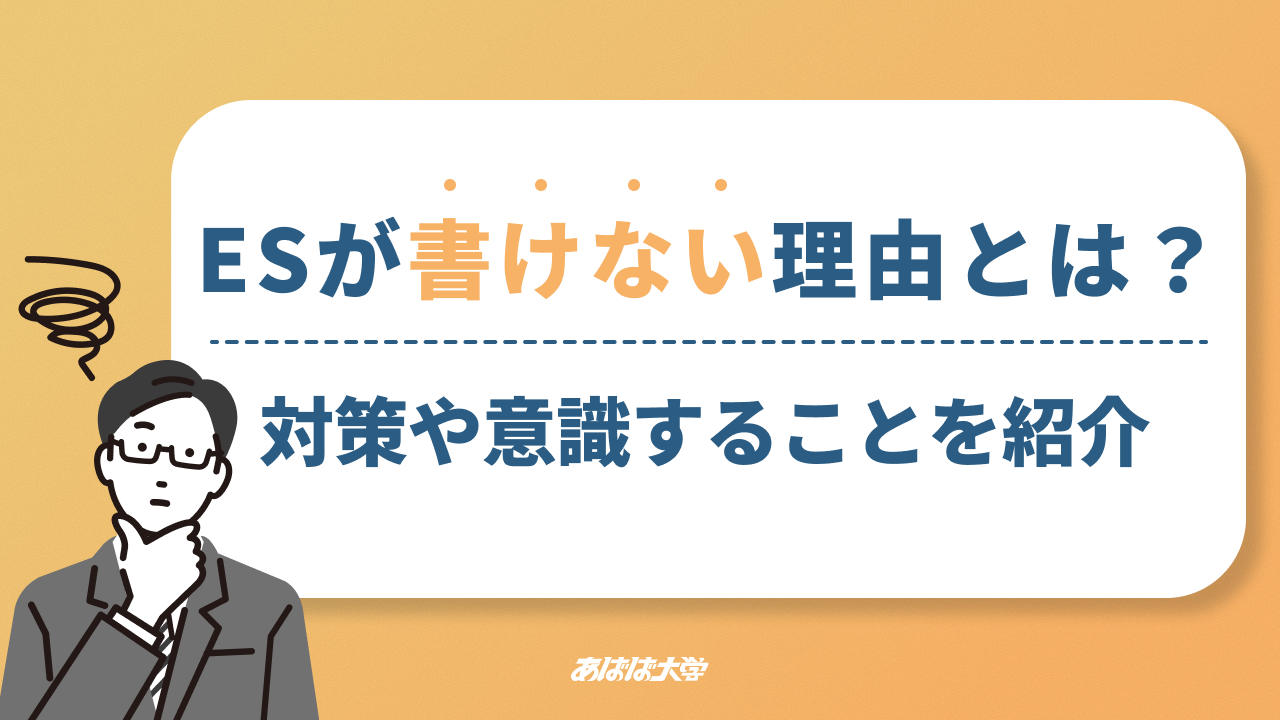
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)