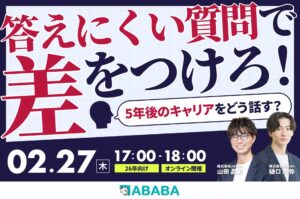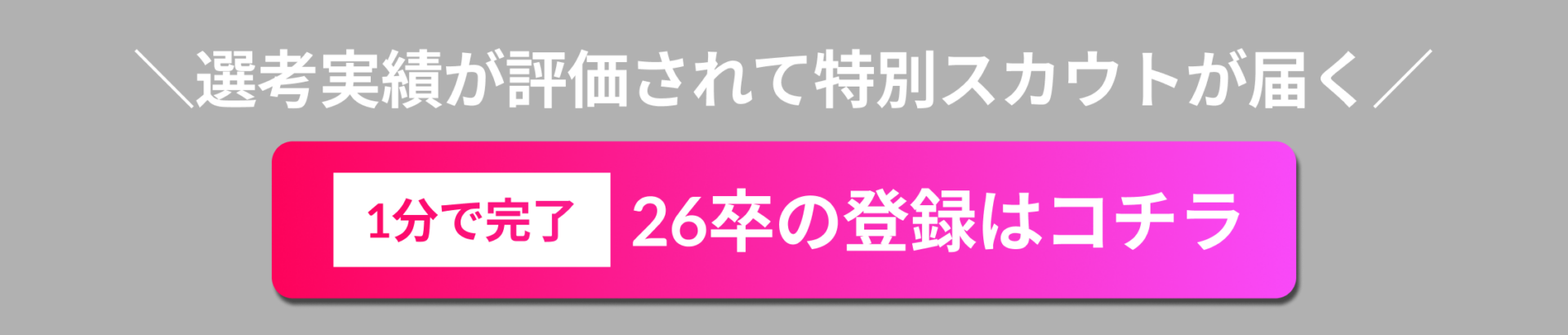「書類選考は通るけれど面接で何度も落ちてしまう」「どう頑張ったら面接に受かるんだろう」そのように悩む方も多いのではないでしょうか。面接を受けて落ちるというのは、精神的にも消耗するものです。
この記事では、面接に受からない理由を解説し、失敗ポイントと改善方法をご紹介します。
記事の最後には就活を支援するサービス「REALME」について解説します。興味のある方は、詳細をご覧ください。
面接に受からない理由と失敗ポイントを解説
面接に受からないと悩んでいる場合には、何らかの理由があります。
ここでは「会話に課題がある」「熱意が伝わらない」「自己分析が不十分」といった、6つの理由と失敗ポイントについて解説します。自分に当てはまるものがないか確認しましょう。
会話に課題がある
まず、面接の場でコミュニケーションがうまく取れていないことが考えられます。
日頃、会話に課題があると感じたことがない人でも、面接という重要な場面では、会話がきちんとできていないのかもしれません。背筋を伸ばし、面接官の目を見て話すようにしているか振り返ってみてください。
面接というのは、一方的に質問されてそれに答えるものではなく、話をよく聞いて相槌を打ったり学生からも尋ねたりする会話のキャッチボールです。
たとえば、面接官が話のはじめに「最近暑い日が続きますね」と天気の話をした場合「はい」とだけ答えるのではなく、自分からも少し話を続けましょう。「ここへ来るまでに、たくさん汗をかいてしまいました」とにこやかに返せば、面接での印象がよくなるだけでなく自分の緊張もほぐれます。
熱意が伝わらない
自分の熱意が伝わっていないことも、面接に受からない理由として考えられます。
質問に対して用意してきた回答を話そうと意識しすぎると、会話が単調になって企業に対する熱意が伝わらなくなる場合があるのです。どうしてもこの会社に入りたいという気持ちを面接官に伝えるよう意識してください。
また、話のアピールポイントが分かりにくい場合も、気持ちが伝わらなくなります。言いたいことが何かを意識して、そこから話すように意識しましょう。
自己分析が不十分である
自己分析が十分にできていない場合も、よい評価を受けられません。自分の強みをしっかり把握して、面接で伝えられているでしょうか。自分のアピールポイントだと思っていた長所が、実際の自分とずれていないかチェックしてみてください。
面接に受からないことが続くと自己評価が低くなってしまう場合がありますが、次の面接に向けて気持ちを切り替えることが必要です。改めて深く自己分析をして、自分の強みやアピールポイントを見直しましょう。
企業分析ができていない
企業が求める人物像を理解できていないケースも、面接での評価が低くなってしまいます。
高いスキルや経験を持っている人でも、企業のニーズとマッチしていないと残念ながら採用されません。
特定の技術や資格を必要としない職種の場合は、学生の人柄が社風に合っているかどうかが重視されることがあります。改めて企業分析を行い、企業の理想とする人物像を把握しましょう。自分にいくつかの強みがある場合は、企業のニーズに合わせてアピールポイントを設定してください。
ビジネスマナーに欠ける部分がある
初歩的なことですが、マナーができていない場合も、面接での印象が悪くなってしまいます。第一印象は面接において重要です。自分の身だしなみを改めてチェックしましょう。
・髪型やメイクは整っているか
・服装に清潔感はあるか
・洋服にしわや汚れ、ほつれたところはないか
・靴はきれいにしているか
また、お辞儀や挨拶のタイミングなども第一印象に大きく響きます。基本的なビジネスマナーを確認しておきましょう。
面接の経験が少ない
面接の経験が少ないと、面接本番で緊張してしまい、実力が発揮できない場合があります。面接という重要な場面に身を置けば、緊張するのは無理もありません。面接官の前に出た瞬間に、体が思うように動かなくなってしまう人もいるでしょう。
最も効果的な対処方法は面接の場数を踏むことですが、第1志望の企業の面接が就活のはじめのほうにくることもあります。このような場合は、後述するように、さまざまな手段で面接の練習をするのがおすすめです。
面接を突破するための改善ポイント
面接に受からない要因を解説しましたが、それを踏まえて、面接を突破するための改善ポイントをご紹介します。1つずつ実践していくことが、面接突破につながるでしょう。ぜひお試しください。
最初に結論を述べる
面接で話す際、最初に結論を述べる「結論ファースト」を意識しましょう。これだけで話がぐっと伝わりやすくなります。話の途中でうっかり話題がそれてしまったとしても、最も言いたい結論だけは伝わります。
さらに、話全体の構成にも気を配りましょう。理想的な話の流れは以下のとおりです。
①結論
②理由やエピソード
③結論と入社後の展望
冒頭で結論を伝えたあとに、その理由や裏付けとなるエピソードを話します。そして最後に結論を再度提示して強調し、入社後にそれをどのように活かして働きたいかという目標を述べてしめくくります。志望企業への熱意が伝わりやすくなるでしょう。
コミュニケーションスキルを養う
面接に向けて、コミュニケーションスキルを養いましょう。一朝一夕で養われるものではないように思えますが、すぐにできることはあります。
まずは笑顔で話しましょう。笑顔でいれば自然と声も明るくなり、話し方に自信が感じられるようになります。
また、背筋を伸ばして堂々と話しましょう。それだけで話の説得力が増します。
なかには、無意識のうちに背中を丸めてしまう人や、顔がうつむき加減になってしまう人がいます。気づかないといつまでもなおらないため、改めて確認しましょう。
さらに、身振り手振りにも気をつけてください。手を膝の上に置いたまま固まっていると、硬い印象になってしまいます。ある程度手振りをつけて、自分の思いをアピールしましょう。
質問の意図を理解する
質問の意図を理解することも重要です。聞かれたこととは違う回答をすると「質問が分かっていない」「話を聞いていない」といった印象を与えてしまいます。聞かれたことに的確に答えられるようにしましょう。
焦ってすぐに答える必要はありません。頭のなかで質問の意味を整理してから話し始めるようにしてください。少し考え、一呼吸おいてから話せば、考えがまとまりやすくなるだけでなく、信頼できる雰囲気が生まれます。
質問の意味が分かりにくかった場合は、遠慮せず「質問は○○○という意味でよろしいでしょうか?」と面接官に尋ねましょう。分からないことをはっきり尋ねることが、好印象につながります。
おすすめの面接対策
ご紹介した改善ポイントを実践するための、おすすめの面接対策は次のとおりです。ぜひお試しください。
・家族や友人に面接官役をしてもらい、面接の練習をする。
身近な人が面接官なら、リラックスして受け答えの練習ができます。よくある質問だけでなく、疑問に思う点について深掘りの質問もしてもらいましょう。終わったら率直な感想を聞いて、よい点や改善点を把握してください。
・面接練習の様子を動画に撮る。
撮影した動画を自分で見ることで、たくさんの気づきがあるでしょう。自分が話している姿を見るのは、はじめのうち抵抗を感じるかもしれません。しかし、客観的に見ているうちに、新たな改善点が見つかります。ぜひ実践してみてください。
・AIを使って面接をする。
面接の相手がAIなら、人間相手よりもリラックスして面接練習ができるでしょう。さらにAIは面接の内容を分析してフィードバックをくれます。これを参考に、面接のスキルを向上させられるでしょう。
AI面接については、このあと詳しく解説します。
面接対策をするなら「REALME」
面接対策としてAI面接を受けるなら、就活支援サービス「REALME」がおすすめです。20~30分程度、AI面接を受けることで、さまざまなメリットがあります。
ここからは「REALME」をおすすめする理由について解説しましょう。
合格者のES閲覧ができる
「REALME」を活用すれば、志望企業の合格ラインをクリアした学生の、過去のESやAI面接データが閲覧できます。
優秀な就活生が就活でどのように自分をアピールしていたか確認できるのは、大きなメリットです。自分のデータと比較して足りない部分を把握し、受け答えを改善していけば、面接のスキルが向上するでしょう
AIとの対話練習ができる
「REALME」を活用すれば、20~30分程度のAI面接が受けられます。AIは深掘りの質問をしたり、相槌を打ったりしてくれるため、本番さながらの面接練習ができます。
さらに、AIによる精密なフィードバックをもとに、自分だけでは気がつかなかった強み・弱み・面接での改善点が把握できるでしょう。
フィードバックのなかでは、就活で重視される「問題解決力」「人間関係構築力」「ストレス耐性」といった14の能力が、10段階評価で視覚化されます。
このような客観的な自己分析は、面接合格に向けて大いに役立つでしょう。
エントリータイミングの判断ができる
「REALME」でAI面接を受けると、これまでに蓄積されたビッグデータをもとに内容が評価され、内定判定が算出されます。試験前に内定を獲得できる可能性が分かるのは大きなメリットです。
AIのフィードバックをもとに面接の受け答えを改善し、内定判定を向上させれば、志望企業へのエントリーのタイミングをしっかりと判断できるでしょう。
しっかり準備して面接を攻略しよう
面接になかなか受からない場合は、その原因を考え、対策することが重要です。この記事でご紹介した対策方法を取り入れて、ぜひ面接を突破してください。
記事のなかでご紹介したように、面接の対策には就活サポートツール「REALME」がおすすめです。ぜひ一度、AI面接をお試しください。