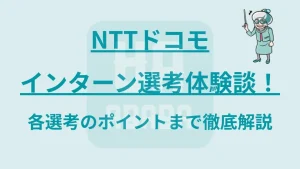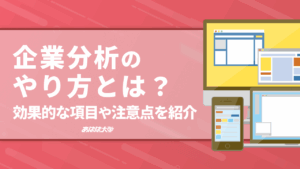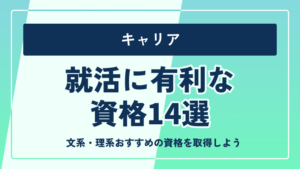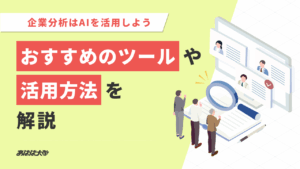就活において、志望する業界の研究は欠かせません。志望企業やその業界への深い理解は、志望度の高さをアピールすることだけでなく、自分に合う業界であるかを確認することにも繋がります。
しかし、何から始めればよいのか分からないという方もいるでしょう。
この記事では、業界研究のやり方や、研究をするにあたっておすすめの業界研究ノートについて紹介します。ノートの作り方も解説しているため、就職活動中の方はぜひ参考にしてください。
また、就活においては「REALME」の活用がおすすめです。AIとの面接を通じて自分の強みや内定の可能性が分かります。
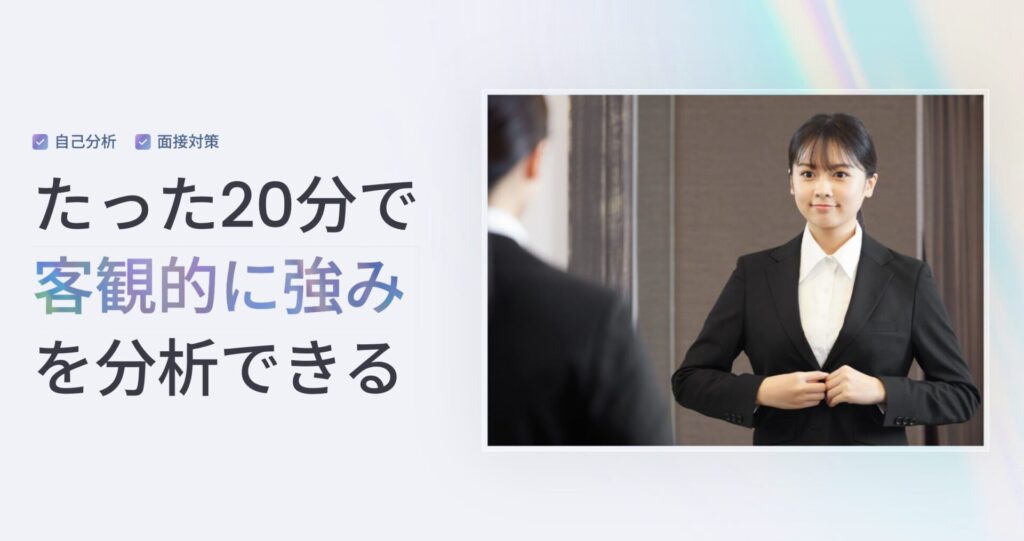
業界研究を実施する目的とは?
ここでは、就活において業界研究をおこなう目的を解説します。業界研究が役立つシーンは、志望動機や自己PRの文章作成だけではありません。より自分らしい働き方や、自分に合った職場を精査するためにも、業界研究は欠かせません。
自分に合う業界、業種を把握できる
業界研究の目的は、自分に合う業界や業種を把握することです。
そもそも業界研究とは、特定の業界の全体像や特徴、動向、将来性などを調査・分析するプロセスです。業界の情報が少ない状態では、自分に合った業界かどうかすらわかりません。
業界の傾向を知ることで、自身の適性やキャリアの方向性を考えられます。数多くある業界のなかから自分に合う企業を見つけ出すことで、ミスマッチが予防され、円滑なキャリアを選択できるのです。
キャリア形成に役立てられる
キャリア形成に役立つことも、業界研究の目的の一つです。たとえば昨今では、非デジタル企業であってもIT化やDX化が拡大しています。デジタル技術を積極的に採用している企業は、時代の流れに敏感かつ柔軟性を携えていると判断でき、将来性にも期待できるでしょう。
将来性のある企業であれば、中長期的なキャリアビジョンが形成できます。このように、企業の社風やビジネスの方向性を把握することは、安定したキャリアを築くうえで欠かせません。ただし、企業の具体的な将来は誰にも予測できないため、絶対的なものではないという認識も重要です。
業界研究のやり方
就活を有利に進めるうえで重要な業界研究のやり方を紹介します。ノートに記載する項目ごとに詳細を解説するため、業界研究ノートの作成に役立ててください。
業界名や企業名を書く
まずは研究対象の企業について基本情報を正確に把握することが重要です。業界名や企業名は略称を避け、正式名称で記載してください。ノートを参照しながら履歴書やエントリーシートを作成する際にも正確さが求められます。
また、興味を持った理由についても具体的に記載しましょう。どのようなきっかけでその業界や企業に関心を持ったかを明確にすると、志望動機を作成する際に役立ちます。
業界の分類は、大分類、中分類、小分類の順で段階的に分けて記載してください。たとえば、小売業の場合、「衣服の小売業」に分類し、さらに「紳士服」「婦人服」「子ども服」と具体的に細分化すると、業界への理解が深まります。
業界の特徴を書く
その業界の特徴や魅力を挙げましょう。市場規模やビジネスモデル、仕事内容について調べることが重要です。市場規模を理解することで、企業の将来性を見極められます。ビジネスモデルを把握すると、企業が求める人物像が明確になります。
業界内で希望する職種を選ぶには、仕事内容を詳しく調べることが必要です。自分に合った職種を見つけるためにも、マッチする点を整理してください。
業界の将来性や課題を書く
業界を選ぶ際は、将来性の有無や抱えている課題を把握することも重要です。どんなに魅力を感じる業界であっても、将来性がなく大きな課題ばかり抱える業界であれば、就職先として選ぶことは避けたいでしょう。
将来性や課題について知ると、志望業界を絞り込む際の判断材料となります。直近数年間の利益推移や企業の売上高、社員の平均年齢・平均年収、経営ビジョンなどをチェックして、どのような課題を抱えているのか書き出すとよいでしょう。
業界の最近のニュースやトピックスを書く
業界の動向を常に把握するために、最新のニュースやトレンドを押さえることも大切です。業界が誕生したきっかけや、現在に至るまでの過程など、業界の歴史についても調べましょう。歴史をたどることで、トレンドがどのような変化を遂げてきたのか、業界や企業はその変化に対してどのような対応をしてきたのかを把握できます。
インターネットや新聞、社会人の先輩から話を聞くなどして、最新のニュースやトピックスを把握して記載しましょう。
自分の感想を書く
業界に関する情報だけではなく自分の感想も書きましょう。調べているうちに生じた気付きや考察を書き出して、あとから見返すと、就活に役立てられます。
自分が抱いていたイメージと合致する点や相違点を挙げたり、実際に働いている人への印象をメモしたりしましょう。
業界の特徴で魅力に感じたところや不安に感じたところを書き出せば、志望業界や企業を選ぶ際の判断材料になります。

【業界研究のやり方】情報を集める方法
ここでは、業界研究の具体的な方法をご紹介します。業界研究では情報収集が要。とはいえ、志望する企業のホームページをチェックしているだけでは、十分な業界研究とはいえません。効果的な研究方法を学び、実用的な情報を集めましょう。
業界で有名な企業のWebサイトなどを確認する
業界研究の第一歩として、業界大手や有名企業のWebサイトをチェックしましょう。事業内容や沿革、企業理念、採用頁などをリサーチすることで、業界の基本構造や主要なビジネスモデルなどの理解に近づきます。
調査対象は大手だけに絞らず、ベンチャー企業や中小企業なども含め、それぞれの強みや戦略を調べていきましょう。また最新のニュースリリースやIR情報には、業界全体の動向や、企業が注力している分野が反映されているため、情報収集に役立ちます。
業界研究につながるセミナー、イベントに参加する
業界研究では、業界に関連性のあるセミナーやイベントには積極的に参加すると良いでしょう。最新の業界動向を身近に感じられるだけではなく、企業ごとの特徴や社風を効率的に把握できます。
とくに「現場や実際に働く人の空気感」や「企業の発信に対する姿勢」などは、ネットの情報だけではわからない情報です。また企業担当者に直接質問できる機会があるのもイベントのメリット。さらに複数の企業を一度に比較できるイベントへの参加は、同業界内での立ち位置や強みの違いも把握しやすくなります。
業界に関する情報をSNSや動画サイトで調べる
昨今では、個人でも業界情報を発信する人が増加傾向にあります。業界に関連する情報を調べる際は、SNSや動画サイトなども参考にしましょう。たとえばYouTubeの検索欄で「IT業界」と検索すると、業界の仕事内容や年収、企業同士の関係性などを解説した動画が多数見つかります。
SNSでは最新ニュースやトレンドをリアルタイムで把握できるため、日々の閲覧を習慣化すると良いでしょう。また実際に働く社員のインタビュー動画や、企業のイベント記録なども企業研究に役立ちます。
OB、OGから情報を直接聞く
OB・OGへの訪問は、業界研究における有効な手段の一つです。実際にその業界で働いている先輩から、リアルな職場環境や仕事内容、キャリアの実態などを直接リサーチできます。ネット情報やパンフレットだけでは得られない情報が手に入るため、ライバルとも差を付けられます。
企業の魅力だけでなく課題も含めて教えてもらえる可能性があるため、より深みのある志望動機につながり、企業が本当に求めるニーズを予測できるのが魅力です。事前準備をしっかりとおこない、誠実な姿勢で臨みましょう。
業界研究で確認するべき必須項目3つ
ここでは、業界研究で確認したい必要項目を3つご紹介します。今回ご紹介するのは、「業界全体の概要、トレンド」「代表的な仕事内容、働き方」「将来性、今後の展望」の3つ。これらを基軸にリサーチを進め、効率的な情報収集につなげましょう。
業界全体の概要、トレンド
業界研究では、業界全体の概要やトレンドをリサーチする必要があります。業界全体の規模や仕組みを理解し、市場規模や主要プレイヤー、参入の難易度、顧客層などの基本情報を押さえていきましょう。
そのうえで近年のトレンドにも注目することで、企業が置かれている環境や直面している課題が見えてきます。たとえばIT業界ならAIやDX、金融業界ならキャッシュレス化やフィンテックなどに注目。トレンドの把握は、自分の貢献のかたちを考えるための土台になります。
代表的な仕事内容、働き方
業界研究の際は、対象の業界の代表的な仕事内容や働き方なども調べましょう。たとえばメーカーでは商品企画・営業・生産管理、IT業界では開発・運用・コンサルティングなど、業界内でもさまざまな役割があります。
仕事内容を把握するほど、求められるスキルや業務フローをイメージでき、自身のキャリアビジョンと照らし合わせやすくなるでしょう。ただ自分がやりたい仕事を探すだけではなく、自身の価値観やライフスタイルに合う働き方ができる業界を探すことが重要です。
将来性、今後の展望
業界の将来性や今後の展望なども、業界研究の要点となります。たとえば昨今ではAIの台頭により、一部の業界や業種で働き方に大きな変化が訪れています。現在の業界の姿だけではなく「今後の技術進化や社会の変化により、どのように変わっていくのか」を把握することが大切です。
とくにデジタル化や環境問題への対応などは、多くの業界に影響を及ぼす要素。長期的かつ自分らしいキャリアを実現するためには、社会全体の動きにまで視野を広げたうえで、業界の方向性を読み取る姿勢が求められます。
業界研究ノートの作り方
業界研究ノートをより効果的なものにするコツを紹介します。これからノートを作成しようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。
業界の基本情報を調べる
興味のある業界についての基本情報を調べましょう。
前述の「業界名や企業名を書く」「業界の特徴を書く」の章で説明したように、まずは業界名と気になる企業の正式名称、特徴や魅力などの情報を集めます。その際、インターネットの情報だけでなく、OB・OGや社会人の先輩から話を聞くとよいでしょう。
新しい情報が入ったら追加する
業界研究ノートは一度作成したら終わりではありません。新しく情報が入ることもあれば、状況が変化することもあります。常に動向をチェックして、最新の情報に書き換えましょう。
作成する際にはあとから情報を書き足せるよう、スペースを空けて作ることがおすすめです。
また、最新情報に書き換える場合、変化の流れを把握するために古い情報も残した方がよいでしょう。
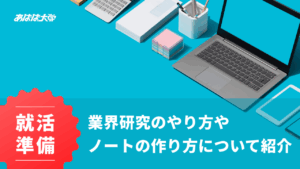
AI面接「REALME」で面接回答例を確認できる

就活を始めるにあたって、業界研究は非常に重要です。業界研究ノートを活用して自分に合う志望企業を選べたら、AI面接サービスの「REALME」を活用してはいかがでしょうか。「REALME」なら他の学生の面接回答例を確認できるため、面接対策に役立ちます。
志望企業の内定可能性が判定できる
「REALME」は、AIと面接を行うことによって志望企業の内定可能性が判定できる就活対策サービスです。過去に志望企業の合格ラインを超えた学生のデータと比較することで内定可能性を判定できる仕組みです。
業界研究ノートを活用して自分とマッチしそうな企業を探し、「REALME」で内定判定を確認しましょう。
AIで抽出したES・面接回答例が閲覧できる
「REALME」なら、優秀な学生のESや面接回答例を閲覧できます。志望企業の合格基準を超えた学生のデータが見られるため、ESを作成する際や面接の回答を用意する際にも役立つでしょう。
ESや志望動機を作る際に業界研究ノートと併せて活用することで、より魅力的な自己アピールを作成できます。
AI面接の後FBが受けられる
AI面接が終わった後に、AIからFB(フィードバック)を受けられます。アピールポイントとなる強みや、対策した方がよい弱みなどを客観的な視点から把握でき、面接対策を効率よく進められます。
入念な業界研究と「REALME」のAIによるFBをもとに、内定判定の向上を目指しましょう。
業界研究のやり方を理解してノートを作成しよう
就活では必須ともいえる業界研究は正しいやり方を理解しなければ、上手く活かせません。また、何のために業界研究ノートを作成するのか目的を明確にすることが重要です。本記事の内容を参考に自分の納得のいく業界研究ノートを作成してみてください。
ノートを作成した後は、「REALME」での面接練習がおすすめです。フィードバックをもとに面接対策を行うと、就職活動がスムーズに進むでしょう。

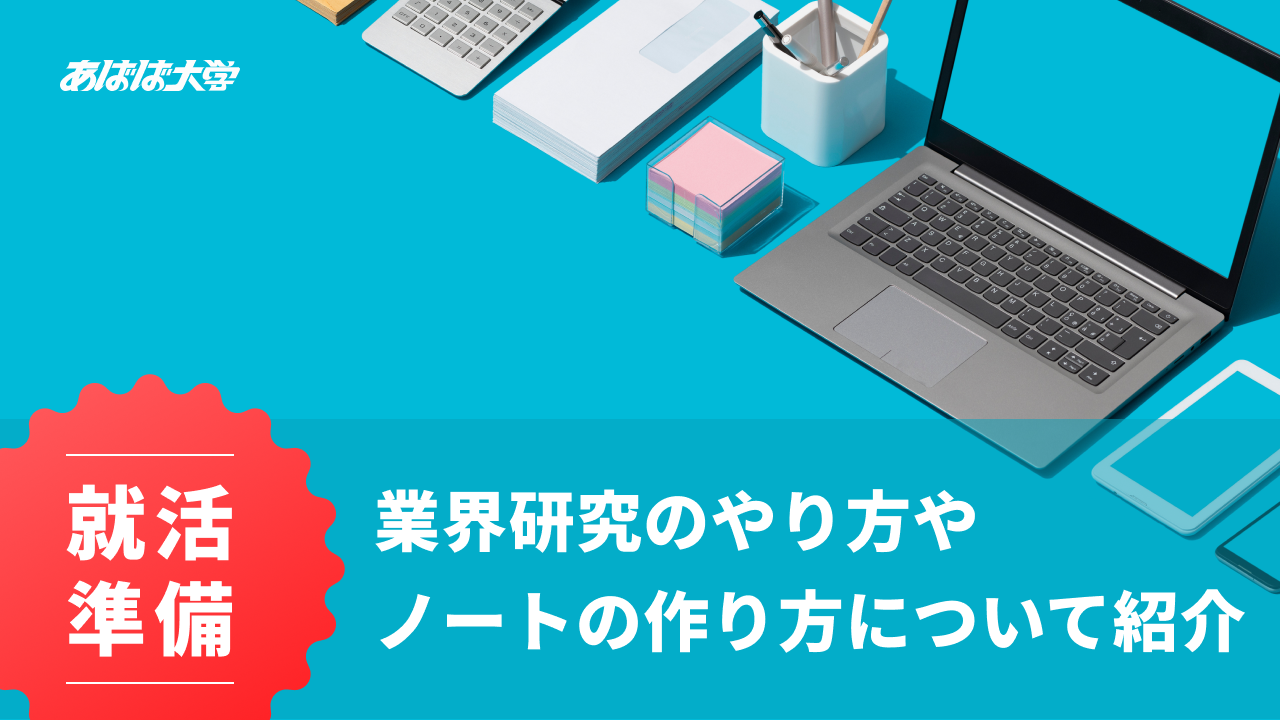
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)