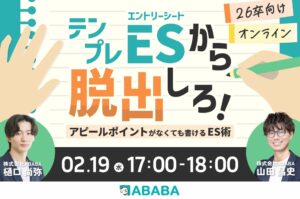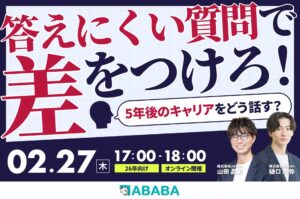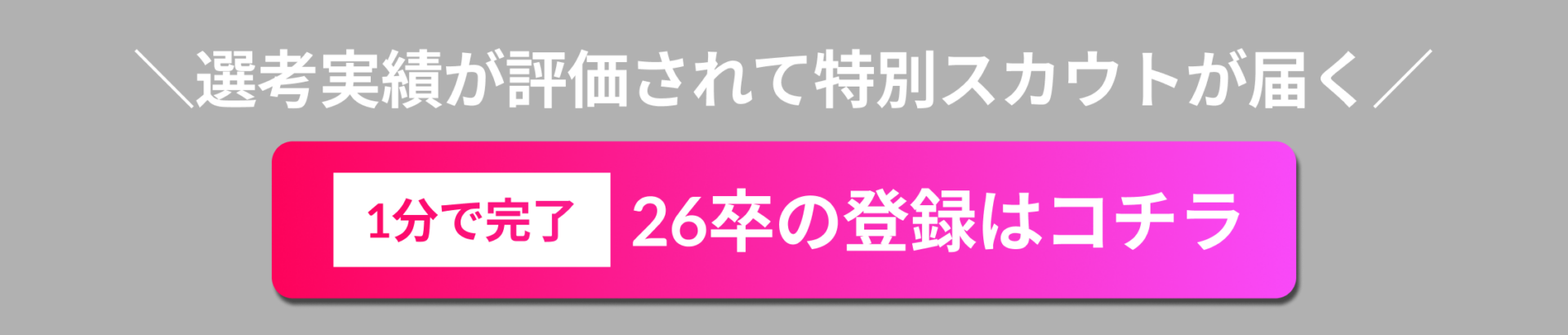新卒採用の面接は企業の担当者と対話できる貴重な機会です。一方、面接でうまく話せないという悩みを抱える就活生は多くいらっしゃるでしょう。この記事では、面接でうまく話せない原因と対策を解説します。面接に自信がない方は、ぜひ参考にしてください。
「REALME」でAI面接を受けると、志望企業の内定判定が算出できます。強みや課題の把握ができ、面接対策を進めるときに便利です。本番でうまく話せるように、AI面接で練習を積みましょう。
面接でうまく話せない要因は?
そもそも、なぜ面接の場ではうまく話せなくなるのでしょうか。過度の緊張や自信のなさなど、精神面に抱える不安が主な要因です。そのほか、回答の準備不足や会話術の面など、事前の対策で改善できる要因も含まれます。
準備不足
準備不足のまま面接に向かうと、質問に対してうまく返答できないことがあります。本番を意識した準備ができなければ、想定外の状況に対応しづらくなります。
具体的には、自己分析や企業研究による準備が重要です。アピールしたい自分の個性と企業の特徴が把握できていれば、多くの質問にうまく対応できます。また、面接の本番を意識したシミュレーションにも効果があります。
面接は普段と違う環境で開催されるため、事前の準備は欠かせないでしょう。
緊張しやすい
もともと緊張しやすい性格の人は、面接でうまく話せないことがあります。面接会場の雰囲気や緊張感にのまれて、本来の力を発揮できないケースも起こり得ます。
とくに、志望度が高い企業の面接では緊張しやすいでしょう。一方で、面接に対して感じる緊張は、真面目に取り組めていることの証拠ともいえます。
適度な緊張であれば、集中力も向上します。緊張を感じたとしても、ネガティブに捉えすぎず平常心を保てばうまく対処できるでしょう。
自分に自信がない
話す内容や自分の能力に自信が持てていなければ、不安が募りうまく話せない状況に陥ります。面接中の態度から自信のなさを見抜かれると、高く評価してもらうことは困難になります。
志望企業の面接で、自己PRやガクチカを正確に伝えられるかを不安に感じる人も多いでしょう。本番で話す内容に対して自信を持つには、事前の面接練習が大切です。具体的な面接練習の方法は、後述の内容を参考にしてください。
完璧を求めすぎている
回答内容を作り込む完璧主義が裏目に出て、面接でうまく話せないケースも存在します。完璧を求めすぎる人にとっては、準備していなかった想定外の質問が弱点です。
たとえば、自己PRの回答を事前に用意していたとしても、エピソードの深掘りが続いた途端にうまく回答できなくなるような展開が考えられます。
面接では、臨機応変な回答も重要です。すべてを完璧に作り込み覚えるだけでなく、想定外の質問が来ることを視野に入れて準備しましょう。
発言にまとまりがない
発言内容にまとまりがなければ、うまく話せない結果につながります。冗長な回答は面接官に意図が伝わりにくく、自分でも何を伝えたいのかが分からなくなります。
面接の限られた時間で最大限の自己アピールをするには、伝えたい要点だけを押さえて簡潔に回答する意識が大切です。
複数回の面接が組まれるケースでは、書類選考から最終面接まで同じ内容に関する質問をされることがあります。選考を通して、発言に一貫性を持たせましょう。
面接でうまく話せない場合の対策は?
続いて、面接でうまく話せない人に取り組んでいただきたい5つの対処法を解説します。回答の組み立て方や話す順序など技術面の改善と、面接に向けた精神面の意識づけが大切です。課題を把握して、繰り返しの練習に取り組みましょう。
繰り返し練習する
面接の反復練習には、大きな効果があります。本番を想定した練習を繰り返すことによって、記憶の定着と慣れが生まれるでしょう。
具体的には、ガクチカや自己PRなどの定番質問に対する回答を用意し、何度も繰り返して声に出す練習が有効です。友人や家族と会話形式で実施する練習もおすすめです。
練習を積むことで、面接に対する自信が生まれる効果も期待できます。「これだけ練習したから大丈夫」と思えると、本番でもうまく話せるでしょう。
結論から話す
面接の回答は、結論ファーストを意識して組み立てましょう。話術に自信がない人でも、結論から話すことで、面接官に対して話の要点が伝わります。
たとえば、自己PRの質問であれば、「私の持ち味は粘り強さです」や「論理的思考力に自信があります」のように、結論ファーストで回答することが有効です。
回答の補足事項やエピソードの内容がうまく話せなかったとしても、結論さえ伝えられれば、最低限の情報は面接官に伝えられます。
話す内容を丸暗記しない
回答内容は、無理に丸暗記しないことをおすすめします。丸暗記には、内容を思い出せなくなる、感情がこもらず棒読みになる、などのデメリットがあります。
必要な回答内容だけを覚えたうえで、細かな部分は面接の場で考える方法が有効です。価値観や軸が明確であれば、一貫性のある回答ができるでしょう。
面接は、一つの質問だけでは終わらず深掘りを繰り返されることがあります。丸暗記で挑むと想定外の質問に対応しづらいため、避けることが得策です。
失敗を恐れない
面接では、失敗を恐れずに積極的な回答を見せる姿勢が大切です。不安そうな態度の就活生よりも、堂々と発言できる就活生のほうが好印象を与えやすいからです。
回答内容に自信がなかったとしても、面接官の目を見て明るく自己アピールすると、誠実な人柄であると評価される可能性があるでしょう。
面接官は、学生が緊張することは理解しています。少し失敗したとしても、大きな低評価にはつながりません。失敗を恐れず、自信を持って臨みましょう。
大きな声で落ち着いて話す
うまく話せない人の特徴として、声の小ささや早口が挙げられます。改善するためには、声量を大きくして、落ち着いたトーンで話すように心がけましょう。
口を大きく開き、口角を上げながら話すと声量は自然と上がります。また、緊張感のある場では早口になりやすいため、意識的に話すスピードを落とすこともおすすめです。
面接の直前は、口周りの筋肉を動かして準備しましょう。聞き取りやすく落ち着いた声で話せると、面接官に好印象を与えられます。
面接でうまく話せない場合にしておきたい事前準備
面接でスムーズに話すためには、本番前の準備が重要です。
ここでは、面接本番でうまく話せない事態を防ぐために、前日までにしておきたい準備を紹介します。
実力を発揮するために入念な準備をしましょう。
頻出質問の回答を準備しておく
面接では、どのような企業・職種・業種でも共通して聞かれやすい頻出質問があります。
よく出される基本的な質問について、回答を考えてあらかじめ準備することで、当日落ち着いて回答できるでしょう。
一度考えた回答を見直すことで、内容もブラッシュアップされます。
考えた答えを知り合いやキャリアセンターの人などに評価してもらうのもよいでしょう。
よく聞かれる質問としては、以下があります。
- 自己紹介
- 志望動機
- 学生時代に取り組んだこと
- 短所と長所
- 将来のビジョン
録画して面接練習する
面接での評価点のうち、話し方や姿勢などは、一人で練習していると振り返りにくいといえます。
話し方や姿勢を改善したいときは、カメラやスマートフォンなどで録画・録音して振り返ることがおすすめです。
録画を見ることで、客観的な視線から自分の面接中の様子を確認できます。
面接マナーや受け答えの癖などを確認し、不自然なところがあれば直しましょう。
入室から回答、退室までの一通りの様子を録画して見直すことがおすすめです。
第三者からフィードバックをもらう
話し方や姿勢などは、自分だけで見ても改善しにくいことがあります。
そのような点を改善したいときは、第三者からフィードバックをもらうことで、独力では気づきにくい問題点を改善できます。
可能であれば、本番までに一度は家族や友人相手に面接練習をするとよいでしょう。
家族や友人などに時間を割いてもらうことが難しい場合は、キャリアセンターを利用して相談することもおすすめです。
面接でよく聞かれる質問と回答のポイント
面接には多くの企業で共通して聞かれる頻出の質問があります。
このような質問に対応できないと、面接準備ができていないと評価されることもあるでしょう。
ここでは、頻出質問の例とその回答内容について紹介します。
自己紹介してください
面接では始めに、応募書類で書いた自己紹介を再び求められます。
氏名や大学名所属学部のほか、アピールポイントを1ついれるとよいでしょう。
また、エントリーシートに書いた内容と矛盾がないようにすることも重要です。
「〇〇秒で」と時間が決められている場合もあるため、20秒や30秒など時間を決めての練習がおすすめです。
志望動機を教えてください
志望動機も、面接序盤で聞かれることの多い基本質問の一つです。
エントリーシートでも記載した内容ですが、事前に提出した内容に沿いつつ、より深掘りして答えることがおすすめです。
志望動機を尋ねる面接官は、職種や業種だけに絞ったあいまいな志望理由ではなく、その企業を目指すに至った明確な志望理由を求めています。
企業に対する志望の経緯に関連させて、入社後にどのように活躍したいか、何をしたいかなどもいれるとよいでしょう。
就活の軸は何ですか
就活の軸についての質問も、面接においてよく聞かれることの1つです。
就活の軸とは、その人の企業選びや仕事選びの基準となるものを指します。
企業とのミスマッチや入社後の目標などを測るために、多くの企業で面接に取り入れられている質問です。
自己紹介や志望動機と異なり、エントリーシートで詳しく書くことが少ない項目であるため、明確に答えられるようにしましょう。
面接前の自己分析において、就活の軸について考えることが重要です。
あなたの強みと弱みを教えてください
強みと弱みを聞かれたときは、面接官側は強みを仕事にどう活かせるか、を求めています。
長所・短所と同じ意味として考える人もいますが、「長所・短所」「強み・弱み」はニュアンスがやや異なります。
長所と短所は本人が持つ人柄を指し、相手に対して直接のメリット・デメリットはありません。
対して、強み・弱みは成果を出すために活かせる能力を指し、相手に対してメリット・デメリットがあります。
入社後のビジョンを教えてください
面接時に聞かれる入社後のビジョンとは、ただ単に自分がやりたいことを答えればよいわけではありません。
この質問をするとき、面接官側は、入社後にどのような分野で活躍したいかの具体的なエピソードを求めています。
この質問によって、入社意欲や社風・仕事内容とのミスマッチも測られるでしょう。
うまく回答するためには、「どのような業務があるのか」「どのようなキャリアを目指せるのか」を事前に調べることがおすすめです。
学生時代に頑張ったことを教えてください
ガクチカとも呼ばれ、多くの企業で聞かれる質問です。
面接官側はこれを聞くとき、取り組んだことそのものよりも過程や得られた成果を仕事にどのように活かすのか、を求めています。
そのため、エピソードや得た学びについて具体性を持たせて伝えることが重要です。
「頑張ったこと」「力をいれたこと」「やり遂げたこと」など、さまざまなニュアンスで聞かれることがあるため、それぞれの形式に合った答え方を考えるとよいでしょう。
面接でうまく話せない場合は「REALME」で事前対策!
「REALME」のAI面接は、自己分析や面接対策に役立つツールです。面接の回答内容をAIが分析し、強みと弱みを可視化させます。また、AI面接を繰り返すことで、内定判定の改善が可能です。面接でうまく話せない悩みを解決しましょう。
AI面接で志望企業の内定判定を確認できる
「REALME」でAI面接を受けると、現時点での志望企業の内定判定が確認できます。回答内容をAIが分析し、過去の合格者データと比較して算出する仕組みです。
面接でうまく話せない人には、AI面接の実践をおすすめします。現状の課題が分かるうえに、練習を積むと内定判定が向上し、自信を持って面接に挑めるでしょう。
AI面接で自分の強みと弱みを客観視できる
「REALME」のAI面接は、自己分析にも役立ちます。回答内容をAIが分析して、新卒就活で重視される14項目の能力を点数化してくれます。点数で確認できるため、客観的な視点で自分の強みと弱みが把握できます。
自分の強みが分かれば、面接で伝えるアピールポイントを明確にすることが可能です。面接でうまく話せないという悩みがある人は、自己分析によって回答内容を準備しましょう。
合格ライン就活生のAI対話データを参考にできる
「REALME」には、優秀な就活生のESやAI面接の対話データを閲覧できる機能があります。志望企業の合格ラインに到達した就活生の選考データを参考にすれば、効率よく面接の準備を行うことが可能です。
ガクチカや自己PRの構成が分からないという理由で本番の面接でうまく話せない人もいるでしょう。自分の回答と比較して、合格に足りない部分を補う対策が大切です。
面接でうまく話せない場合は入念に事前準備をして臨もう!
この記事では、面接でうまく話せない原因と解決策について紹介しました。
準備や自信が足りないときは、反復練習を積んだうえで面接に臨みましょう。
面接対策には、「REALME」のAI面接が最適です。AI分析で自分の強みを知り、適切にアピールできるように回答の準備をすると、選考通過の可能性は広がります。