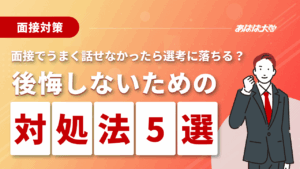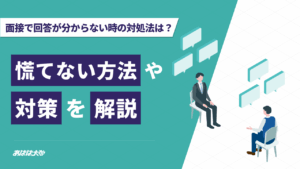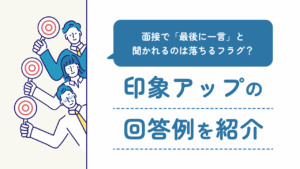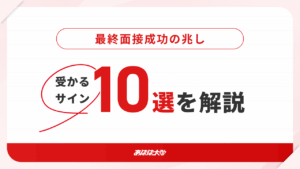「面接で話すために準備した内容を、どうしても覚えられない」
「話の途中で言葉に詰まると、先に進めなくなってしまう」
そのように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、準備した内容が覚えられない要因を考えてみます。また、面接の前や当日の対処法も解説します。
記事の最後には、面接本番に向けてサポートしてくれる就活支援サービス「REALME」についてご紹介します。気になる方は、ぜひ詳細をご覧ください。
面接で話す内容は覚えたほうがいい?
結論から言うと、面接で話す内容はある程度は覚えたほうが良いでしょう。なぜなら面接では、どの企業でも聞かれやすい「定番の質問」がいくつか存在しているからです。本番で聞かれる内容を想定して回答を覚えているほうが、スムーズに答えられます。
思考や価値観を誤解なく伝えるためにも、事前に回答内容を明文化したうえで調整し、覚えておくのが効果的。とはいえ丸暗記に頼ってしまうと想定外の質問が来たときに動揺しやすいため、覚え方にはコツが必要です。
面接で話す内容を覚えるメリット
ここでは、面接で話す内容を覚えるメリットについてご紹介します。面接では暗記のみに頼っていては面接官に見抜かれてしまう場合がありますが、概要の全体を覚えておくことは非常に大切。メリットを把握したうえで準備に充てていきましょう。
伝えたいことを漏れなく伝えられる
面接で話す内容を覚えておけば、伝えたい内容を漏れなく伝えられます。面接会場は緊張感が高く、本来のポテンシャルを発揮できないことも。重要な内容さえ頭に入っていれば、失敗のリスクが大幅に下がります。
そもそも面接官は、応募者が一定の緊張感を抱いていることを前提としています。だからこそ「緊張時での対応」が円滑であることが高評価につながるのです。内容を漏れなく伝えられれば、事前にしっかりと備えていた姿勢も伝わります。
話す内容が頭から抜けることがなくなる
どれほど入念に準備しても、緊張感が高まると頭が真っ白になることも。話す内容がまったく思い出せなくなると、表情や声色にも不安や焦りが滲みます。失敗を避けるためには、事前に内容を頭に叩き込み、情報を定着させることが重要です。
おすすめしたいのは、文章ではなくキーワードで覚える方法です。文章のみを丸暗記すると、緊張で忘れたときに対処が難しくなります。しかし「SDGsに根差した事業展開」や「自己成長につながるキャリアアップ制度」のようなキーワードだけを覚えれば、ワードから逆算するかたちで文章を作りやすくなるでしょう。
回答内容の矛盾を防げる
話す内容を事前に覚えるメリットとして、回答内容の矛盾を防げることも挙げられます。回答内容に一貫性があれば、どのようなアプローチの質問にも適切に回答できます。その反面、緊張によってその場限りの回答ばかりしていたのでは、どこかで矛盾が生じてしまうでしょう。
矛盾した回答は評価が落ちる原因であり、面接官に「表面的な回答しかしていない」と思われかねません。回答の基盤となる内容だけでも覚えておけば、全体的に軸のある対応につながります。
面接用に準備した内容を覚えられない要因は?
なぜ面接用に準備した内容を覚えられないのでしょうか。「すらすらと覚えたことを話せる人もいるのに、なぜ自分はできないのか」と悔しく思っている人もいることでしょう。ここでは、その要因を探ってみます。
回答の内容が本心とは違う
まず第一の理由として、用意した回答の内容が自分の本心とは違うため、覚えられないケースが考えられます。
本当に思っていることであれば、すぐに覚えられますが、本心と異なることはなかなか覚えられません。
たとえば、本当は控えめな性格であるのに面接の自己PRで社交的な性格を前面に出そうとしたケースを例に挙げます。本当の自分とは違う自分を語ろうとすると、思うように話せず、つい口ごもってしまうでしょう。
自分が本当に強みだと思える点や経験してきたこと、自分が持っているスキルについて正直に記述すれば、自然に覚えられます。本心から思っていることを、回答として用意するように心がけましょう。
文章を丸暗記している
覚えられない第2の理由として、文章を丸暗記しようとするケースが考えられます。
「せっかく用意した内容なのに暗記できない」と悩む人は、その原稿を一言一句間違えずに覚えようとする傾向があります。しかし、きっちり丸暗記しようとすると、かえって覚えられません。もし完璧に覚えられたとしても、話し方がどことなく不自然になったり、一部分を忘れたために、そのあとのすべてが記憶からこぼれ落ちて何も話せなくなったりすることがあるでしょう。
完璧に丸暗記する必要などないと、心に留めておきましょう。
文章に無駄が多い
第3の要因として、文章に無駄な言葉が多いケースも考えられます。
原稿を作成する際に不要な言葉をたくさん入れてしまうと暗記に苦労することになります。
それだけではなく、たとえすべて覚えられたとしても、面接官に伝わりにくい内容になっている可能性が高いでしょう。自己PRや志望動機は、言っていることが相手に伝わらないと意味がありません。
面接で話す言葉はできるだけ無駄な言葉をそぎ落として、すっきりと簡潔な文章にまとめるようにしましょう。
面接用の内容を覚えられない場合の対処法
面接用に考えた内容をどうしても覚えられない場合、考えられる対処方法は以下の4つです。ぜひ、じっくりと時間をかけて試してみてください。
自分の考えに対する理解を深める
就活では自分の考えをしっかりと理解することが重要です。
志望動機や自己PRを文章にまとめる前に、自分がなぜそのような考えを持つに至ったのか、さまざまな思い出を掘り起こして考察しましょう。
体験にひもづけて考えることによって、自分自身のことが根本的に理解でき、作成した志望動機や自己PRをスムーズに覚えられるようになるでしょう。
要点をまとめたメモの作成
次に試したいことは、要点を短くまとめたメモの作成です。
文章として暗記できない場合は、原稿のなかの重要だと思われるポイントだけを覚えておけば十分です。要点だけなら文章よりもはるかに記憶しやすいでしょう。面接で話しているうちに忘れてしまったとしても、要点なら比較的思い出しやすいです。
また一言一句思い出して話すわけではないため、面接官との対話も自然になります。伝えたい部分で気持ちがこもったり、表情や声がやわらかくなったりする効果もあるでしょう。
マインドマップを活用する
続いて試していただきたいことは、マインドマップです。これは、紙の中心に書いたキーワードから連想ゲームのように、思いついたキーワードを書き込んで放射状に広げていく思考法です。
面接用に作成した文章のなかから自分にとって重要な単語をいくつか抜き出し、それを関連付けて並べることでマインドマップができます。文章ではなく、図として目に焼きつけるところがポイントです。書き込んで何度も見ているうちに、内容が頭に入ってくるでしょう。
頻出する質問への回答を優先的に覚える
面接用の内容をなかなか覚えられないときには、頻出する質問への回答を優先的に覚えることをおすすめします。たとえば自己紹介・自己PRや志望動機、ガクチカ、逆質問、企業への魅力などに関する質問は、どの企業の面接でも聞かれやすい「定番の質問」です。
「絶対に答えられる質問」をいくつか覚えておくと心にも余裕が生まれ、ほかの質問への対策もしやすくなるでしょう。とくに自己紹介や志望動機などは、あらゆる回答の基軸となる内容です。基礎を押さえることでほかの回答にも一貫性が生まれやすくなります。
面接練習を繰り返す
もう1つやっておきたいことは面接練習です。ただ覚えるというインプットの作業だけではなく、アウトプットも重要です。それによって記憶がより定着し、面接のスキルも向上します。
友達や家族に面接官の役をお願いして、面接で頻出する質問をしてもらい、実際の面接のつもりで答えましょう。
話の内容だけでなく、声の大きさ・話す速さ・視線などもチェックしてもらってください。慣れてきたら面接官役の人から深掘りの質問をしてもらいましょう。緊張感を持たせたいなら、大学の先生やOB・OGに依頼することもよいでしょう。少しでも場数を踏んで、面接に慣れましょう。
面接用の回答を覚えるコツ
ここでは、面接用の回答を覚える際のコツをご紹介します。学校のテスト対策でも暗記にはコツが必要ですよね。面接でも同様に、ポイントを押さえることで覚えるのが楽になり、精神的にも余裕がある状態で本番を迎えやすくなります。
覚える内容は1分程度の長さにまとめる
面接用の回答を覚える際は、覚える内容を1分程度の長さにまとめることが推奨されます。1分間のテキストは、文字に起こすと約300~400字程度の長さです。長すぎる文章の暗記は、本番で詰まったときに思い出すのが難しくなり、パニックにつながります。
ストップウォッチで時間を計測しながら、トータル時間を調整していきましょう。企業によっては3分、5分など長めに時間を与えられる場合もあるため、「基本の1分間」の内容をしっかり覚えたうえで付け足していくことをおすすめします。
繰り返し声に出して覚える
繰り返し声に出して覚えることでも、面接用の回答を覚えやすくなります。知識を定着させるためには、インプットだけではなくアウトプットも大切。覚える・声に出す・覚える……と繰り返していくことで、少しずつ記憶に深く刻み込まれていきます。
声に出して練習していると、覚えきれていないところで言葉が詰まるため、補強すべき弱点を見つけやすいのもメリット。「一度も詰まらずにスラスラと話せる状態」になるまで、何度も声に出していきましょう。
PREP法を意識した構成にする
面接の回答を覚えるためには、PREP法を意識することをおすすめします。PREP法とは、「結論(Point)、理由(Reason)、具体例(Example)、結論(Point)」の順番で伝えるフレームワークです。
PREP法では結論で始まり結論で〆るため、聞いている側にとって「今何を話しているのか」が伝わりやすくなります。また文章構成に論理性があるため自分も覚えやすく、双方にメリットがあります。練習時から、結論ファーストの文章を作成していきましょう。
話している様子を自分で見返す
「自分が相手からどのように見られているのか」がわからないままだと、不安や緊張が増幅しやすく、本番でも忘れやすくなります。回答を定着させるためには、自分が話している様子を録画して見直し、表情や声色を含めた改善を繰り返しましょう。
「このシーンでは目線が泳ぎやすい」「あー、えー、などの無駄な言葉が多い」など、客観視することによる発見は多いものです。自分を冷静に分析しつつ改善するプロセスで、回答内容も定着しやすくなり、スムーズな本番が期待できます。
本番になるべく近い環境で練習する
面接時の回答を覚えるためには、本番になるべく近い環境で練習しましょう。言葉だけを繰り返して覚えるのではなく、本番で着用するスーツを着たうえで、髪型やメイクも整えることが大切。見た目を本番に近づけると緊張感が高まり、ロールプレイとしての練習の質がグッと上がります。
本番に近い緊張を抱いた状態で練習できれば、自分の弱点にも気づきやすくなり、より定着に効果的な改善が進むでしょう。就職エージェントのようなプロ相手に模擬面接を頼めれば、的確なフィードバックも得られます。
面接用の内容を覚えるときに丸暗記をおすすめしない理由
ここでは、面接用の内容を覚えるときに、丸暗記を避けるべき理由をご紹介します。丸暗記は安心感を高めてくれますが柔軟性に欠けやすく、かえってマイナスの印象を与えてしまうことも。丸暗記のデメリットを把握しつつ、より効果的な覚え方につなげていきましょう。
一部分でも忘れた場合、全部思い出せなくなってしまうため
面接での回答を丸暗記に頼っていると、一部分でも忘れたときに全部を思い出せなくなってしまいます。丸暗記では、すべての内容が1つの記憶として処理されます。たとえば「A・B・C・D」と話すつもりで「C」の途中で内容を忘れてしまうと、また「A」から話し始めないと思い出せません。
丸暗記の覚え方では、前後の情報によって連鎖的に内容を思い出す必要があります。「忘れてしまった部分だけ思い出す」が難しいため、最初から同じ内容を繰り返し話さざるを得なくなってしまうのです。
棒読みの話し方になりやすいため
丸暗記に頼っていると、抑揚のない話し方になってしまいがち。文章を覚えることだけを重視してしまい、目線や表情、ニュアンスなどに意識が向きにくくなってしまいます。その結果、面接官に丸暗記がバレやすく、「情熱や人間味が感じられない」と評価されやすくなります。
回答内容を覚えること自体は大切ですが、練習時から感情を込めた話し方も意識するように努めましょう。暗記内容を再現するだけではなく、面接官の目を見たり、要所で強調するような話し方をしたりなども重要です。
想定外の質問に対応できなくなるため
丸暗記の最大の弱点ともいえるのが、想定外の質問への弱さです。丸暗記は、当然ながら暗記した部分以外の回答には対応できません。また暗記の練習をするうちに、覚える内容がただの「暗記用の情報」となり、本質の理解からズレてしまう場合があります。
暗記した内容から派生する質問や思考に対応できず、「暗記部分以外はしどろもどろな対応」になってしまいがちに。質問ごとに反応が大きく変わると、丸暗記を察知されやすくなるリスクがあります。
自分らしさが伝わりにくいため
自分らしさが伝わりにくいのも、丸暗記特有のデメリットです。丸暗記で覚える内容といえば、面接においてお決まりの「定番質問」ですよね。どうしても回答内容がテンプレート的になり、自分ならではの魅力や個性を発揮しにくい傾向にあります。
事前に用意した回答にはリアリティが少なく、自分を良く見せるために誇張した内容になってしまうことも。本来の自分の良さが伝わらずに、普遍的で無個性な印象を与えてしまうリスクがあります。
面接当日に覚えられない不安を解消する方法
面接当日になっても覚えられないと不安が募ります。そのような不安を解消する方法を、ここではご紹介します。参考にしてぜひ実践してください。
完璧に話せなくてもよいと考える
面接では、完璧に話せなくても大丈夫だと考えるようにしましょう。冒頭から最後まで、すらすらと完璧に答えたり話したりする必要はありません。
これは、あきらめているわけではなく、前向きな考え方です。少し言葉に詰まった程度で不採用になることはないという気持ちで臨みましょう。
緊張してもよいと考える
緊張しないようにと強く念じていると、なぜかかえって緊張が増すこともあります。逆に緊張してもよいと考えるようにすると不安解消に効果があります。緊張することは悪いことではないと念じてみてください。
実際のところ、面接や試験などの集中力が求められる場面では、程よい緊張感が不可欠です。まったくプレッシャーがない状態よりも、ある程度緊張感もあった方が、実力を発揮できます。
メモをお守り代わりに持参する
面接当日に内容を覚えられないときは、メモをお守り代わりに持参するのも良いでしょう。もちろん本番環境でメモを見るのはご法度ですが、面接開始時間ギリギリまでメモに目を通しておけば、記憶力を最大限生かしやすくなります。
お守り代わりのメモの内容は、文章ではなく「要点を箇条書きにまとめたもの」がおすすめ。短文やキーワードを見ただけで、頭の中でスラスラと文章を作れるように練習しておきましょう。詰まりやすい部分にマークをつけておくのもおすすめです。
面接で話す内容を覚えておきたい質問項目3つ
ここでは、回答例を押さえておきたい質問項目を3つご紹介します。定例的な質問への回答を覚えておけば、企業や業種が変わっても面接に対応しやすくなります。基本的な質問だからこそ、堂々と答えてライバルとの差を付けましょう。
自己紹介をしてください
自己紹介は、ほぼすべての企業の面接で聞かれる項目です。必ず覚えておくべき回答であると同時に、企業の事業内容や風土に合った要素をアピールする必要があります。自分の第一印象を的確に説明しつつ、簡潔な説明で要約力も伝えましょう。
【回答例】〇〇大学〇〇学部の△△です。学生時代はアルバイトでチームリーダーを経験し、計画的に行動する力を磨きました。人との関わりを大切にしながら、課題に前向きに取り組む姿勢を強みとしています。
将来のキャリアビジョンを教えてください
キャリアビジョンに関連する質問では、「入社後の成長意欲」や「企業との方向性の一致」を評価されます。ポイントは、入社後数年の「短期的な目標」と、将来を見越した「長期的な目標」をセットで話すこと。抽象的な説明は避け、具体的な貢献のかたちを伝えましょう。
【回答例】まずは現場で経験を積み、周囲から信頼される人材になることが目標です。将来的にはチームをまとめ、課題解決をリードできる存在を目指しています。貴社で長期的に成長していきたいです。
最近気になっているニュースはありますか?
時事問題に関する興味や関心も、面接で聞かれやすい項目の一つ。この質問では、社会への関心や思考力が評価されます。ニュースの内容自体よりも、「関心を持った理由」や「どのように捉え、何を考えたのか」を伝えることが大切です。業界に関連する話題を選ぶとより効果的です。
【回答例】生成AIの活用に関するニュースが気になっています。効率化だけでなく、使い方次第で新しい価値を生み出せる点に魅力を感じます。自分も新しい技術を前向きに取り入れられる社会人になりたいです。
面接用の内容を覚えられない人は「REALME」を活用しよう!
面接用の内容を覚えられなくて不安な人は、就活をサポートしてくれるツール「REALME」を活用してはいかがでしょうか。ここからは「REALME」をおすすめする理由を3つご紹介します。
AIとのリアルな面接で志望企業の内定を判定できる
「REALME」ではAI面接が受けられます。面接を受けると、AIが自身の面接データと過去に志望企業の最終面接に進んだ学生のデータを比較して、現時点での内定獲得の可能性を算出してくれます。内定判定は、A+・A・B+・B、などの10段階で表され、客観的な視点で自分の現在地が把握できます。
本番前に自分の立ち位置を知り、内定判定が向上するように面接での受け答えを改善できれば、最適なタイミングで志望する企業にエントリーできるでしょう。
合格ライン就活生のAI対話データが見られる
「REALME」には、志望企業の合格ラインにいる就活生のAIデータが閲覧できる機能もあります。優秀な就活生のESや面接回答をテキストで見ることによって、自分の改善点や足りない部分が把握でき、今後の就活の参考にもなります。
自分1人では分からないような新たな課題を見つけ、改善していける点は大きなメリットといえるでしょう。
AI面接で客観的に自己分析ができる
「REALME」のAI面接を受けるとAIから詳細なフィードバックが受けられるため、客観的な自己分析ができます。AIによる精密な分析により、就活で重視される「成長意欲」「ストレス耐性」「柔軟性」などの14項目の能力が10段階の点数で可視化され、自分の隠れた強み・弱みが分かります。
客観的な自己分析を自己PRや志望動機に活かして、効率的に内定をつかみましょう。
事前準備や対策で覚えられない状況を克服しよう!
面接のために準備した内容を覚えるには「自分への理解を深める」「要点をまとめたメモの作成」などの対処法が有効です。また、適度な緊張を味方につけることも大切です。
面接の事前準備を抜かりなく行いたい方は、就活をサポートしてくれるツール「REALME」を活用してはいかがでしょうか。気になる方は詳細をご覧ください。

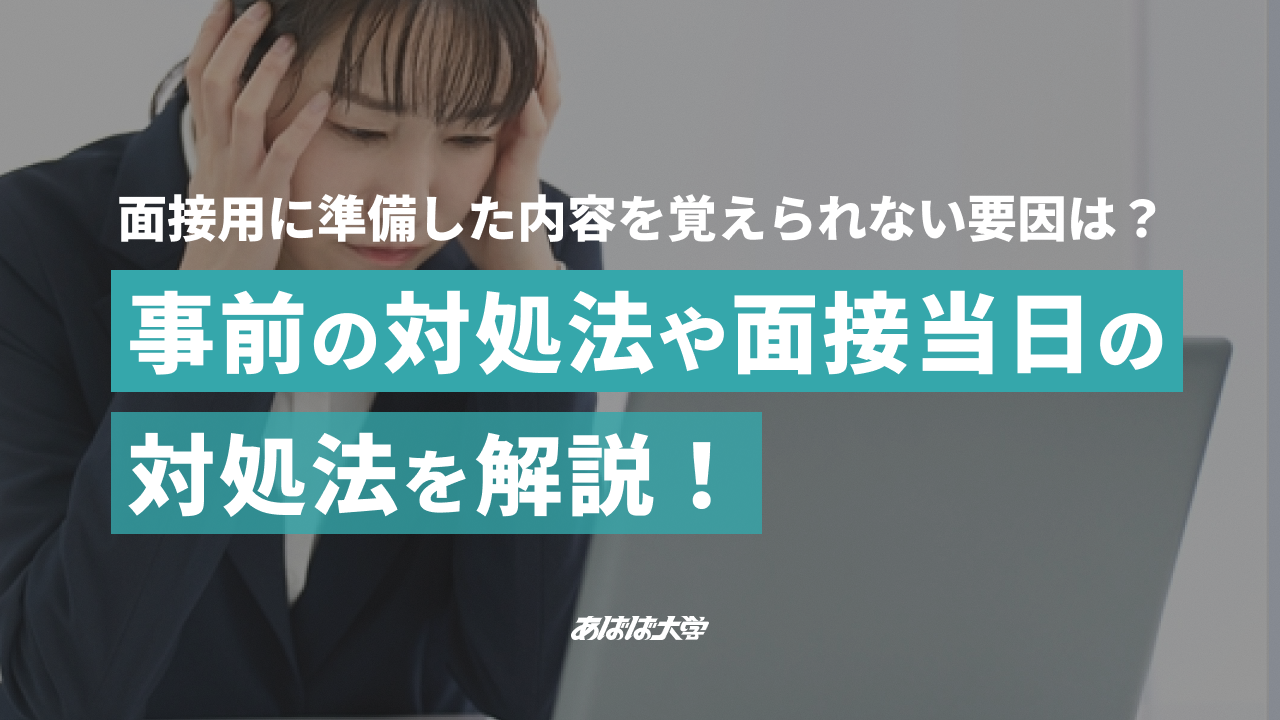
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)