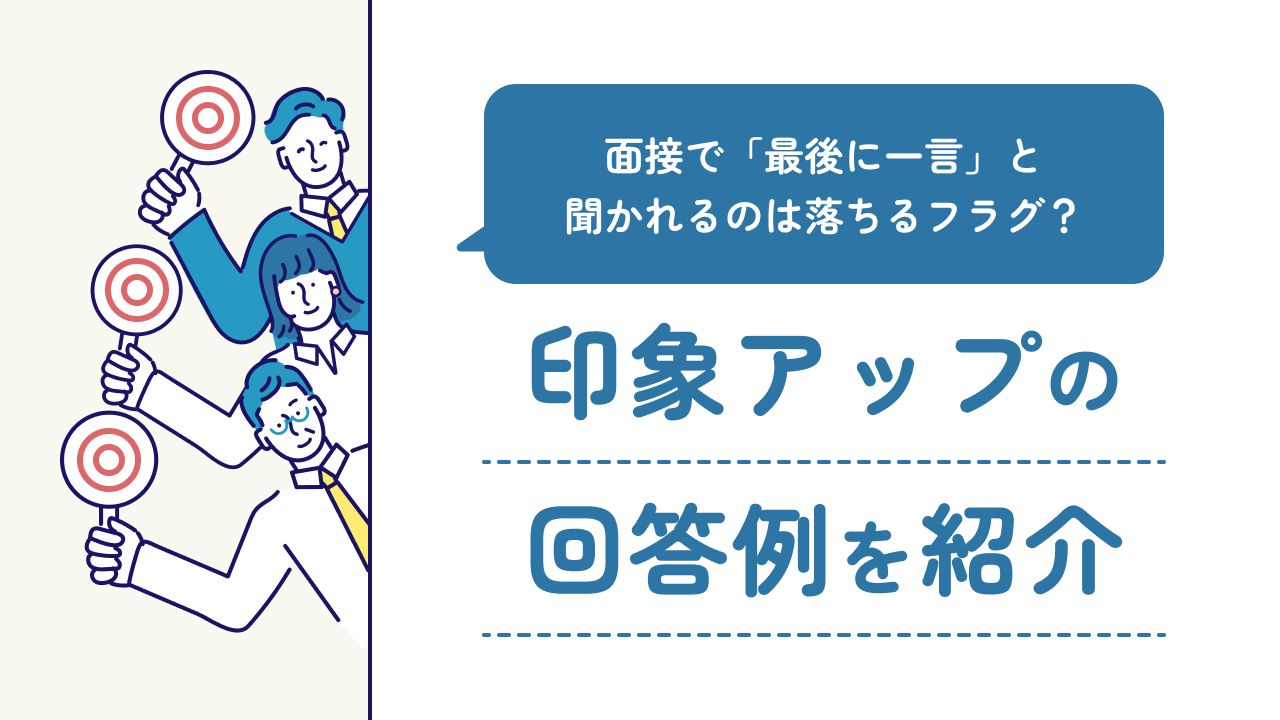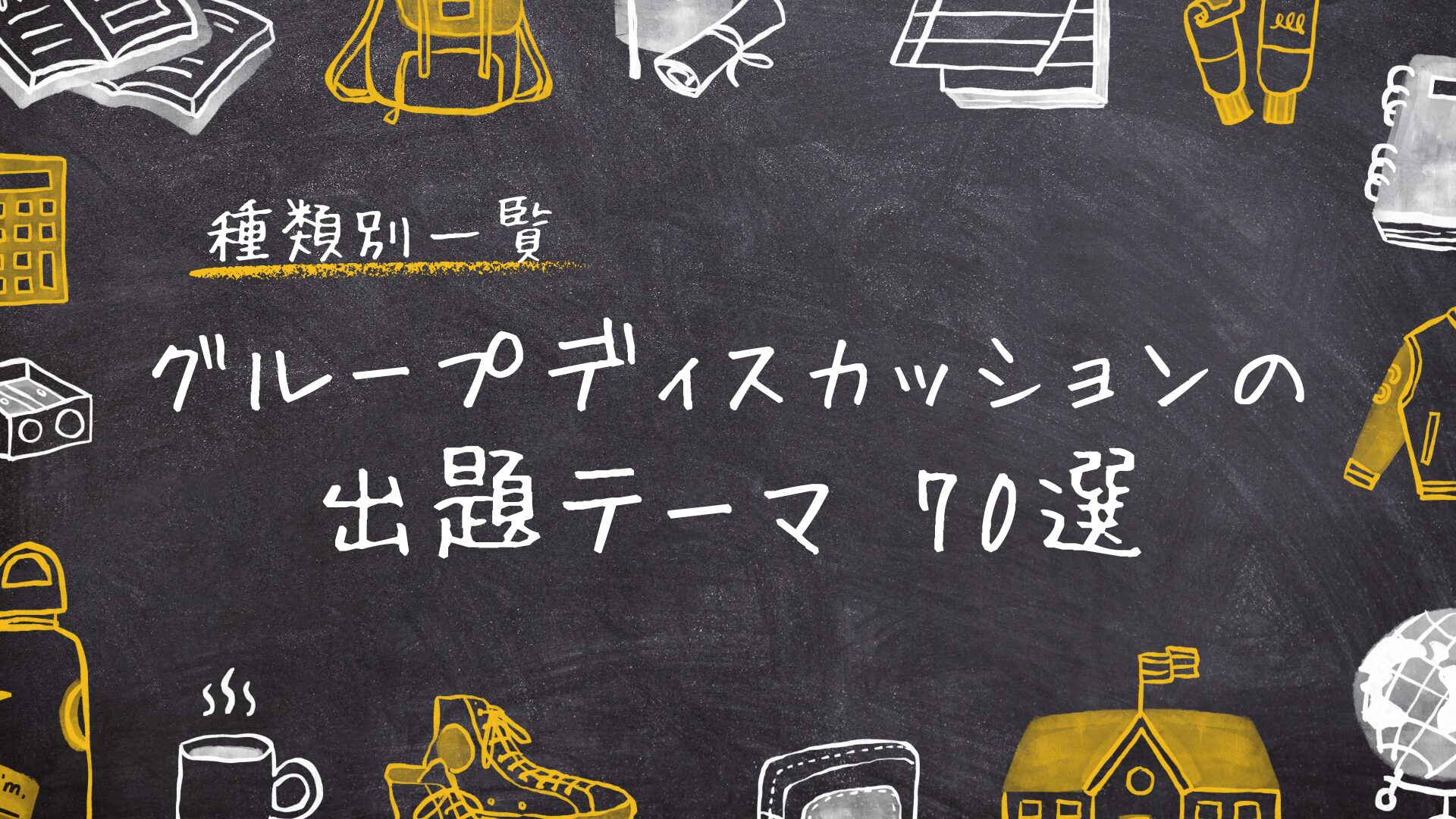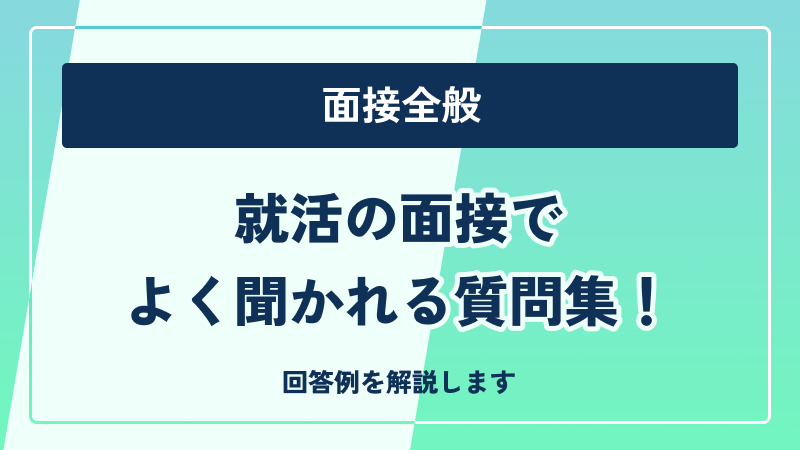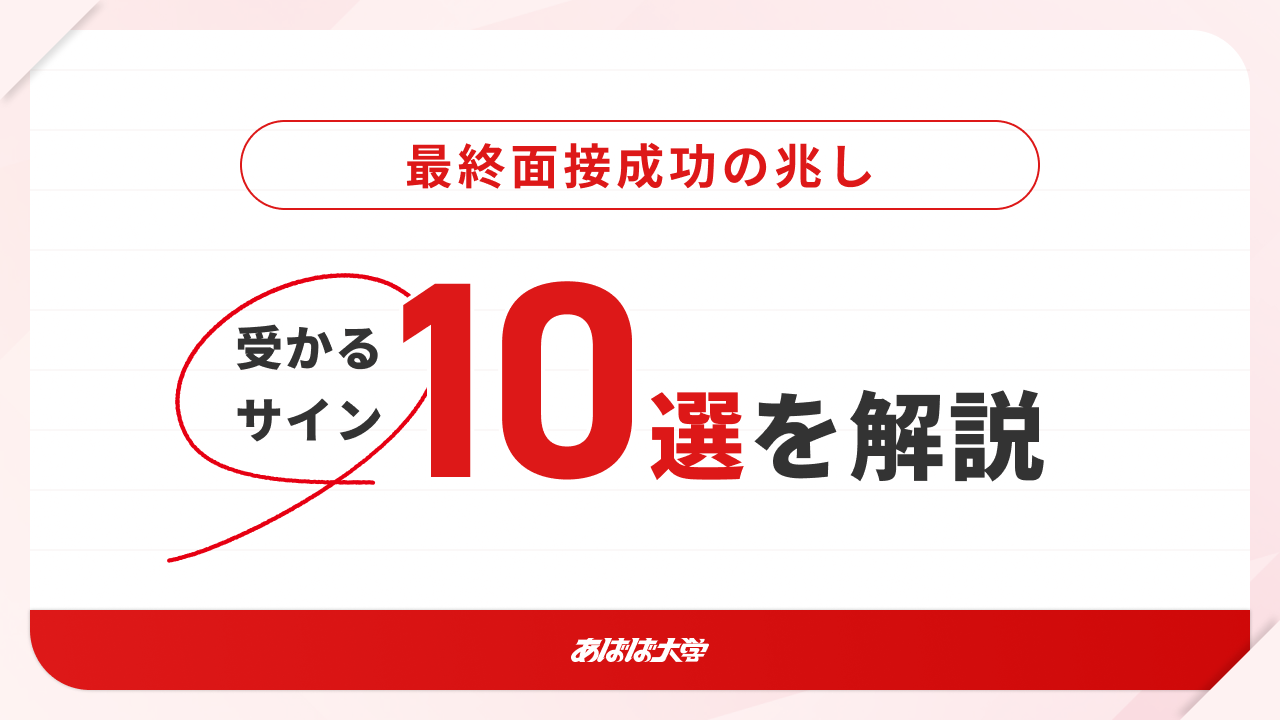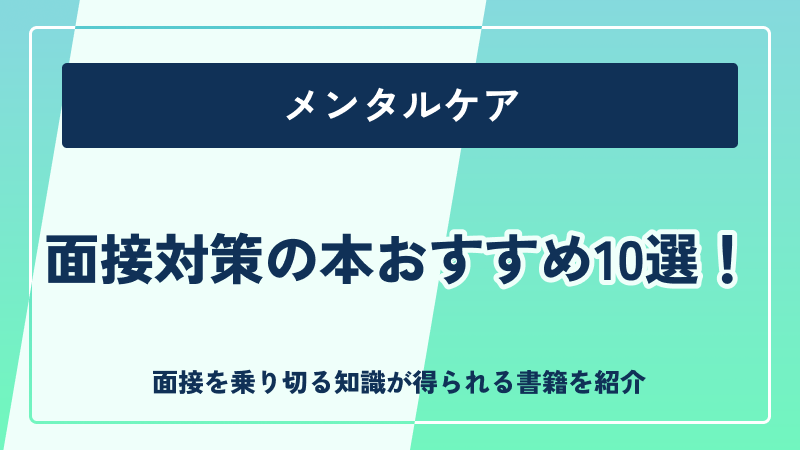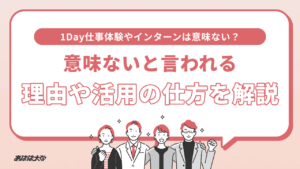採用面接を受けるにあたって、下記のような悩みを持つ人もいるのではないでしょうか。
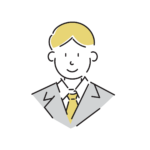
面接練習に行ってきたけど、何をすればいいかわからなかったよ
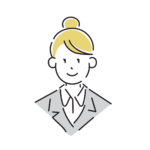
忙しくて面接練習できなかった
本記事では練習なしで面接に臨む場合のリスクや、最低限やっておいた方がよい対策を紹介します。記事の最後には、面接やES、自己PRの対策が可能な就活対策サービス「REALME」についても紹介します。就活の準備がこれひとつで完結できるためおすすめです。
採用面接は練習なしでも平気?
練習なしで面接を受けることは絶対に避けた方がよいでしょう。面接の対策をした人としていない人では結果に大きな差が表れます。
練習をせずに面接に臨むと採用担当者に面接の練習をしていないと気付かれる場合もあるため、よい印象を持たれません。
そのため、自分には練習が不要していると感じる人は採用面接を受ける前に必ず練習をしておいた方がよいでしょう。
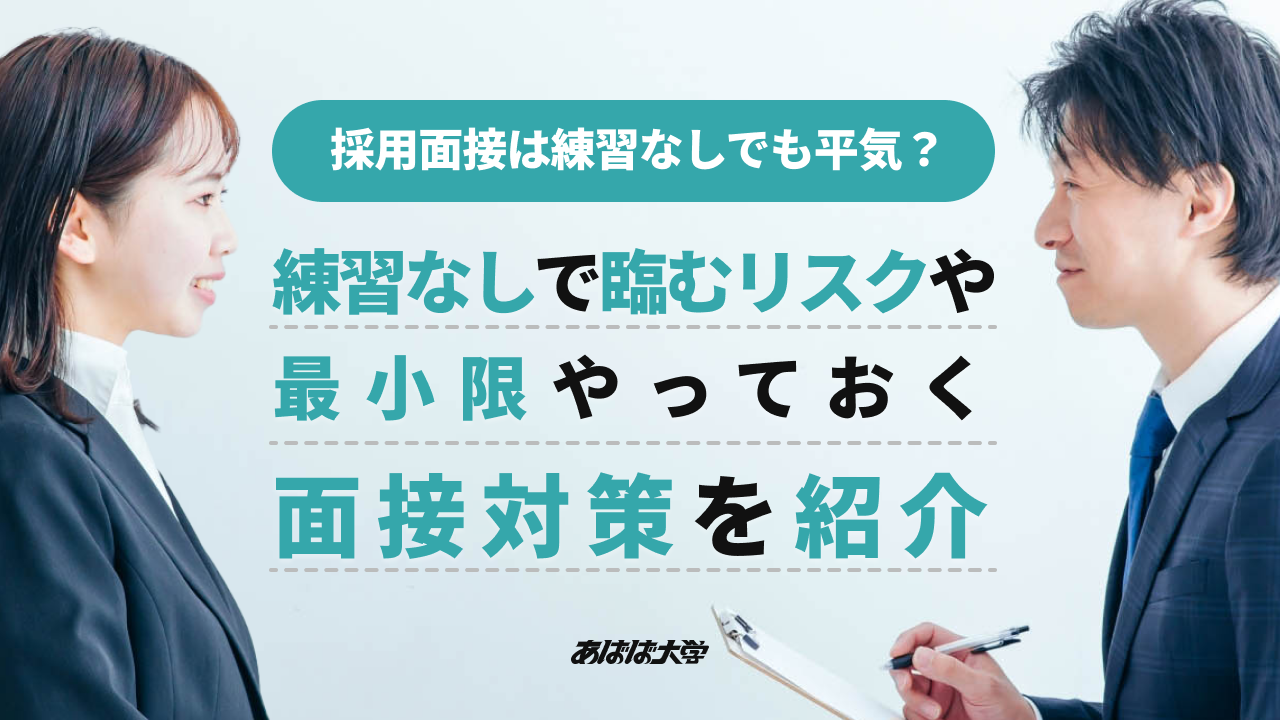
面接練習なしで本番に臨む人のよくある理由
就活では「面接の練習をしないと」と思いながらも、実際は準備せず本番に挑む学生もいるでしょう。時間がなくて後回しにしたり、何を練習すればいいかわからなかったりして「なんとかなる」と思ってしまうと、後悔するかもしれません。ここでは、面接練習なしで本番に臨む人のよくある理由を紹介します。
練習に割く時間がもったいない
面接練習に取り組むまでの準備って、意外と手間がかかります。自己PRの整理や志望動機の見直し、過去の経験の棚卸しなど、やることが多くて「面接練習のやる気がない…」と感じる学生もいるのではないでしょうか。
ほかの課題や選考対策、授業、アルバイトを優先してしまい「時間を割く価値ある?」と後回しにしてしまいます。しかし準備を省くほど、当日の受け答えに不安が残りやすいため、短時間でも効率よく練習する方法を見つけるのが大切です。
答えを暗記すれば大丈夫と思っている
「よくある質問の答えだけ覚えておけば何とかなる」と考える人もいるでしょう。また自己紹介や志望動機、ガクチカは「テンプレがあるし、暗記すれば本番で困らない」と感じる人もいます。しかし、実際の面接は想定外の深掘りや切り口の違う質問を投げかけられます。
普段から話すのが得意だったり、瞬発力に自信があったりする人ほど「練習しなくても対応できる」と判断してしまいがちです。ただし暗記だけでは、会話の流れを変えられた瞬間に答えが崩れたり、表情が固くなったりするため注意しましょう。面接は暗記ではなく「伝える力」が試される時間です。

面接練習なしで臨むリスクは?
面接の練習をせず本番に臨む場合はさまざまなリスクがあります。「面接練習はしなくてもよいのでは?」と考えている人は、どのようなリスクがあるのかを事前に理解したうえで判断しましょう。
質問に対してうまく答えられない
自己PRやガクチカ、長所・短所など、どのような業界を志望しても必ずといってよいほど面接で聞かれる質問が多数あります。
こうした基本的な質問は、企業研究や自己分析がしっかりできているかを確認する目的があります。答えられなければ、入社意欲が低いと感じられて不合格になる可能性が高まるでしょう。
一貫性のない回答をしてしまう
練習なしで面接に挑むと、一貫性のない回答をしてしまうリスクが上がります。面接では、自己PR・志望動機・逆質問・ガクチカなどさまざまなテーマで発言の機会があります。すべての回答において、全体で一貫性のある内容であることが大切です。
一貫性のない回答をすると、面接官に「プレッシャーに弱い」「その場限りのことを言っている」と思われてしまいがちに。練習が不足している場合、自分のなかで要点を整理する機会に恵まれず、回答に矛盾が生じる可能性があります。
論理的に回答できなくなる
論理的に回答できなくなることも、練習なしで面接に臨むリスクの一つです。たとえば多くの企業では、自己PRに1分程度の時間を与えられます。練習をしていないと、どの部分を強調してアピールすれば良いのかわからず、思いつくままに情報を詰め込むような内容になってしまいます。
自分の強みやスキルなどを論理的に説明できず、面接官に良い印象を与えられません。また論理性に欠けた説明は説得力も乏しく、自分ならではの魅力を伝えきれないことも考えられます。
マナー違反をする可能性がある
練習不足のまま面接に臨むと、知らず知らずのうちにマナー違反をしてしまう可能性もあるでしょう。面接はれっきとしたビジネスシーンの一つ。社会人として求められる基本的なマナーやルールを覚えていないと、常識が備わっていない人物だと思われてしまいかねません。
面接では言葉遣いだけではなく、入室や退室、化粧や髪型を含めた身だしなみなども審査対象です。間違った動きやマナーをしていると、準備不足であることが露呈あれ、本気度や情熱を疑われてしまいます。

最小限やっておく面接対策は?
自分には練習が不要だと感じる人や、何をすればよいのか分からない人でも、最低限やっておいた方がよい面接対策があります。以下の点だけでも押さえておくとよいでしょう。
定番の質問は対策する
前述の通り、志望動機・ガクチカ・自己PRなどは、どの企業でも必ずといってよいほど聞かれる定番の質問です。これらの回答はあらかじめ準備し、本番でスムーズに伝えられるようにしましょう。
事前の面接練習を怠ると面接本番に適切に回答することが難しいです。また、1次面接を突破できても2次面接や最終面接に進むと準備の粗さが目立ってしまう可能性があります。その場しのぎで回答していると一貫性がない内容になりかねないので、定番の質問は対策を最低限行う必要があります。
笑顔や受け答えを意識する
どのように対策をすればよいのか分からない場合は、笑顔で受け答えする練習から始めてみてはいかがでしょうか。
硬い表情や不安げな表情では、採用担当者も不安に感じてしまいます。そのため、明るく笑顔で受け答えし、自信を持った姿をアピールしましょう。
笑顔で元気にハキハキと挨拶をされて嫌な気持ちになる人はいません。練習不足で面接本番に臨むことになったとしても、笑顔や気持ちの良い挨拶でカバーできるように意識しましょう。
入退室の動きを確認する
回答の内容や受け答えだけではなく、入退室の流れも確認するとよいでしょう。立ち居振る舞いや仕草などの所作も評価ポイントのひとつです。入室する際のノックや最初の挨拶、着席の際や終了後の挨拶、退室時など、一連の流れを通して練習しましょう。
基本的なマナーが身についていて、スムーズな流れで入退室ができれば採用担当者からも良い印象を持ってもらいやすいです。部屋に椅子を置いて、家族や友人に面接官役をやってもらって練習することがおすすめです。

面接練習をするときに気をつけるべき項目3つ
面接練習は「とりあえず声に出せばOK」ではなく、意識するポイントを押さえると本番で安定した回答になります。特に大事なのは、長さや話し方、回答がズレていないかの3つです。練習で丁寧に整えていくと、説得力や印象が一気に変わります。
長すぎる回答になっていないか
面接でつい熱が入りすぎて、気づけば長々と話してしまうのは、よくある失敗の一つです。回答が長すぎると、面接官は途中で情報を整理しきれなくなったり、結局「何を伝えたいのか」がぼやけてしまったりします。だからこそ、1つの質問に対して「結論→理由→具体例→再結論」の流れで、要点だけをまとめて話す工夫が大切です。難しい表現より、伝えたいことが正しく届くほうが、印象はずっと良くなります。長すぎる回答ではなく「伝わる長さ」に調整してみましょう。
早口になっていないか
面接になると、緊張でつい早口になってしまう人もいるでしょう。早口は「焦っている?」「準備不足なのかな?」という印象につながりやすく、もったいないです。どれだけ回答が良くても、落ち着きのない話し方だと伝わりきらないこともあります。意識的に、普段よりワンテンポ遅く話すくらいでちょうどよく、ゆっくり話すと呼吸が整って言葉を整理しやすくなります。練習するときはスマホの録音でチェックすると、自分のクセがよくわかり改善しやすいでしょう。
ズレた回答をしていないか
面接でよくあるのが「質問と答えが噛み合わない」パターンです。自分ではしっかり答えているつもりでも、面接官が知りたい内容から外れてしまうと、どうしても「話を理解していない」「コミュニケーションが弱いのかな?」と判断されてしまいます。質問を受けたらまず短く結論を伝え、次に必要な補足を乗せるイメージで話すとズレにくいでしょう。聞かれていないことは長々と語らず「何を聞かれているのか?」を一度頭の中で整理してから答えるのがコツです。録音して練習すると、ズレているかどうかが客観的にわかります。

面接練習を行うメリットは?
ここまで練習をせずに面接に臨むリスクを紹介しましたが、練習にはどのようなメリットがあるのでしょうか。リスクとメリットの両方を理解しておきましょう。
自然な受け答えができる
あらかじめ聞かれやすい質問を想定しておくことで、スムーズに受け答えができるでしょう。またその際、声に出して回答する練習を繰り返すことがおすすめです。
口頭で何度も練習することで、どのような話の展開方法や間の取り方が身に付きます。それらが身に付いていれば、本番で想定外の質問をされても焦らず冷静な対応ができるでしょう。
回答を伝わりやすくできる
自分の頭で伝えたいことをイメージできていても、それを分かりやすく言語化することは難しいです。伝えたいことを正確にかつ分かりやすく伝えるためには、言葉選びや表現方法、話の展開など、言い回しを練習する必要があります。
伝え方を間違えてしまうと、魅力が上手く伝わらず、誤解を与える可能性もあるでしょう。そうすると悪い評価につながってしまう恐れもあるため、採用担当者に伝えたいことを的確に伝えられるよう欠かさず練習しましょう。
落ち着いて対応できる
入念な準備をして練習を事前に行うことで、心にゆとりを持って落ち着いた対応ができるでしょう。自信を持って面接に臨めば、本来の魅力をアピールできます。
練習なしでいきなり本番に挑むと、緊張の影響で基本的なミスや質問に回答できない恐れもあるでしょう。少しでもリラックスして本番に挑むためにも、面接の練習は重要です。
よりよい話し方に改善できる
採用担当者に自分の魅力を上手く伝えて好印象を持ってもらうために、回答内容だけではなく、声のトーンや表情、姿勢などを意識することも大切なポイントです。
たとえば、良い自己PRをしても、早口でまくし立てるように話すと、採用担当者は内容を理解しづらく、あなたに魅力を感じられません。聞こえづらいほど小さな声で話していたり、不安げな表情や下を向いてばかりで目が合わないなど、自信のなさが表れる態度だと良い印象を与えないでしょう。
より良い話し方に改善できるよう、練習を重ねて客観的に自分を観察し、課題を洗い出すことが大切です。
客観的な視点で改善ができる
面接の練習を行う際に、家族や友人などに聞いてもらうことで客観的な視点でアドバイスをもらうことができます。
回答内容を入念に準備していても、文字に起こしただけでは面接本番でどのような評価を受けるのかまでは把握できないでしょう。内容自体に問題がなくとも、マナーや伝え方、話し方の部分で印象は大きく変わります。自分以外の人に聞いてもらうことで、自分では気が付けなかった改善点に気が付くかもしれません。
家族や友人などに面接官の役をやってもらってアドバイスを受けたり、録画して自分でチェックするなどするとよいでしょう。
面接練習なしでも受かる人の特徴
ここでは、面接の練習をしなくても受かる人の特徴をご紹介します。何度練習しても受からない人と、練習不足でもサラリと合格をつかみ取る人との違いは、どのような部分にあるのでしょうか?本番に強い人の特徴を把握して、改善の指針にしていきましょう。
物事を論理的に考えて言語化するのが得意
面接練習なしでも受かる人の特徴として、物事を論理的に考えて言語化するのが得意であることが挙げられます。日常的に、あらゆる物事を論理的に考え、文字や言葉としてアウトプットする習慣を持っています。
語彙力や文章構成力にも優れており、思考をすぐに明文化できるのが強みです。また洞察力や想像力にも長けており、面接官からの質問の意図を即座につかみ、適切な文脈で回答できます。本番に強い人は、さまざまな非認知能力が総合的に高い人ともいえるでしょう。
就活軸が明確である
就活軸が明確な人も、練習せずとも合格できる場合があります。就活軸とは、就職活動をする際に企業を選ぶ基準になる「譲れない条件」のこと。自分のなかで絶対的な判断基準を持つ人は、思考や言動にも一貫性があり、面接官に自信や誠実さを伝えられます。
ゼロから志望動機を考え直さなくても、企業を選んだ理由が最初から明確であるため、練習せずとも自信を持って志望動機を答えられるのが強みです。働き方やキャリアプランのイメージも定まっており、回答に窮することもありません。
企業研究や自己分析が十分にできている
練習しなくても合格できる人の特徴としては、企業分析や自己分析が十分できていることも挙げられます。わざわざ文章として考えなくても、脳内に蓄えられた知識のみで対応できます。総じて、柔軟性や対応力、その場での文章作成能力も高い人といえるでしょう。
自分のなかで一貫性のある思考や価値観を持っているため、深掘り質問にも迷いなく答えられます。わからない部分は素直に伝えつつ、持っている知識を工夫して回答を作成する能力も高い傾向に。自己PRや志望動機などでも、具体的なエピソードを交えつつ話せるのが強みです。

時間がない!練習なしで面接を迎えたときの対処法
ここでは、練習なしで面接を迎えてしまったときの対処法をご紹介します。学業や生活に追われていると、どうしても練習時間を捻出できないこともありますよね。練習不足を面接官に悟られないコツを知り、合格につなげていきましょう。
最低限のマナーを守って対応する
練習なしで面接を迎えたときは、最低限のマナーを守ることを心がけます。前項でも触れたように、面接にはさまざまな「暗黙のマナー」が存在しています。入室や退室はもちろん、面接中の目線の配り方などのマナーは最低限押さえておきましょう。
面接官にとって、基本的なビジネスマナーは「足切り」するかどうかのボーダーラインです。ほかの部分に多少不安が残っても、最低限のマナーさえ守れていれば、審査対象には残れる可能性が高いでしょう。
身だしなみに気を付ける
面接官が求めるマナーのなかには、身だしなみも含まれます。練習不足で本番に臨む場合にも、服装・髪型・髪色・化粧などには最低限気を配りましょう。初対面である面接官にとって、身だしなみによる第一印象は合否の結果に大きな影響を与えます。
清潔感はあることは大前提として、誠実な印象を与える見出しに整えることが大切。たとえクリーニングしたスーツでも、着こなしによってイメージは大きく変わります。肩周りのサイズ感や口紅の色合いなど、細かなポイントも要チェックです。
沈黙しないようにする
準備不足の面接では、質問にスムーズに答えられないシーンも想定されます。しかし面接において「沈黙」はタブーの一つ。回答に迷うこと自体は大きな問題ではありませんが、一言の断りもなく沈黙してしまうと、準備不足やプレッシャーへの弱さを面接官に感じさせてしまいます。
とくに志望動機をはじめとする「定番の質問」で沈黙してしまうと、志望度の低さを疑われてしまうでしょう。少なくとも聞かれやすい質問に関してだけは、即座に答えられるよう備えておくべき。もしすぐに言葉が出てこない場合でも、「少々お待ちください」のような断りを入れましょう。
明るく笑顔で対応する
準部不足で面接に挑む場合でも、絶対に忘れないでほしいのが「笑顔」。もちろん笑顔が素敵なだけで合格できるわけではありませんが、明るく快活な印象は無条件に高評価につながります。
自信がなくても、笑顔でハキハキとした受け答えを心がけましょう。たとえ表面的であっても、明るい振る舞いは自信をアピールするための武器になります。ポジティブな人間性を伝えられれば、「入社後も周囲の人間とうまく働けそう」と思ってもらえる可能性が上がります。
面接で最低限答えられるように練習するべき質問
面接では企業ごとに質問内容は違っていても「どの会社でもほぼ必ず聞かれる定番質問」が存在します。ここを押さえておくと本番で焦りにくく、落ち着いて話せるようになります。志望動機やガクチカなど、頻出質問への準備は面接対策の土台として練習しておきましょう。
自己紹介をしてください。
自己紹介は、30〜40秒かつ120〜150文字程度が適度な長さです。経歴を細かく並べて自己紹介するより「自分が何をしてきた人なのか」が相手にすぐ伝わる構成がポイントです。話す順番は、名前→所属(学部・学科)→力を入れた取り組み→面接への一言の流れにしておくと、簡潔に伝えられます。
【例文】
「〇〇大学△△学部の□□です。在学中は~に取り組み、●●した結果、▲▲を身につけました。本日はよろしくお願いします」
学生時代にがんばったことを教えてください。
ガクチカは、1分前後かつ200〜250文字程度で答えるのが適切な長さです。話す際は「結論→行動→結果→学び」の順番で伝えましょう。面接では、最初の10秒で何に取り組んだかを言い切るのがコツです。また数字や工夫した点を入れると、説得力がアップします。たとえば「サークルでイベント集客を改善し、SNS運用を担当。投稿頻度とテーマを整理して参加率を○%向上させました。課題発見と改善の進め方を学びました」のように、具体性+学びのセットでまとめるのが理想的です。
長所と短所は何ですか?
長所・短所は1分前後かつ200〜250文字程度にまとめるのが理想です。まず長所を結論から伝え、次に長所が活きた具体的なエピソードを簡潔に添えると、説得力がグッと増します。短所だけ話したまま終わらせるとマイナスな印象を与えるので「改善のために工夫していること」までセットで伝えるのが必須です。短所→改善策の構成ができていれば、面接官は「成長意欲がある人」と判断しやすいでしょう。
【例文】
「長所は、物事を継続して取り組む粘り強さです。ゼミでは毎週の分析レポートを欠かさず提出し、改善点を積み上げ成果につなげました。短所は慎重になりすぎる点ですが、期限を決めて判断するようにし改善しています。」
志望動機を教えてください。
志望動機は、1分〜1分半かつ230〜300文字程度にまとめるのがベストです。構成は「結論→過去の経験→なぜその会社か→入社後のビジョン」がおすすめです。抽象的な言葉だけだと内容が薄く見えるので、自分の経験と会社の特徴がどう結びつくのかを具体的に語りましょう。企業研究が浅いと深掘り質問に弱くなるので、事業内容や他社との違いを踏まえて話せると説得力が高まります。最後は「貢献したい領域」を一言添えると印象がアップするでしょう。
【例文】
「人の選択を支える仕事に魅力を感じ、人材業界を志望しています。アルバイトで接客改善に取り組んだ経験から、課題発見と提案力を活かして御社のサービス価値向上に貢献したいと考えています。」
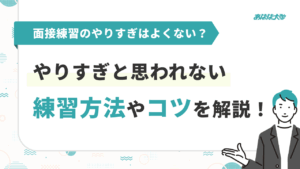
面接練習なしは避けて「REALME」を使った面接対策がおススメ!
面接の合格率を高めるために、練習が欠かせないことを紹介してきました。しかし、どのような対策をすればよいのか分からない人もいるでしょう。不安に思う人は就活対策サービス「REALME」のAI面接を使って面接対策をしてみてはいかがでしょうか。
AI面接で志望企業の内定判定を確認
「REALME」のAI面接を受けることで、志望企業の内定判定が確認できます。志望企業の最終面接に進んだ学生のデータと自分のデータを比較した上で内定の可能性を割り出してくれるため、自分の正確な現在地の把握が可能です。
また、「REALME」のAI面接は何度でも実施が可能です。現在の就活状況に応じてAI面接を受け直し、内定の判定向上に繋げましょう。家族や友人相手に練習するのがどうしても恥ずかしい人は、「REALME」のAI面接を活用してみてはいかがでしょうか。
AI面接で客観的な自己分析が可能
「REALME」のAI面接を受けると、面接内容をもとに14項目の能力を点数化してもらえます。強み・弱みが明確になるため、客観的な視点で自己分析を行うことが可能です。客観的な視点から自身のアピールポイントや不足しているところを把握して、質問の回答内容を効率よく準備しましょう。
合格ライン就活生のAI面接データを活用
「REALME」では、志望企業の合格ラインをクリアした学生の面接回答例や、自己PR・ガクチカの閲覧が可能です。面接の練習方法や自己PRの作り方がわからない人は、他の学生の志望動機や自己PRを確認し、志望企業の質問内容や回答例などを参考にするとよいでしょう。面接内容を把握することで、改めて面接対策の重要性を知ることができるでしょう。
面接練習なしでよいと考えずにしっかり対策しよう!
普段からあまり緊張しない人は、面接練習を不要に感じることもあるでしょう。なかには、面接練習の始め方がわからず、練習を行わずにそのまま本番を迎えた人もいるでしょう。
しかし、就活において面接の練習は必要不可欠です。面接本番で混乱してしまい、本来の自分をアピールできなかったといった失敗をしないためにも何度も面接練習を重ねましょう。
効率的に面接練習をするならば、就活対策サービス「REALME」のAI面接をおすすめします。