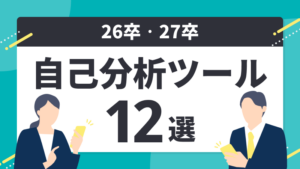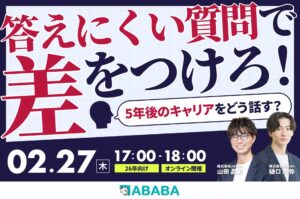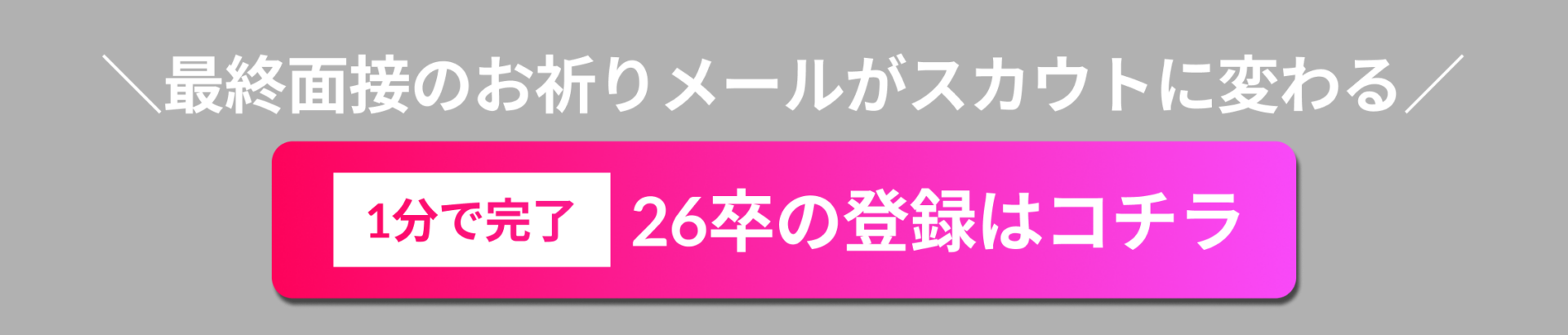「面接練習」や「面接対策」についてどのようにするとよいか、また練習は必要かと疑問に思う人もいるでしょう。結論から申し上げますと、面接練習は必要です。なぜ「面接練習はしないほうがよい」などの意見があるのでしょうか。
本記事では、練習しない方がよいと言われる理由や面接練習の必要性や重視するポイントについて解説します。また、記事の最後には株式会社ABABAが提供する就活版全国共通模試ツール「REALME」についても紹介します。
面接練習はしない方がいいと言われる理由
「面接練習はしない方がよい」と言われるのには2つの理由があります。
1つは、面接ではしばしば想定していない質問をされる場合があるためです。物事を即座に言語化できる人や自己分析や企業研究などを徹底する人は、面接練習を重ねずとも臨機応変に対応できるでしょう。そういった人からすると「面接練習をしても意味がない」と捉えることができるので、意味がないという声が挙がるのだと考えられます。
2つめに、丸暗記した志望動機や自己PRなどをアウトプットしてしまう可能性があるためです。本番の面接で、棒読みまたはセリフのように丸暗記した内容を話してしまうと、面接官にマイナスな印象を与えることがあります。
ただし、面接に慣れていない人は面接を練習する方がいいです。ここからは、面接練習の必要性についてさらに詳しく説明し、意識したいポイントについて解説します。
面接練習をしないリスクとは
面接練習をしないことにはさまざまなリスクがあります。面接では想定外の質問をされることも多いことから、練習は意味がないと感じる人もいるでしょう。しかし、練習せずに面接に臨んだ人と練習をした人では合格率に差が出るのが事実です。
以下では、練習をしなかった場合のリスクについて解説します。
面接マナーを間違える
面接では、質疑応答や自己PRの内容だけではなく、基本的なマナーについても見られています。入退室の際や面接中の態度など、社会人としての基本マナーが間違っている可能性もあるでしょう。基本的なマナーが身についていないと判断されると、不合格の可能性が高まる恐れがあります。
練習することで自分の癖や姿勢、話し方などを客観的に見て改善できますが、練習していない場合は自信が持てず、不安や緊張が態度や表情に表れてしまう可能性もあるでしょう。
回答に一貫性がない
就職活動における選考は、複数回にわたって実施されます。ESの提出から一次面接・二次面接を経て最終面接まであるケースがほとんどです。
志望動機や自己PR、自分の長所などの質問は、どのフェーズでも聞かれる可能性があり何度も同じ質問をされることがあります。そうしたときに、練習をせずその場しのぎで回答してしまうと、「回答に一貫性がない」と判断される恐れがあるでしょう。
一貫性のない回答だと、話に信憑性がないと思われて不採用の可能性が高まってしまいます。
深堀り質問に対応できない
面接には頻出質問があり、ある程度は想定して回答を準備して臨む人が多いでしょう。しかし、本番では想定内の質問だけが来るとは限りません。時には想定外の質問をされたり、より深掘りして質問されることもあるでしょう。
想定される質問への回答内容を準備していても、面接練習をしていなければ想定外の質問や深掘り質問に対して上手く対応できない場合があります。
深掘りされてもしっかり答えられるよう、入念な自己分析や企業研究による対策が必須です。質問にきちんと答えられなければ、準備不足だと思われて志望度が低いと判断されてしまう可能性があります。
面接練習するメリット
面接練習は、回答内容を丸暗記してアウトプットするためではなく、面接の対応力をつけるためなど、さまざまなメリットがあります。
ここでは面接練習することのメリットについて解説します。
質問に対して臨機応変な対応ができる
面接練習を重ねることで、質問に対して臨機応変に対応ができるようになります。
面接では想定外の質問をされる場合があるため、準備した回答を丸暗記しても、想定外の質問に慌ててしまう可能性があります。
そのため、自己分析や企業研究を十分に行い、想定外の質問にも対応できるよう面接の練習を重ねましょう。練習を繰り返すうちに、自分の言葉で落ち着いて回答できるようになります。
一貫性のある主張ができる
面接の練習を重ねることで、「一貫性のある主張」や「アピール」ができます。
一方で、その場しのぎで対応すると、発言内容にブレが生じる可能性があります。
面接官は、さまざまな視点から質問を投げかけ、一貫性のある回答が返ってくるかを見極めています。面接練習を行うと客観的なフィードバックが受けられるため、発言のブレや改善方法の把握が可能です。面接練習を繰り返し行うことで、良い評価をもらえる可能性が高まるでしょう。
自信を持って答えられる
面接練習を重ねることで、面接の雰囲気に慣れるため、不安や緊張が緩和されます。緊張が緩和されると、本来の自然な表情や仕草とともに、落ち着いて、堂々と話せるようになるでしょう。
そのため、慣れ合いでなく緊張感のある環境で、「面接マナー」を意識した練習が必要です。
面接練習のやり方
必要だとは思っていても、やり方が分からなくて練習できないという人もいるでしょう。
面接練習のやり方にはいくつかの方法があります。以下でおすすめの練習方法を4つ紹介するので、これから面接を受ける方はぜひ参考にしてみてください。
スマホで動画撮影する
現在もっともスタンダードともいえる基本的なやり方が、スマホでの動画撮影です。
面接を想定した受け答えを動画で撮影して確認することで、自分の話し方や姿勢などを客観的にチェックできます。
自分で気が付かなかった癖がないかどうか、姿勢が正しいかどうかや、声の大きさや話すスピードが適切であるかどうかなどを客観視できるため、自身の改善点を見つけやすいでしょう。
可能であれば椅子や机も用意して、入室から退室まで一連の流れを撮影すると、マナーの部分も含めたチェックが可能です。
YouTubeを活用する
近年はYouTubeが普及しており、面接に関する動画も数多く出ています。それらを活用するのもよいでしょう。
面接の見本や解説動画などを見ながら練習すると、知識も身につくためおすすめです。
質問を投げかけてくれるような、模擬面接の感覚で練習できる動画もあります。想定外の質問を投げかけられることもあるため、自分一人ではできなかった部分まで対策ができるでしょう。YouTubeの活用は、知識・実践の両面で役立つ方法です。
アプリを活用する
面接練習のアプリも普及しており、種類が豊富です。細かな機能はアプリによってさまざまですが、面接結果や内容のフィードバックがあるものが多いでしょう。
AIによる模擬面接やフィードバックで自分の良い点・悪い点を客観的に見られるため、改善点を把握しやすくなります。
また、面接練習アプリには録音機能や時間計測機能がついているものも多く、非常に便利です。ひとりで面接練習をしようと考えている人は、アプリを活用してみるのもよいでしょう。
友人や家族に協力してもらう
客観的な意見を得るのに最適なのが、友人や家族に協力してもらう方法です。面接官役をやってもらって、模擬面接の形式で練習してみるとよいでしょう。
面接練習の基本は、客観的な視点からのフィードバックです。身近な存在である家族や友人に率直な感想をもらうことで、自身の改善点が客観的に分かります。
練習をする際は、同じく就活中の友人と、面接官役と学生役を交代して練習するのもよいでしょう。学生役だけでなく面接官役もやることで、友人の改善点から自身の改善点に気付ける場合もありおすすめです。
面接練習で重視するポイント
面接では、内容だけではなく伝え方や表情、時間配分なども大切です。以下では、面接練習をする際に重視した方がよいポイントをいくつか紹介します。
練習をより効果的なものにして本番で存分に活かすために、以下のポイントを意識して練習に取り組みましょう。
伝える内容を整理する
まずは伝える内容を整理しましょう。
自己分析や企業研究を行い、自分をどのように企業へアピールしたいかを考える必要があります。アピールポイントを明確にすることで、想定外の質問にも対応できるためです。定型の回答をそのまま使用せず、自分の言葉で話せるように整理しましょう。整理する際は、要点が何かを意識しましょう。
伝え方を意識する
伝え方を意識することも大事です。
「伝える」と「伝わる」は別物です。面接では、自分は伝えたつもりでも、相手に伝わっていない場面がしばしばあります。限られた時間内で、端的に伝えるなら「結論から話す」「簡潔に伝える」「ゆっくりハッキリ話す」ことを意識しましょう。
伝えようとするあまりに、結論に至るまでの経緯を長々と話すと冗長な表現になりがちです。回答が冗長であると、面接官の集中力が途切れ、結局何を話していたか伝わらない可能性があります。質問に対する回答時間は1分程を目安にし、簡潔に伝えましょう。
内容を詰め込みすぎて早口で話してしまうことも伝わりにくい要因の1つです。ゆっくりハッキリ話すことを意識し、1分程度に収まるよう構成を考えましょう。
表情を確認する
面接練習時にどのような表情で受け答えするか確認しましょう。
面接では笑顔が好印象を与えます。ただ、話す内容を考えることに集中するあまり、硬い表情をする人がいます。これは面接初心者の人によくある光景です。
自分の表情については、第三者に確認してもらい客観的なフィードバックを受けることがおすすめです。一方、一人で行う場合は動画を撮影したり、鏡の前で練習することも一案です。
基本的なマナーができているかチェックする
面接マナーが身についているかを確認しましょう。
面接マナーを「知っている」のと「実践できる」は別物です。身だしなみや入退室の所作、お辞儀や話を聞く際の姿勢など、本番の面接を想定して実践しましょう。
一人でも一連の動作の確認はできますが、できれば第三者にチェックしてもらい、フィードバックを受けることが望ましいです。話す内容や伝え方を整理した上で、キャリアセンターやイベントなどに足を運び、本番さながらの環境で面接の練習をしましょう。
時間を測る
学生ひとりあたりの面接時間は限られており、ひとつの質問にかけられる時間は大体1分~2分程度です。長すぎると面接時間をオーバーしてしまったり伝えたいことを上手く伝えられなかったりする可能性があり、短すぎても面接官に熱意を伝えられません。
回答にかかる時間は必ず計測し、長すぎたり短すぎたりしないかどうかを確認しましょう。
その際は面接全体の時間も測ることで、一連の流れをスムーズに進めやすくなります。
回答時間は〇分で、と指定される場合もあるため、時間を確認しながら練習するとよいでしょう。
丸暗記しない
面接に臨む前にある程度質問を予想して、あらかじめ回答を用意してから臨む場合が多いでしょう。ただし、用意した回答を丸暗記することは避けなければなりません。
丸暗記で乗り切ろうとした場合、万が一冒頭を忘れてしまうと頭が真っ白になり、何も回答できなくなることがあります。
暗記したことを思い出しながら話そうとすると、棒読みになったり原稿を読んでいるような印象を与え、面接官に気持ちが伝わりません。練習する際は伝えたいポイントだけを押さえておき、自分の言葉で伝えることが大切です。
また、面接では質問を深掘りされることもあります。その場合は丸暗記では対応できないため、深掘りされたときのことも想定して回答を考えておきましょう。
面接の練習にはAI全国共通模試「REALME」
「臨機応変な対応」や「一貫性のある回答」など面接本番に向け徹底的に準備するならば、面接の練習は必要不可欠です。面接で重視する4つのポイントを意識するためにも、緊張感のある環境で面接練習を心がけましょう。
株式会社ABABAが提供する就活版全国共通模試ツール「REALME」なら自己PRやES、面接などすべての対策が可能です。
AIとの面接で内定判定向上につながる自己分析ができる
「REALME」では、あなたの強みや弱みを客観的に分析し、14項目の能力を点数化してくれます。またAIとの面接内容をもとに改善すべき点や効果的であった内容をフィードバックをしてくれるため自分では気づかなかった長所や短所を把握することも可能です。
「面接練習をしない方がいい」と言われても、客観的なフィードバックを得たい人は「REALME」を活用してみてはいかがでしょうか。
合格ラインを突破した就活生のES・面接回答例を閲覧できる
「REALME」では志望企業の合格ラインをクリアした学生のES・面接回答例を閲覧できます。面接練習を行う際は、回答内容を事前に準備しておくことでより高い成果が期待できます。回答例を参考に、自分の言葉で表現できるように回答内容を作成することをおすすめします。
内定判定によりベストなタイミングでエントリーできる
「REALME」では志望企業の「内定判定」を確認することができます。約20分のAI面接によって、志望企業の最終面接をクリアした学生のデータとあなたのデータを比較して内定の可能性を割り出してくれます。そのため、自分の正確な立ち位置を把握できるでしょう。
「面接練習をしない方がいい」と言われても、本番一発の勝負では不安は残るものです。AIと面接練習を重ね、課題を改善することで自信をもって志望企業へエントリーしましょう。
「面接練習しない方がいい」はNG!選考通過には対策が重要
「面接練習をしない方がいい」と、囁かれることは嘘だと心得ましょう。自己分析と企業研究を十分に行っていて、想定外の質問にも臨機応変に対応できるなら不要かもしれません。ただ、多くの学生はそのようにうまく対応することは難しいでしょう。だからこそ、面接練習を通じて自己分析や企業研究を深め、選考通過のための対策を講じることが大切です。
「REALME」の本番以上に深堀りされるAI面接を活用しながら、さまざまな質問にも対応できる柔軟さを養い、徐々に自信をもって面接に臨めるように準備を重ねましょう。