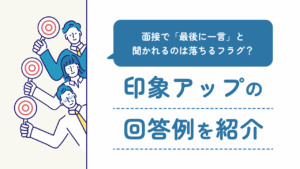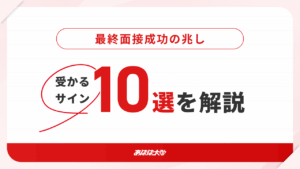自己PRでアピールできる長所はたくさんありますが、相手の思いを慮る共感力についてアピールしたい学生もいるでしょう。自己PRで共感力があることを伝えるためには何に気を付けるとよいでしょうか?詳しく説明します。
ほかの学生がどのように共感力をアピールしているか気になりませんか?REALMEならほかの学生の自己PR文を閲覧できます。
自己PRで共感力を伝えるときの構成
共感力を自己PRで伝える際、「結論・具体的なエピソード・結果・仕事への活かし方」の順番で伝えるようにしましょう。
結論から伝える理由はインパクトを与えるためです。採用担当者はいくつもの自己PRを読んでおり、全文読むとは限りません。採用担当者に興味を持ってもらうためにも結論ファーストを心がけましょう。
その後、結論で出した強みの根拠となるエピソードを話します。共感力を活かすことでどのような課題を乗り越えたのか、得られた結果まで伝えましょう。そして、共感力を活かして会社でどのように活躍したいか伝えて締めくくります。自分を採用するとどのようなよいことがあるのか、企業側がイメージできるような情報を伝えましょう。
自己PRに使えるエピソードの探し方
自己PRに盛り込むエピソードは漠然としたものを避け、具体性のある内容を選びましょう。エピソードを探すために使える手法は2つあります。
1つ目は過去の自分の振り返りです。学生時代に乗り越えた困難やトラブルをいくつかピックアップし、なぜその課題を乗り越えられたのか振り返ります。乗り越えられた理由が共感力と関連するならエピソードとして使ってもよいでしょう。
2つ目は周りに聞くことです。自分では無意識のうちに共感力を活かして誰かを手助けしているかもしれません。家族や友人などに共感してもらって嬉しかった話を聞き出しましょう。
出てきたエピソードから、入社後どのように活用するか話しやすいエピソードを選んで自己PRに盛り込みましょう。
自己PRで共感力を伝えられる例文
共感力を伝えるエピソードとして使えるジャンルはさまざまです。今回は4つのジャンルで共感力に関する自己PR文を作りました。
勉強や留学のエピソードを使う場合
私は共感力と諦めない心が強みです。大学受験の際、同じ大学を目指している友人がいました。一緒に受験勉強をするなど切磋琢磨する関係でしたが、友人の成績が伸び悩み、志望校を変えるかもしれないと相談を受けました。
一緒に頑張る仲間だからこそ共感できる辛さも理解しています。そのつらい気持ちに寄り添いながらも、苦手科目をどのように克服するか解決策を一緒に考えました。その解決策をベースに一緒に勉強に取り組んだ結果、同じ大学に合格できました。
御社に入社して多くの壁にぶつかっても、一緒に取り組む仲間とともに困難を乗り越えたいと考えています。
アルバイトのエピソードを使う場合
私の強みは共感力とリーダーシップです。大学1年生から勤めているドラッグストアで、半年前から指導係を任されています。
私の働くドラッグストアは医薬品の取り扱いが多く、医薬品によっては社員を呼んで対応をお願いする場面もあります。指導係としてついていた後輩はこの医薬品の分類を覚えることが苦手で、次のステップに進めずにいました。
そこで私は彼がなぜそこで躓いているのか、苦手な気持ちに寄り添った上で解決案を提案しました。自信を持てるよう励ましながら成長を見届け、無事後輩がぶつかった壁を乗り越えて、今も活躍中です。
御社でも共感して寄り添いながら、お客様と伴走できる営業として活躍したいです。
ゼミや研究室のエピソードを使う場合
私の長所は共感力と傾聴力です。大学3年生から配属されたゼミでは、地域の方々の協力を受けながら研究を進めています。
協力いただく方の多くが高齢者で、ゼミの研究とは関係ない話も出ます。関係のない話もさえぎることなくしっかり聞き、「それは大変でしたね」と共感することで信頼関係を構築しました。
相手の考えを推し量り、寄り添う気持ちは御社の求める介護の姿そのものです。強みを活かし、利用者様が身をゆだねられる空間を作っていきたいと考えています。
ボランティアのエピソードを使う場合
私は相手の気持ちに寄り添うことが得意です。高校時代から障がい者福祉施設のボランティア活動に参加しており、利用者さんとも深い仲です。
ある日、特に仲がよい利用者さんの精神状態が急に不安定になり、職員の方も手を焼いてしまうことがありました。私はその利用者さんに話しかけ、「全部私に話してもらえる?」と時間をかけて会話しました。会話が苦手な利用者さんなので、時間はかかりましたが彼の本心を聞き出すことに成功しました。
御社のお客様にも、自分の思いを上手に伝えられない方がいらっしゃると考えています。そういったお客様の思いをくみ取れる社員になりたいと考えています。
インターンシップのエピソードを使う場合
私は広告代理店のインターンに参加した際、チームで新商品のプロモーション企画を担当しました。
メンバー同士の意見が食い違う場面も多くありましたが、私は一人ひとりの考えや背景を丁寧にヒアリングし、相手の立場に立って意見をまとめることを心がけました。その結果、全員が納得できるアイデアを形にすることができ、最終的にクライアントからも高い評価をいただきました。
この経験から、共感力を活かしてチームの調和や成果につなげることができると実感しています。今後も相手の気持ちを理解しながら、より良い結果を生み出せるよう努めていきたいです。
自己PRで共感力をアピールするのがおすすめの理由
高いスキルを持っていることも魅力的ですが、自己PRでは共感力をアピールすることをおすすめします。やはり、どんなに優れたスキルを持っていても、仕事相手は人間であるため共感力は必要です。
自己PRで共感力をアピールするのがおすすめな理由について、具体的にご紹介します。
「周囲とうまく協力できる人材」と認識されるから
共感力が高い人は、周囲が求めているものを敏感に察知し、相手の立場や気持ちを理解しながら行動できるため、企業から周囲とうまく協力できる人材と認識されやすいです。
また、周囲と合わせることが得意なため、職場でのコミュニケーションも円滑になり、信頼関係を築きやすいです。チームの中でも自然と調和を生み出してくれるため、共感力のある人材は多くの企業で高く評価されています。
「周りを引っ張れる人材」と認識されるから
共感力が高い人は、他人の意見や感情をしっかりと受け止めたうえで、相手の立場を考えて行動できます。そのため、企業から周りを引っ張れる人材と認識されるケースが多いです。
単に周囲に合わせるだけでなく、メンバーの気持ちや状況に配慮しながら最適な判断を下せる姿勢は、自然と周囲の信頼を集めていきます。チームをまとめるリーダーとしての素質があると評価されやすいです。
さらに、共感力を持つ人は、意見が対立した場面でも双方の気持ちを汲み取り、全員が納得できる方向へ導くことができるため、組織の中核を担う人材として期待されます。
「売上アップに貢献できる人材」と認識されるから
共感力が高い人は、相手の立場や感情を理解しながら行動できるため、社内外のコミュニケーションが円滑になり、信頼関係の構築がスムーズに進みます。そのため、企業から売上アップに貢献できる人材と認識されやすいです。
共感力が高い人は、営業や接客の場面で顧客のニーズや悩みに寄り添い、最適な提案を行うことができるため、顧客満足度の向上やリピート率の増加につながります。結果的に、企業の売上アップに直接貢献できる存在として評価されます。
共感力は単なる「優しさ」ではなく、ビジネスの成果に直結する重要なスキルとして、多くの企業が重視しているからこそ、自己PRでは積極的にアピールしましょう。
自己PRで共感性をアピールできる人の特徴とは?
相手に共感することは、単なる優しさではありません。そのため、優しいだけの人は共感性をアピールしにくい場合もあります。
では、自己PRで共感性をアピールできる人はどのような特徴があるのかご紹介します。
傾聴力が高い
共感力を持つ人は相手の話をただ聞くだけでなく、しっかりと耳を傾ける「傾聴」の姿勢が強いです。傾聴力が高い人は、相手の立場や感情を深く理解しようと努め、時には自分の経験や感情を重ね合わせながら相手の状況を感じ取ります。
話し手の気持ちや考えを受け入れられるため、相手は安心して本音を語ることができ、信頼関係の構築にもつながりやすいです。
傾聴力はビジネスシーンでも重視される能力であり、チームワークや課題解決の場面でも大いに役立ちます。
どんな内容でも否定することをしない
共感力のある人は、自分と異なる意見や価値観に対しても頭ごなしに否定せず、まず受け入れる姿勢を大切にしています。
たとえばチームで議論をしていて自分とは異なる提案が出た場合でも、「そのような考え方もあるのだな」と相手の立場や背景を理解しようと努めます。
相手の意見をまずは受け入れることができる人は、チームワーク向上にも大いに役立ちます。そのため、どんな意見や話でも否定しない人は、共感力が高いと言えるでしょう。
他人に対する興味や関心が強い
他人に対する興味や関心が非常に強い人は、共感力が高いです。
他人に対する興味や関心が非常に強いと、相手の考えや感じていることをもっと知りたい、深く関わりたい思いが自然と生まれます。そのため、会話の中でも相手の話に耳を傾け、内容を深掘りする質問を投げかけることができます。
逆に退任への興味や関心がなければ、相手の気持ちや状況に共感することは難しいです。
良好な人間関係を築くうえで大きな強みとなり、職場やチーム内でも信頼される存在となりやすいため、積極的にアピールしましょう。
自己PRで共感力をアピールするときのNGとは?
共感力が高い人は企業にとって魅力的な人材ですが、自己PRでアピールする際には注意しなければならない点があります。
自己PRで共感力をアピールする際のNGについてご紹介します。
結論ファーストになっておらずわかりにくい
自己PRで共感力をアピールする際は、結論ファーストを意識しましょう。最初に結論を述べないと、何を伝えたいのかが相手に伝わりづらくなります。相手に共感されない伝え方をしている時点で、共感力がないと判断されてしまいます。
【NG例文】
私は大学時代、友人の相談に乗ることが多く、さまざまな悩みに耳を傾けてきました。相手の気持ちを理解しようと努め、信頼関係を築くことができました。
NG例文では結論が後半に来ているため、読み手は途中まで何をアピールしたいのか分かりません。そのため、自己PRで共感力を伝えたい場合は、「私の強みは共感力です」「相手の気持ちに寄り添えるところです」と冒頭で明確に述べましょう。
採用後に活躍するイメージが沸かない
自己PRで共感力をアピールする際、採用後にどのように活躍できるかを示さないと、企業側に自分を採用するメリットが伝わりません。
【NG例文】
私は共感力が高く、友人の悩みをよく聞いてきました。
NG例文では、共感力があることは分かりますが、入社後の業務でどう活かせるのかが伝わらず、アピールとしては不十分です。共感力を強みとして伝える場合は、具体的にどのように活かすかまで述べる必要があります。活躍するイメージを持ってもらえなければ、評価へつながりにくい点に注意しましょう。
社会人に求められる共感力とは
”共感力”という言葉にはさまざまな意味が込められています。共感力を分類するなら以下の3つに分類できます。
- 相手の感情を感じ取って共鳴できる感情的共感
- 相手の考え方を理解して価値観を把握する認知的共感
- 他人の幸福のために動く共感的関心
これらを仕事に生かすと、以下のような取り組みが可能です。
- 顧客の意見や感情に寄り添える
- 顧客が求めるものを理解できる
- 社内の結束力を高められる
- 同僚や上司とうまくコミュニケーションが取れる
仕事をする上で、他人とともに何かをする場面が多くなればなるほど共感力が活かせます。
共感力を活かせる業界や職種
共感力を活かせる業種や職種は以下の通りです。どの仕事も顧客や利用者に向けて寄り添う場面が多く出てきます。
- 心理カウンセラー
- 塾講師やチューターなど教育業界
- 看護師や介護士など医療従事者
- 保育士
- 営業
- コンサルタント
- マーケティング
自己PRに使える共感力の言い換え表現
共感力に近い自己PR文を準備する学生も多数います。その中で自分のPR文が埋もれないようにするために、共感力という言葉の言い換え表現を複数持っておきましょう。例えば、以下のような表現も可能です。
- 相手の気持ちを優先できる
- 傾聴できる
- 柔軟性がある
- 協調性がある
- 課題を解決できる
- コミュニケーションが得意
共感できることをどのような言葉で伝えるかを判断するには、その企業や仕事の特徴をとらえるとよいでしょう。より多くの人を巻き込む仕事なら、相手の気持ちを優先できると仕事がスムーズに進みやすいです。チームワーク重視の企業なら協調性があることをアピールできると、社風になじみやすいと判断してくれるでしょう。
「REALME」で自己分析を効率的に進めよう
ここまで説明した内容をもとに自己PR文を作っても、本当に企業の担当者に刺さるかは、選考結果が出るまで分かりません。もし事前に知りたいならREALMEを使ってみてはいかがでしょうか?
客観的な自己分析ができる
REALMEではAI面接を行い、AIの判定に基づいたフィードバックを実施します。就活で重視する14の要素をベースに、どれが強みか客観的に判断してくれます。他己分析でないと得られない客観的な意見が得られます。
内定判定を確認できる
志望企業から内定をもらえるかどうか判定を出します。AI面接の結果にあわせて判定しており、どの部分が足りていないかも判断できます。大学入試の模擬試験と同じように自分の立ち位置を確認可能です。
合格ラインにいる就活生の回答を閲覧できる
REALMEの企業ページで確認できることは内定判定だけではありません。選考の合格ラインにいる学生がAI面接でどのように答えているかを確認できます。ほかの学生の自己PR分をもとに自己PRをブラッシュアップでき、より内定に近づけます。
自己PRの作成と面接練習は「REALME」におまかせ
共感力に関する自己PR文を準備する際は、共感力でもどの部分を求められているか考えてから文章作成を始めましょう。結論ファーストで書き出し、共感力を活かして課題解決したエピソードを伝えた後、その能力を企業でどのように活かすか書けば完成です。
実際に作った自己PR文が本当に企業に刺さるか、事前に試すならREALMEへ登録ください。


 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)