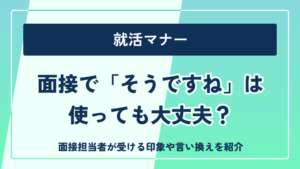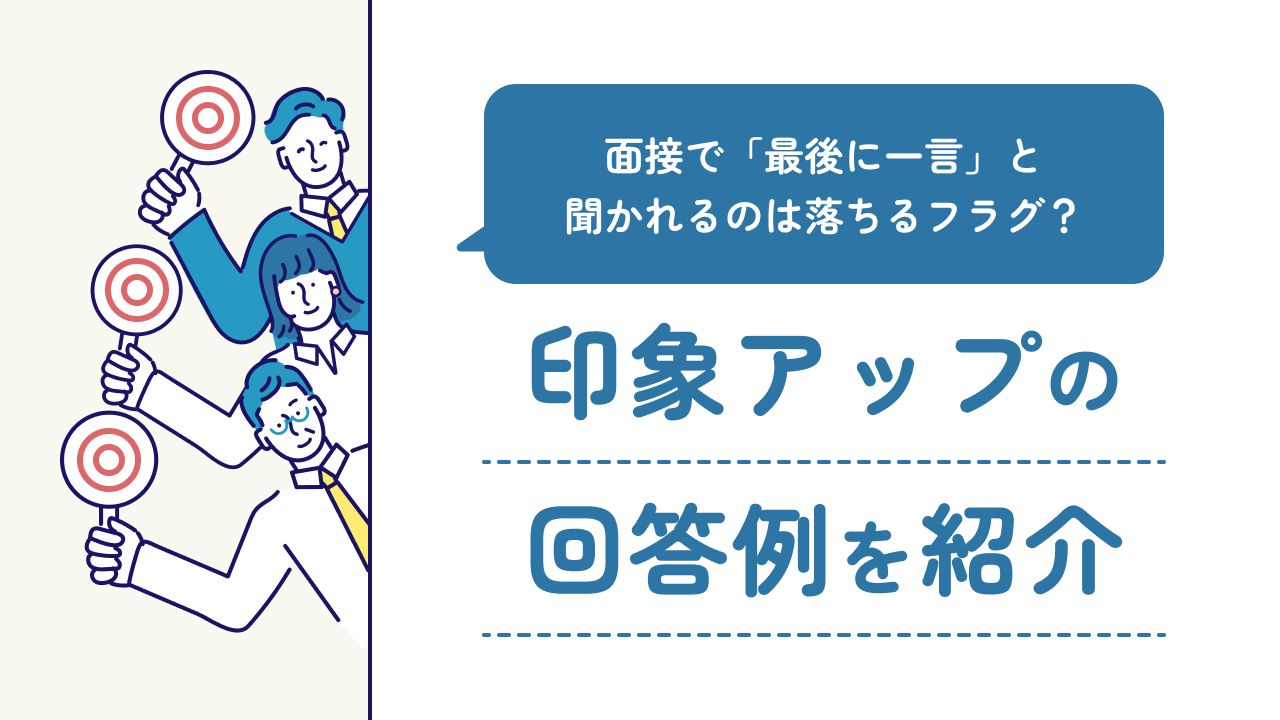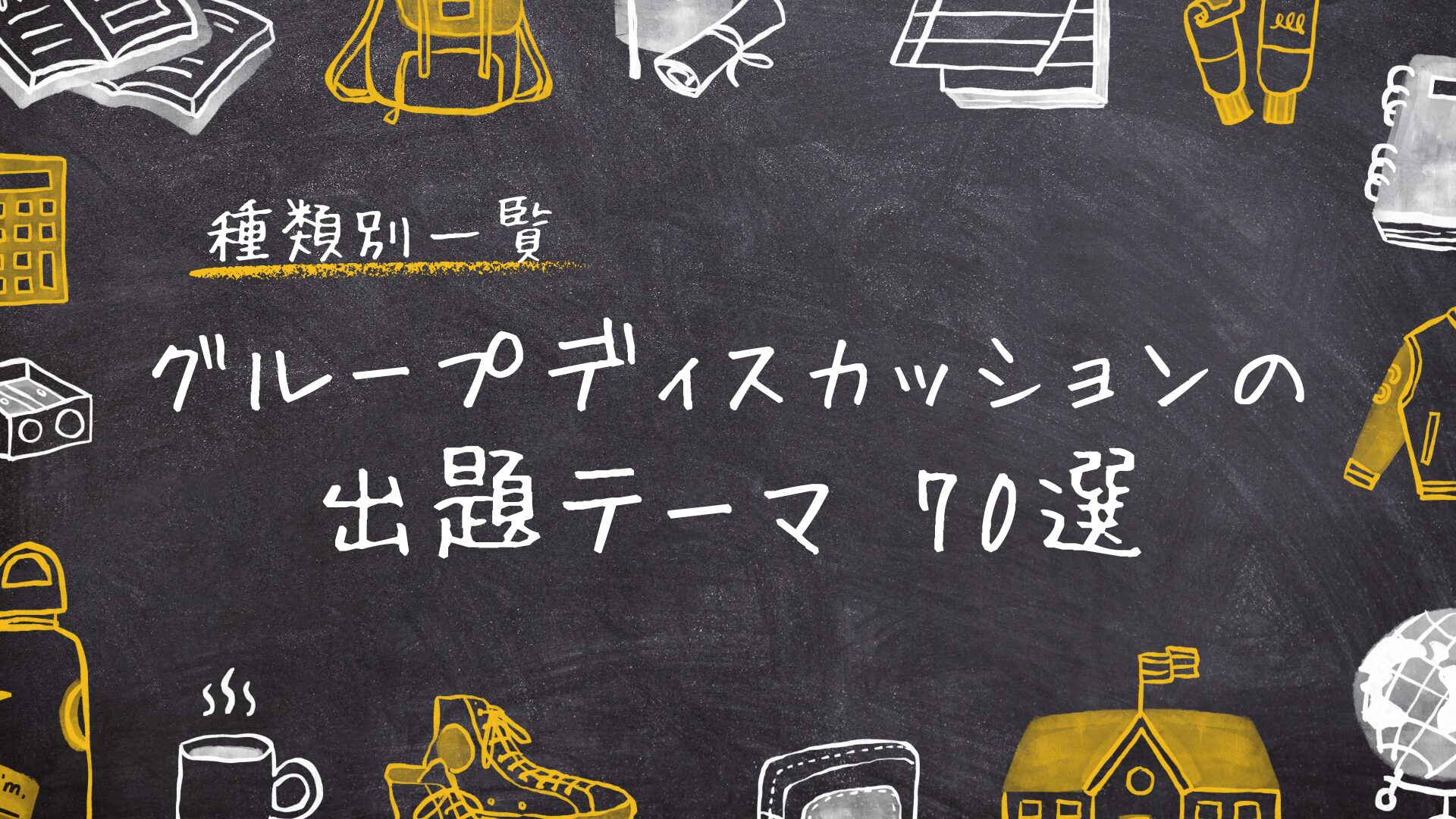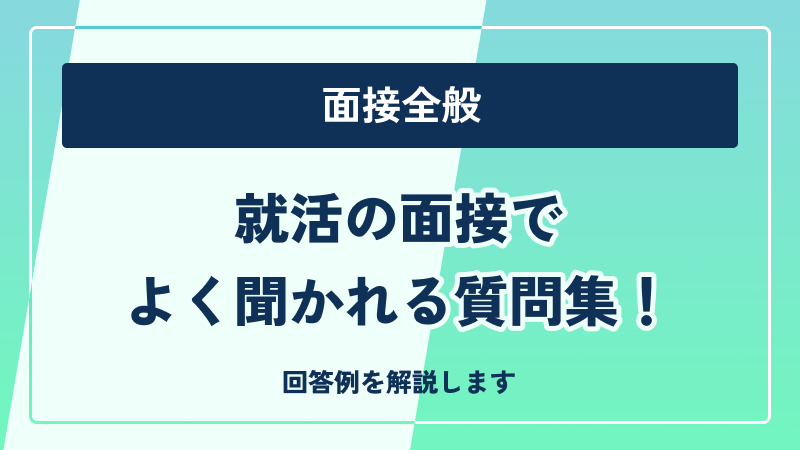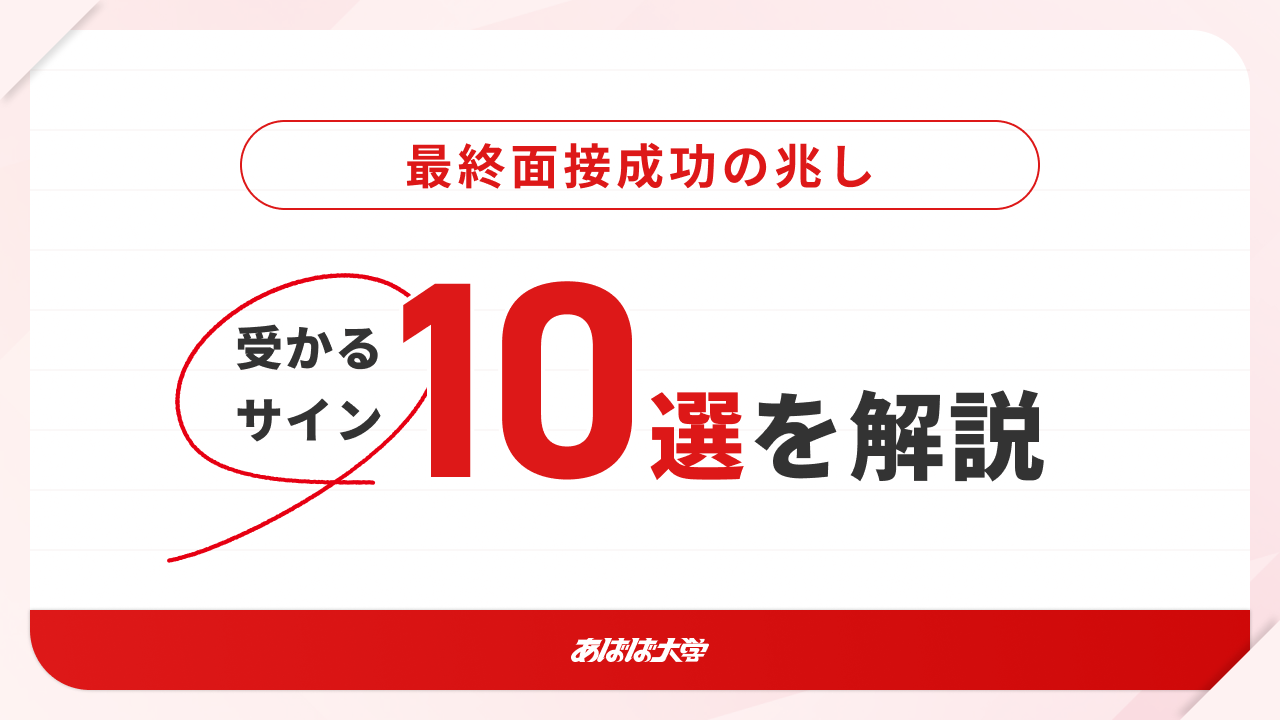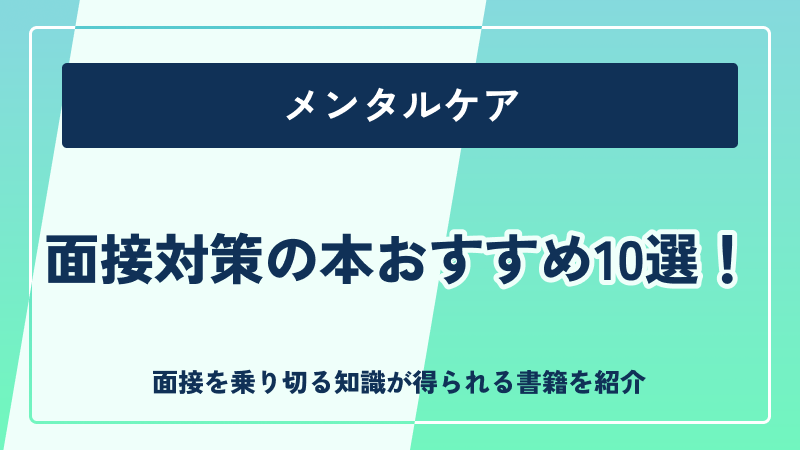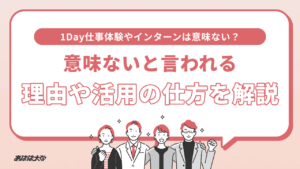「面接ノートって何だろう」「作りたいけれどどのようにして作ればよいのだろう」これから就職活動を始める方の中には、面接ノートの作り方や活用方法に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。面接ノートは、効率的な就職活動の対策に役立ちます。
この記事では、面接ノートの作り方や活用法について紹介します。ぜひ就職活動の参考にしてください。
「REALME」は、AI面接を通じて自分の強みや弱みの確認ができるサービスです。面接結果をもとに自分の強みや弱みを評価してくれます。客観的な分析結果を参考にすることで、自分のアピールポイントや改善点が把握できます。「REALME」を活用し、内定獲得に向けて効率よく就職活動の準備をしましょう。
面接ノートとは
面接ノートとは、就職活動や面接対策をまとめるノートのことです。企業や業界についての情報や選考情報、自己分析や就職活動に必要な情報を自分なりにまとめます。
ノートにまとめておくことで、企業の情報や話す内容が整理できるため、面接の対策に効果的です。自己分析の内容をまとめることで適切な自己PRが作成でき、内定の可能性を高められるでしょう。
面接ノートを作るメリット
面接ノートを作ることは、面接対策に大きな効果があります。その理由は、面接ノートを作ることには以下のメリットがあるためです。
・情報整理と対策が同時にできる
・いつでも振り返りができる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
情報整理と対策が同時にできる
面接ノートを作る過程で、情報整理と対策を同時にできる点がメリットです。なぜなら、書きながら情報をまとめることで頭に入りやすくなるためです。
「読む」より「書く」ことで情報は頭に入ります。内容が頭に入っていれば、緊張していても伝えたい内容を分かりやすく伝えられます。
面接にぶっつけ本番で臨むと、緊張感のある面接会場に入った途端に頭が真っ白になったり、伝えたい内容をうまくまとめられなかったりする人がほとんどです。しかし、面接ノートを作成すれば、作成しながら冷静に面接対策ができるため、緊張しても伝えたい内容を分かりやすく伝えられます。
いつでも振り返りができる
ノートに書くことで、いつでも振り返りができる点もメリットです。
デジタル化が進む今日、情報はデジタルにまとめることもできます。しかし、常にスマートフォンやタブレット、PCが使えるとは限らず、いつでも振り返りをすることは不可能です。
しかし、ノートにまとめて持参していれば、いつでも振り返りができます。面接が始まる直前に見直すこともできるため、再度伝えたい内容を確認して面接に臨めます。
面接ノートの作り方
ここまで、面接ノートの概要と面接ノートが就職活動に役立つことを解説しました。
ここからは、面接ノート作りに必要なアイテムやノートに記載する内容について解説します。作成際の参考にしててください。
面接ノート作成に必要なアイテムを用意する
ルーズリーフ、色ペン、色鉛筆やインデックスシールなど、面接ノートの作成に必要なアイテムを用意しましょう。基本的にはどのノートでも問題ありませんが、ルーズリーフだと後からページを足し、面接日にその企業のページのみを持ち運べるためおすすめです。
また、書いても消せるペンは、修正ペンを使わなくてよいため便利です。持ち運びやすさや使いやすさを確認し、自分にあったアイテムを選びましょう。
記載したい情報をまとめる
希望する企業の情報や選考スケジュール、志望動機や自己分析など、ノートに記載したい内容をまとめましょう。どこに何を書いたか分かるようにすると、後で読み返す時にも便利です。
ノートの始めには、予定がすぐ確認できるように、スケジュールの記入をおすすめします。就職活動では面接や書類提出日など、日程を確認する場面が多いです。スケジュールを把握するためにも、ノートの始めに記入しましょう。
後ろのページには自己分析の記入をおすすめします。自分の強みや就職活動の軸を明確にすることはとても重要です。就職活動を進めることで、徐々に自分の価値観や強みに気がつくこともあります。その場合は、後ろのページに付け足すように書きましょう。
面接ノート作成のポイント
面接対策に効果的な面接ノートを作るためには、以下のポイントを意識しましょう。
・ページは会社ごとに分ける
・後から書き足す前提でレイアウトする
・色分けを活用する
・付箋やインデックスシールを使う
・きれいに作成することを目的にしない
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
ページは会社ごとに分ける
全ての会社を一つにまとめるのではなく、会社ごとにページを分けましょう。なぜなら、ページを分けることで志望した会社の情報が混ざらないようにできるためです。
企業によって、社風や業務内容はさまざまです。どの会社にも当てはまる内容を伝えても、印象には残りません。また、「自社に合っていない」と思われると内定率が下がります。
会社ごとにページを分けて、それぞれの会社にあわせた内容の面接ノートを作りましょう。
後から書き足す前提でレイアウトする
後から書き足すことを想定してレイアウトしましょう。なぜなら、面接ノートは一度書いたら終わりではなく、随時書き足します。
書き込みたい情報が後から増えることを見越して余白が多いレイアウトにすることで、後から書き足してもページが見づらくなりません。また、余白がないと書きたい情報を書き足せなくなる可能性があります。
余白を作るとともに、消せるペンを使うこともおすすめです。消せるペンを使えば、適宜修正を行うことでより見やすいノート作成が可能です。
色分けを活用する
色分けを活用して、見やすいノート作成を目指しましょう。
情報の種別や重要度などで色分けをすることで、一目で欲しい情報を得られます。同じ色のみを使ったノートは、確認したい内容を探す際に時間がかかります。
面接ノートは書いたら終わりではなく、振り返りをしたり面接対策のために活用したりするものです。ただ単に書くのではなく、見やすいノート作りを心がけましょう。
付箋やインデックスシールを使う
付箋やインデックスシールの活用も大切です。なぜなら、会社ごとにページを分けていると、ページ数が多くなるためです。付箋やインデックスシールを使えば、見たいページにすぐ飛べます。
就活では、複数の企業にエントリーするケースがほとんどです。10〜20社前後エントリーする就活生も多く、その分ページ数が増えます。
付箋やインデックスシールを使えば、ページ数が増えてもすぐに確認したい企業のページを見つけられます。
きれいに作成することを目的にしない
自分が活用できればよいため、完成度やきれいさを目指す必要はありません。あくまでも、自分が見やすいと思うノート作成を目指しましょう。
見やすいページ作成のコツとして、文章で書くのではなく要点だけをまとめるようにすることもおすすめです。文章で長々と書いても、振り返った際にポイントが分かりません。端的に要点のみを記入した方が、振り返った際も内容を理解できます。
面接ノートに記入する項目
ここまでで、面接ノート作りの概要や作成時に必要なものについて紹介しました。ここからは、面接ノートに記入する項目について詳しく解説します。
面接や選考の日程
前述のとおり、面接ノートの始めには、企業ごとに書類の締切、面接日や会社説明会の日程などのスケジュールを記入しましょう。スケジュールを把握することで、面接対策を事前に行った上で選考に臨むことができます。
また、日程をまとめることで、ダブルブッキングや書類の提出漏れを防げます。選考書類の提出を忘れると面接に辿り着けない可能性もあるので、スケジュール管理は適切に行いましょう。
企業や業界の情報
各企業の代表者名と経歴、経営理念や求める人物像など、各企業情報を記入しましょう。
他にも、業界規模や業界の現状や将来性など、面接で問われやすい情報をまとめておくことが重要です。
企業や業界について聞かれた時にスムーズに受け答えができると、その企業に対する熱意が伝わり、面接官からの高評価も期待できます。
志望動機
企業・業界を選んだ動機もまとめましょう。志望動機は選考において、必ずと言ってよいほど聞かれる重要な質問です。
内容は企業ごとに変える必要があります。しかし、ある程度のひな形は作りつつ、集めた情報や自分の思いをもとに、個々にカスタマイズしましょう。その際に、その企業や業界に対する熱意、企業に貢献できることや入社後のビジョンは、自分のエピソードを交えて記入すると高評価が期待できます。志望動機を面接ノートにまとめておくと、面接対策だけでなく、エントリーシートや履歴書を書く際にも役立ちます。
エントリーシートの内容
エントリーシートとは、学生が企業に提出する応募書類です。面接で質問された際、エントリーシートと全く違う回答をすると一貫性がないと思われる可能性があります。エントリーシートに書いたことを忘れないように、面接ノートにも書くことで一貫性のある受け答えができるでしょう。書く手間をできるだけ省きたい方はエントリーシートのコピーをノートに挟んでおくこともおすすめです。
予測される質問内容と回答
面接の質問には、多くの企業で頻出するものがあります。志望動機やガクチカなど、予測できる質問内容やその回答はノートにあらかじめまとめましょう。
予測できる質問に加えて、意外性のある質問に対する回答についても考えておくと役立つ可能性があります。面接前に読み返すと自信を持って面接に臨めるでしょう。
逆質問の内容
面接の最後には、学生から企業側に質問をする逆質問の機会があります。質問ができないと準備不足の印象になり、熱意が足りないと思われてしまう可能性があるでしょう。
企業研究や説明会に参加した際に分からなかったことや質問したいことをまとめ、面接の際に質問ができると高評価が期待できるでしょう。
自己分析の情報
自分の興味関心や強み・弱み、特技を自己分析の情報としてまとめましょう。自分の強みや弱みの把握は面接でのアピールにつながります。
客観的な視点で自己分析を行い、その結果を面接ノートにまとめておくと、効率的に就職活動を進められます。自分はなぜその企業・業界を志望するのか、就職活動の軸をしっかりと持って、面接の場でも堂々とアピールできるでしょう。
面接ノートを活用するコツ
面接ノートは作成したら終わりではなく、面接に向けての活用が大切です。しかし、どのように活用すればよいか分からない人もいるでしょう。
そこでここでは、面接ノートを適切に活用するコツをご紹介します。
面接前に必ず見返す
面接会場に面接ノートを持参して、面接前に見返すようにしましょう。面接前に見返すことで、情報の確認と共に緊張を和らげる効果があるためです。
面接の直前は、緊張から頭が真っ白になることがあります。しかし、面接ノートを見返せば落ち着きを取り戻せて、緊張が和らぎます。
緊張しすぎると、練習の成果を発揮できなくなる恐れがあるため、面接ノートを有効に活用しましょう。
書き込みは面接後すぐ行う
面接で感じたことや得られた情報は、記憶が鮮明なうちに書き込んでおくことが大切です。なぜなら、人の記憶は時間の経過とともに薄れるためです。
面接直後であれば、記憶が鮮明であるため正確な情報や気持ちを書き込めます。面接を終えたら、なるべく早く書き込みましょう。
面接直後の書き込みでは、以下の内容を書き込むと次回に活かせます。
・スムーズに回答できた質問
・言葉に詰まったりうまく回答できなかったりした質問
・面接の雰囲気
・自己評価
・面接の感想
・面接で気づいた点
AI面接「REALME」で自分の強みを知ろう
面接ノートで自己分析をまとめる時に、客観的な視点で自己分析することに難しさを感じる人もいるのではないでしょうか。そのような方へ、AI面接を通して客観的に自分の強みが分かる「REALME」をおすすめします。
「REALME」は、AIとの面接結果をもとにあなたの能力を数値化し、志望企業の内定判定を出してくれるサービスです。「REALME」を使うことで、効果的な面接対策が可能です。ここからは「REALME」について詳しく解説します。
志望企業に対する自分の現在地が分かる
「REALME」は、AI面接の結果をもとに、志望企業の内定判定を算出することが可能です。A~Eの5段階で評価されるため、志望企業の内定獲得率がどの程度であるのかを把握できます。就活ノートにまとめたことを活かすために「REALME」のAI面接で事前に練習しましょう。
AIで抽出したES・面接解答例が観覧できる
「REALME」のAI面接には、能力を14個の項目に分けて評価してくれるフィードバック機能が搭載されています。最終面接に進んだ学生と比較したグラフを確認し、自分の強みや課題を把握できる点が特徴です。また、最終面接に進んだ学生のエントリーシートやAI面接のデータを閲覧できるサービスもあります。
最終面接に進んだ学生の解答例を閲覧することで、自己分析をブラッシュアップできます。合格から逆算して対策し、内定獲得率を向上させましょう。
自身の強みが客観的に判断できる
「REALME」では、面接時に重視される35の項目をもとに、あなたの14の能力を点数化します。志望企業の合格ラインに足りない場合は、合格ラインに達するための的確なフィードバックが提案されます。自分の強みのアピールと弱みの対策を行うことで、面接対策を効果的に行うことが可能です。
面接ノートを作成して面接に役立てよう
就職活動は、企業情報や志望動機、面接の回答方法をまとめた面接ノートが役立ちます。「REALME」のAI面接で、客観的な自己分析や自分の現在地を把握し、内定の可能性を高めましょう。