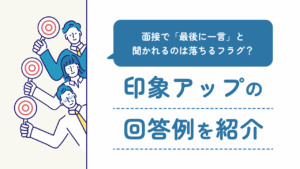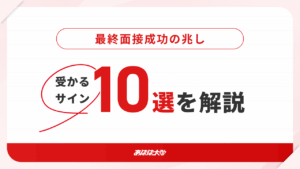「なぜその活動に力を入れたか」「学んだことを当社でどう活かせると考えているか」などの質問に対する最適な答えはなんでしょうか。ガクチカは話せるものの、深掘りされると自信をもって答えられないという就活生は多いでしょう。この記事ではガクチカに対する深掘り質問への対策をご紹介します。
面接対策そのものに自信がないときは、AIと面接練習ができ、客観的な分析がしてもらえる「REALME」をぜひ使ってみてください。
企業がガクチカを深掘りする理由は?
企業は就活生のさまざまな特性を掴むために、就活生が学生時代に力を入れたガクチカについて深堀りして質問します。ここでは、企業がガクチカを深堀りする理由を解説します。
自社に合っているか知るため
面接は、自社の方針・社風・特徴に学生が合うのかを企業が判断する場です。自社に合う学生が入社すれば、長期にわたって活躍し、企業の発展に寄与してくれます。
具体的なエピソードを伴うガクチカは人柄や価値観がより詳細に伝わります。ガクチカの深堀りは、早期退職防止や入社後のモチベーション維持の観点からも、企業と学生双方にとって有益な方法です。
論理的思考力を知るため
ガクチカで話したエピソードにまつわる質問に対して分かりやすい回答ができるかを企業側は重視しています。学生は事実とともに、当時の行動・判断の理由や自身の理想とした結果などを伝えることが大切です。
「発生した問題に対応し、適切な判断のもとに成果の出る行動をしたか」「一連の流れを分かりやすく他者に伝えられるか」この2点が論理的思考を図る基準です。具体的な事例を交えた回答によって、入社後のトラブル発生時にも論理的に対応できる能力があることをアピールでき、企業からの評価が高まるでしょう。
思考の傾向を知るため
深掘り質問では「なぜ」「どのようにして」という質問が投げかけられます。Yes・Noで答えられない質問をすることで、該当事項に学生が取り組んだ背景や、当時の気持ちを推し量れることができるようになります。
ガクチカを深掘りする目的は、学生を責めるためではなく、学生本人が大切にしている価値観や重きを置く考え方を理解するためです。思考の傾向を知ることは、入社後の働き方を想像する材料となるため、企業は重点的に確認します。
ガクチカの深掘り質問例を大公開
ここでは、ガクチカの深掘りで聞かれやすい質問例をご紹介します。また質問に対する回答の例もピックアップ。自分のガクチカ内容から予測される深掘り質問を考え、内容に説得力を与えられるような返答を作成していきましょう。
なぜその活動を選び、頑張ろうと思ったのか
ガクチカの深掘り質問では、そのテーマを「なぜ選んだのか」を聞かれやすい傾向にあります。動機を上手に説明できれば、人間性や向上心をさらにアピールできます。以下の返答例を参考に、自分らしい回答を考えてみましょう。
【『なぜその活動を頑張ろうと思ったのか』に対する返答例】
- 英語力を伸ばしたいと考え、将来のキャリアにも役立つと思い留学を決意しました。自分の力を試し、成長できる機会だと感じて全力で取り組もうと思いました。
- サークル活動を選んだのは、チームで一つの目標に挑戦する経験を積みたかったからです。仲間と協力し合いながら課題を解決する力を養えると考えました。
なぜ頑張れたのか
ガクチカを深掘りする際に「なぜ頑張れたのか」と質問するのは、行動の背景にある原動力を知りたいからです。途中で壁にぶつかったとき、どのような気持ちで乗り越えたのか、何が支えになって継続できたのかを具体的に語れると、話に説得力が生まれます。
たとえば、悔しさや責任感、達成したい目標など、自分の感情を言語化することが重要です。結果だけでなく、その過程での思考や感情の動きを丁寧に話すと、面接官にも人柄や価値観が伝わりやすくなり、印象に残る回答につながります。
活動を通じて一番困難だったことは何か
企業はガクチカを通して、応募者の課題発見力・解決力を審査しています。エピソードのインパクトよりも、課題への気づきや取り組みが重要です。活動における困難に関する回答例は、以下の通りです。
【『活動を通じて一番困難だったことは』に対する返答例】
- 留学中は、現地での会話がスムーズにいかず、授業で意見を発表する際にうまく伝えられないことが一番の困難でした。
- アルバイトでは、繁忙期に新人が多く入り、指導と通常業務を同時にこなさなければならず、時間的にも精神的にも大きな負担となりました。
その困難にどう向き合い、どんな行動をとったのか
課題解決力は、ガクチカにおける最重要ポイントともいえるでしょう。企業はガクチカの課題解決を通し、応募者の行動力や実行力、入社後の再現性をチェックしています。以下の例文を参考に、自分のエピソードに当てはめていきましょう。
【『困難にどう向き合い、どんな行動をしたか』に対する返答例】
- 英語の壁に直面した際は、授業後に現地の学生へ質問したり、毎日欠かさず英語日記を書いたりして克服に努めました。自ら交流の場を増やすことも意識しました。
- 新人教育の負担を感じたときは、マニュアルを作成し、共通の基準を設けることで指導の効率化を図りました。また、先輩にも協力を依頼し、体制を整えました。
結果や成果はどうだったか、具体的に説明できるか
ガクチカでは「成果や結果がともなわなくてはいけない」と思っている人もいますが、大事なのは行動そのもの。また行動の結果が思わしくない場合でも、それを具体的に説明できる力が大切です。数字や固有名詞を取り入れながら、説得力のある説明を心がけましょう。
【『結果や成果はどうだったか』に対する返答例】
- 努力の結果、英語でのプレゼンを一人で行えるまで成長し、授業でも積極的に発言できるようになりました。また、現地の友人も増え、人間関係も広がりました。
- マニュアル整備の結果、新人の習熟度が早まり、店全体の作業効率が改善しました。その成果が認められ、店長からも感謝されると同時に責任ある業務も任されました。
活動を成功させるために何を工夫したのか
「活動を成功させるために何を工夫したのか」という質問は、結果に至るまでの思考や行動プロセスを確認する意図があります。企業は、課題に直面した際に指示を待つのではなく、自ら考えて行動できる人材かどうかを見ています。
そのため、工夫した点を答える際は「なぜその工夫をしようと考えたのか」「どのような行動を取ったのか」を具体的に伝えることが重要です。周囲を巻き込んだ工夫や、試行錯誤を重ねた経験を交えると、主体性や実行力のある人物像をより強くアピールできます。
活動から何を学んだのか
「活動から何を学んだのか」という質問では、経験を通じて得た学びをきちんと言語化できているかが重視されます。ただ頑張った事実を伝えるだけではなく、その経験によって考え方や行動にどのような変化があったのかを示しましょう。
学びが複数ある場合でも、すべてを並べるより、最も印象的で再現性のある学びを1つに絞って話したほうが、面接官に伝わりやすくなります。また、その学びを今後どのように活かしていきたいのかまで触れると、成長意欲や入社後の姿を具体的にイメージしてもらいやすくなるでしょう。
当時に戻れるなら何を改善するか
「当時に戻れるなら何を改善するか」という質問は、結果そのものよりも、経験をどう捉え直しているかを見る意図があります。成功や失敗を感情的に語るのではなく、冷静に振り返り、改善点を客観視できているかが重要です。うまくいかなかった点を正直に認めたうえで、次はどのように行動するかを語れると、成長意欲が伝わります。
また、過去の自分を否定せず当時の判断には意味があったと整理して、今ならこう工夫できると前向きに話す姿勢が好印象につながります。こうした振り返りは、入社後も学びを活かしてキャリアアップしていける人材であると示す材料になるでしょう。
この経験から得た学びを今後どう活かした
ガクチカの最後は、「学びをどのように会社への貢献につなげるか」で締めます。ガクチカによって得た能力や気づきを、入社後にも発揮できるような内容を伝えましょう。再現性を重視しつつ、具体性のある自己アピールが重要です。
【『経験から得た学びをどう活かしたいか』に対する返答例】
- 困難に直面しても工夫と努力で克服できるという自信を得ました。今後も新しい環境や挑戦に臆せず取り組み、柔軟に対応する力として活かしていきたいです。
- チーム全体の効率を考えて行動する重要性を学びました。社会人になっても、自分だけでなく組織全体の成果を意識しながら働く姿勢に活かしたいと考えています。
ガクチカの深掘りへの対策
ガクチカの深掘り質問には万全な対策を施し、どのような角度からの質問でも返せるように準備することが大切です。ここでは、ガクチカの深堀りに自信を持って応じるための対策を解説します。
自己分析を徹底的に行う
ガクチカに関する自己分析を十分に実施することで、ガクチカの深掘り質問に適切な応答ができます。決断の要因となった考え方や、行動の基準となる価値観などを、時間をかけて細かく分析しましょう。自分の長所や志望企業に適した特性を、ガクチカの内容にからめることで、説得力のあるアピールが可能です。
自分の行動や考え方を細かく分析し、自己理解を深めておくことで、想定していなかった深掘りの質問に対しても、筋の通った回答が慌てずにできます。
第三者からの意見を聞く
ガクチカの深掘り対策では、第三者からの意見を取り入れることが効果的です。どれだけ自分なりに質問を想定し、回答を準備していても、視点が偏ってしまうのは避けられません。第三者に話を聞いてもらうと「なぜそう考えたのかが分かりにくい」「ここはもっと具体的にしたほうがよい」といった、自分では気づきにくい改善点が明確になります。
友人や先輩、大学のキャリアセンターの担当者など、立場の異なる相手に意見を求めると、多角的な視点が得られるでしょう。客観的なフィードバックをもとに内容を磨き上げると、説得力のあるガクチカにつながります。
エピソードを時系列に整理する
ガクチカで使うエピソードの流れを、始まりから結果が出るまでつじつまが合うように整理することが大切です。エピソードの背景や課題、それを解決するまでの過程と結果、そこから学んだことなどを箇条書きにして、分かりやすく整理します。
時系列で考えると、それぞれの段階で自分がどのように考えていたかが明確になり、前述の自己分析もより深く行えます。価値観や行動基準の変化などをしっかり把握しましょう。
自問自答を繰り返す
ガクチカへの深掘り質問は、些細な部分に対しても「なぜ」「どのようにして」と細かく追及されます。学生が、課題の核心を認識したうえで対応しているかを確認するためです。回答に対する追求を自分で何度も繰り返すことで、面接でもスムーズに答えられるでしょう。
課題の本質を知って対応できる力は、就職後に発生したトラブルに対しても、背景を知ったうえで適切な対処ができる能力として捉えられます。自問自答の中であいまいな点があれば、分析を深めて明確化することが大切です。
面接の練習を行う
ここまで取り上げた項目について十分に準備できたら、模擬面接を通して、実際に口に出して答える練習をします。本番で緊張して焦っても、自然と口から答えが出るくらい、何度も面接練習を繰り返すことが大切です。
ある程度数をこなせば、気持ちに余裕が出てきます。面接練習は、家族や友人だけでなく、大学の就職支援職員やキャリアセンターの先生など、就職面接のポイントを知る人に頼むとよいでしょう。
ガクチカの深掘りを回答する際のポイント
質問に回答する際は、相手に伝わりやすく話すことが大切です。ここでは、ガクチカの深掘り質問に回答する際のポイントを解説します。面接全般で使える部分もあるため、十分に確認してから面接に臨みましょう。
結論から伝える
結論ファーストで伝えることは、面接全般における基本です。結論を伝えた後、裏付けとなる補足情報を伝えることで、相手が話を理解しやすくなります。また結論を先に伝えると、話す側も伝えたい軸を把握でき、内容に一貫性と説得力が出ます。
併せて、「なぜ~?」という質問に「~~だからです。」という答え方で結論を明確化して伝えることも大切です。
背景や状況を簡潔に分かりやすく伝える
ガクチカのエピソードの背景や状況は、導かれた結果が適切であるかを判断する材料の1つです。伝えた結論の根拠を支える補足情報として、内容はできる限り掘り下げておき、そこから相手に伝えたい部分をピックアップして整理します。
どのような過程を経てその結論や決断に至ったかを分かりやすく伝え、採用担当者が結論の理由に納得できるように答えることが大切です。
自分なりの考えを焦点を絞って話す
ガクチカの深掘り質問に回答する際は、自分なりの考えに焦点を絞って話しましょう。一つの課題に対しての感想や行動は、一人ひとり異なります。世間一般やマジョリティの考えに左右されるのではなく「自分だからこそこう思った」という気持ちを伝えることが大切です。
エピソードを通じて得られた学びや発見も、自分ならではのオリジナルな要素です。「何を話したいのか」が明確であるほど、エピソード説明の骨子もブレにくくなります。
成果は数値や頻度を用いて定量的に伝える
深掘り質問に答える際は、ガクチカの本編と同様に、定量的な表現を心がけましょう。数字や固有名詞を使える部分は使い、内容に説得性や一貫性を取り入れていきます。感想においても抽象的表現を避けるべきですが、肝心の「得たもの」に関しては定性的であるほうが再現性が見込まれます。
たとえば説明部分では「売上を〇%上げた」や「〇〇大会で〇位に入賞した」のような定量的表現が大切。学びのフェーズでは「将来のリスクを見越した計画力や慎重さの大切さを学んだ」のように、非認知能力を押し出しましょう。
企業が求める人物像を把握しておく
企業がガクチカを深掘りする背景には「自社に合う人材かどうか」を見極めたい意図があります。そのため、企業が求める人物像を把握せずに回答すると、どれだけ良い経験を語っても評価につながりにくくなります。
募集要項や公式サイト、採用ページには、企業が重視する価値観や行動特性が言語化されているケースが見受けられます。求める人物像から共通点を見つけ、自分の経験や強みと結び付けることが重要です。企業目線を意識したアピールができれば「まさに求めている人材だ」と感じてもらいやすくなり、選考通過の可能性も高まるでしょう。
ガクチカの深掘りに答えるときの注意点
ここでは、ガクチカの深掘り質問に答える際の注意点をご紹介します。思いもよらぬ方向から質問が飛んでくると、つい焦った内容の回答になってしまうこともありますよね。パニックになりそうなときこそ一呼吸置き、効果的な回答につなげていきましょう。
専門用語の使用は控える
深掘り質問への回答では、専門用語の使用は控えるように心がけてください。たとえ類似する業種の面接であっても、面接官相手であれば「誰にでもわかりやすい単語」を使用するべきです。専門用語の多用はコミュニケーション能力や想像力を疑われ、「相手の目線に立てない人物だ」と評価されかねません。
難しい表現を使う際は、必要に応じて説明や補足を追加しましょう。目安としては「初めて聞く中学生でもわかるような言葉選び」を意識すると、自然とシンプルかつ簡潔な文章になっていきます。
なぜそう考えたのかていねいに答える
深掘り質問では、自分がなぜそのように考えたのかをていねいに答えましょう。ガクチカでは深掘り質問も含め、思考の言語化能力も審査対象です。もし咄嗟に言葉が出てこないときは、「考えをまとめますので少々お待ちください」と素直に伝えるのも一つの手段です。
一問一答で終わらせるのではなく、思考プロセスを段階的に説明することが大切です。判断に至るまでの基準も説明に取り入れ、人間性や価値観をアピールしましょう。一文一文は簡潔であるほど内容が伝わります。
ガクチカの深掘り質問についてよくあるQ&A
ガクチカの深掘り質問について「どこまで答えればいいのか」「想定外の質問が来たらどうするのか」など、不安を感じる就活生もいるでしょう。ここでは、ガクチカの深掘りに関して特によく寄せられる疑問をQ&A形式で整理し、面接本番で落ち着いて対応するための考え方を解説します。事前に疑問を解消しておくことで、自信を持って受け答えできるようになるはずです。
ガクチカを深掘りする企業の割合は?
ガクチカを深掘りする企業の割合を、正確な数字で示すことは難しいのが実情です。ただし、一次面接から最終面接に至るまで、何らかの形でガクチカを掘り下げる企業は多いといえます。理由として、ガクチカは就活生の人柄や価値観、行動特性を知るうえで汎用性の高いテーマだからです。
表面的なエピソードだけでは判断できない部分を確認するため、自然と「なぜ」「どのように」といった深掘り質問が増えていきます。こうした背景から、ガクチカは「話せれば十分」という考え方だけでは、評価につながりません。想定される深掘り質問まで含めて準備しておくことが、選考を安定して突破するために欠かせない対策といえるでしょう。
深掘り質問に答えるときは何秒ぐらいで話すべき?
深掘り質問に答える際の回答時間は、30秒〜1分程度を目安にするとよいでしょう。結論・理由・具体例をバランスよく伝えやすく、面接官も内容を理解しやすくなります。1分を大きく超えてしまうと要点がぼやけ「話が長い」「まとめる力が弱い」という印象を与えかねません。
限られた時間の中で、自分が何を伝えたいのかを明確にし、不要な前置きは省く意識が大切です。もし話している途中で長くなりそうだと感じた場合は、要点に立ち返り簡潔に締める判断力も求められます。事前に時間を測りながら練習しておくと、本番でも適切な長さで落ち着いて回答できるようになるでしょう。
回答を差別化する方法はある?
特別な経験がなければ差別化できないわけではありません。多くの就活生が似たような活動を経験しているからこそ、その経験をどう捉え、何を考え、どう行動したのかが重要です。結果の大きさよりも、過程で感じた葛藤や工夫、気づきに目を向けてみましょう。
同じアルバイト経験でも、課題に対してどう向き合ったのか、どのような判断基準で行動したのかは人それぞれ異なります。自分の言葉で具体的なエピソードとして語れば、自然とオリジナリティが生まれます。誰かの正解をなぞるのではなく「自分はそのとき何を考えていたのか」を丁寧に言語化することが、回答を差別化する一番の近道といえるでしょう。
うまく答えられないときの対処法は?
深掘り質問は想定外の角度から聞かれることもあり、うまく答えられない場面があって当然です。うまく答えられないときは焦って言葉をつなげず、まず一呼吸置くことを意識しましょう。
たとえば「少し整理してからお答えしてもよろしいでしょうか」と伝えれば、落ち着いて考える時間を確保できます。頭の中で結論→理由→具体例の順に組み立ててから話すと、内容がぶれにくくなるのです。また、曖昧なまま話すより「当時は◯◯と考えていました」と前提を置くと、伝わり方も整います。沈黙を恐れず、短くまとめてから答える姿勢は、冷静さや誠実さとして評価されやすいでしょう。
REALMEで自分を客観視してガクチカを深堀しよう!
ガクチカの深掘りをしようにも、一人でやり切れるか不安だと思う人はいるでしょう。その際は身近な人だけでなく、AIの力を借りることがおすすめです。「REALME」では、ガクチカの深掘り対策をサポートするコンテンツが充実しています。
AI面接を通して客観的に自己分析ができる
「REALME」の最大の特徴はAI面接です。AIからの質問に対して返答するだけで、客観的な自己分析結果が提供されます。ガクチカを考えるときだけでなく、就活準備全般を通しても自己分析が欠かせません。「REALME」は自己分析結果を強み別にグラフでまとめてくれるため、客観的に自分の長所が分かります。
合格ラインの学生のガクチカが見られる
他の学生がどのようなガクチカを話しているかを、個人で把握することは困難です。「REALME」なら、志望企業の合格ラインに至った学生の回答が確認可能です。過去の就活生が残したデータをもとに、志望企業の方針や社風に合ったエピソードの作り方が分かります。
志望企業の内定判定を確認できる
「REALME」では、AI面接の結果をもとに志望企業への内定判定を算出しています。A~Eの10段階で判定を行い、ガクチカの内容をよりよいものにするためのアドバイスも受けられます。AI面接を何度も繰り返して、ガクチカの回答内容をブラッシュアップし、内定判定の結果を向上させましょう。
ガクチカは深掘りに備えて対策を行おう!
ガクチカの深掘り質問は、企業が学生をより理解し、本当に活躍できる人材か見極めるための質問です。自己分析やガクチカエピソードの振り返りを徹底して行うことで、論理的で説得力のある回答ができ、自身のアピールにつながります。十分な準備をしたうえで、模擬面接を通して受け答えの練習を繰り返すことが大切です。「REALME」によるAI面接を活用すれば、模擬面接を納得するまで繰り返し、ガクチカの深掘り質問に自信を持って対応できる力を身につけられます。周囲に遠慮することなく何度も面接練習を繰り返し、自分の特性を的確に知りたい人は、ぜひ「REALME」をご活用ください。

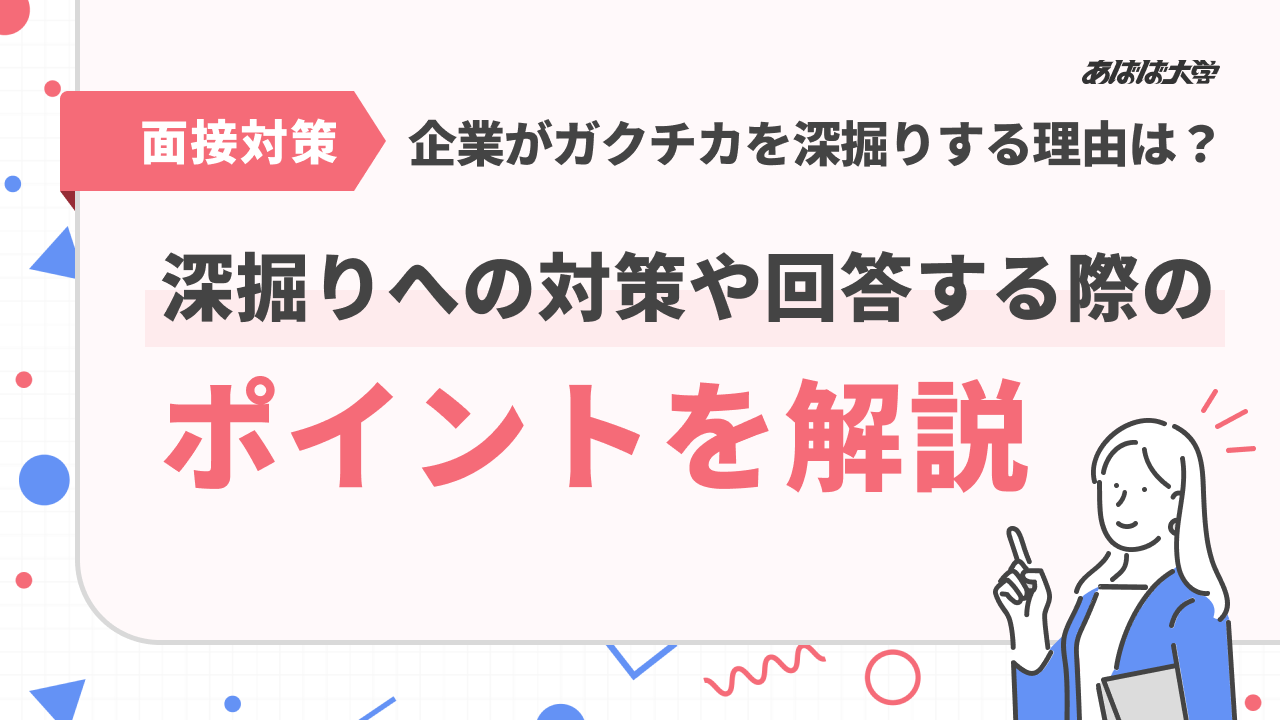
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)