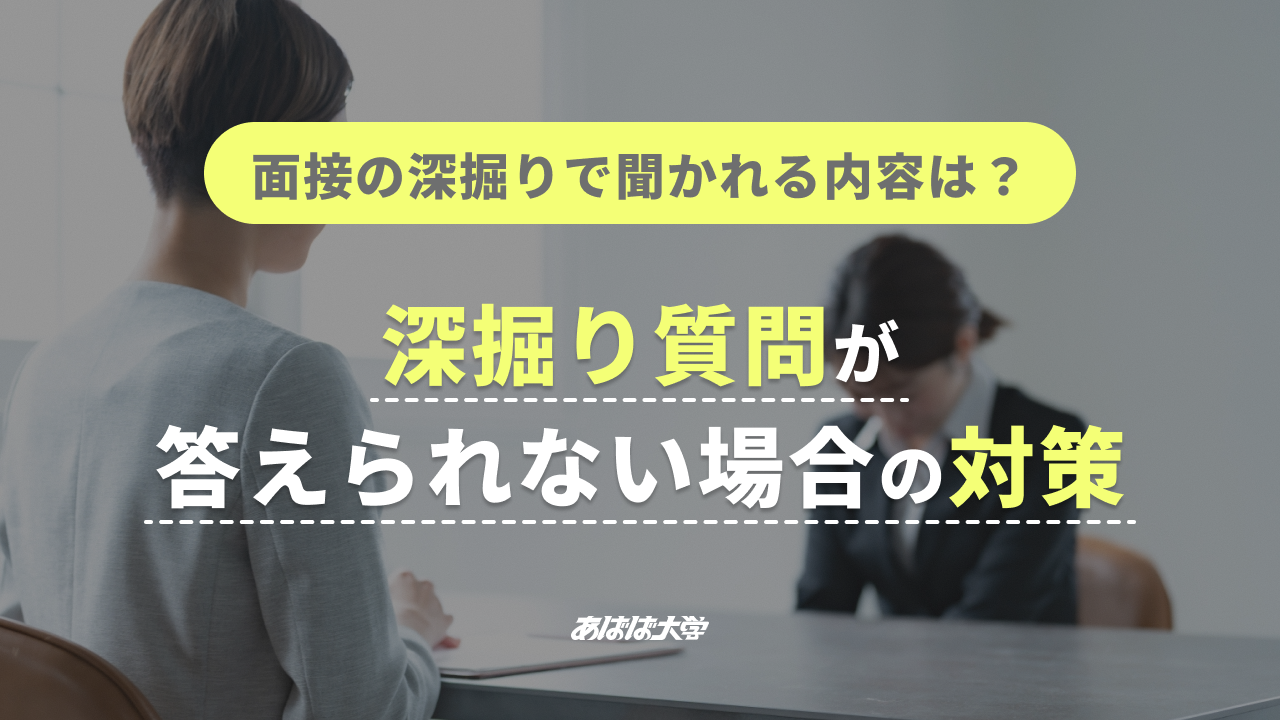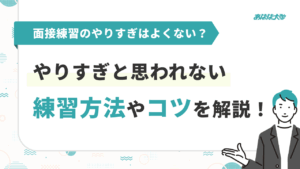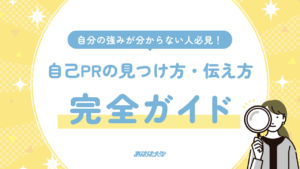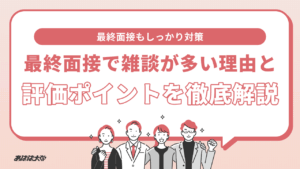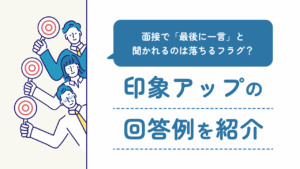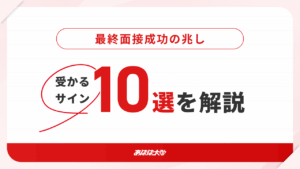就活の面接で困ることは何でしょうか?多くの学生が自分の回答に関する深掘り質問が苦手だと答えます。よくある質問への回答は事前に準備できますが、深掘り質問への回答は事前準備が難しいでしょう。今回は面接の深掘り質問への対策法をお伝えします。
深掘り質問をはじめ、よりリアルな面接対策なら「REALME」がおすすめです。
面接の深掘り質問に答えられない場合でも100%落ちるとは限らない
前提として、面接の深掘り質問にスムーズに答えられない場合でも、100%落ちるようなことはありません。もちろんスラスラと答えられれば良い印象を与えられる可能性はありますが、面接官が深掘り質問で知りたいのは、厳密には回答内容自体ではないのです。
面接官は深掘り質問を通し、応募者の人柄・考え方・相性など、さまざまな要素を総合的にチェックしています。完璧そうな回答をした場合でも、考え方に相違があれば落ちることもあります。大切なのは、たとえしどろもどろであっても、自分の意思を伝える姿勢なのです。
企業が面接で深掘り質問をする意図は?
そもそも企業が面接で深掘り質問をする意図はどこにあるのでしょうか?面接は、企業側・学生側がお互いを理解する場です。
深掘り質問により、企業側は学生について理解を深めます。
ここでは深掘り質問の意図を、3つに分けて説明します。
企業にマッチした人材か確かめるため
企業にはそれぞれ文化や社風があり、それに合うかどうかは重要な指標のひとつです。企業文化や社風に合うか判断するためには、学生の性格や価値観、適性を判断する必要があります。社風や企業文化と学生の相性が悪いと、早期退職につながります。早期退職は企業にとっても学生にとっても大きな損失です。「自分の希望と合わなかった」や「社風が自分に合わなかった」などの理由で退職することを避けるために、企業は深掘り質問を実施しています。
志望度合いを確認するため
深掘り質問を通して、学生の本気度や志望度の高さを推測する企業もあります。特に志望動機に対する深掘り質問では、なぜその企業でないといけないのか、を深掘りして確認します。学生がどの程度企業に興味を持っているか、入社後どのように貢献できるかを見極めているのでしょう。内定辞退を防ぐため、学生の本気度を知るために深掘り質問をしています。
人柄や思考を把握するため
事前に準備した回答だけで、企業側がその人のすべてを把握することは難しいでしょう。そのため、その出来事が起きたときの考え方や、学生の人柄をより理解するために深掘り質問をします。
応募者の内面をより理解するために、「なぜそうしたのか」「なぜそのように考えたのか」などを質問しています。直感タイプか、データ重視か、どちらのタイプかによって社風に合う・合わないも出てくるでしょう。深掘り質問には本音で答えることで、入社後のミスマッチも避けられます。
対応力を見るため
面接官は深掘り質問を通して、応募者の対応力をチェックしています。回答の内容自体よりも、イレギュラーに対する立ちまわり方や機転の利かせ方、柔軟性などを審査している可能性も高いでしょう。
面接官のなかには、わざと答えにくい質問を投げ、応募者の動揺を煽るケースも。回答を準備していないだろう質問への対応を通し、「その場でどのように考え、どのような発言をするのか」に焦点を当てています。応募者からすると意地が悪いように感じるかもしれませんが、社会においてイレギュラー時の対応力や冷静さは重要な要素なのです。
面接の深掘りで聞かれる内容は?
面接の深掘り質問では、面接官がもっと聞きたい・知りたいと思った部分について聞かれます。どの観点から質問するかによって、企業の意図が分かります。ここでは具体的に聞かれやすい内容を4つご紹介しましょう。
Why(なぜ?)
5W1Hを聞いたことはありませんか?これは英語の「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どうして」の頭文字を集めたものです。深掘り質問では、Why(なぜ)がよく聞かれます。なぜその行動をしたのか、なぜその経験を積もうと思ったのか、動機を聞きたい場合に使われます。単にそうしたかったから、と答えるのではなく、当時の心境を振り返って理由を論理的に話しましょう。
What(何を?)
5W1HでWhyの次に注目されやすいものがWhat(何を)です。これは事実確認のために使うことが多く、「具体的に何をしたのか?」「どのような課題があったのか?」で質問されます。面接官に分かりやすく伝えるためには、具体的な数値などを踏まえて説明しましょう。そうすることで、より分かりやすく伝えられます。また、何をしたか深掘りすることで、学生の行動や思考を掘り下げたい場合にも使われます。
How(どうやって?)
5W1Hの”H”の部分に対応するHow(どうやって)にまつわる深掘り質問もよく聞かれます。「どのように実現したのか?」「どのような工夫をしたのか?」など、プロセスを知りたいときによく用いられる質問形式です。
学生が課題解決のためにどのような工夫をしたか、最終的にどのような手法で解決まで導いたかを知るために、この質問を投げかけています。企業は考え方も含めた過程を知りたいため、結果だけを伝えるのではなく結果までの具体的な取り組みについて述べると、説得力ある回答になるでしょう。
今後どのように活かすのか
ここまでは過去の出来事に関する回答への深掘りでしたが、将来の展望を問う深掘り質問もよく聞かれます。「その出来事で得たことを入社後どのように活かしたいか」「その出来事をもとにどのようなキャリアを描きたいか」などの質問です。
学生が学んだことを入社後にどのように応用できるかや、将来の長期的なビジョンを持っているかを判断するために聞いています。この手の質問に曖昧に回答すると、準備不足を疑われます。どのように将来につなげるか、具体的に答えるようにしましょう。
面接で深掘り質問に答えられないときの対処法
ここでは、面接で深掘り質問に答えられないときの対処法をご紹介します。とくに人前で話すのが苦手な人は、想定外の質問をされると頭が真っ白になってしまうこともありますよね。本番で動揺が現れないように、深掘り質問への対応に備えましょう。
時間をもらいたい旨を伝えて考えをまとめる
もし深掘り質問に答えられないときは、無理にすぐ言葉にする必要はありません。正直に「回答に少しお時間をいただけますか」「自分のなかで少々考えをまとめさせてください」と伝えれば、多くの面接官は肯定的に応じてくれます。
最大1分間程度であれば、考える時間をもらっても問題ありません。慌てて思ってもいないことを言ってしまうよりも、多少待ってもらってでも誠実な回答をしたほうが、遥かに良い印象を与えられるでしょう。
わかる部分だけでも回答する
面接の深掘り質問では、聞かれた内容にすべて答える必要はありません。「この質問には自信を持って答えられる」という箇所だけを、真摯な姿勢で伝えましょう。
とはいえほかの質問を完全に無視してしまうのは印象が悪いため、「〇〇については今すぐにお答えすることは難しいですが、△△についてはこのように思っております」と断りを入れることも忘れずに。答えられる内容を最後の順番に持ってくることで、より良い印象を伝えられます。
どうしても答えが思いつかない場合は「わからない」と伝える
考える時間をもらえても、どうしても答えが思い浮かばない場合もあるでしょう。深掘り質問に答えられないときは、嘘や表面的な意見をいわず、素直に「わからない」と伝えたほうが得策です。
その場しのぎの回答をしてしまうと、その後のやり取りで整合性を取るのが難しくなります。もし二次面接・三次面接に進んだ場合でも、「一次面接で言ったことと違う」と評価されてしまうでしょう。わからないときは、「勉強不足により」「〇〇と△△の理由から」などのように、わからない理由も添えるとより誠実です。
面接の深堀りに答えられないときに取ってはいけない行動
ここでは、面接の深掘り質問に答えられないときに、取ってはいけない行動をご紹介します。答えにくい質問をされると、パニックになって自分らしくない行動を取ってしまうこともありますよね。咄嗟の言動で自分の首を絞めてしまわぬように、事前に注意点を確認しておきましょう。
長時間黙り込む
深掘り質問でやってはいけないことの一つが、長時間黙り込むことです。回答を真剣に考えようとすると、つい自己中心的な態度を取ってしまうことも。もし考える場合は事前に断りを入れ、最大でも1分程度に収めるように心がけてください。
断りがない状態で長考すると、面接官にとって「回答がない」というネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。また時間の使い方において自分本位なイメージを抱かせ、誠実さの欠けた人物として受け取られてしまうかもしれません。
事実とは異なる回答をする
深掘り質問では、事実とは異なる回答は絶対にしないように心がけましょう。面接官は人を見るプロでもあります。深掘り質問に慌てて思ってもいないことを言うと、「今、適当なことを言ったな」「その場しのぎの嘘をついたな」とバレてしまうものです。
もし嘘がバレなくても、後々の対話で整合性が取れず困るのは自分自身です。事実とは異なる内容を伝えるくらいであれば、素直に「わかりません」と伝えたほうが誠実な印象を与えられます。
すぐに「わからない」と回答する
前項では「わからない」も一つの手段であることをお伝えしましたが、深く考えもせずに「わからない」と伝える対応は逆効果です。質問されてすぐに「わからない」と答えると、「諦めが早すぎる」「思考力がない」と評価されてしまう可能性があります。
面接での言動は働き方のイメージに直結するため、「仕事で難しい課題が出てもすぐに投げ出しそう」「トラブルが起こっても他人任せにしそう」のような悪い印象を与えてしまうことが懸念されます。
面接の深掘りが答えられない場合の対策は?
深掘り質問の傾向を知っていても、面接で答えられないこともあるでしょう。どのような質問が来ても答えられるように、事前にできる深掘り対策をご紹介しましょう。
自分で深掘りをしてみる
最初に紹介する方法は今すぐにでもできるやり方です。ガクチカや自己PRで話すエピソードに対して自分で「なぜ?」を繰り返し、自分で深掘りする方法です。
一つの事項に対して5回「なぜ?」を繰り返し、その回答を考えるやり方が一般的でしょう。自問自答を繰り返すことで、当時の理由だけでなく現在の価値観に至った背景が分かるといわれています。同時に、忘れていた記憶もよみがえり、新たな発見にもつながります。一つの質問に対して、5回「なぜ?」と問いかけてみましょう。
周囲の人に深掘りしてもらう
次に紹介するやり方は、周りの人に協力を仰ぐやり方です。自問自答を繰り返す方法は限界があるでしょう。自分自身では分からないこともあるため、第三者から深掘りしてもらう方法も効果的です。両親や兄弟、友人、先輩、などに質問してもらうこともよいでしょう。人によっては思わぬ変化球を投げてくれます。予想外な深掘り質問にも対応できるように、第三者の視点を活用しましょう。先ほど紹介した「なぜ?」を5回繰り返す方法がおすすめです。
企業分析を徹底的に行う
面接の根ほり質問に答えられないときは、企業分析を徹底的におこなうように努めましょう。企業の理念やミッション、事業内容などを詳しく把握することで、「会社のどの部分に惹かれたのか」や「どのようなキャリアアップを望むのか」などが明確になります。
実際、深掘り質問で聞かれやすいのは、企業概要やキャリアプラン周りが中心的です。回答の軸となる部分への思慮を深めておけば、どのような質問にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。
面接対策は「REALME」を活用!
面接での深掘りに対応するには、事前準備だけでなく面接練習も有効です。キャリアセンターでの模擬面接もよい方法ですが、面接練習はできるだけ回数をこなしたいでしょう。そこでおすすめしたいものが「REALME」です。
AI面接を通して自己分析ができる
「REALME」ではAI面接が何度でもできます。AIがよくある質問から深掘りまでさまざまな質問を投げかけてもらえるため、効果的な面接練習ができるでしょう。
面接練習だけでなく、面接の回答内容から自分の強み・弱みも分析できます。就活で問われやすい14の能力を定量化して客観的に分析し、強みに合った企業や職種も分かります。
AI面接の結果で志望企業の内定判定が分かる
AI面接の分析結果を過去の合格者データと比較することで、企業ごとに内定判定が確認できます。A+~Eまでの10段階で、どのような企業なら内定が出やすいかが分かるでしょう。面接で深掘りする理由の一つである社風に合うかどうかを、あらかじめ把握できるともいえるでしょう。内定判定を上げるためのフィードバックも提供しています。
合格ラインにいる就活生のAI面接データが見られる
内定の可能性をより上げるために、合格ラインにいる就活生のESやAI面接でどのような受け答えをしたかが確認できます。合格者データをもとに自分のガクチカや自己PRをアレンジしてもよいでしょう。別のエピソードを準備するなど、面接の質を上げる効果的な対策が可能です。データはテキストで確認できるため、ESのブラッシュアップにも応用できます。
面接対策をして深掘り質問に備えよう!
面接対策でも準備しにくい深掘り質問ですが、企業側とのマッチング率を上げるために、対策は必要不可欠です。企業は学生をより理解し、本当に自社に合うかを見極めるためにさまざまな観点で深掘りします。面接前に、深掘り質問の準備を済ませておくと、落ち着いて対応できるでしょう。
「なぜ?」を何度も繰り返す、周りの人に聞く、などできるだけの対策をして面接当日を迎えましょう。
深堀り質問対策の自己分析には「REALME」がおすすめです。