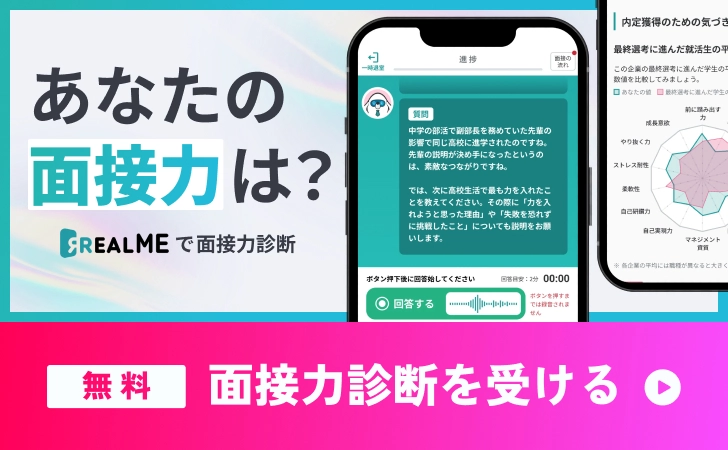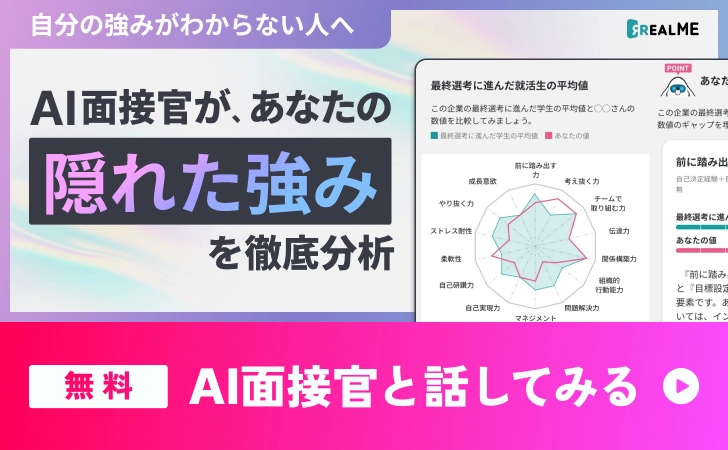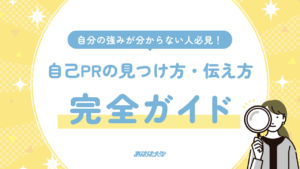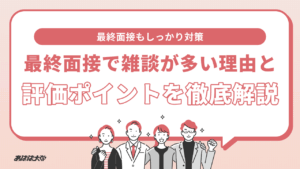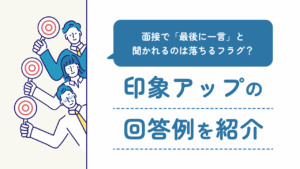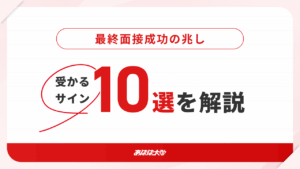面接対策の一環として欠かせない面接練習ですが、やみくもに繰り返せばよいというわけではありません。面接練習のやりすぎはよくない?と検索されるほど、やり方次第で逆効果になることもあります。
この記事では、やりすぎない面接練習の方法や効果的な取り組み方について解説します。
効果的な面接練習には、REALMEがおすすめ。今までの合格基準に達したデータをもとに、AIから的確なアドバイスをもらえます。
面接練習のやりすぎはよくない?
面接練習には、「何回やれば十分」などの明確な正解はありません。人によって理解度や成長スピードが異なるため、練習回数にこだわるよりも、自分が納得できるまで取り組むことが大切です。面接の目的は、話す内容を丸暗記することではなく、自分の考えを的確に伝えられるようになることです。
面接練習のやりすぎはよくない、といわれるように、繰り返しすぎて内容が機械的になったり、緊張感が薄れることは避けたいところでしょう。時間や回数に固執せず、目的意識を持った練習がポイントです。
面接練習のやりすぎが逆効果になるとき
面接練習は就活対策として非常に有効ですが、やりすぎることで逆効果になる場合があります。練習の目的を見失い、内容が形式的になると、本来伝えたい人柄や熱意が伝わらないこともあるため注意しましょう。
ここでは、面接練習のやりすぎが逆効果になるときについて紹介します。
回答を丸暗記しているとき
面接練習を繰り返すうちに、回答をそのまま丸暗記するケースがあります。これが「面接練習のやりすぎ」といわれる典型的な例です。内容をセリフのように覚えてしまうと、話し方が棒読みになり、感情が伝わらず面接官に違和感を与える恐れがあります。
また、複数の企業で同じ内容を使い回していると、志望度や熱意が低いと判断される可能性もあります。面接では伝えたいポイントを自分の言葉で自然に話すことが大切です。練習は必要ですが、伝える姿勢や話し方に気をつけましょう。
想定外の質問に答えられないとき
面接練習をやりすぎた結果、暗記した質問にしか対応できない場合があります。よくある質問を丸暗記していると、少しニュアンスの違う質問が出た際に戸惑い、答えに詰まることもあるでしょう。このような反応は、柔軟性やコミュニケーション能力が不足している印象も与えかねません。
また、自分の言葉で考える習慣が身についていないと、深掘りされた質問に対応できず、表面的な受け答えに終始する恐れもあります。面接練習は大切ですが、臨機応変に対応する力を養うためにも、毎回同じパターンに頼りすぎないようにしましょう。
型を意識し過ぎてしまうとき
型を意識した面接練習をやりすぎると、本番での咄嗟の対応ができなくなってしまいます。面接では定番の質問のほかに、企業や面接官ならではのオリジナルな質問もされます。確立された型ばかりに頼っていると、臨機応変な受け答えが難しくなってしまうのです。
想定外の質問に慌てると頭がパニックになり、質問とずれた回答をしてしまうことも。面接官からすると「質問を聞いていない、読解力が低い」「緊張やプレッシャーに弱い」などのような、ネガティブな印象を与えてしまいます。
面接練習をやりすぎないためにはゴールを考えることが大切
ここでは、面接の練習における本質的なゴールについてご紹介します。面接練習をやりすぎないためには、明確なゴールや目的を意識することが大切。ただ同じ内容を反復して覚えるだけではなく、自分を適切にアピールするための手段として、面接練習を進めていきましょう。
面接に対する緊張を和らげるため
面接における練習は、本番に対する緊張を和らげるために役立ちます。緊張には「初対面の相手と話すことによる緊張」や「当日の環境や体調などによる緊張」など、さまざまな種類があります。
緊張の種類のなかでも「練習不足による緊張」は、事前の反復練習によってある程度解決できる要素です。苦手な部分を練習し、本番の形式に慣れることで、自信を持って面接に挑めるようになるでしょう。練習による緊張のケアは、落ち着きのある冷静な受け答えにつながります。
面接官に伝えたい内容を正しく伝えられるようにするため
面接官に伝えたい内容を正しく伝えるためにも、面接の事前練習は役立ちます。「思考をまとめる能力」と「思考を文章にする能力」と「文章を相手に正しく伝える能力」は、それぞれ異なるものです。反復練習では、上記の能力をそれぞれ向上させ、本番での失敗率を下げられます。
面接では「正しく伝える」だけではなく「わかりやすく伝える」も非常に大切。練習によって文章構成を改善したり、「あの」「えっと」などの余計な言葉を言わない状態にしたりすることで、面接官の印象が上がります。
想定外の質問にも冷静に対応できるようにするため
面接の事前練習は、想定外の質問に冷静に対応するためにも効果的です。なぜなら練習を繰り返すことで、自分のなかの価値観や思想が固まっていくからです。「自分がどのような人間か」「どのような思想や気持ちを持って働こうとしているか」が自覚できるほど、咄嗟の質問にも明確に回答できるようになります。
普段の練習から、一つひとつの回答に至った理由や価値観などを掘り下げておけば、本番での言語化も容易に。心理や思想を根掘り葉掘り聞かれても、焦らずに対応できるでしょう。
面接練習をするメリット
ここでは、本番前に面接の練習をするメリットについてご紹介します。繰り返し練習する目的は、本番での受け答えの完成度を上げるためだけではありません。練習により自信が芽生え、同じ内容でもより堂々とした表情や声色になっていきます。
受け答えに不安がなくなる
面接の練習をするメリットは、受け答えに不安がなくなることです。繰り返し練習することで、伝えたい内容や、テンプレートとなる文章構成が脳に定着していきます。その結果、本番で緊張していても円滑に言葉が出てきやすくなります。
練習では、自分を客観的に分析するプロセスが必要です。練習を重ねるごとに内容が改善され、本番で「本当にこの受け答えで良かったのか?」と不安に思う機会も減っていくでしょう。内容だけではなく、文章や単語ごとの間合いも体に染み込んでいきます。
自分の話し方のクセや改善点がわかる
面接の本番前に練習を繰り返せば、自分の話し方のクセや改善点がわかります。たとえば緊張すると早口になったり、「えー」「あー」などの言葉が挟まりやすくなるのはよくあること。本番前に悪癖を改善できれば、面接で良い印象を与えられる可能性も増えていきます。
ほかにも「相手から目を逸らしてしまう」「気を抜くと猫背になる」「考えていると口が開きやすい」など、人によって悪癖は異なります。ただ練習するだけではなく、録音や録画も通して繰り返すことで、より改善点を発見しやすくなるでしょう。
面接練習の最適な頻度・時間
ここでは、面接練習に最適な頻度や時間をご紹介します。学業・仕事と就職活動の両立では、練習する時間も限られるものですよね。最低限必要とされる頻度や時間を確保したうえで、効率的な面接練習につなげていきましょう。
1日あたりの練習時間は30分~1時間程度
面接の練習は、1日あたり30分~1時間程度が最適とされています。一度に長時間練習すると、後半は疲れて集中力が下がり気味に。頭の回転の速さを維持できる時間帯で、集中して練習したほうが定着しやすくなります。
面接における一般的な自己PRの長さは、1分程度とされています。とはいえ企業によって、30秒程度や5分程度など求められる時間も異なるもの。面接の練習では反復回数も重要ですので、企業が求める時間によってトータルの練習時間(反復回数)も調整しましょう。
練習する頻度は週2~3回
面接を練習する頻度は、週2~3回程度が理想的。もちろん面接直前の数日間であればこの限りではありませんが、基本的には2~3日に1回以上のペースで進めていけば問題ないでしょう。
毎日練習するのも一つの手段ですが、人によっては練習自体に慣れてしまい、流れ作業のような感覚になってしまうことも。本番まで適度な緊張感を維持するためにも、あえて2~3日に一度に収めておくことが推奨されます。上記を参考のうえで、自身のライフスタイルや進捗に合わせて調整してくださいね。
効果的な面接練習の方法
面接練習はやみくもに繰り返すだけでは意味がありません。前述のように面接練習のやりすぎによって臨機応変な対応力が落ちることもあるため、練習方法の工夫が大切です。
ここでは、効果的な面接練習の具体的な方法について解説します。
動画を撮影する
一人で面接練習する際におすすめの方法が、面接練習をスマートフォンなどで撮影することです。何度も撮り直しができるため、自信がつくまで繰り返すことが可能です。後から映像を見返すことで、自分では気づけなかったクセや無意識の動き、話し方のトーン、表情の硬さなどを客観的に把握できます。
改善点の明確化ができるため、着実に面接のブラッシュアップが可能です。面接練習をやりすぎて内容が型にはまる前に、俯瞰での確認を取り入れることで自然な受け答えを身につけやすいでしょう。
面接アプリを活用する
面接練習アプリを使うことで、実際の面接に近い雰囲気で練習を重ねられます。最近はAIを活用した面接アプリなども人気です。さまざまな業界や職種に合わせた模擬面接が用意されているため、想定外の質問に対する応答力を養えるでしょう。
たとえば、「REALME」ではAI面接だけでなく、自己PRやES、FBなどすべての対策が可能です。
面接練習をやりすぎて同じ答えばかり繰り返さないためにも、このようなアプリを使って新たな角度の質問に挑戦し、柔軟性を高めましょう。
YouTubeを活用する
話し方や表情、マナーなどに不安がある場合は、YouTubeの面接対策動画を活用すると効果的です。実際の面接を模したシミュレーション動画や、質問ごとの模範回答を紹介する動画が多数公開されています。これらを参考にすることで、自分の受け答えとの違いを確認しやすく、改善点が見つかるでしょう。
また、動画を視聴するだけでなく、自分でも同じ質問に答えてみると、思考力や表現力のトレーニングにつながります。面接練習をやりすぎてパターン化しないためにも、新たな視点を得る手段としておすすめです。
鏡の前で表情やジェスチャーの練習をする
面接の効果的な練習方法としては、鏡の前で表情やジェスチャーの練習をすることも挙げられます。自分が思っている姿勢や表情は、相手からすると大きく印象が異なることも。鏡によって面接官の視界をシミュレーションすることで、より好印象な対応につながります。
とくに表情が硬くなりやすい人や、緊張で肩に力が入りやすい人などは、鏡での練習が役立ちます。自分の正面に鏡を設置し、自己紹介しているときの全体の動きや印象を確認しましょう。
就活イベントに参加する
時間に余裕がある場合は、就活イベントやセミナーへの参加も非常に有効です。これらのイベントでは模擬面接が実施されることも多く、企業の採用担当者やキャリアアドバイザーから直接フィードバックを受けられる貴重な機会があります。
実践を通じて自分の強みや課題に気づけ、面接練習をやりすぎて形式的になってしまった人にも、自然なやりとりを取り戻す助けとなり得ます。志望企業のセミナーがあれば積極的に参加し、業界理解や人物像の把握にもつなげましょう。
第三者からフィードバックをもらう
一人での面接練習だけでは、自分の改善点に気づきにくい場合があります。そのため、家族や友人に面接官役を依頼し、フィードバックをもらう方法もおすすめです。第三者の視点によって、自分では意識していなかった言葉の使い方や表情、受け答えの内容などを具体的に指摘してもらえます。
また、可能であれば志望企業のOB・OGにお願いすると、企業に即したリアルなアドバイスを得られるでしょう。面接練習をやりすぎて、型通りの受け答えに偏ってしまうリスクを避けるためにも、他者からの評価を取り入れて柔軟性を磨くことが重要です。
就活エージェンシーを活用
効果的な面接練習のためには、就活エージェンシーも活用しましょう。各種就活エージェントでは、エントリーシートの添削や面接対策、グループディスカッションの準備まで、幅広く対応してもらえます。
模擬面接はもちろん、自身の自己PRや志望企業に応じたフィードバックを貰えるのも大きな魅力。就活エージェントは、いわば就活のプロ。企業のミッションやビジョンとの親和性も踏まえたPR内容も一緒に考えてくれます。
面接練習で押さえるべきポイントとは?
ここでは、面接練習で押さえておきたいポイントについてご紹介します。面接では、話す言葉の内容以外でも、さまざまな要素をチェックされているものです。自分の言動を客観視しつつ、面接官に与える印象を改善していきましょう。
早口にならないよう落ち着いて話す
面接の練習では、早口にならないように落ち着いて話すことが大切です。練習不足で慌ててしまうときはもちろん、何度も練習して内容が定着している人も要注意。脳内で文章が完成されているからこそ、機械的な早口で言葉に出てしまう場合があります。
練習段階から早口に慣れていると、本番でも早口になってしまいがちに。日頃から録音で自分の声を聞きながら、適切なスピード感に調整していきましょう。早口すぎる自己アピールは聞き取りにくいだけではなく、丸暗記の印象を与えてしまいかねません。
堂々とした態度を意識する
面接の練習では、堂々とした態度を意識してください。自信のある様子は、たとえば以下のような要素に現れます。
- ハキハキと聞き取りやすい声
- 早すぎず遅すぎず、適度なスピード感の喋り方
- 美しい姿勢で胸を張る
- 相手の目を真っすぐに見る
- 基本的に口角を上げ、笑顔を心がける
「目を見ればいい」「声が大きければいい」というわけではなく、さまざまな要素が複合的に合わさっていることが大切です。自信のある態度はそれだけで良い印象につながり、合格率に直結します。
相手の目を見て話す
上記のなかでも、とくに心がけたいのが「相手の目を見て話す」こと。どれほど優れたガクチカや自己PRでも、いざ伝えるときに自信が無さそうであれば、面接官の心象が下がってしまいます。
相手の目を見ての発言は、自信を伝えられるだけではなく、精神的に落ち着いた印象も与えられます。面接中に終始目を合わせ続ける必要はありませんが、なるべく焦点を合わせるように心がけましょう。練習の時点でも他者に付き合ってもらい、目を逸らさない訓練をするのがおすすめです。
声の大きさは適切か
練習時点から、声の大きさにも気を配りましょう。ただし、ただ声が大きければ良いというわけではありません。相手にハッキリと聞こえる大きさを心がけつつも、口を普段より大きめに開け、活舌よく話すことが大切です。
そのため練習前から顔をマッサージしたり、口元を動かしたりして筋肉をほぐしておくのがおすすめ。「日常的な話し声よりも少し大きめの声」を意識し、鼻にかからないように喋る練習をしましょう。Web面接の際は、声が大きすぎて割れてしまわないように、デバイスの集音環境にも注意を払ってください。
姿勢は曲がっていないか
面接の練習では、美しい姿勢であるかどうかにも留意しましょう。猫背で顎が出ているような姿勢では、一見するだけで「自信が無さそう」「社会性が低そう」といった印象を与えてしまいます。
面接時の正しい座り方は「背筋を伸ばして椅子に浅く座り、足と手を正しい位置に置く」が基本。とくに普段から猫背の人は、気を抜いたときに姿勢が悪くならないように要注意。男性はガニ股にならない練習を、女性は長時間足を開かずに座る練習をしておきましょう。
やりすぎと思われない面接練習のコツ
面接練習はやりすぎによって逆効果になる恐れもあるため、少ない時間で本番を想定して行うなど、質の意識が大切です。また、練習の目的を「改善点の把握」として明確にし、形式だけに偏らないよう注意しましょう。
ここでは、やりすぎと思われない面接練習のコツについて解説します。
本番に近い雰囲気を意識する
面接練習は、ただ回数を重ねればよいというものではありません。本番に近い雰囲気を意識して取り組むことが重要です。一人で練習する場合でも、本番と同じスーツを着て身だしなみを整えることで、緊張感や集中力を高められます。さらに、本番と同じ時間帯の練習によって、体調や思考のリズムも調整しやすいでしょう。雰囲気や環境づくりも結果に影響します。形式的な反復ではなく、自然体で挑む姿勢を養うことが大切です。
入退室まで練習する
面接は話の内容だけでなく、第一印象やマナーも評価に影響します。そのため、入室や退室といった一連の動作も面接練習に含めることが大切です。ドアのノック・あいさつ・着席のタイミング・退出時の礼など、細かな動作を繰り返すことで、本番でも落ち着いて行動できます。
面接練習をやりすぎると内容に意識が偏り、動作が不自然になったり所作に戸惑うケースがあります。話す練習と同様に入退室の流れも、身につくまで繰り返し確認しましょう。
回答を丸暗記しない
面接練習では、回答の丸暗記は避けましょう。セリフのように覚えてしまうと、抑揚がなく棒読みになり、面接官に熱意が伝わりません。また、想定外の質問に柔軟に対応できず、焦ってしまう原因にもなり得ます。伝えたい要点だけを覚えておき、自分の言葉で自然に話す練習を心がけるとよいでしょう。
練習では、暗記に頼らず自分の考えや経験を言葉にする力を養うことが重要です。面接練習をやりすぎることで、形式的な回答ばかりに偏ることもあるため、練習では表現の幅を広げましょう。
分かりやすく簡潔に話す
面接で好印象を与えるには、分かりやすく簡潔に話す力が欠かせません。練習の際は「結論ファースト」を意識し、何を伝えたいのかを最初に述べる習慣をつけましょう。その上で、理由や具体例を簡潔に補足すると説得力のある回答ができます。
要点が整理された話し方は、コミュニケーション能力の高さを印象づけます。面接練習をやりすぎると、内容を詰め込みすぎて話が冗長になることもあるため、注意しましょう。相手に伝わりやすい構成を身につけることが、よい面接対策に直結します。
最少工数で面接練習するならAI模擬面接「REALME」
「面接練習をやりすぎてしまった」「やりすぎて丸暗記にならないか心配」という方にはREALMEがおすすめ。最小限でより実りのある面接練習の時間にしましょう。
20分の面接練習で志望企業の合格可能性がわかる
REALMEを使えば、20分間AIと模擬面接するだけ。まるで大学模試のように志望企業の合格率判定が出ます。
本番の面接前に客観的なフィードバックを貰いながら面接練習できるので、余計な面接練習に時間を費やさなくて済みます。
過去の合格基準に達した就活生のAI対話が見れる
まずは先人の例を参考に。REALMEなら合格ラインに達した就活生のAI対話をテキストで閲覧できます。
「どういった受け答えが評価されるのか?」など、本来なら集団面接といったリアルな場でしか見られない情報を閲覧できるのはREALMEだからこそのメリットです。
自分の強みにマッチした企業からLINEでスカウトが届く
REALMEは単なる面接練習アプリではありません。AI面接で可視化された強みをもとに、企業からスカウトが届きます。
※REALME招待状送付機能の利用企業(一部抜粋)
住友商事株式会社/アサヒグループ食品株式会社/株式会社NTTドコモ/東京海上日動火災保険株式会社/株式会社三菱UFJ銀行/株式会社毎日新聞社/LINEヤフー株式会社/株式会社ディー・エヌ・エー/株式会社Speee/株式会社ワンスター/株式会社CARTA HOLDINGSなど
面接練習のやりすぎに関するQ&A
ここでは、面接練習のやりすぎに関連する質問・回答をご紹介します。「何度も繰り返して練習しているのに不安が拭えない」「練習の頻度や内容について周りに相談しにくい」と思っている人は、ぜひ参考にしてくださいね。
面接練習はしない方がいい?
まず「面接練習はするべき?しないべき?」という疑問についてお答えします。結論から言うと、基本的に面接練習は「したほうがいい」が回答です。人前で話すのが得意な人であっても、練習を繰り返すことで内容がより洗練されていきます。
「自分の言葉を誤解なく伝えられているか?」「目線は泳いでいないか?」など、面接練習でチェックするべき項目は多いもの。反復練習の度に改善点が見つかっていくため、ブラッシュアップの回数に応じて自信にも結びついていきます。
面接練習は何回やるべき?
面接練習における回数には、とくに明確な決まりはありません。強いて言えば「自分が安心できるまで」「自信を持って面接に挑めると確信できるまで」が目安といえるでしょう。そのため「数回程度で十分」という人もいれば、何十回やっても足りないと感じる人もいます。
目標回数を決めるのは、あくまで自分の心なのです。何度練習しても不安が拭えないのであれば、それは回数ではなく心の持ち方の問題ということになります。自分の心や性格とも向き合いながら、「どこまで練習すれば安心できるのか」を考えることが大切です。
面接練習は何日前から始めればいい?
面接練習を始める時期にも明確な基準はありませんが、一般的には1~2週間前から始める傾向にあります。直前のみの練習では十分な練習ができず、記憶も定着しません。ある程度の期間を設けて反復することで、緊張していても自然と言葉が出てくる程度に内容を暗記しやすくなります。
何より、「自分はこれだけ練習した」という自負は、当日の自信につながります。とはいえ当日までのスケジュール調整もありますので、「最低1週間は確保する」を目安にしつつ、無理のない練習予定を組みましょう。
練習前に何をすればいいですか?
闇雲に練習をするよりも、事前に「今回の練習のテーマ」を決めておくと、より建設的かつ効果的な練習時間になります。たとえば「笑顔を絶やさないように心がける」「最後までハキハキと喋る」のように、練習ごとの目標を設定してみましょう。
課題があれば明確にしておき、克服するための準備をしたうえで練習に望みます。また話す内容に関連するキーワードをまとめておくと、本番を想定した練習中でも思い出しやすくなるためのおすすめです。
まとめ
面接練習は自信を持って本番に臨むために必要ですが、やりすぎによって逆効果になる場合もあります。丸暗記に頼ることで会話の自然さが失われたり、練習本来の目的を見失って内容ばかりにとらわれないようにしましょう。
適切な回数と方法によって本番に近い環境を再現し、回答だけでなく所作やマナーまで含めた総合的な準備が大切です。面接練習では、「伝える力を磨く」意識を持ち、質重視の練習を心がけましょう。準備の仕方一つで、面接本番の成果は大きく変わります。

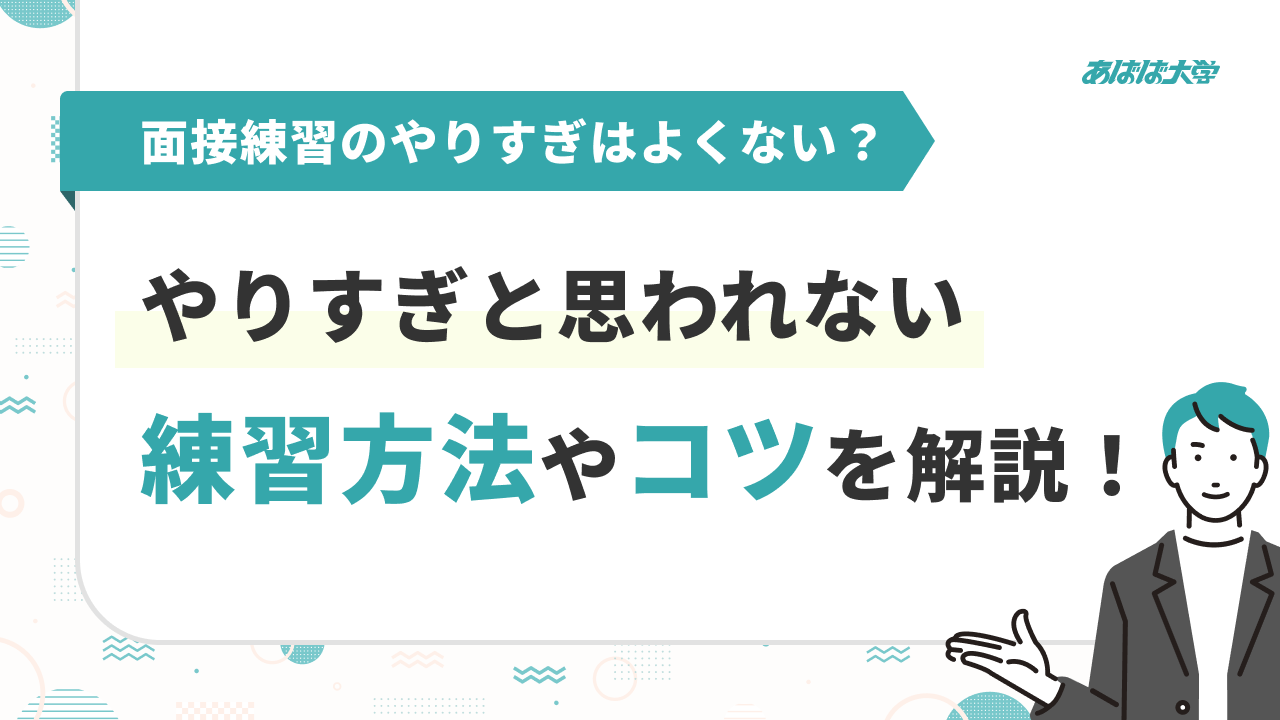
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)