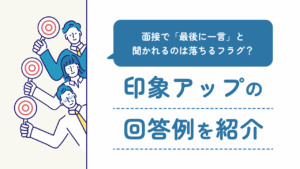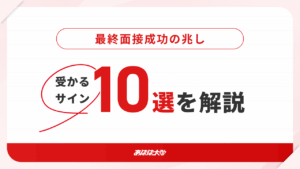面接での逆質問は、入社意欲や企業理解を示す大切な機会です。「特にありません」と答えると、熱意が感じられずマイナスの印象を与えかねません。
しっかりと企業研究を行い、自分の強みを活かした質問を複数用意することが重要です。
さらに、本番に向けてAI面接「REALME」を使えば、逆質問も含めた練習ができ、自信を持って面接に臨めます。
効果的な逆質問の準備方法と回避術について解説します。
面接で逆質問が重要な理由は?
面接でも逆質問は単なる形式的なやり取りではなく、採用担当者が応募者の姿勢や思考力を見極める大切な場面です。質問内容次第で志望度や理解力、さらにコミュニケーション能力まで評価されることがあります。面接における逆質問の重要性についてご紹介します。
自社への志望度をチェックされるため
面接の終盤で行われる逆質問は、企業が応募者の志望度を見極める重要なチェックポイントです。
質問の内容によって、どれだけ企業研究を行い、自社の特徴を理解しているか把握できます。採用担当者は質問の有無だけでなく、質問の意図や具体性を通して本気度を判断します。
また、逆質問は質問の場であると同時に、学生が自らの興味を掘り下げる貴重な機会です。企業文化や業務内容について前向きに尋ねれば、意欲がより明確に伝わり評価にも大きく影響するでしょう。
コミュニケーション能力を判断されるため
逆質問の時間は、応募者のコミュニケーション力を見極める場でもあります。質問内容の組み立て方や会話の展開によって、相手の話を理解し、自分の考えを整理して伝える能力が把握できます。
曖昧な質問や調べれば分かる内容を聞いてしまうと、準備不足や理解の浅さを印象づけてしまう恐れがあるため注意が必要です。逆に、相手の説明に関連づけて質問を展開すれば、思考力や対話力を高く評価されやすくなるでしょう。
逆質問は学生主導の時間となるため、コミュニケーション能力があらわになります。的を射ていない質問をすると、評価を下げてしまいかねない点を意識することが重要です。
面接で逆質問に「特にありません」は避けたほうが良い
面接時に逆質問を求められた際、「特にありません」と返答することは避けるべきです。
特にありませんと答えると「興味や熱意が感じられない」「志望度が低いのでは」などの印象を面接官に与え、評価を下げる一因になります。
もちろん「特にありません」と答えた人は、必ず不採用になっているわけではありません。中には採用されるケースもありますが、やはり不採用となる可能性は高まるでしょう。
そのため、企業や仕事に対する関心や意欲が伝わるよう、質問をいくつか用意して臨むことをおすすめします。
逆質問「特にありません」を避けるための面接対策
面接の逆質問で「特にありません」と答えると、意欲不足と受け取られるリスクがあります。やはり効果的な面接対策は、事前に逆質問をきちんと用意することです。
では、逆質問に「特にありません」と答えないために、効果的な面接対策について解説します。
企業研究を事前におこなう
面接で逆質問を準備するならば、企業研究を徹底して行いましょう。
まずは企業のホームページを隅々まで確認し、会社概要や事業内容、経営理念だけでなく、最新のIR情報や業績、社長メッセージなども目を通しましょう。加えて、競合他社と自分が志望する企業の違いや強みもしっかり調べておくことで、独自の視点を持った質問が可能となります。
企業研究を徹底することによって、深い関心や主体的な姿勢を示す逆質問ができるようになり、好印象を与えることができます。
アピールしたいことを決めておく
自分がアピールしたい強みや経験、得意分野を整理しておくと、面接で印象に残る逆質問を考えられます。
どのような人物やスキルを必要としているかを企業研究でしっかり調べたうえで、自身の能力と企業のニーズがどう重なるかを見極めましょう。
たとえば「◯◯の資格を活かしたいですが、御社に貢献するにはほかにどのようなスキルが必要ですか?」と、自分の強みを交えた質問をすると、自己PRと企業理解を同時に伝えられます。
アピールしたいことを決めておくことで、企業が求める人物像に自分が当てはまると自然に主張でき、面接官にも関心と熱意が伝わるでしょう。
3つ以上の逆質問を準備しておく
さまざまな状況に合わせて、それぞれ違うパターンの逆質問を3つから5つほど事前に準備しておきましょう。
複数の複数のテーマや方向性で質問を用意しなければならない理由は、面接中に用意した質問の一部が会話の流れで解消されてしまう場面はよくあるからです。そのため、事前に準備を整えて、柔軟に対応できる状態にしておくと安心でしょう。
保険の意味でも多めに準備しておくことで、「特にありません」と返さずに済み、積極的な意欲や企業理解への熱意も伝わります。
面接で「特にありません」と同じくらいNGな逆質問
面接における逆質問で「特にありません」と答えることは、評価を下げる原因になるため避けるべきですが、同じくらいNGな内容の逆質問があります。
逆質問でNGな内容の質問と、聞いてはいけない理由について解説します。
「はい」「いいえ」と答えるしかない質問
回答が「はい」や「いいえ」で終わる質問は避けるべきです。
「はい」「いいえ」と答えるしかない質問は「クローズドクエスチョン」と呼ばれ、会話を広げにくい特徴があります。
本来、逆質問は応募者の主体性や関心の深さを示すチャンスとなるため、会話を通じて理解を深めることが大切です。自分の考えや興味を踏まえてオープンな質問に置き換えると、より印象的な対話につながります。
せっかくの質問の機会が活かされないため、クローズドクエスチョンには注意が必要です。
待遇についての逆質問
待遇に関する逆質問は、面接で熱意のなさを感じさせるため避けるべきです。
待遇のよさだけを目的に就職を考えていると誤解され、評価が下がるリスクがあります。また、面接官から「仕事への興味が薄い」と受け取られる可能性も高いです。
具体的には「給与はいくらですか?」「残業は多いですか?」「福利厚生はどのようなものがありますか?」などの質問が挙げられます。
もしも待遇面をより詳細に確認したい場合でも、企業研究で得た情報以上の質問は控えましょう。
調べればすぐにわかること
面接で企業のホームページに記載されている内容を、そのまま質問するのは避けるべきです。調べればすぐにわかる質問は、企業研究が不足していると判断され、熱意が感じられない印象を与えます。
たとえば、「御社の企業理念は何ですか?」や「主力商品について教えてください」など、公式サイトで簡単に確認可能な事項を聞くことはNGです。面接では事前に情報をしっかり読み込み、より深い内容や自身の関心に基づく質問を用意しましょう。
ネガティブな逆質問
面接で面接官が答えにくいネガティブな逆質問は避けましょう。
たとえば、「残業時間はどのくらいですか?」や「ネットで見かけた悪い噂について教えてください」などの質問は、応募者に対する印象を悪くしてしまう可能性があります。ネガティブな質問は「仕事に対して前向きでない」「企業に対する理解が浅い」と見なされやすく、評価を下げる原因となることもあります。
ネガティブな逆質問は面接の場でマイナスに働くため、質問内容はポジティブで企業への関心や意欲を示せる内容にしておくことが望ましいです。
逆質問が思いつかないときに使える逆質問リスト
どうしても逆質問が思い浮かばないときに、参考になるリストをご紹介します。
- 熱意が伝わる逆質問リスト
- 面接官についての逆質問リスト
- PRにつながる逆質問リスト
ぜひ、企業や自身の状況に合わせて、逆質問をアレンジしてみてください。
熱意が伝わる逆質問リスト
面接での逆質問では、志望度の高さをアピールできる内容を考えるとよいでしょう。
企業研究をしっかり行い、会社の特徴や事業内容に基づく質問を準備すると熱意が伝わります。企業研究に基づいた逆質問は、熱意を自然に伝えられるため、面接での好印象につながります。
【熱意が伝わる逆質問の具体例】
- 御社の今後の経営戦略について教えていただけますか?
- 入社後に求められるスキルや資質は何でしょうか?
- 現在注力されている新規事業の背景と展望を伺いたいです。
- 社内で特に重視されている価値観や文化について教えてください。
- 将来的に成長するために推奨される研修や学習機会はありますか?
面接官についての逆質問リスト
面接官についての逆質問は、対話を深めるきっかけとなり、応募者の興味と理解度を示すうえで効果的です。
なお、プライベートに踏み込みすぎる内容や答えにくい質問は避け、質問は仕事に関する内容に限定してください。
【面接官についての逆質問の具体例】
- 面接官が仕事で大切にしていることは何か教えてください
- これまでの経験の中で印象に残ったプロジェクトはありますか?
- 社内で特に重視されている価値観や文化についてどう感じますか?
- チーム内でのコミュニケーションや連携はどのように行われていますか?
- 入社してからの成長を促すために心がけていることは何ですか?
PRにつながる逆質問リスト
面接で自己PRにつながる逆質問をすることも、効果的なアピールの手段になります。しかし、自慢話のように聞こえないよう注意が必要です。
逆質問を通じて自分の強みや意欲をさりげなく伝え、企業とのマッチングをアピールしましょう。
【PRにつながるの具体例】
- 私のチームワーク力を活かす場面はどのようなところにありますか?
- ◯◯の経験を入社後にどう活用できるか教えていただけますか?
- 御社で成長するために特に重視されているスキルは何ですか?
- 今後の事業展開において、私の強みをどのように生かせそうでしょうか?
- 御社の価値観に共感していますが、その価値観を具体的に仕事でどう表現されていますか?
どうしても逆質問がないときの対処法
逆質問は基本的に用意しておくべきですが、面接中に疑問がすべて解消してしまうこともあるでしょう。どうしても逆質問が思い浮かばなかった場合に使える対処法をご紹介します。無理に逆質問をひねり出すよりも、好印象を残せるケースもあるため、ぜひ参考にしてみてください。
無理に質問しない
逆質問の時間に焦って何かを口にしようとすると、意図しない発言をしてしまうことがあります。内容に一貫性がなくなると、かえって印象を下げる恐れがあるため、無理に質問を作る必要はありません。
質問をする目的は、企業への理解を深めることであり「沈黙を避けるために何か言う」ではありません。すべての応募者が必ず質問を用意する必要はなく、話の流れで疑問が解消されている場合は無理をせず感謝を伝える選択も適切です。
無理に逆質問を用意するよりも、落ち着いて状況を判断し、誠実な姿勢を示す方が評価につながるため「絶対に質問しなければならない」と考える必要はありません。
感謝の気持ちを伝える
逆質問が思いつかない場合でも、沈黙せずに感謝の気持ちを伝えることで好印象を残せます。面接官は誠実な姿勢や礼儀のある受け答えを重視するため、質問にこだわるよりも丁寧にお礼を述べる方が良い場合もあります。
もしも事前に聞きたいことがすべて解消されているならば、無理に新たな話題を出さず「本日の面接で疑問は解消しました。貴重なお話をありがとうございました」と丁寧に感謝の気持ちを伝えましょう。
質問がない場合は、感謝の気持ちを伝えることもひとつの手です。焦らず誠意を持って対応する姿勢が評価につながります。
あらためて入社後の意気込みを伝える
逆質問の時間は面接の締めくくりになるケースが多く、最後の印象を決める重要なタイミングです。うまく質問が思いつかない場合でも、入社後にどのように貢献したいかを簡潔に伝えると、前向きな姿勢を示せます。
たとえば「本日お話を伺い、より一層御社で働きたい気持ちが強まりました。入社後は〇〇の分野で力を発揮できるよう努めます」と意欲を表すと効果的です。
より好印象を残すならば、前向きな形で終われることが理想です。そのため、あらためて入社後の意気込みを伝え、真向きな印象を残しましょう。
逆質問の精度を高めるコツ3選
逆質問で重要なのは「質」です、精度の高い質問を用意しておくと、より好印象へとつなげられます。以下のコツを押さえつつ質問を考えると精度を高められるでしょう。
- 抽象的ではなく具体的な質問にする
- 面接官の役職に沿った質問にする
- 回答に対する深掘りの質問を想定しておく
逆質問の精度を高めるコツについて解説します。
抽象的ではなく具体的な質問にする
面接での逆質問は、内容の具体性が評価を左右します。曖昧で抽象的な質問をしてしまうと、熱意や理解度が伝わりにくく、印象が薄れるでしょう。
そのため「どのような人材を求めていますか?」のような漠然とした質問よりも「御社で評価される社員の行動特性にはどのような傾向がありますか?」と具体的な切り口を意識するのがおすすめです。
質問に的確さがあれば、事前に企業研究を行っている姿勢も伝わります。抽象的でわかりづらい質問は、それだけで面接官の印象を悪くしてしまうため、より具体的かつピンポイントな質問を心がけると、精度を高められます。
面接官の役職に沿った質問にする
面接官の立場や役職を踏まえて質問内容を調整することもおすすめです。採用方針や研修制度について尋ね、現場の管理職には職場の雰囲気やチーム体制など、具体的な実務に関する質問をするとよいでしょう。
たとえば、人事の面接官に「広報の業務の流れを知りたい」と聞いても、詳しい回答を得られない可能性があります。誰に対して何を尋ねるのが効果的かを意識すれば、質問の質が格段に上がります。
面接官の役職に応じて、聞きたい質問をピックアップすることを意識しましょう。相手の専門分野に沿った内容であれば、理解の深さや準備の丁寧さも伝わりやすくなります。
回答に対する深掘りの質問を想定しておく
質の高い逆質問をするためには、質問を考える段階で「どんな答えが返ってくるか」を想定する必要があります。
回答を予測したうえで、その内容を踏まえてさらに掘り下げられる質問を準備しておくと、会話の流れが自然になり理解も深まるでしょう。たとえば「新入社員の育成体制について教えてください」と尋ねた後に「その中で特に評価される行動はどのようなものですか」と続ければ、関心の高さと考える力を印象づけられます。
逆質問を考える際は、質問に対する回答も想定し、もう一段階踏み込んだ質問を考えるとより精度を高められます。
AI面接「REALME」で逆質問も含めた面接練習をしよう!
就活の面接では、最後に逆質問を求められる場面がありますが、「特にありません」と答えてしまうと意欲不足と思われる可能性があります。
AI面接サービス「REALME」ならば、本番さながらの模擬練習を通じて、逆質問も含めた万全の面接準備が可能です。
AI面接で本番さながらの練習をして逆質問を考えよう
面接で逆質問の時間に「特にありません」と答えてしまうと、熱意が伝わらずマイナス印象になることがあります。REALMEのAI面接では、志望動機や自己PRだけでなく、逆質問の練習も含めて本番同様のシチュエーションを体験可能です。
面接官役のAIが質問を投げかけるため、実際の面接の流れを掴みながら、自分らしく意欲的に逆質問を伝える力を身につけられます。
他の就活生の対話データをチェックして逆質問を準備しよう
REALMEでは、他の就活生が実際に行った面接の対話データを閲覧できます。そのため、どのような逆質問が面接官に好印象を与えやすいパターンかを学べます。
自分の視点だけでなく多くの事例からヒントを得ることで、企業への関心や理解度を示す質問の事前準備が可能です。REALMEで事前準備をしておくことで、本番で「逆質問は特にありません」と答えるリスクを減らせます。
AI面接で強みが可視化され、あなたに合った企業からオファーが届くので安心
REALMEのAI面接は受け答えの内容や声のトーン、表情などを総合的に分析し、自分の強みや改善点を見える化できます。診断結果にもとづき、自分にマッチする企業からオファーが届く仕組みもあるため、納得感のある企業選びが可能です。
納得感ある企業選びによって、逆質問の準備に行き詰まってしまうリスクも回避でき、採用の可能性を広げられるでしょう。
面接の逆質問に「特にありません」と答えるのはもったいない
面接で逆質問に「特にありません」と答えるのは非常にもったいないです。なぜならば、逆質問は応募者の熱意や関心を示す絶好のチャンスであり、自分をアピールする場面として活用すべき機会だからです。
さらに、逆質問を用意していないと、準備不足や興味の薄さと受け取られ、評価が下がる可能性が高まります。面接で好印象を残すためには、事前にしっかりと質問を考え、企業への関心や意欲を示せるようにしておくことが重要です。
ぜひ、逆質問の対策をきちんと整えて、自分の強みを伝える機会として大いに活かしましょう!

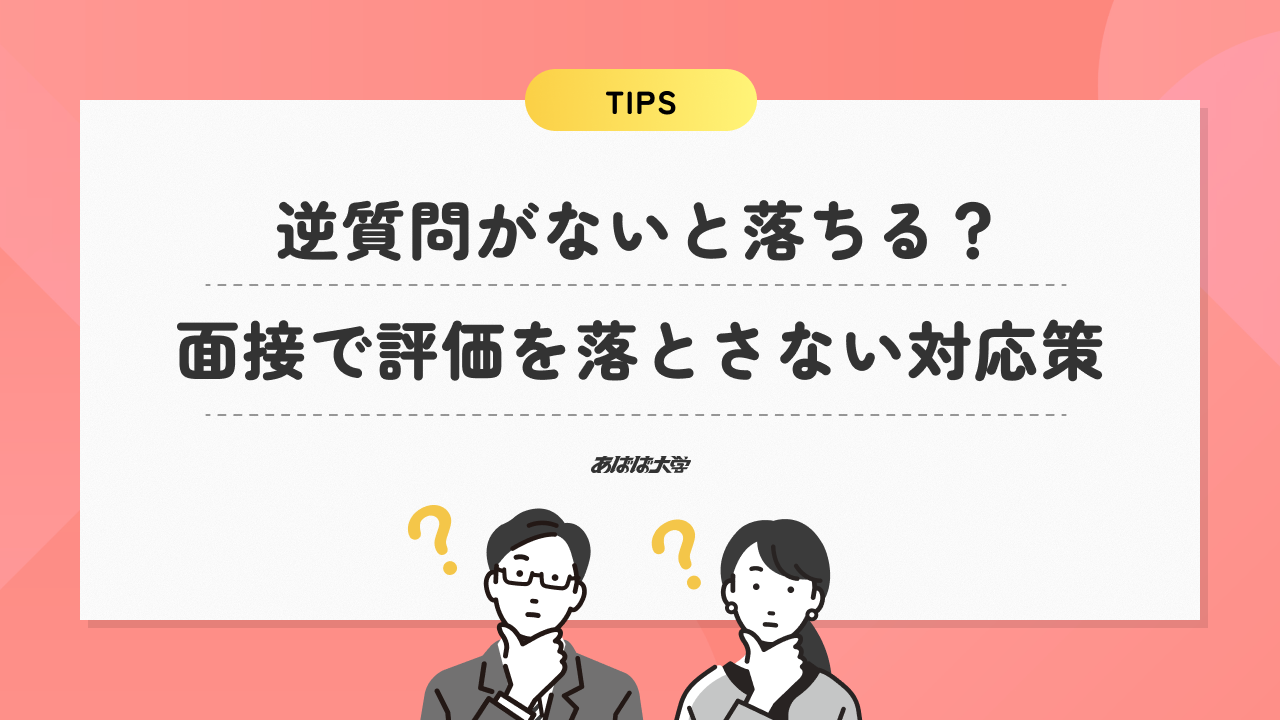
 監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)
監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)